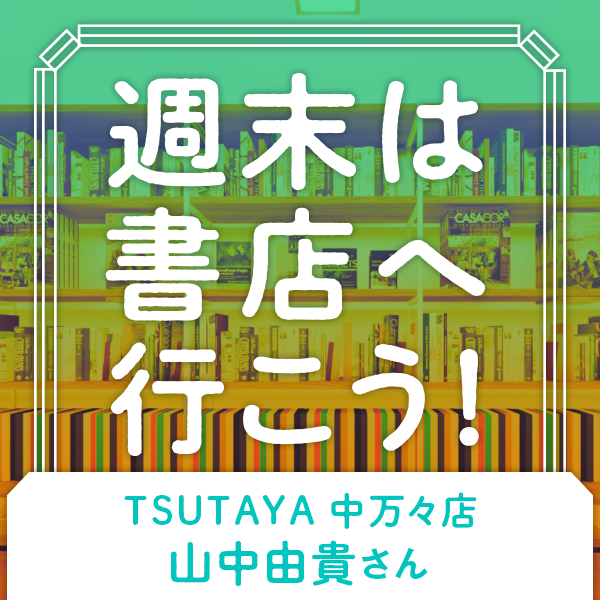藤谷 治さん『ニコデモ』
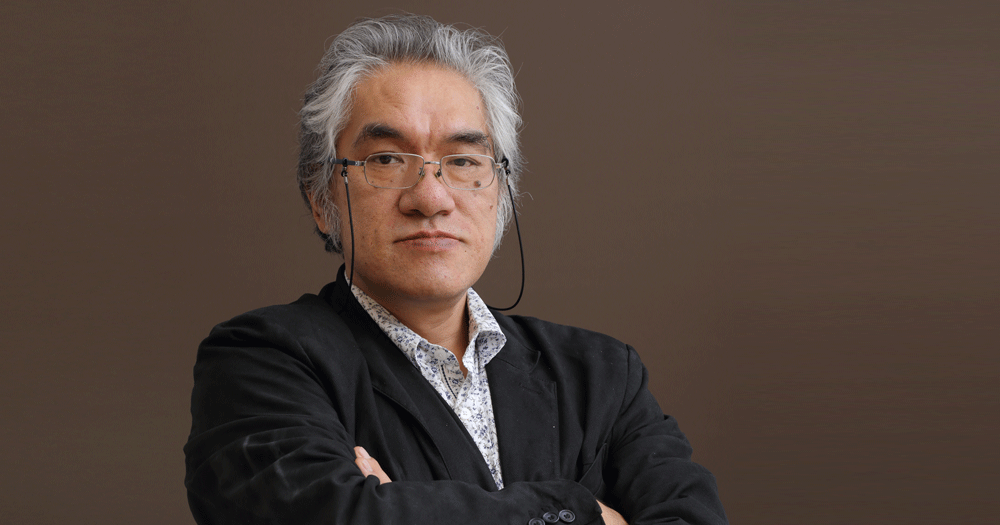
小説というのはある意味、歴史とは逆の表現形式だ
藤谷治さんの新作『ニコデモ』は、戦時中にフランスに留学していた青年と、北海道の開拓民となった家族の数奇な運命の物語。意外にも出発点は、「ファミリーヒストリーを書かないか」という依頼だったとか。さて、その経緯とは?
一人の男と、とある家族の不思議な縁
藤谷治さんの新作『ニコデモ』は一人の男の一代記と、ひとつの家族の年代記が交互に語られ、終盤には胸に迫る大きな驚きが用意された長篇だ。少し前にも『睦家四姉妹図』で平成時代のある家族の変遷を描いた藤谷さんだが、今回は実に100年ほどにわたる長い時間の話である。
「『睦家四姉妹図』を書いた時にすでに『ニコデモ』の構想は練っていました。なので、ふたつの小説を近景と遠景に分けて考えたように思います。『睦家〜』で書いたのは僕たちが見てきた景色。『ニコデモ』で書いたのは僕たちが見ていない景色なんです」
今回、登場人物の設定はすべてフィクションだが、ヒントになったのはご自身のルーツだという。
「NHKの『ファミリーヒストリー』を観た編集者が、ああいうのを書きましょうと連絡してきたのがはじまりだったんです。僕も自分の家のことを調べてみたいという気持ちがありました。それで、親に改めて取材をしたんです」
語り手の一人は、昭和のはじめ頃、裕福なキリスト教徒の家に生まれたニコデモ。ちなみにニコデモとは、新約聖書に登場するユダヤ人の名前だ。理知的な少年に育った彼は、ある時に気ままな旅に出て、会津で出会った少年の美しい歌を耳にするのだが、この歌が彼の胸に刻まれ、後の人生に大きな影響を与えることになる。
「人間だれしも届かないものがある。小僧の歌はニコデモにとって届かないものの象徴なんです」
と、藤谷さん。やがてフランスに留学したニコデモは音楽にのめりこみ、親に黙って大学を辞め、師匠のもとで世界中のあらゆる音楽を学んでいく。しかし戦争が始まり、思いもよらないことが起きて……。
この物語のどこが藤谷家のファミリーヒストリーと関連しているのか。
「僕の母方の曽祖父は二度結婚しているんです。二度目に結婚したのが僕の曽祖母ですが、その前にフランス人と結婚して息子が生まれている。その息子は成長して結婚して子どももできたんですが、その後なぜか外国人部隊に入って行方不明になったらしい。なにせ遠い親戚ですから詳しいことが分からず、藤谷家では伝説化しているんです」
また、ニコデモに歌を披露した少年、鈴木正太郎から始まる鈴木家の面々も語り手として登場する。
「最初は直線的にニコデモの話だけを書こうと考えていたんですが、会津で出会ったあの小僧をほったらかすのもどうかなと思って。というのも、あの小僧は僕の祖父にあたる人間のつもりだったんです。父方の祖父は会津の筆の職人で、開拓民として北海道に行き、農業のかたわら代筆みたいなことをやって家計を助けたそうです」
大戦のさなか、フランスのニコデモのパートも北海道の鈴木家のパートも、人々の暮らしは変化していく。
ニコデモは音楽の才能を磨いていく。彼は周囲から商業的な活動に誘われるが、「私は自分のために音楽を使いません」と固辞する。かつて天女と、栄誉や利益、盛名のために音楽を奏でることはしない、と約束を交わしたからだ。また、ピアノの演奏は達者であるにもかかわらず、自分で作曲することはできずにいる。
「『宇津保物語』を読んだ影響もあるでしょうね。あれは四代にわたる琴の名手の話ですし、天女も出てきますから。日本においては音楽に限らず、技芸というものの達人ほどそれをひけらかさないという美意識があったようです。それをこの小説では宗教的な、神への捧げものに置き換えました。それともうひとつ、才能のグラデーションについても考えました。ものすごくピアノが上手くても作曲ができない人や、編曲はできるけれどオリジナルが作れない人もいる。ニコデモはそのグラデーションの、中の上くらいの人のイメージです」
しかし誘惑と策略によって、ニコデモは天女との約束を破り、いってみれば悪魔との契約をかわしてしまう。
「『ファウスト』でも『今昔物語』でも悪魔に魂を売るかどうかという話が出てきますよね。あの古典的な物語の枠を使いました」
一方、北海道の鈴木家の暮らしぶりは、父親から聞いた話を反映させたという。
「北海道の田舎だったこともあり、野山に行って何か採ってきたりできたので食べ物に困りはしなかったそうです。一方で、母親は都市部の人間だったのでひもじい思いをしたらしい。同じ1945年前後の思い出もふたりの間で全然違う。でも両方とも真実なんですよね。北海道のパートで、戦争が終わった時に鉱山で安い賃金で働かされていた朝鮮の人たちが山から下りてきて村で暴れたけれど鈴木家は何もされなかった、というエピソードを書きましたが、あれは父親の体験です。彼らは今まで誰が自分たちに物を売らなかったり、水をかけたり、蹴ったりしたか、誰が自分たちに親切にしてくれたかを全部憶えていた。彼らの間で、藤谷家は親切にしてくれたから手を出すなと言われていたらしいです」
大局的なことは描かれないが、市井の生活がよく伝わってくる本作。
「書いている期間がコロナ禍だったことは大きいですね。これからどうなるか分からない、ということを人間はずっと繰り返してきたんだなという気持ちがありました。いつだって一寸先は闇なんですよね。今だって、この先コロナ禍が社会にどういう影響を与えていくのか見当もつかない。でも、僕や僕のまわりの人がやっていることは、あまり出掛けない、よく手を洗う、マスクをつけるということくらい。全世界的な現象を前にして、あまりに小さなことをやっている。そうした、たいしたことじゃない日常が歴史の年表に書かれることはない。それについて語るのは小説なんです。僕は小説というのはある意味、歴史とは逆の表現形式だと思っているんです。つまり歴史では人々は〝民衆〟〝日本人〟などと集団として表現されますが、その中にいる一人一人のことを見るのが小説だと思う。フランスにドイツ軍が侵攻していた頃、パリでピアノを弾いていた青年はどうしていたのか。小説なら、それを知ることができる」
戦後の軽薄男の秘めたポリシーとは
戦後の鈴木家の重要な語り手は、正太郎の孫にあたる哲次だ。東京にやってきた彼はレコード喫茶にハマり、やがてその店の二号店の店長となってさまざまなバンドに演奏をさせる。そこには意外な出会いも。
「哲次は複数の、今80代の人がモデルになっています。多感な頃に、終戦を境にして威張っていた連中の態度が真逆になったことに対して不快感を抱き、軽薄になった人間ですね。ニコデモみたいに音楽理論を究めるのではなくノリでいいんですよっていう。彼のやっていた店は実在しませんが、実際に戦後、ジャズが流行ってロカビリーが来てロックンロールに移っていく間、バンドをやっていればステージに立たせてくれる店がボコボコあったそうなんです」
モデルになった一人は、藤谷さんの父親のようだ。
「北海道で戦後、朝鮮の人たちが暴れた時に駐在所がもぬけの殻だったというのは父が実際に見たことです。あんなに威張っていた奴が逃げたということで、親父はその後、大所高所から政治的な発言をする人たちに非常に不信感を抱いていた。それだったら自分は好きなことをして笑って過ごすというポリシーを決めた人なんです。その息子なんですよ、僕は(笑)」
哲次が、安保反対のデモ隊が「トウソウ、ショーリ!」と叫ぶ姿を見かけ、〈闘争が「勝利」するとはどういうことだ。安保条約が間違っているというのなら、ただ正せばいいんじゃないか。それがなぜ勝ち負けになる?〉と疑問に思う場面が印象的。
「政治家を批判するにしても〝こういう政治にしろ〟と文句を言うなら分かるけれど、〝辞めろ〟とだけ連呼する風潮には違和感があります。それに、何かあった時に会社や組織といった大きなものを責め立てるより先に、もっと個人個人について考えたほうがいいと思う。差別や暴力は目の前にある問題だし、自分の中にも偏見はきっとある。それを一人一人が反省して修正していかなくちゃいけない。僕は、それができるのが小説だとも思っています。書く経験、読む経験を通して自分の苦い部分、恥ずかしい部分を知るのが小説だから」
過去を見て、現在を見て、未来を見る
ニコデモと鈴木家の物語は、やがて意外な形で近寄っていく。作中、効果的な形で登場するのがアレクサンドル・デュマの『黒いチューリップ』という小説だ。
「これに関してはびっくりしたことがあって。外国人部隊の場面で小道具が必要だったので、積読本の中からたまたまデュマの『黒いチューリップ』の中のはじめのほうに出てくる文章を使ったんです。その時はそこだけ読んでほったらかしていたんですが、書きながら読み進めていったら、とある偶然にびっくりして。それで小説の後半にもう一度出しました。神はいる、と思いましたね、あれは」
そんな奇跡も呼び込んで、祝福に満ちた物語となった。今回はいつも以上に調べものをし、そして、何度も書き直したという。
「つねに事実に対して物語はあくまでも物語でなければいけない、という気持ちを持っていますが、今回は特にそれを貫けたという満足感があります。歴史事実に引っ張られて〝外国人部隊はこうだった〟〝移民はこうだった〟という書き方をするのではなく、あくまでもニコデモという個人、鈴木正太郎という個人を見て書いて、歴史はその背景にある、という書き方ができた、ということですね」
書き終わってから、以前自分が言った言葉を思い出したという。
「我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこに行くのかという三つをよく見る必要がある、という話をしたことがあって。東日本大震災の後、古川日出男さんが1000年に一度の震災というなら、1000年前はどうだったのかを見ようといって源氏物語や平家物語の新たな物語を書いた。僕がいうのはおこがましいけれど、僕と古川さんのその意識は似ている気がします。コロナ禍で自分たちがこの先どこに行くか分からない今、自分たちがどこから来たのか、よく見る必要を感じます。それにはやっぱり、物語が必要なんです。今回改めて、そうしたことを考えました」
藤谷 治(ふじたに・おさむ)
1963年東京都生まれ。2003年『アンダンテ・モッツァレラ・チーズ』でデビュー。主著に『いつか棺桶はやってくる』『船に乗れ!』『世界でいちばん美しい』(織田作之助賞)などがある。
(文・取材/瀧井朝世 撮影/浅野剛)
〈「WEBきらら」2022年3月号掲載〉