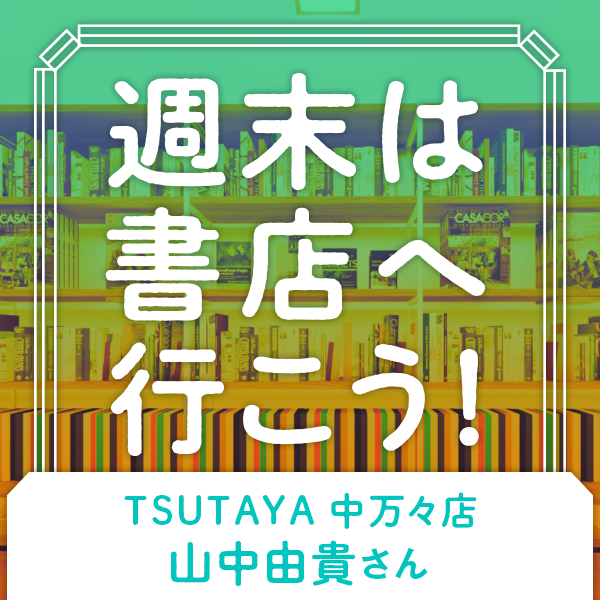藤谷 治さん『船に乗れ!Ⅲ』
最初から、哲学のことしか頭になかった。
第1巻の発売時から、書店員や読書家の間で話題となっていた青春小説『船に乗れ!』。高校の音楽科を舞台に、ひとりの少年の3年間を1冊ごとに追った3部作が、ついに完結した。しかも、圧倒的な感動をともなう傑作となって。自身も高校では音楽科に通っていたという藤谷治さんにとって、本書の執筆には特別な思いがあったようだ。
人に言いたくないような恥ずかしい思いを
音楽一家のもとで育ち、チェロの腕前には自信のあった"僕"、津島サトル。しかし東京芸術大学附属高校の受験に失敗し、新生学園大学付属高校の音楽科に進学。普通科は女子のみ、音楽科も男子はたったの6人。挫折からのスタートを切ったサトルが、仲間たちと切磋琢磨して音楽家を目指す青春音楽小説──と思いきや、第2巻の後半で、音楽とは関係のないところで、とんでもない事件が相次ぐ。藤谷さんにとって一番長い小説となった本作の出発点はどこにあったのか。
「青春小説を書いてくれという依頼があったんです。今まで、自分の会社員時代や子供の頃を書いたことはあったけれど、実は高校生時代のことは、どうしても触れたくなかった。実は思い出すと、軽いトラウマを感じていたんですよね」
藤谷さん自身、音楽一家のもとで育ち、チェロを弾き、芸高の受験に失敗したという。祖父のことを"おじいさま"と呼んでいたというところまで、サトルと同じだった。
「子供の頃から音楽教育を受けてきたし、サトルのように短期留学もした。でも僕は結局、音楽の道には進まなかった。それを申し訳なく思ってしまうんですよね。挫折の記憶でもある。僕はその後映画の道に進んだけれど、結局サラリーマンを10年やって、今は本屋を経営しながら小説を書いている。あの時そのまま音楽をやっていれば……と言われるのがキツイ。苦い思い出は苦いままなんですよね。でも、これをきっかけに、やってきたことに落とし前をつけようと思ったんです。だから、"音楽のことがよくわかりました"という小説にするつもりはなかった。若い頃というのは、本当に冷や汗や脂汗が出るくらいの思いをするんだということを書きたかった。もちろん、青春にはキラキラした部分もある。でも、人に言いたくないような、恥ずかしい思いだってするはず。それが青春の正体だと思う」
最初に音楽があって、小説が生まれた
とはいえ、もちろん音楽の描写も見事。オーケストラでの演奏のシーンは臨場感があり、好きな女の子のためにオペラの解説を考える様子は、そのまま読者にとってもガイドとなる。登場するさまざまな楽曲にも興味がわく。また、各巻のサブタイトルにある「合奏と協奏」「独奏」「合奏協奏曲」が、サトルの置かれた状況、そして成長と照らし合わせた表現となっていて見事だ。
「実は、どういう展開にするかは、音楽を聴きながら考えていきました。この音楽がバックに流れていたとしたらどうなるんだろう、と。小説の中に音楽が流れているように書かれてあるけれど、実は最初に音楽があって、小説が生まれたんです。音楽を聴いた僕がブラックボックスとなって、小説を書いていったというわけですね。もちろん、音楽を知らない人のためにもわかりやすいように、とは考えました。ただ、先にも言ったように、音楽は主軸ではなくて、あくまでもデコレーションです」
高校生活でサトルが直面する事件はフィクション。最初に頭にあったのは、本書に登場する倫理社会を教える教師、金窪先生のことだったという。ニーチェを愛読するサトルにとっては、先生の授業は興味深いものだった。
「音楽よりも、人はどうやって生きるかということがこの小説の主軸。最初から、哲学のことしか頭になかった。金窪先生の授業では、どうして人を殺してはいけないのか、という問いも出てくる。そういう根源的なところをいくらでも時間をかけて考えることができるのが青春のいいところ。どんなに青臭いことでも徹底的に語れるというのは、哲学者と高校生だけなんですから。人を殺しちゃいけないというのは大人なら当たり前のことだけれど、一度そういうことをきちんと考えてみたいと思っていたんです」
経験から獲得する、自分だけの哲学
だが、金窪先生の授業に引き込まれていたはずのサトルが、ある日犯してしまう過ち。そして訪れる人生の迷い……。
「これを僕の自伝的な小説ととらえる人もいるだろうけれど、僕の考えではこれは非常に抽象的な小説。全編、哲学対話だと思っているんです。1巻より2巻、2巻より3巻のほうが難解になっていっている」
といっても、難しい形而上学的議論が交わされるわけではない。サトルのような運命を背負ってしまった少年が、人生をどう選び取っていくかという物語になっているのだ。
「哲学はもちろん、自分の頭で考えるもの。でも考えることって、結局経験に基づくものなんですよね。経験と抽象的な思考というのは、どこかで区切られているものではない。まして哲学者でもない我々の哲学というのは、人生経験で得ていくものでしかない。それは低レベルな内容かもしれない。例えば"男を信用しない"という哲学かもしれない。でも、自分の経験によって得た哲学だったら、それはこれ以上ないくらい尊い、自分ひとりの哲学なんです。ひとりの人間が何かを経験して何かを感じる、その総体が哲学だと思うんです」
ニーチェを好んで読んでいたサトルが、ある日その本に書かれている内容を実感できないと気づいて愕然とするシーンがある。
「ニーチェにしろ誰にしろ、哲学者の哲学というのは、その人にしかわからない言葉で書かれていると思う。それを解釈しようとする人でもっとも優れているものは、その人が言ったことについて、自分の経験に基づいて勝手に解釈できる人なんですよ」
自分の過ちと向き合おうとするサトル。しかし、失敗はもう起きてしまっている。それはもう、許されないことだ。
「ガラスのコップを割ってしまった時、それを割らなかったことにすることはできない。割れない状態に戻すなんてありえない。でも、そのことについて、しっかりと悔恨の念を持つことが大事なんじゃないでしょうか。学校で誰かをいじめたら、その子が学校に来なくなっちゃったけど、私もあの頃は若かった、といって終わりにしたら、その出来事は何でもないことになっちゃう。そのことについて悔恨できるかどうかが大事」
苦い思いを抱き続けて生きなければならない時、救いはどこにあるのか。
「救いは、悔恨そのものにある。悔やむことができるということ自体にあると思う。なかったことにして、看過してしまうことこそ、何も救いがないんじゃないでしょうか」
小説の話法について書きながら学んだ
実は本書は、プロローグからもわかるとおり、大人になったサトルが高校時代を振り返って綴っているという形式。青春の苦さを抱いて生き続ける姿に、人生というものの厳しさと同時に「それでも人は生きていくのだ」という切実な希望を感じさせられる。また、高校生のサトルの一人称ではないところが、主人公と語り手の間に絶妙な距離感と客観性を生み、身勝手な感情にどっぷり浸かった文体になる危険性を免れている。
「高校生の"僕"の一人称ではないということは、無意識のうちに小説の視野が狭くなることを嫌っていたからだったのかもしれません。それに現に僕は今おっさんなので(笑)、おっさんが高校生のフリをして書いたものなんて人には見せられない、という気持ちがあったと思います。今回の小説は、ナラティブ、つまり小説の話法というものについて書きながら学ぶところがありました。というのも、僕はこれまで、一人称で書くことに非常に抵抗があったんです。今はみんなが一人称で書いている。そこに飛びつく安易さが嫌だったし、それにある人間の視点からしか見ていないから、小説の世界が非常に狭くなると思っていた。だから『アンダンテ・モッツァレラ・チーズ』では"ぼくたち"という視点だったし、『おがたQ、という女』や『いつか棺桶はやってくる』は三人称、『またたび峠』や『いなかのせんきょ』は落語という客観主義的な視点をとっていた。でも、今回の小説はどうにもこうにも、一人称で書くしかなくて」
とはいえ、サトルの視点を通してであっても、オーケストラの仲間や教師たちも血の通った人間としてくっきりと描かれている。サトルが恋心を抱く南枝里子の音楽に対する情熱と野心、金窪先生の抱く憤懣、そしてオーケストラの仲間たちの片思いやすれ違い。一人ひとりの思いがしっかりと伝わってくる。
「僕が思っていたよりも、一人称でできることは大きかった。みんながままならない思いを抱いている、ということを一人称で書けたのは本当によかった。僕はすごく近くにいる人のことも本当はわからない、という気持ちが強いんです。でも、今回の小説で、どんな人にもその人なりの魂があると書けたことは、僕の人に対する見方が、ちょっと広がった気がします」
僕は徹頭徹尾、アラビアンナイトのような物語を書いてきた
自分とシンクロする部分があるだけに、この3部作の執筆はかなり疲弊した、とも。
「小説を書いている"自分"というものがいると考えた時、今までは"自分"よりも小説のほうに軸足を置いていたんです。今回は、小説を書いている"自分"に重きが置かれていたんですね。これを書いている間は本当に疲れましたけれど(笑)、それは書いている小説=自分の実人生ということの疲れだったんです。今後は"自分"に重きを置くにしても、己を表すようなフィクション、という風に考えていきたい。小説の形式を借りずに書くこともしなくちゃいけない時期に入ったんだと思います」
とはいっても、自己表現、という言葉に対しては恥じらいがあるようだ。
「僕が何かをした、ということに興味を持ってもらうなんて傲慢だと思う。日本では告白や自己表現の小説というものが随分書かれてきて、それがすっかりスタンダードになっているけれど、僕はそれはやりたくなかった。僕が小説のほうに軸足を置きたいというのは、生来の恥ずかしがり屋のせいもあるけれど、小説としていいものを書けば、そこからあぶり出すように、僕という人間を読み取ってもらえるだろうという気持ちがあったんです。でも僕は徹頭徹尾、普通の小説を書いてきたつもり。それはつまり、面白い話ってこと。アラビアンナイトのような物語ですよね」
語り継がれていく"語り"であり、"騙り"であるところの物語。それが藤谷さんが目指してきた小説なのだ。ただ、今回はそうした衒いを捨てざるを得なかったわけ。そして苦しみぬいて生み出された本作。そこから著者自身が、小説の手法とは別に、獲得したものは。
「すっきりした気持ちになったわけではありません。苦い思い出は苦いまま。でも、気持ちに折り合いがついたのかもしれません。もう20年以上音楽をやめていたけれど、1巻を書き終わった時に、ケースにしまっていたチェロを修理に出して、去年の夏くらいからまた弾き始めたんです。弾いても苦しくならなくなった。執筆に行き詰まった時も演奏していました」
そんなエピソードが下敷きとなっているのが、アンソロジー『Heart Beat』に収録されているスピンアウトの短編「再会」。
「あの短編の話をするのは恥ずかしい(笑)。女房が言った言葉まるまるそのまま使っているので、自分にとっては妙に生々しくて」
これが実に温かく、優しい言葉。悔恨の思いを抱く人生に与えられる、救いの言葉となっている。