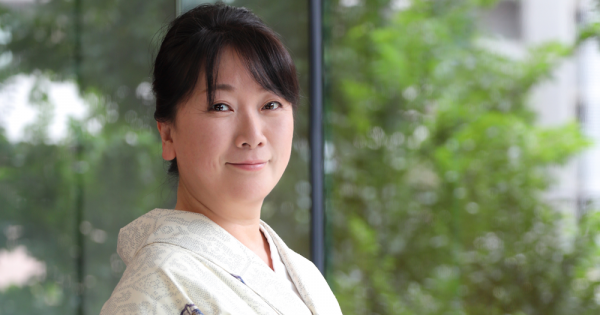村山由佳さん『風よ あらしよ』
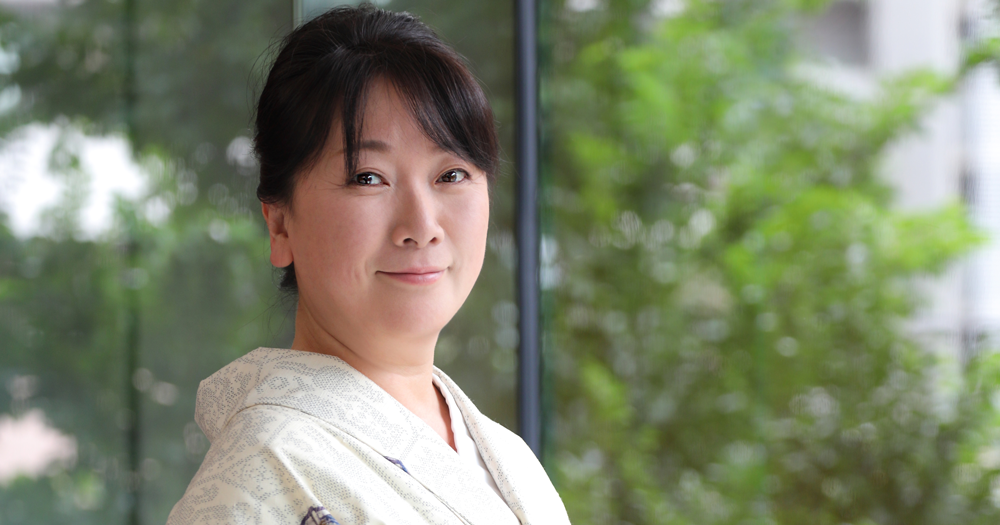
彼女を突き動かしているのは、義憤なんだと思います
村山由佳さんの新作長篇『風よ あらしよ』は、著者にとって初の評伝小説だ。描かれるのは明治から大正にかけて短い生涯を駆け抜けた伊藤野枝の生涯。「青鞜」の編集に携わった婦人解放運動家であり無政府主義者であった彼女の人生はまさに波瀾万丈。村山さんにとって最長の小説となった本作を、どのような思いで書き切ったのか。
きっかけは編集者の言葉
「2016年に『La Vie en Rose ラヴィアンローズ』を書き終えた後、編集者たちとの打ち上げで次に書くのはどんなものがいいか、という話をしていたんです。その時、栗原康さんが伊藤野枝について書いた『村に火をつけ、白痴になれ』を読んだ編集者が何人かいて、〝伊藤野枝が村山さんと重なる。村山さんの書く野枝が読みたい〟と言われたんです。どこが似ているんだろうと思いながら栗原さんの本を読んで、ああ、なるほど、って(笑)。私はここまで振り切れないけれど、他人ではない気がしました」
と、村山由佳さん。そうして生まれたのが、『風よ あらしよ』だ。村山さんにとって一冊の本としては最長の小説となった。
伊藤野枝は1895年に福岡の今宿で生まれ、親戚に懇願し上京して進学、卒業後は地元に戻り親の決めた相手と結婚するが、出奔して再び上京。のちに雑誌「青鞜」の編集に携わった編集者であり作家であり翻訳家であり、婦人解放運動家、無政府主義者でもある。習俗打破を目指し、人工妊娠中絶や売春など女性に関する評論なども発表。自分の教師だった辻潤と結婚したものの彼を捨てて無政府主義者の社会運動家、大杉栄と内縁関係となり、大杉の妻と愛人との四角関係の末に愛人の神近市子が大杉を刺した日蔭茶屋事件が大スキャンダルに。その後1923年、28歳で憲兵に捕まり、大杉と甥っ子の橘宗一とともに殺され、遺体は井戸に遺棄された。
「私もずいぶん前に瀬戸内寂聴さんの『美は乱調にあり』『諧調は偽りなり』といった大杉栄と伊藤野枝の評伝は読んでいたんですが、詳しく憶えていたわけではなくて。いろいろ読んで知るうちに、野枝の時代も今も、女性たちが置かれている状況があまり変わっていないと感じて。野枝の時代より今はだいぶ良くなっているでしょうけれど、女性が行動を起こそうとしていろいろ叩かれるのは、あの頃も今も同じなんだなって」
野枝について書いてみたいとは思ったが、その自信を得るまでには時間がかかったという。実際、連載を開始したのは「小説すばる」の2018年7月号、野枝の話題が出てから約2年後だ。
「最初は、100年前ってかなり昔だなと感じたんです。私は、頭の中に映像が浮かばないと書けないタイプなので、たとえば家の中で野枝が正座をして何か考えている姿の描写にしても、彼女の目に見えている景色が浮かばなければ書けない気がしたんです」
では、突破口は何だったのか。
「野枝は大杉と甥っ子と一緒に果物屋さんに立ち寄った時に憲兵に捕まっている。それが最後の目撃情報なんですが、その時に子どもが林檎を持っていたという証言があったんです。それまでモノクロ映画のように感じていた世界が、赤い林檎から一気に全部がカラーになっていったんですよね。ああ、これを導入部にして書ける、と思いました」
その場面が本作の序章となっている。そこから時間が遡り、本編は野枝の誕生から描かれていく。全生涯を書こうと思ったのは、
「なにしろ短い人生ですから。そのうえ、こんなに可哀そうな死に方をして、どれだけ心残りだったんだろうと思う。もしももっと長く生きていたら、執筆活動でも行動でも、どれだけのものを残していたんだろうと思うと、本当にもったいないですね」
野枝への批判に対する反発心
野枝を描くにしても、その思想や「青鞜」の編集や評論執筆、さまざまな論争、そしてもちろん恋愛と、題材は山盛りのはず。すべてを詳細に盛り込むことは不可能だろう。
「野枝に関する本を読んでいてすごく癪だったのは、日蔭茶屋事件の後に、刺した神近市子よりも野枝のほうが批判されたこと。〝あの人に思想はない〟〝その時好きな男の人の思想が自分の思想になるだけ〟などと言われていますよね。それを読んだ時、〝本当にそうか?〟と、ものすごく反発心がわきあがりました。辻潤に反発して家を出るきっかけとなるのが足尾銅山の公害事件で意見が対立したからですが、男の思想に染まるだけの女性だったら、そこで別れませんよね。それに彼女は、自分の生まれた村にあった組合というものを回想して、社会主義の本質についてよくよく考えている。野枝こそ、思想ばかり振り回している人たちより、本当の意味での理想を分かっていたんじゃないかと思うんです。彼女の思想と恋愛がすごく強く結びついて見えるから、男についていくだけの女性に思われるけれど、実はそうではなくて、つきあう男たちから一番いいものを得て、それを踏み台にしていっているところがある(笑)。もちろん、そのためにつきあっているのではないですけれど。そういう部分をちゃんと書きたかったんです」
あふれんばかりのエネルギーをもって行動し、自分を貫き通す姿は時に我儘、あるいは感情的だと思われていたようだが、
「彼女を突き動かしているのは、義憤なんだと思う。まわりからはすぐ同情するから浅い考えのまま行動を起こすと思われていましたが、大杉が〝センチメンタリズムほど強いものはない〟と言っているように、センチメンタリズムと生命力の強さがあいまって、野枝という強固な感情の生き物が作りあげられている気がします。だから、恋愛も何もかも、生な感じで書きたかった。どんなに愚かな瞬間も」

大杉に関していえば、とにかく女性関係に関して身勝手な印象だ。たとえば〈自由恋愛〉を提唱し、その三条件というのが〈お互いに経済上独立すること〉〈同棲しないで別居の生活を送ること〉〈お互いの自由(性的のすらも)を尊重すること〉。
「読者としては、大杉の株はダダ下がりというか、地に潜るくらいですよね(笑)。自由恋愛の三条件なんて男に都合のいいだけの机上の空論だし、しかも大杉は経済的に独立もしなかったし、野枝ともすぐ同棲している(笑)。そりゃ奥さんや愛人たちは文句も言いたくなります。ただ、大杉は野枝に対して〝愛人である前に同志だ〟と言いますよね。その言葉は野枝のいちばん深いところに刺さってしまったんでしょうね」
当時の「女性はこうあるべき」という価値観をすべて吹き飛ばしていく野枝にとって、彼女を彼女のままでいさせてくれる存在が、大杉だったのかもしれない。
「夫だった辻は尊敬できる先生でもありましたが、大杉とはオスの度合いがあまりにも違う(笑)。ギョロっとしたあの目で射すくめられると女として心と身体が悦んでしまう部分はあったのかも。また大杉は脇が甘いので、ついていてあげなきゃ駄目かしらとつい思わされたのでは」
彼女に関わったさまざまな人々
本作で圧倒されるのは、野枝だけでなく、彼女と関わったさまざまな人間の視点が挿入されていく点だ。母親や学校の同級生、平塚らいてうや大杉栄、大杉の愛人の神近市子──。
「資料を見ると、野枝の人生は場面場面がどれもドラマチックで、野枝が生まれた夜のことも印象深いんです。それで、出だしは野枝の母親のムメさんの視点でその夜のことを書きたくなりました。ただ、ムメの視点だけあって他は全部野枝の視点だと小説として構造がいびつだし、子どもの頃のことなどはやはり彼女の視点だけでは書き切れない。だったらいっそ、最後まで通して、彼女に関わったいろんな人たちの視点から描写していこうと思いました。否応なく長い小説になるだろうな、とも思いましたけれど(笑)」
しかしだからこそ、野枝の人物像が立体的に浮かびあがるうえ、視点人物一人ひとりの人生背景や複雑な思いが見えてくる。
「自分の想像も含めてなんですけれども、地味に見える人でも書いていくとその人にはその人なりの想いや苦しみがあると分かってくる。たとえば大杉の愛人だった神近市子も、書く前は〝こんなおっかない人に手を出すなんて大杉もうかつだな〟と思っていたんですけれど、彼女の視点から書いてみたらやっぱり、そりゃ刺したくもなるわな、となりました(笑)。刺して服役して釈放された後は憑き物が落ちたかのように未練を見せない。女だなあ、と。自分の中にも似た部分があるだけに、イタいけれども愛おしかったですね。それに、市子は新聞記者だし野枝も大杉も本を出している。みんな言葉人間。言葉人間同士の恋愛って、本当に面倒くさいんです(笑)。言葉って、肉体以上に深く食い込むことがあって、言葉で揉めたり冷めたりもする。だから、なおさら分かるなあと思うところがあります」
気に入っている周辺人物はというと、
「個人的な推しキャラは、なんたって村木源次郎(笑)。どんな時も大杉と野枝の味方をして世話をして、父性より母性を感じさせますよね。四面楚歌の状況でもついていてくれて、思想的に対立した時はちゃんと意見する、心ある人。彼の存在は野枝にも大杉にもものすごく救いだったと思う。なのにいちばんニヒリストでテロリズムに近い人だったという」
村木ももちろん裕福だったわけではない。野枝たちは驚くほど困窮しているが、それでも互いに助け合い、時に資金援助をしてくれる人にめぐりあったり……。
「互助関係がすごいですよね。みんな、自分の感情に対して誠実だったと思う。ただ、お金をポンと出してくれた有島武郎にしても、心中事件を起こしていますが、惚れぬいての結果というよりも観念の死にとらわれたように思えて。みんな、頭が良すぎて生命力がついていっていない気がします。そういう意味では、野枝は生命力が抜きんでている。どれだけ勉強して、思想が時代の先を走ったとしても、彼女の生命力があればついていけたと思うのに」
未来を変えられると信じて
理不尽な権力に抗い、習俗打破を目指し続けた野枝たち。
「本当に熱い人たちだったなと思う。今みたいに〝どうせ変わらないじゃん〟という空気ではなくて、〝今変わらなくても、自分が踏み石のひとつになれば何かが変わるかもしれない〟ということをみんな信じているんですよね」
彼らの姿と今の時代とを照らし合わせると、さまざまな思いを抱かせる。
「アーティストやスポーツ選手やミュージシャン、そして作家に〝政治的な発言をしないでほしい〟という人は多いけれど、野枝の時代、物書きはみんな政治的な発言をしていますよね。野枝も勉強不足を指摘されることはありましたが、何も考えていないわけではなかったし、それが議論のきっかけになっていた。私自身はあまり過激なことを言えない性格ですが、こればっかりはおかしいと思ったことは言っていこうと、そのためにペンはあるのだと、この小説を書きながらずっと折れかけている心につっかえ棒をしてもらっている気持ちでした。思ったことが言える社会であってほしいなと、つくづく感じています」
村山由佳(むらやま・ゆか)
1964年東京都生まれ。会社勤務などを経て作家デビュー。93年『天使の卵──エンジェルス・エッグ』で小説すばる新人賞、2003年『星々の舟』で直木賞、09年『ダブル・ファンタジー』で中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞、島清恋愛文学賞を受賞。他の著書に今年完結した「おいしいコーヒーのいれ方」シリーズ、『噓 Love Lies』『燃える波』など。
(文・取材/瀧井朝世 撮影/浅野剛)
〈「WEBきらら」2020年11月号掲載〉