河﨑秋子さん『絞め殺しの樹』
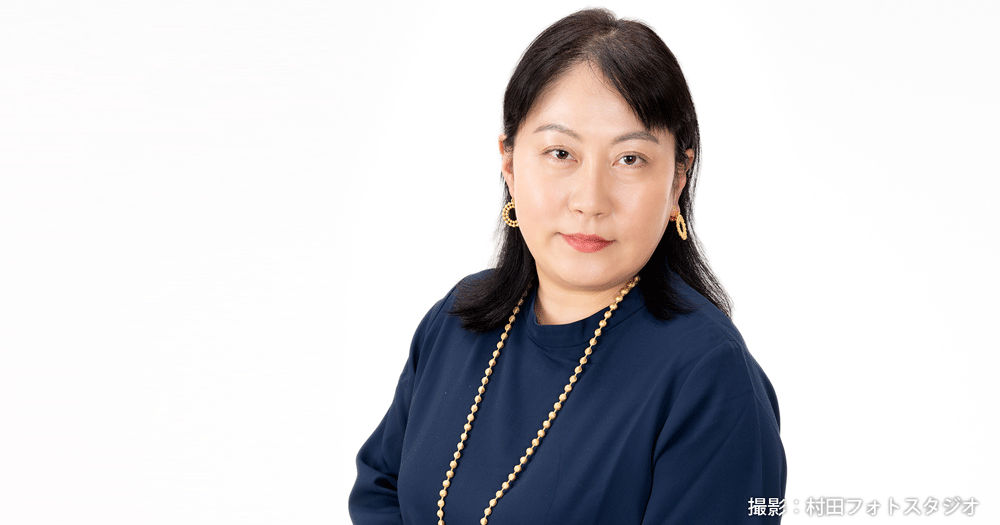
いいものも悪いものもいつかは終わりを迎えるんです
発表する作品が毎回高く評価される河﨑秋子さんが、待望の新作『絞め殺しの樹』を発表。根室に生きた一人の女性と、彼女の人生を想う青年の物語。書名はなんとも不気味だが、実はこれ、菩提樹のこと。主人公たちの人生のなかで、この言葉が意味したものとは?
昭和の根室で、懸命に生きた一人の女性
北海道で生まれ育ち、羊飼いをしながら小説を執筆してきた河﨑秋子さん。2014年に『颶風の王』で三浦綾子文学賞、19年に『肉弾』で大藪春彦賞、20年に短篇集『土に贖う』で新田次郎文学賞を受賞するなど、発表する作品がどれも高く評価されてきた。そんな彼女が専業となってじっくり取り組んできた最新作『絞め殺しの樹』は、北海道の根室を舞台にした大河巨編である。
本作は二部構成だ。第一部の主人公は昭和元年、北海道の根室で生まれたミサエ。幼いうちに新潟の農家に引き取られるが、十歳の時に根室で畜産業を営む元屯田兵の吉岡家に引き取られ、この地に戻ってくる。大婆様と夫婦、二人の子どもは彼女を冷たくあしらい、こき使い、学校にも通わせない──。
明治政府の政策によって北海道の各地に移住した屯田兵は、当初は士族に限られていた。吉岡家は元士族であることと、「この土地に最初に鍬を入れた者」であることを過剰なほどに誇りに思っている。
「私が育った別海町は地理的な関係で開拓は遅かったのですが、屯田兵については郷土の歴史として学校で習っていました。それとは別に、母の実家が根室のほうで農家をやっていて、そちらでは屯田兵由来の農家は別格として見られている、みたいな話を聞いていたんです。最初に入植した人間が偉いなどといったことが制度で定められているわけではありませんが、やはり人間ですから、最初に来た人は苦労した分発言権が強かったようです。そうした部分を物語の芯の部分として組み立てていきました。ただ、吉岡家にモデルがいるわけではありません」
吉岡家の人間ではなく、ミサエという下働きを視点人物にしたのは、
「その家で受け継がれてきた価値観ではなく、別のところから来た人間の価値観でその家を見たいと思いました。吉岡家の人たちは、自分たちがミサエに意地悪している意識はないんですよね。最初に入植した大婆様が厳しくて、それを見て育った子どもたちもそれが当たり前になっている。フィクションとして主人公にあえて苦労させようという意図はありましたが、自分に甘く他人に厳しい人たちで構成された家庭では、途中から来た血の繫がらない一員は自然と苦労するだろうとは思いました。吉岡家は近所の人からは〝あの家の人たちはきつい〟と思われていますが、本人たちは家族の中で完結しているので、客観的に見られずにいるんです。それに当時は児童を保護する制度もないですから、他の人もなかなか介入できないんですよね」
部屋も与えられず、廊下を寝床とするミサエの生活がなんとも過酷。根室の冬の寒さがこちらにまで伝わってくる。
「この地方は雪がたくさん降るというよりも、とにかく風と地面が冷たいんですよね。気候条件が厳しいので米も野菜も作れない。消去法の結果、畜産くらいしかできなかったんです」
慰めとなる存在がまったくいないわけではない。時折登場する白猫とその子どもたちは、ミサエだけでなく読者の心も和ませる。また、富山から定期的にやってくる薬問屋の小山田や、後から入植した林家など、ミサエに手を差し伸べようとする大人もいる。そのおかげもあってミサエは学校に通い、札幌の薬問屋に奉公に出て、住み込みで働きながら北海道帝国大学医学部附属医院の看護法講習科にも通わせてもらう。だが、それは束の間の幸福な日々。戦後、根室に家族とともに移住した小山田に頼まれ、ミサエは保健婦となってこの町に戻り、距離を置いていた吉岡家と再び関わるようになる。
保健婦となったミサエの日常
保健婦として、各家庭をまわって健康相談にのり指導し、栄養を考慮した家庭料理のレシピを教えるなど尽力するミサエ。時には助産師を務めたり、マヨネーズの作り方を広めたりと、その仕事内容が細かく描かれ興味をかき立てる。それには、一冊の冊子が大いに役立ったという。
「うちの実家でも、保健婦さんに作り方を聞いて家でマヨネーズを作っていたそうです。お世話になった保健婦さんがいるんですが、その方が関わった『北の開拓地で生命をむかえる 拓殖産婆と開拓保健婦たちの足跡 ──北海道別海町のお産の歴史──』という冊子をいただいたので読んでみたら、これが非常に面白くて。地域の家族に寄り添っていろいろなアドバイスをすることや、それがなかなか理解してもらえない苦悩などが端的な形でまとめられているんです。それに、保健婦になるとよその家庭の事情に深く立ち入っていくので物語的にもいいなと思いました」
その後、ミサエはお見合いで銀行員の男性と結婚。娘も生まれて道子と名付ける。道子は順調に成長するが、幼い頃から苦労してきたミサエにしてみると、道子の子どもらしい言動は甘えや怠けに思えてしまい、つい?ってしまう。
「道子については書いていて胸が痛かったです。ミサエだけでなく、周囲の環境の影響もありますが、こういう厳しい子育てをして娘の辛さを汲み取れないでいたらこうなるよな、という感じで書き進めていったので……」
そして、悲劇的な事件が起きる。そこに関わってくるのが小山田家の息子、俊之だ。まだほんの少年だが、彼が実に恐ろしいのだ。
「いちばんキャラクター立てに苦労した人物です。先代の小山田は商才もあり、視界が広かった人ですが、根室では余所者扱いされている。俊之は親の頭の良さを受け継いだけれども、自分を活かしきれていない。そうなるとどういう人間になるのか、逆算して考えていきました。同年代の友達はなかなかできないけれど、年下からは尊敬され、お山の大将になって暴走していく。そういう人間も世の中に揉まれるうちに変わるものですが、でも一定の割合で変わらない人もいる。俊之はそういう人ですね」
タイトルにこめた意味は
苦しみが続くミサエの人生を追ううちに、タイトルの「絞め殺しの樹」の意味が見えてくる。実はこれ、日本で菩提樹と呼ばれるシナノキのこと(日本ではシナノキ科のボダイジュ、本場のインドではクワ科イチジク属のインドボダイジュを菩提樹としている)。この蔓性の植物は、他の木に絡みついて絞めつけながら栄養を奪い、その木を枯れさせるという。別名が、シメゴロシノキだ。
「仮タイトルでつけていたものをそのまま採用しました。人間でも、強い人に絡みついて自分を確立し、相手を絞め殺すような人はいる。もちろんミサエはこの小説のなかで絞め殺されていく木を象徴する存在ですが、そんなミサエも、娘のことを絞めつけるところがあった。人間同士は、支え合ったり絞めつけたり、一方的に絞めつけたりするものだなと思います」
絞めつけられ、絞めつけて苦しむミサエに、ユリという女性がそっと語りかける場面がある。「あなたは、哀れでも可哀相でもないんですよ」と。ミサエはその真意をすぐに理解することができない。読者も最初は、ミサエよりももっと哀れで可哀相な人間がいるという意味かと思ってしまいそうだが、それは違う。
「自分は可哀相な人間だ、という思いに寄りかかるのは逃避の手段のひとつではあるけれど、そのままだと最終的に自分がいちばん辛くなるんじゃないかと思いました。それは、人のあり方としてすごく悲しいことなんじゃないか、ということをユリさんには言わせたかったんです」
また、ユリの「どんな木だって、いつかは枯れる」という言葉にミサエは救いを感じ、心の中で反芻していく。
「物事には期限がある。いいものも悪いものもいつかは終わりを迎えるんですよね。そのどうしようもない平等さが、人を救うこともあるんじゃないかなと思います。自分を苦しめた人も助けてくれた人も、最後はどうしても死ぬ。その言葉は、ミサエには響いたのではないでしょうか」
第二部は一人の少年の成長物語
第二部の主人公は昭和三十九年生まれ、吉岡家の養子となった雄介だ。ミサエの一代記だけでなく、この第二部を加えた理由とは。
「実は最初、雄介がミサエについて調べていく話を考えていたんです。バランスなどを考えて現在の構成にしました。雄介とミサエはほとんど接点がありませんが、ミサエの人生を見つめ直し、彼女からのロングパスを受け取る人というイメージがありました。ハートウォーミングな形ではないけれど、それがひとつの落としどころというか。それに、第二部では小山田家の行く末も書きたかった」
雄介もまた、吉岡家でミサエ同様こき使われるが、異なるのは将来家業を継ぐように言われていることだ。彼自身も、養子としてそれが当然だと思っている。
「跡を継ぐために育ててもらったので、自分のアイデンティティがこの家を継ぐことになってるんですよね。それが自分の存在意義だと思っている。でも、大学に進学して根室のことを客観的に見るなど、いろんな出来事を通して、それでいいのか、答え合わせを繰り返していくんです。雄介は万能ではないし失敗もしますが、経験を積みながら自分の意志で将来を選択し、居場所を作っていってほしいなと思いながら書きました」
成長物語として読ませる第二部。最後の一文からは、雄介の決意と、さまざまな思いが読み取れて、万感の思いがこみあげる。
二百海里水域問題や牛肉・オレンジ問題。ソ連による漁船の拿捕など、昭和の頃によく見聞きした時事問題もさりげなく盛り込まれ、この土地だからこその昭和史も感じさせる本作を書き上げた河﨑さん。専業作家となったことで、執筆環境に変化はあったのだろうか。
「ずいぶん身体は楽になりました。ただ、専業になってやりたかったことのひとつに長期の取材があったんですが、タイミング悪くコロナ禍になってしまったのでそれができなくて。今後落ち着けば、そうしたことをやりたいですね。息長く書いていくために、いろんなことをインプットしていきたいです」
河﨑秋子(かわさき・あきこ)
1979年北海道別海町生まれ。2012年「東陬遺事」で第46回北海道新聞文学賞(創作・評論部門)受賞。14年『颶風の王』で三浦綾子文学賞、16年同作でJRA賞馬事文化賞、19年『肉弾』で第21回大藪春彦賞を受賞。20年『土に贖う』で第39回新田次郎文学賞を受賞。他書に『鳩護』がある。
(文・取材/瀧井朝世)
〈「WEBきらら」2022年1月号掲載〉






