南原 詠さん『特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来』
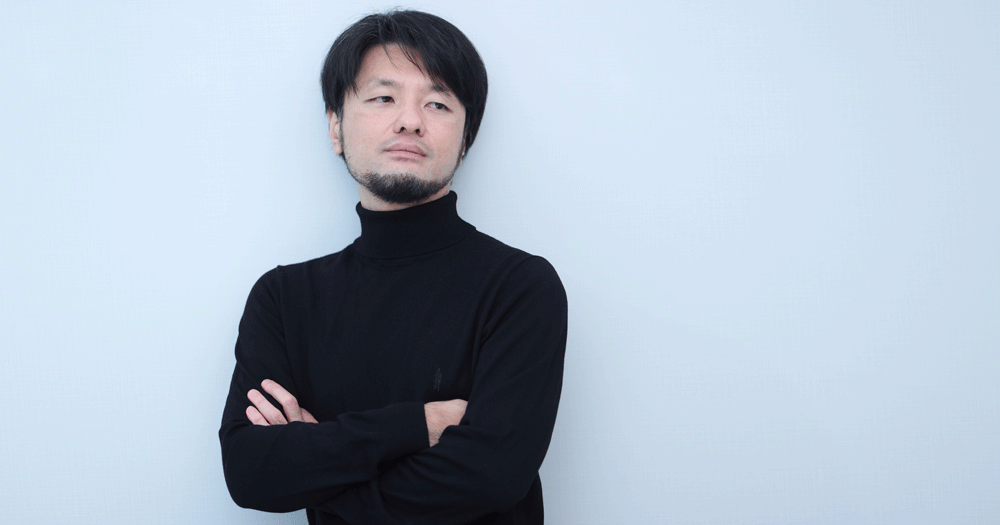
ふと、ここに好き勝手に物語を書いてみたいなと思ったんです
第20回を迎えた『このミステリーがすごい!』大賞。昨年大賞を受賞したのは、現役弁理士の南原詠さんだ。自身と同じ職業、しかしまったく異なるキャラクターを主人公とした『特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来』は、特許権侵害をめぐる難題に挑む女性の奮闘を描く一作である。
現役弁理士が書いた、特許問題を扱ったエンターテインメント
「8年前、弁理士の試験に合格し、研修が終わったその日から小説を書き始めて投稿を続けてきました」
と語るのは、昨年第20回『このミステリーがすごい!』大賞で大賞を受賞した南原詠さん。弁理士とは特許や商標など知的財産の出願や利用に関わる業務を行うスペシャリストで、南原さんは現在、現役の企業内弁理士だ。受賞作『特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来』(応募時のタイトルは「バーチャリティ・フォール」)は、敏腕弁理士の女性が難しい案件に挑む痛快な一作である。
弁理士の大鳳未来が弁護士の姚愁林と組んで設立した《ミスルトウ特許法律事務所》は、特許権侵害を警告された企業を守ることを専門としている。東奔西走の日々を送る彼女の許にある時舞い込んだのは、人気 VTuber、天ノ川トリィが映像技術の特許権侵害を警告されたという案件。
「それまでも特許を題材にした小説を書いていましたが、純粋な法律論争みたいな話ばかりだったんです。でも『アイデアは交差点から生まれる イノベーションを量産する「メディチ・エフェクト」の起こし方』という本を読んだら、アイデアは掛け算が源泉だ、ということが書かれてあって。それで特許と何かを掛け合わせてみようと思い、時事ネタとして思い浮かんだのが VTuber や5Gでした。実際、会社の仕事で仮想現実や5Gの技術について取り扱ったこともあって知識はあったんです。もちろん企業秘密を書くわけにはいきませんが、公開されている情報を組み合わせて考えていきました」
凄腕なのは確かだが、勝気で強引、時には限りなくグレーな荒技に出ることもある大鳳未来。彼女に負けずとんでもなくパワフルなのが天ノ川トリィだ。VTuber の映像と同じ容姿の持ち主で、歌唱力も身体能力も抜群だが、いったん怒りだしたら手がつけられない彼女。この、未来とトリィが実に魅力的。これまでも執筆した小説の主人公はほぼ女性だという。
「はじめて書いた小説の主人公は高校生の男の子だったんですが、読んだ人みんなから〝なよなよしている〟と言われたんです。どうも自分が男性を書くと内向きなキャラクターになるようです。でも、それだと物語を引っ張っていけない。それであえて女性を主人公にしてみたら、書きやすかった。何も知らないから書けるところがあるんでしょうね。主人公はパワフルであってほしいし、何かを引っ張っていってほしいので、自然と強気なキャラクターになります」
2人の女性がぶつかりあいながらも距離を縮めていく様子も読みどころ。「人物描写が苦手なので、下手なことを書いても興ざめだと思ってあえてあまり書かなかった」と言うが、素直になれない人間同士だからこそ、互いへの信頼を安易に口にしないほうが自然に思える。
「天ノ川トリィは『メタルギアソリッド』や『シャドウ・コンプレックス』といったゲームの映像の影響もあり、砂漠に並んだ戦車から砲撃を受けても無傷で歩きながら歌う女性のイメージが最初に出てきました。知らないことのほうが書けるというのは VTuber についても同じで、仕組みなどについて書かれた新書を3、4冊読んだくらいで、動画はそれほど見ませんでした。見てしまうと書けない気がしたんです」
トリィが使用していた撮影システムの機材が特許権侵害の警告を受けたものの、それを使わなければ動画はクオリティを保てない。では彼女は機材をどこで入手したのか。本人いわく、なんとフリマサイトだという。出品者の正体は分からず、完全に不利な状況のなか、未来は出品者や撮影システムの内容、そして警告主の背景について調べていくこととなる。
「特許の問題に関しては、分かりやすいものを選びました。実は弁理士の間では常識で、試験にも出たことがある案件です」
トリィが所属する事務所の社長や、警告主の企業の社長などもキャラクターが立っており、また、出番は少ないものの未来の相棒の姚愁林や、周辺調査を依頼する3人の男性もサイドストーリーが作れそうなほど存在感を残す。
「最初に登場する技術コンサルタントの新堂は、エンジニアなら知らない人はいない《ARM》社というCPUの設計図を売っている会社の元エンジニアという設定です。VTuber にやたら詳しいことにしたので、オタクっぽい感じになりました。2番目に登場する情報サービス会社の磯西は、実際に私の勤め先にものすごく特許関係の文献調査が上手い人がいて、その人がベースにあります。場合によっては依頼して1時間くらいで資料を見つけてくるんです。3人目の夏目は興信所の所長で、探偵といえば探偵ですね。私は経験がありませんが、特許の背後関係を調べてもらうために興信所に依頼することはあります」
答案用紙を眺めるうちに小説が書きたくなった
なぜ現役弁理士が小説を書き始めたのか。もともと南原さんは、企業のエンジニアだったという。
「大学院で半導体工学の研究をしていたんですが、開発のほうが向いていると感じて電機メーカーに就職し、回路設計のエンジニアとして3年くらい働いていました。でも、どうも自分にはセンスがないなと思って。30歳手前で自分のキャリアパスについて考えていた頃、特許の業界を知りました。調べてみると、エンジニアから知的財産の世界に舵を切るのは〝理系の裏の王道〟と言われているくらいよくあることらしくて(笑)。それで、弁理士の国家資格を取るための勉強を始めたんです」
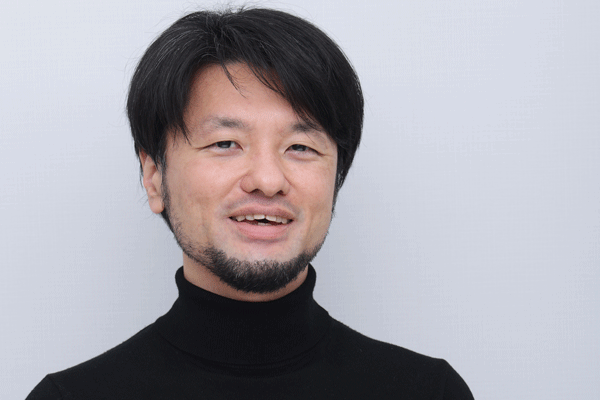
受験のための予備校にも通い、社内では知的財産の部署に異動した。
「昔から問題を解くのは好きでした。後から考えると特許の事例問題って、ある意味ミステリに似ているんです。何年何月何日にA社が特許を出願して、その後何年何月何日にB社がこういう出願をして……と、アリバイ崩しのように時系列を確認していくパズル的なところがありました」
だが、もともと弁理士試験の合格率は高くはない。そのうえ、政府の方針で試験内容が自身にとっては苦手な傾向に変化するなど、苦労した。また、論文試験で「個性を出すな」と強く教えられたことも窮屈だった。
「基本的には最高裁の判例を一言一句暗記して書かなければいけない。手垢のついた表現しか駄目で、同じ意味の言葉であっても、言い換えてはいけないんです。それが自分にとってはめちゃくちゃきつくて。答案練習をしていて、ふと、ここに好き勝手に物語を書いてみたいなと思ったんです」
その頃、池井戸潤さんが『下町ロケット』で直木賞を受賞して話題になった。
「特許の話だと私の周辺でも話題になり、読んでみたんです。たしかに特許の国内優先権の話でしたが、分かりやすくするためにそこまで法律には踏み込んでいないと感じて。それで、ひょっとしてもっと専門的なところで物語を作れるんじゃないかと思いました。でもそうした小説を書くなら専門家としての資格をちゃんととらなければと思い、頑張ってその年の試験に受かり、研修が終わったと同時に若桜木虔先生の小説講座に申し込んで小説を書き始めました」
それからはずっと、特許や商標を題材とした小説を書き続けた。7年間で新人賞に応募したのは11作。間口が広そうな『このミステリーがすごい!』大賞への応募回数が一番多かったが、最終選考まで残ったのは今回の作品がはじめてだったという。それまでとは何が違ったのか。
「今までは最後の解決策をしっかり考えずに書き始めていたんですが、今回は2か月かけてプロットを組み立てました。それと、はじめてシナリオ作成時の鉄則と言われていることを忠実にやってみたんです。序盤で説明的にならずに特許のルールなどを盛り込み、中間で重要なイベントとなるミッドポイントを入れて話を転がして、切り札となる解決策を作って……。そうすれば山も谷もある話になるなと思いました」
分かりやすく伝えるための大改稿
執筆方法はユニークで、まず先に台詞を全部書き出し、その後で地の文で繫げていくという。応募時の原稿は専門用語や法律の説明があまりに細かく、選考の過程で「難しい」「分かりにくい」という声も多かった。
「新しいマーケットを切り拓くくらいのつもりだったので、一般読者を想定せず、現役の弁理士が読んでも問題がないくらいかっちり書き込んだんです。キャズム の理論では、市場で製品が広まっていく過程には、新しいものに手を出そうとするアーリーアダプターがいて、その後にすでに広まってきたものを取り入れるアーリーマジョリティがいる。選考委員はアーリーアダプターだから、一般受けする・しないとは別の価値を見つけてくれると思ったんです。ある意味チャレンジでした」
その難解さがマイナス評価であったものの、ストーリーやキャラクターの魅力で加点されて受賞に至ったのだから、危ない橋を渡ったともいえる。もちろん、書籍化にあたって大幅に改稿した。
「もともと、受賞したら分かりやすく書き直すつもりでした。でもまさか、あんなにオミットすることになるとは(苦笑)。宝島社の局長に、〝分かる人が分かればいいと思って書いていませんか?〟と言われて、確かにそういうところがあったなと気づきました。指摘はありがたかったです。そこから、正確性よりも分かりやすさを優先して、〝専用実施権〟という言葉を〝ライセンス〟にするなど専門用語を全部書き直しました。想像していないところまで直すことになり、自分はどこまで分かりやすくすれば伝わるのか理解していなかったんだなと、勉強になりました」
本作の反響次第ではあるが、今後も大鳳未来の活躍を書いてシリーズ化していきたいという。また、会社勤務は続けるつもりだ。
「仕事で得た知識を小説に活かせるし、小説を書くために調べた法律的知識を仕事に活かすこともできる。いいサイクルになるんじゃないかと思っています」
南原 詠(なんばら・えい)
1980年生まれ。東京都目黒区出身。東京工業大学大学院修士課程修了。元エンジニア。現在は企業内弁理士として勤務。
(文・取材/瀧井朝世 撮影/浅野剛)
〈「WEBきらら」2022年2月号掲載〉



