深緑野分さん『スタッフロール』
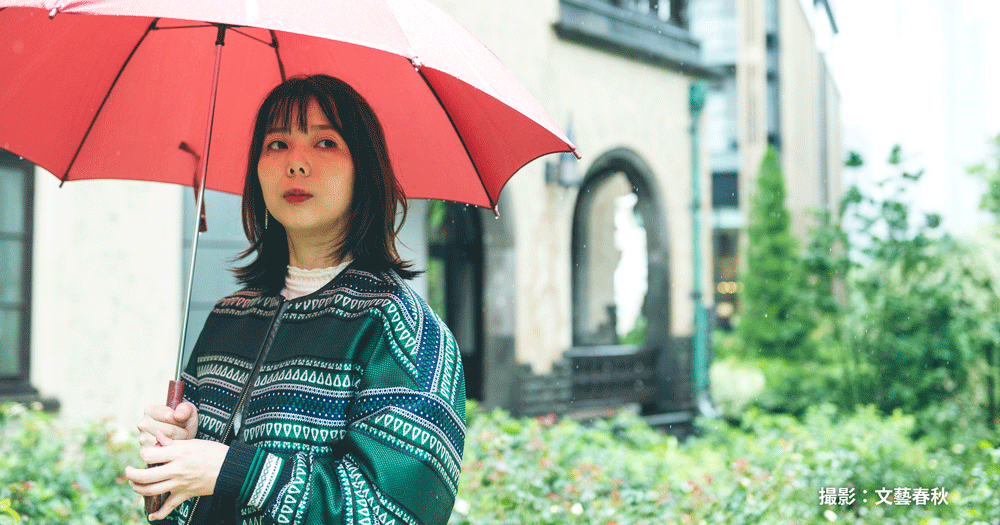
一生懸命働いた人のクレジットがないという問題は気になっていました
読み進めるうちに、名作映画の数々を観返したくなってくる。深緑野分さんの新作長篇『スタッフロール』は、映画愛にあふれる一作だ。80年代のハリウッドで活躍した特殊造形師と、現代のロンドンで働くCGクリエイター。映像に夢を託した2人の女性の情熱と葛藤、不思議な縁を描いた作品だ。
特殊造形とCG。映像技術に魅せられた2人の女性
映画好きとしても知られる深緑野分さん。新作『スタッフロール』はそんな彼女の映画愛と、クリエイターたちへの敬意が詰まった長篇だ。
「『戦場のコックたち』を書いた直後に編集者から声をかけていただいて、確か、〝映画の話はどうですか〟と言ってもらったんです。それで、自分は映画の何が好きなのかを考え直してみました。そもそも最初に映画っていいなと思わせてくれたのは人形師のジム・ヘンソンだし、やっぱり自分は特殊造形や特殊メーキャップやCGなどの特殊効果が好きだな、と思いました。振り返ってみると、そういう人について書いたものもあまりないな、とも気づいたんです」
ちなみにジム・ヘンソンは『セサミストリート』のパペットや映画『ラビリンス/魔王の迷宮』、テレビシリーズ『ジム・ヘンソンのストーリーテラー』などで知られる人物だ。
本作の主人公は2人いる。前半の主人公は、第二次世界大戦直後にアメリカで生まれたマチルダ・セジウィック。幼い頃に犬の影絵を見て怪物だと信じて怯えた体験が強烈に心に刻まれている彼女は、やがて映画に魅せられ、父親の反対を振り切って特殊造形師に弟子入りする。
後半の主人公は、現代のロンドンに暮らすヴィヴィアン・メリル。特殊造形を含め、映画の視覚効果全般を愛して育った彼女は、現在はCGの制作会社に勤務し、アニメーターとして働いている。
「特殊造形とCG、どちらかを贔屓することはしたくなかったので、最初から主人公は2人にすると決めていました。〝特殊造形といえばハリウッド〟という時代が長かったですから、マチルダのパートはアメリカを舞台にしました。ヴィヴィアンのパートは、2000年代に入ってからはロンドンやバンクーバーなど海外の会社にCG制作を委託することが増えたと聞いていたことと、自分が何回か行っているので書きやすいということから、ロンドンを舞台にしました」
彼女たちの人物造形に関しては、対比が出るように考えたという。マチルダは幼い頃に見た怪物の影をどこまでも愚直に追い求め、ヴィヴィアンは組織の中で実績を残しているものの自信がなく、体力的にも疲弊している。
「マチルダは真面目でおとなしくて、無垢な感じ。夢見がちなところがありますね。ヴィヴィアンは現代っ子で活発。ただ、書いている当時の自分の心理状態と重ねたところがあって、悩みを抱えています。連載当時は2人の章を交互に進めていたんですが、マチルダのほうがすごく人気があったんですよ。なので、ヴィヴィアン負けるな、と思いながら書いている部分がありました(笑)」
映画業界&技術の変遷も読みどころ
長い時間が描かれた物語なだけに、時代の移り変わりが見えてくるのも読みどころだ。
「マチルダに関しては、80年代のハリウッドの特殊造形全盛期に30代になるように逆算して生まれた年を決めました。マッカーシズムやベトナム戦争といった政治的な背景が映画界にも影響を及ぼしているので、そのことを頭に置いて書き進めていきました」
もちろん、映画業界の変化もよく分かる。マチルダが師匠に弟子入りした頃、映画の流行は社会派作品や諷刺コメディ、スパイものなどで、特殊メイクや特殊造形を使ったSFやホラー作品の地位は高いとはいえない状況だった模様。だが1968年に『2001年:宇宙の旅』、1977年には『スター・ウォーズ』が公開され、80年代のハリウッドでは特殊効果を駆使したSFやホラーが大流行する。だが、ほどなくCG技術が注目されるように。それは当然、マチルダに衝撃を与える。
深緑さん自身は、特殊造形もCGも好きだという。
「どっちが優れているかということではない、という点はすごく考えながら書きました。ただ、技術が進むなかで現場の人たちは職を追われたりするわけで、必ずしも発展=正義とはならないのは事実。それに取材をしていくなかで、特殊造形に携わる人はCGに対して思うところがいろいろあるんだなという印象も受けました。実際、今の技術ではどうしてもCGは画面から浮いて見えたりするし、鑑賞者からは特殊造形の映像のほうが愛着を抱かれやすいし、評価も高い傾向がある。CGはいろんなところで使われているのに、軽んじられているように感じます。私はどちらも均等に好きですが、そうした不憫さがあって、〝CG頑張れ〟という気持ちです(笑)。それに、今CGに携わっている人たちに取材すると、子どもの頃から特殊造形がすごく好きだったから映画業界に入ったけれど、今はこういう時代だからCGをやっている、という方が多いんです。そういう人たちの苦しさみたいなものも書きたいと思いました。基本的には、読み終わった時に、どちらもいいものだなって思ってもらえたら嬉しいです」
タイトルにこめた思い
粘土やゴム、合成樹脂などを使っての特殊造形の創作や、コンピュータを駆使したCG制作の場面も分かりやすく、興味深く読ませる。後者に関しては相当苦労したという。
「そもそも私はコンピュータのことが全然分かっていないんです。もちろん事前に取材もしたし勉強もしましたが、座標など数学の知識も必要だったりして、完全に情報をインストールできたとは言いづらい。それに置き換えのできない専門用語があまりにも多く、作業過程をきちんと説明しようとするとものすごく長くなってしまうんです。それをどこまで引き算したり、分かりやすい言葉にして書くかが、ものすごく難しかったです。取材でお世話になった方々に後から〝ここは違う〟などと?られそうで、戦々恐々としているところです」
実在の作品やクリエイターたちの名前も多数登場する。そのなかで、同一人物が数々の有名作品に関わっていることも多く、改めて驚かされる。たとえばリズ・ムーア。彼女は10代の頃に『2001年:宇宙の旅』のラストシーンに登場するスター・チャイルドを造形したが、映画のクレジットにその名前はない。その後、『時計じかけのオレンジ』でも才能を発揮、『スター・ウォーズ』ではストームトルーパーの原型を手掛けたものの作品の完成前に交通事故で亡くなってしまっている。
最初から決めていたという本作のタイトルからは、こうしたクリエイターたちへの想いが感じられる。
「本来はエンドクレジットと呼ぶのが正しいと思いますが、〝スタッフロール〟としたほうが読者にピンときてもらいやすいと考えてこのタイトルにしました。私は子どもの頃、親から映画館ではエンドクレジットが終わるまで席を立つなと言われて育ったんです。〝なぜ?〟と訊いたら、〝スタッフの人たちに対する敬意だ〟って言われました。それを人に強要する気はなくて、途中で帰りたい人は帰っていいと思っていますが、個人的には親の言うことになるほどなと納得しているんです。だから、リズ・ムーアもそうですが、一生懸命働いた人のクレジットがないという問題は気になっていました。もちろん、当時はエンドクレジットをそこまで長くはできなかったという事情もあるし、現代ではスタッフの数が膨大になりすぎてどこまで載せるかという問題があると思いますが、でも、重要な部分に関わっている人がクレジットすらされないというのは正当ではないな、と感じています」
ライバルはあの名監督?
架空の映画作品も登場する。なかでも重要なのが、80年代に作られた子ども向け映画『レジェンド・オブ・ストレンジャー』。いじめられっ子の少女が犬の頭を生やした漆黒のクリーチャー、Xを召喚してしまい、魔法を使えるようになったことから次第に暴走していく。これまでも少女を助けてきた主人公の少年は、仲間とともに少女とXを止めようとするのだが……というストーリーで、現代においてそのリメイク版の話が持ち上がる。
「『グーニーズ』が流行っていた時代にいかにもありそうな話を考えました。80年代だったら異形のものを元の世界に送り返すというのが定番の展開ですが、リメイク版では現代らしい結末に変えることにしました」
作中、リメイク版を手掛けるアンヘル・ポサダ監督は、どこか『シェイプ・オブ・ウォーター』などのギレルモ・デル・トロ監督を彷彿させる。
「そうです、ギレルモです。私がめちゃくちゃライバル視している映画監督です(笑)。あの監督は、私がやりたいことを全部やっていて腹が立ちます。私は中学生の頃から『ロスト・チルドレン』や『デリカテッセン』のジャン゠ピエール・ジュネ監督がずっと好きで、ジュネ作品に出ている俳優のロン・パールマンもすごく好きなんです。ギレルモは、そのロン・パールマンを起用するんですよ。他にも明らかにジュネやテリー・ギリアムのダーク・ファンタジーへのオマージュを作品に紛れ込ませるので、そこに腹が立ちます。まあ、ツイッターもフォローしているし画集も買っていますけれど(笑)」
つまりはそれだけギレルモ作品が好きだということなのでは、と訊くと「ツンデレなんです(笑)」と、深緑さん。ポサダ監督による『レジェンド・オブ・ストレンジャー』が観たくなった、と伝えると、
「私は作中でポサダ作品としてちょっとだけ言及している『親指姫』が観たいなと思っているんです。アンデルセンの童話を大胆に脚色したという設定で、王子様との結婚でハッピーエンドとなるのではなく、結婚を破棄した親指姫がツバメの背に乗って旅に出る話なんです。そちらのほうがギレルモっぽい気がします」
ギレルモに対抗すべく、ご自身もまた今後ダーク・ファンタジー長篇は書かないのだろうか。
「まだ自分の趣味全開のものを書けていないので、いつかできたらいいなと思います。ギレルモはオマージュを盛り込んでいますけれど、私は完全オリジナルでやります(笑)」
目下取り掛かっているのは、ブレジネフ時代のソ連を舞台にしたミステリーと、『カミサマはそういない』に収録された「新しい音楽、海賊ラジオ」の世界設定を活かした長篇だという。趣味全開のダーク・ファンタジーはもちろん、そちらの2作も楽しみに待ちたい。
深緑野分(ふかみどり・のわき)
1983年神奈川県生まれ。2010年「オーブランの少女」でミステリーズ!新人賞佳作に入選。13年に入選作を表題作とした短編集でデビュー。著書に『戦場のコックたち』『ベルリンは晴れているか』『この本を盗む者は』など。
(文・取材/瀧井朝世)
〈「WEBきらら」2022年5月号掲載〉




