小西マサテルさん『名探偵のままでいて』
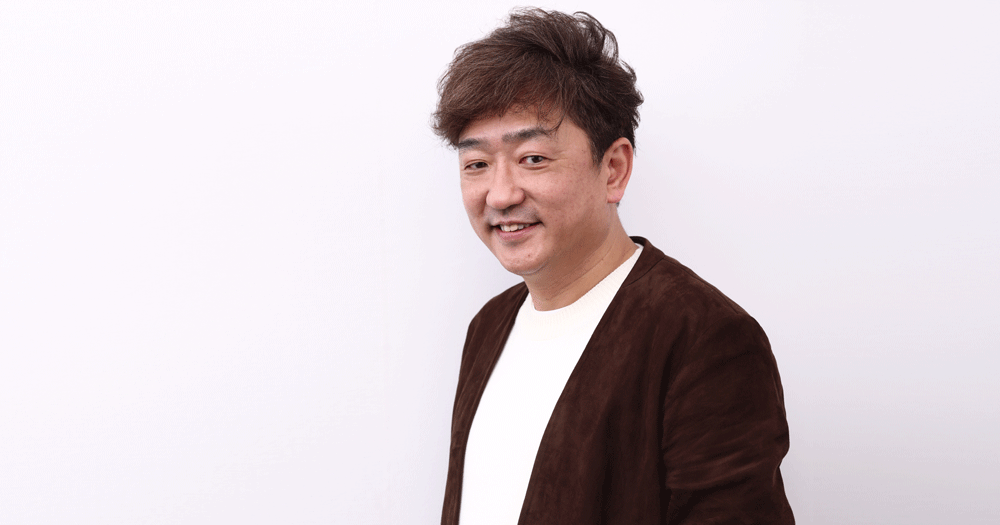
こういう病気もあるんだよ、ともっと世間に知ってもらいたかった
第二十一回『このミステリーがすごい!』大賞で大賞を受賞した小西マサテルさんの『名探偵のままでいて』が評判だ。教師の孫が持ち込む謎を、認知症の祖父が名推理で解き明かす安楽椅子探偵もの。レビー小体型認知症という聞きなれない病気を題材にしたのは、ご自身の実体験がもとにあったという。
おじいちゃんは幻視する安楽椅子探偵
第二十一回『このミステリーがすごい!』大賞の大賞受賞作『名探偵のままでいて』は、ミステリ好きの小学校教師・楓が遭遇した謎を、レビー小体型認知症の祖父が解き明かす安楽椅子探偵もの。著者の小西マサテルさんは、ラジオ番組「ナインティナインのオールナイトニッポン」などを手掛ける放送作家だ。じつは幼い頃からミステリ読みだったという。
「ルパンとホームズに始まり、コーネル・ウールリッチ、アガサ・クリスティ、E・S・ガードナー、セバスチアン・ジャプリゾ、イアン・フレミングを読み……。海外ミステリが大好きでした。でもミステリ作家になりたいというより、名探偵になりたかったんです。小学生の頃、地元である香川県内の探偵事務所に電話して〝少年探偵団に入れてください〟と言ったこともありました(笑)。高校生くらいになると、名探偵ものを書いて人に見せたりもしていました」
本腰を入れて小説を書いたのは今回がはじめてだという。そのきっかけは?
「一番大きかったのは、勅使川原昭さんですね。現在ニッポン放送プロジェクトの常務取締役の方で、昔一緒にラジオ番組を担当していたことがあるんです。まさにラジオマンという印象の方ですが、志賀晃というペンネームで『このミス』大賞の隠し玉として『スマホを落としただけなのに』でデビューして、大ヒットした。読んだら本当に面白くて、傑作だと思いました。それで自分の中で、ふつふつとミステリ熱がわきあがってきたんです」
もうひとつのきっかけは、父親の死だ。
「父はレビー小体型認知症を六、七年患い、コロナ禍の直前に誤嚥性肺炎で亡くなりました。母は僕が中二の時に亡くなっているので、父はずっと香川で一人で暮らしていたんですが、最後の四年くらいは東京に呼び寄せ、家から五分くらいの施設に入ってもらったんです。そこから一年三六五日のうち僕は三五〇日通い、妻は三六五日全部通ってくれました。香川にいた頃は一日誰とも喋らない日があったそうなんですが、東京に来て僕や妻や孫と会話をしていたら、ドラスティックによくなったんです。自分が病気だと理解する、つまり病識ができて本人もすごく楽になったようでした。お薬の配合が父に合ったということもありますが、一番効いたのはやはり、会話だと思います」
レビー小体型認知症の大きな特徴は、幻視があることだという。本作でも、祖父が「青い虎が入ってきた」と言ったり、「血まみれの楓がここに倒れている」と言い出すエピソードがあるが、それは小西さんの実体験だという。
「父は毎朝起きると、口を開けた虎が見えたようです。本人は本当に怖かったと思います。でもこれは病気なんだと自覚してからは、虎も幻視だと認識していたようです」
お父さんの当時の日記には、毎日のように「無視」という言葉が書きこまれている。目の前に虎が出てきても「無視」、というわけだ。
「父らしいなと思うのは、長年タイガースのファンなのに〝これ以上虎が出てきたらもう阪神応援せえへんぞ〟とか、〝巨人ファンやったら兎だったから、もうちょっと楽やったのにな〟と言って僕や妻を笑わせるんです。最後の二年くらいは幻視もなくなり、頭もしっかりして、それはもう、本当に安らかに旅立ちました。そういう姿を見てきたからこそ、認知症という言葉ではくくりきれないものがある、という実感がありました。お医者さんでもレビー小体型認知症に詳しくない方もいましたから、こういう病気もあるんだよ、ともっと世間に知ってもらいたかった。でも、患者でも専門家でもない僕がノンフィクションを書いても誰も読んでくれない。僕がやるならミステリだと思いました。もうひとつ小説を書いた理由を挙げるとするなら、コロナ禍に入って仕事もリモートが増えて、ちょっと時間がとれるようになったんですよね。それで挑戦する気になりました」
お父さんは昔から笑いのセンスがあったのだそう。
「父一人子一人だから、笑わないとやっていけないんですよ。お互いに弁当を作るんですが、父親はご飯にツナ缶をドーン、僕はご飯に塩サバをドーン。それで点数をつけあって笑っていました。父は当時ステータスだったクラウンという車に乗っていたんですが、CMで〝いつかはクラウン〟というキャッチコピーが流れるたびに、〝わしは前からクラウンや〟って返してました(笑)。面白い人だったんです」
先行作品へのオマージュをたっぷりこめて
楓の祖父は早稲田大学のワセダミステリクラブ出身のミステリ好きで、元小学校校長の紳士然とした人物だ。
「自分が好きだった海外の名探偵、名刑事のキャラクターから醸成されたキャラクターですね。ホームズとかフェル博士とか刑事コロンボとか。ポワロも入っていると思います」
主人公である孫を女性にしたのは、
「父と息子だと男同士のせいか、なかなかお互いに本音を言わない。でも僕の父も、妻や孫には愛情を前面に出していたんですよ。それで、お互いにわかりやすく愛情を伝えあえるのは祖父と孫娘かなと考えました」
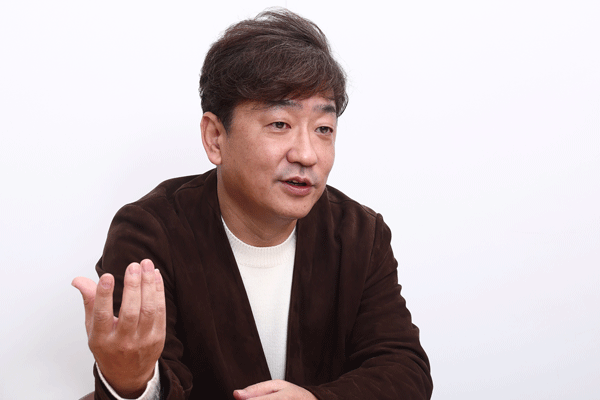
第一章では、楓がミステリ評論家、瀬戸川猛資氏の評論集を古書で購入したところなぜか四枚の切り抜き記事が挟まっていた、という謎が描かれる。
「まず第一章でフォーマットを作ろうと思い、なぜ幻視するのかという理論づけを含め書いてみました。僕はもともと書評が大好きで、瀬戸川さんの書評集『夜明けの睡魔 海外ミステリの新しい波』なんかは本家よりも面白いと思っています。瀬戸川さんとミステリの御三家であるクイーンとクリスティとカーがお茶を飲んでいる様子を書きたくて、こういう謎になりました」
第二章以降では、楓の同僚教師で料理好きな青年、岩田と、その友人で売れない劇団員の四季も物語に絡んでくる。岩田はどうやら楓に気があるようだ。
「岩田先生については、僕の友達にそっくりな奴がいるんです。元学校教師で、岩田先生のように『クッキングパパ』を全巻持っています(笑)。四季くんと好対照な存在になると思いました」
四季はというと、クラシカルなミステリを〈つくりものに過ぎない鋳物の中にさらにいくつかの鋳物が入っちゃっている〉と評し、〈マトリョーシカ・ミステリ〉と呼んで楓と口論となる。つまり、口論できるくらい、四季もミステリを読んでいるのである。
「四季くんは絶対出したかったんですよね。ただ内省的なだけの話にはしたくなかったんですが、こういう存在がいると主人公も饒舌になってくれる。彼が言うように、古典的な海外ミステリを読んでいるとツッコミたくなることはあるんですよね。でも僕は、マトリョーシカであっても面白いからいいんじゃないかと思っています」
第二章では密室殺人、第三章では人間消失と、ミステリ好きにはお馴染みの謎が描かれていく。第四章は萩尾望都の漫画『11人いる!』へのオマージュ、第五章は、殺人の容疑をかけられた青年が、自分のアリバイを証明する女性を探しまわるウイリアム・アイリッシュの『幻の女』がモチーフである。
「『11人いる!』は傑作SFミステリなので入れたかった。アイリッシュも大好きな作家です。『幻の女』を入れたのは、安楽椅子探偵ものの話ばかり続くと読者が飽きそうなので、登場人物たちが室内から外に出ることで動きをつけたい、という意図もありました」
終章で扱うのはリドル・ストーリー。謎に対する答えを明かさないまま終わる話のことで、F・R・ストックトンの「女か虎か?」という有名短篇が作中にも登場する。さらに最後にも読者に対して、あるリドルを提示してくる展開だ。
「『女か虎か?』をただ紹介するだけでなく、出来がいいか悪いかは別として新解釈を入れたかったんです。ただ、読んでくれた方の感想を聞くと、リドル・ストーリーというもの自体がわからない人も多いみたいで……(苦笑)」
ミステリの先行作品への愛と敬意を詰め込みながら、楓と岩田と四季のなんともキュートな関係性や、祖父の病状や受けるケアについて丁寧に盛り込んだ本作。
「レビー小体型認知症については本当は悲しいこともたくさんありましたが、完全なリアリティは求められていないだろうから抑制をきかせました。以前、明石家さんまさんに教えられたことがあって。さんまさんのお祖父さんは家族の中で一番面白くてギャグのセンスも最高だったそうなんですが、歳をとってから庭に干したTシャツにペコペコしてたんだそうです。うちの父と同じだと思ってドキリとしましたが、さんまさんはそれを笑いにして喋るんですよ。笑いものにしているのではなく、これで笑いがとれたらじいちゃんも本望だろう、という意味合いの話しぶりなんです。陰々滅々にとらえて隠すのではなく、テクニックがともなえば笑いやミステリにしてもいいんじゃないかと思えました」
落研、漫才師、放送作家、そして小説家デビュー
相当なミステリ好きだった小西さんが、なぜ放送作家になったのか。
「高校でミステリ研究会に入ろうと思ったら、そんなものなかったんですよ。それでオリエンテーションで各部活を見て回ろうとしたら、ひとつの教室から大爆笑が聞こえてくる。入ったら、机ふたつをくっつけた上に座布団を敷いて、着物で落語やっている人がいる。それが南原清隆さんだったんです。爆笑に次ぐ爆笑でした。僕はそこではじめて落語を知ったんですが、落語とミステリって、発端の意外性、中盤の急展開、綺麗なオチという構造が似ていると思いました。それで落研に入り、高校時代は落語とミステリ漬けでした。南原さんの背中を追いかける形で大学進学で東京に来て、ウッチャンナンチャンが先にデビューして、僕も田舎にいた頃から一緒にお笑いやっていた奴と漫才で『お笑いスター誕生!!』というオーディション番組に出たら受かったんですね。当時はバブルだったので営業の仕事も多かったんです。六本木のショーパブでパイを一枚ぶつけられるごとに千円もらう仕事もあり、一日で五〇枚くらいぶつけられていました。でも僕が大学四年の時に相方が就職しちゃったんです。宙ぶらりんの状態になっていたら、コント赤信号の渡辺正行さんがご自身のラジオ番組に放送作家として入れてくれた。そして現在に至ります」
その間、漫画のノベライズを手掛けたこともあった。ミステリ小説を書きたいとは思わなかったのだろうか。
「逆にハードルが高くなりました。放送作家をやっていると、駄文でもお金になる。文学賞に挑戦するとなると、99.9%、それは一銭にもならない。それでなかなか踏ん切りがつかなかったんです」
放送作家と小説家、二足の草鞋となった今、どちらの仕事も「全力でやっていくだけです」と小西さん。本作でもクスリと笑える場面が多々あるが、長年お笑いと関わってきただけに、コミカルなミステリも書けるのでは?
「やってみたいですね。コミカルな部分もあるけれど実は陰を帯びている話が好きです。映画でいうと、『愛と追憶の日々』とか。笑った後の涙って、より熱くなりますから」
次作は、本作の続篇を準備中だという。「最後のリドルはどうなるのか」と訊いてみると、「まあ、『女か虎か?』にも『三日月刀の促進士』という続篇がありますからね(笑)」とのこと。それは気になる……!
小西マサテル(こにし・まさてる)
香川県高松市出身。東京都在住。明治大学在学中より放送作家として活躍。ラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』『徳光和夫 とくモリ!歌謡サタデー』『笑福亭鶴光のオールナイトニッポン.TV@J:COM』『明石家さんま オールニッポン お願い!リクエスト』や単独ライブ『南原清隆のつれづれ発表会』などのメイン構成を担当。
趣味・特技は落語。
(文・取材/瀧井朝世 撮影/浅野 剛)
〈「WEBきらら」2023年3月号掲載〉


