上田岳弘さん『最愛の』*PickUPインタビュー*

現代社会を活写した恋愛小説に挑む
著者初の本格的恋愛小説
デビュー10周年を迎えた上田岳弘さん。これまでSF要素をまじえたスケールの大きな作品を多く発表してきたが、最新作『最愛の』は意外にもリアリズムで描かれた恋愛小説である。
「今回はSF要素を使わず、完全なリアリズムの小説です。裏テーマとしてある程度読みやすいものにする方向で自分の技術を使いたいと思いました。『私の恋人』という小説でも要素として恋愛を扱いましたが、本格的な恋愛小説を書いたことはなく、書きこぼしている感覚がありました。それと、『ニムロッド』では感情を排除した、恋愛かどうかよくわからない関係を書きましたが、あれはあまりエモくないなと思っていて(笑)。これまで感情を伴わない合理的な付き合いを書いてきましたが、そうはいっても人間には二面性がある。合理的な関係の裏には表出していない感情があって、それを長篇なら書き切れるんじゃないかと思いました。僕は合理的に生きていると思われがちかもしれませんが、実は割とエモーショナルに生きているタイプです(笑)。その部分をパッケージ化して、こちら側もありますよ、みたいな作品を書いておかないとバランスが悪い気がしていました」
表出しない感情を書こうと思った時に、恋愛を選んだのはどうしてか。
「個人の小さな物語としては一番身近なものだと思うので。僕は1979年生まれで、トレンディードラマ全盛期の後半に青春時代を過ごしてきました。だんだんそういうドラマがなくなり、たとえば童話のように王子様と結ばれてめでたし、という話は幻想だという感覚が強くなってきた。むしろ現代は、恋慕と性的な回路を切り分けて処理している人が増えている気がします。リスクを負わない合理的な生き方が常識となってきた中で、恋愛はあまり意味がある物語と思われていない。他人からは取るに足らない、個人の小さな物語なんですよね。そういった小さな物語をこの時代にきちんと描くことは、合理主義がすべてを陵駕するようなご時世に対する抗いになるんじゃないか。そう考えて個人の小さな物語としての恋愛をやってみることにしたんです」
現代に生きる人々を描く
「現代社会の人々を活写したいという思いもありました」と上田さん。主人公であり物語の語り手である久島は、外資系の通信機器メーカーに勤務する38歳の男。会社の本社機能が恵比寿から八王子に移転し、彼は渋谷のビルの高層階のコワーキングスぺースで働いている。
「30代後半にしたのは、ギリギリ自分に構っていられる年齢かな、と思ったから。青春の終わりのような感覚です。40歳をこえて〝昔のあれが忘れられない〟というのはなんとなく僕の肌感に合わなかった」
自身でも〈現実への適合だけはうまい〉といい、すべて合理的にそつなくこなす久島は、私生活では既婚者の渚と逢瀬を重ねている。だがつねに心のどこかに存在しているのは中学校で出会い、大学時代まで手紙を交わしていた望未だ。事故に遭い遠くへ越していった彼女からの手紙はいつも「最愛の」という呼びかけで始まり、そして「いつか私のことは忘れて欲しい」と綴られていた。
久島の学生時代の回想や、望未からの手紙などを挟みつつ、望未にいったい何があったのか、謎や違和感を読者に覚えさせながら物語は進む。
「時系列が交錯するので、読みやすいように配慮しました。早いうちに意外な事実を明かして違和感や緊張感を与えたのは、ページターナーにする目的以外に、自分に対する無茶ぶりでもありました。早々に事実を明かして、それが自分に処理できるのかという。それと、僕は読むのも書くのもアンチクライマックスが好きなんです」
と、ご本人はおっしゃるが、終盤の真実が明かされる場面で読者の気持ちは否応なしに盛り上がるはず。
主人公をとりまく人々
個人的な恋愛感情を細やかに掘り下げるというよりは、久島の日常が丁寧に描写され、彼や周囲の人々の人生の物語となっている本作。
「現在の久島にとって望未はおとぎ話の世界の女性。別の女性とセックスもして彼女のことは忘れたつもりになっているけれど、心のどこかに残っている。性的なものと恋慕が乖離している状態です。一方、望未にとって久島は、その固有性がすごく好きだというよりも、ただ遠くにあって、自分を活かしてくれる存在だったように思います」

現代パートの久島はある夜、取引先の社長に連れられて夜の街をハシゴし、ある店で童話や小説に詳しい女性に出会う。ラプンツェルと名乗る彼女は実は大学院生だ。客の老人からお台場のタワーマンションの一室を与えられて暮らしていたが、その老人がコロナで亡くなり、今後のことはわからないという。
「いろんな女性の状況を描きたかった。性的なものだけでは解消できないものを生の声として入れ込んだ時に、どう読んでもらえるんだろうと思っていました。渚でいうと夫との家事分担がうまくいかない状況とか、ラプンツェルでいうと、自分に求められているものをちゃんとこなしているつもりで、こなしきれていないところとか。彼女は自分の立つ瀬を塔の下の世界、一般社会にはなかなか見いだせずにいる」
他にも、学生時代に久島が関係を持った女性が複数登場する。それにしても、久島って案外、モテるタイプ?
「いや、久島君は相手が寄っていくタイプではなくて、ちゃんと自分からいってるんです。そこは意識してちょいちょい描写しました(笑)」
また、久島が親しくなる男性たちも個性的だ。コワーキングスペースで出会い、意外な再会をする坂城、大学時代の飲み友達で、暇さえあればピアノの練習をしている先輩、同じく大学生時代に「友達になってほしい」と声をかけてきた、勉強も恋も非常に要領のいい向井。
「彼らは僕のいろんな友達から要素を抽出して書きました。久島君は自分は世の中に適合していると思っていますが、いちばんアジャストしているのは坂城さん。先輩や向井君はアジャストできないタイプ。そのはざまに久島くんがいて、両側から揺り動かされている」
向井などは要領がよすぎてアジャストできていない印象だ。
「何かを手に入れれば幸せ、というわけではないことはわりと共有された価値基準なので、それについてきちんと納得できる登場人物として作品の中で書いた、というのが向井君の位置付けかなと」
向井は、自分が若死にするなら27歳だがそんな綺麗には死ねないだろう、という言葉を繰り返す。27歳といえば、カート・コバーンら多くのミュージシャンがその年齢で亡くなったことで有名だが、上田さんはこの年齢にどのような印象を抱いているのか。
「若者でなくなるというか、将来を期待されなくなる年齢のような気がします。25歳くらいまでならフリーターでいても、今後すごいビッグになるかもしれないと言われる人もいるだろうけれど、27歳くらいまでにあまり変化がないとそう言われなくなる。久島君の大学時代のバイト仲間の女性が、自分が結婚するとしたらたぶん27歳と言っているのも同じ感覚です。まあ僕がデビューしたのは34歳なので矛盾してるんですけれど(笑)」
それとは別に、後半に黒石という老人の告白があり、その内容が強烈だ。
「黒石さんは傲慢な人間です。結構老人の登場人物のセオリーとして〝僕は失敗した〟と語る人が多くて、失敗しなかったと語る人ってほぼいないと思うんです。作中人物の中で、論理的後悔がないという人が出てきたら新鮮だろう、という気持ちもありました」
意識した先行作品
小説を書く前に、事前準備として戯曲や詩を書くこともある上田さん。実は本作のベースになったのは20歳過ぎの頃に書いた恋愛小説だそうだ。
「内容はちょっと変わっていますけれど、今回は20年前に書いた小説のリメイクといえます。特に過去パート、不幸な事故で相手がいなくなって、文通して……みたいなところは同じです」
また、本作の前半部分は、登場人物のシチュエーションなどに1987年発表の村上春樹作品『ノルウェイの森』を思い起こさせる部分があるのは確か(後半はまったく違った展開になります)。これは?
「僕がはじめて読んだ恋愛小説が『ノルウェイの森』だったので、原案というか、20年以上前に書き上げた初めての小説が基にあるという部分が強いのかなと思います。でも、やはり、当時と今は時代が違う。通信手段が手紙や電話だった時期は長くてそれでひとつの時代を作ったと思いますが、今はごっそり変わり、LINE やメールがあり、すれ違いが存在せず、連絡が戻ってこないのはただの拒絶。今は離婚率も3割を超え結婚しても合わなければ組み替えましょう、みたいな時代。SNSによってなんでもメタ化して見ることができ、自分にとって特別で大事なこともそれは勘違いで、ありがちなことだと思いながら生きざるをえない。そうしたことが『ノルウェイの森』の昭和の時代から比べると全然違ってきています。それはおのずと恋愛関係にも敷衍されているし、アップデートが必要な時期であろうと。そのなかで恋愛に重きを置いた、王道的なものを書きたい気持ちがありました」
同じモチーフを繰り返す理由
本作の執筆においては、他にも強く意識したことがあった。
「これまでに使った個人として大事にしてきたモチーフを全部出したかった。『旅のない』などの作品でも繰り返し書いてきたような、友達がオーバードーズするとか、CDを置いていなくなるとか、そのCDが決まって Nirvana と Radiohead だとか。これまでそうしたモチーフは個別のシーンとして描いていましたが、それを繋げてひとつの統合されたストーリーにすることによって、僕のこれまでの作家人生の中での結束点、一旦の着地点を作りたかった」
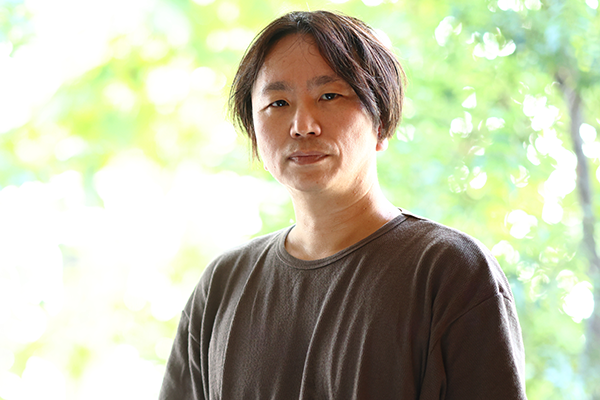
他にもこれまでの上田作品に登場したモチーフや言葉が多数登場する。私の恋人、サリンジャーの金庫、肉の海、座標、引力、重力……。ラプンツェルが暮らすタワーマンションも、上田さんがたびたび扱う〝塔〟と重なる。これまで塔に関しては高みを目指すイメージもあったが、ここ最近の上田作品は違う。
「高みを目指した先について、これまで考え尽くしてきたから一旦いいだろうというところを『キュー』で書ききった感じがあって。今回は塔から降りる感覚でした。高みに憧れる自分も結局は重力に引っ張られる人間として生きている。今回は重力に引っ張られる側の物語です」
まったく異なる物語であっても、同じモチーフを繰り返し使うのはどうしてか。
「ここまで粘着質に使う人も珍しいですよね(笑)。肉の海と私の恋人は僕にとって二大モチーフで、一塊になってしまう人間の未来と、永遠の憧れというふたつは大きなエンジンです。他のモチーフに関しては、書いているうちに、今ならあの道具が使えるな、この道具が使えるな、という感じです。そうした道具を作るための作品も書きます。『私の恋人』や『太陽・惑星』は道具を作るための作品でした」
頭の中に地図みたいなものがあり、「ここをはめたから次はこっちをはめよう」という感覚で小説の題材を選んでいるという。たとえばコロナ禍の間に本作の他に『旅のない』、『引力の欠落』を発表したが、対比性を考えた。
「作品同士がリンクするわけではないんですが、『最愛の』は『引力の欠落』と並行して書いていたので、表と裏となる2作です。『引力の欠落』ではクラスターなどの言葉は使いましたがコロナ禍という現実は書かなかった。今回はコロナ禍をバンバン出していきました。『旅のない』と『最愛の』はリアリズムの面でワンパッケージで、それと対となるものとして『引力の欠落』があります。今『群像』に連載している『多頭獣の話』はわりと道具作り系に近いですね。その次はSFの世界と現実世界を完全に分けて並行して書く、という話を考えています。って、話している内にちょっと働きすぎかな、という気がしてきましたね(笑)」
おそらくそこでも、上田作品の重要なモチーフがちりばめられていくのだろう。これはもう、上田作品モチーフ一覧表がほしい。
上田岳弘(うえだ・たかひろ)
1979年兵庫県生まれ。早稲田大学法学部卒業。2013年「太陽」で新潮新人賞を受賞し、デビュー。15年「私の恋人」で三島由紀夫賞を受賞。16年「GRANTA」誌の Best of Young Japanese Novelists に選出。18年『塔と重力』で芸術選奨新人賞、19年「ニムロッド」で芥川賞、22年「旅のない」で川端康成文学賞を受賞。







