吉田修一さん『永遠と横道世之介』
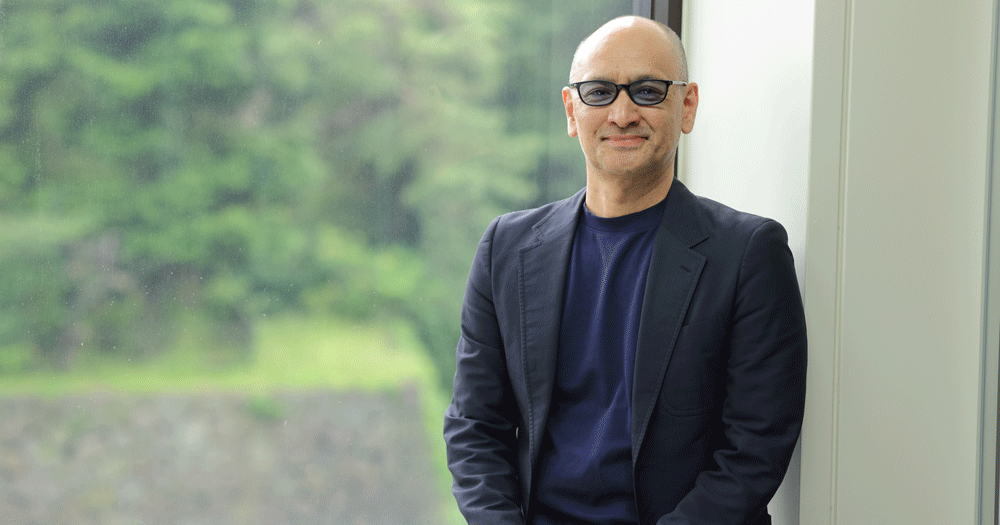
世之介の世界がどこかにあって、それを見聞きして書いている
第一作『横道世之介』が刊行されたのは二〇〇九年。その後映画化もされ、愛され続けたお気楽青年、横道世之介。その三部作の完結編『永遠と横道世之介』がついに上梓された。三十九歳となる世之介の一年間や主要人物たちの過去を、作者の吉田修一さんはどのような思いで書いたのか。
愛され続けたあの青年の三部作最終作
「ここまで読者の方々に好きになってもらっていなかったら、絶対に三作目までたどり着いていなかったと思います。本当に感謝しています」
吉田修一さんがそう語るのは、お気楽で暢気でとびきり優しい男、横道世之介の三部作のことだ。二〇〇九年刊行の第一作『横道世之介』、二〇一九年刊行の『続 横道世之介』(文庫化の際に『おかえり横道世之介』に改題)に続き、このたび、完結編『永遠と横道世之介』が上梓された。
主人公の横道世之介は、吉田さんと同じ一九六八年生まれの設定。第一作では大学進学で上京した一九八七年、第二作では二十代半ばの一九九三年、そして本作ではもうすぐ三十九歳となる二〇〇七年九月からの一年間が舞台だ。
「一作目を書いた時の世之介は、ひょろっとした男の子のイメージだったんです。それがみなさんに愛され、映画化もされ、ひょろっとした木がいつのまにか太い幹になっていました」
カメラマンとなった世之介が今暮らしているのは、東京郊外にある下宿、「ドーミー吉祥寺の南」。家主のあけみと事実婚の関係にある世之介は、彼女や個性的な下宿人たちと暮らしている。相変わらず人が良くて飄々としている姿を読み、ああ、世之介は相変わらず世之介だ、と嬉しくなる。
「自分で話を作っているというより、この世之介の世界がどこかにあって、それを見聞きして書いている感じがします。『横道世之介』の頃からその感覚がありましたが、今回はそれがさらに強くなりました」
学生たちの修学旅行に同行して写真を撮ったり、後輩の江原とともに先輩カメラマンにこき使われたり。下宿にはあけみのほかに、元芸人の礼二さんや書店員の大福さん、大学生の谷尻くんたちがいる。そこに知人の教師夫婦から預かってほしいと相談され迎え入れた、部屋に籠もりっぱなしの高校生の一歩も加わる。
「世之介シリーズは青春小説だと思っているんですが、三十八、九の男を主人公に青春小説を書くのは厳しい気がしたんです。一作目や二作目の世之介の年齢と同じ年代の人がそばにいてくれたら、青春小説っぽいにぎやかさが出せるかな、と。そのあたりから下宿に暮らしていることを思いつきました」
仕事を終えた世之介が帰宅して、夕飯のメニューに「うまそー」と喜ぶ様子、みんなでお月見をしながら焼酎を飲み、とりとめのない話をしている様子──そんな、なんでもない場面を読むだけで、なんでこんなに楽しいのだろう。
「自分も書いていて本当に楽しかったので、それが文章に出ているのかもしれません。なんでもないことって、実は書くのが難しいんですが、世之介に関しては楽しいんですよね。今さら純文学とエンタメを分けてもしょうがないですけれど、一応分けるとすると、やはり書き方って違う。簡単にいうと、たとえば『悪人』の時は、何時何分にどこにいた、などと書かなきゃいけなかった。つまりミステリーなどは書かなきゃいけない情報がいっぱいあるんです。でも純文学は書かなくてもいいことのほうがたくさんあって、書く必要のないことを文章にする難しさがある。そういう意味では『永遠と横道世之介』はエンタメっぽい作品ですが純文学寄りの話なんですよね」
誰もが死ぬ前のキラキラした日々を送っている
第一作の中盤ですでに、世之介が四十歳の時に駅のホームから線路に落ちた女性を助けようと飛び降り、電車にはねられたことは明かされている。読者の中には、〝もうすぐ世之介は死んでしまうのだな〟と思いながら読み進める人も多いはずだ。
「一作目を書いた時、〝世之介が死んでしまうって分かっているから、なんでもない学生生活がキラキラして見えた〟という感想を多くいただきましたし、僕もそう思っていたんです。でも、この年齢になると、世之介が死ぬのが特別なのではなく、みんな死ぬわけだよな、と思うようになりました。みんな死ぬ前のキラキラした日々を過ごしている。そこにたどり着けたのは作家として大きかった。これからは自分も、誰のどの作品を読んでも、〝ああ、この人はいつか死ぬんだな〟と思いながら読むだろうし、そうすると見え方が違ってくる。すごく当たり前のことに改めて気づかされました」
彼の最後の一年を書いて、世之介の人生を完結させたくなった、というのも完結編を書いた動機。前二作では随所に世之介と関わった人々の後日譚、つまり未来が挿入されていたが、本作では主要人物やその親の過去が挿入されていく。そのなかで、世之介の両親の出会いの経緯や、彼を出産した日のことも描かれる。つまり世之介の誕生から最期までを読者は知ることができるのだ。
「過去編を書くために一作目を読み返してみたら、最初のほうで世之介が上京して実家に電話した時、お母さんが感極まって、難産だった話から語り出して隙あらば泣こうとする、という場面があって(笑)。そうだったと思い、過去編でその難産の場面を書くことにしました」
世之介の悲しみ方、立ち直り方
あけみと籍を入れず、事実婚状態なのは世之介の希望だ。彼は数年前、あけみの前につきあっていた恋人、二千花を病で亡くしており、その存在が理由のようだ。作中では二千花の視点から、当時の彼らの出会いからが語られていく。
「本当は完結編では世之介が亡くなる瞬間を書くべきなんでしょうけれど、そこはあまり筆が進まなくて。亡くなり方というよりは、誰かが亡くなった時の乗り越え方を伝えたい気持ちがありました。というのも、読者の方からよく〝こんな時世之介だったらどうするのかと考えます〟という声をいただくんです。なので、世之介は大切な人が亡くなった後こうでした、ということのほうが書きたくなりました」
二千花が亡くなった時、世之介は葬式では僧侶が引くほど泣き、その後も彼女の墓や両親のもとに通い続け、嘆き続けた日々があった。
「どん底だったんでしょうね。でも、そこまでどん底になっても人は立ち直れるってことなんです。作中には出てきませんが、たぶん、当時、すでに知り合いだったあけみちゃんが心配してご飯に誘ったりしたんだろうな、ということも想像して書いています」

鎌倉の寺でボランティア活動をしていた際、世之介と出会った二千花。その時彼女はすでに余命二年と宣告されていた。最初は彼を一風変わった人だと思ったようだが、少しずつ惹かれていく。彼女が自分の余命を伝えた時に世之介が返した言葉には、ほろりとさせられる。
「あの台詞は、自分の中から出てきた感覚はまったくないです。世之介だったらこんなことを言うだろうな、という感じでしか台詞が出てこなかった」
世之介にとって、その後も二千花は大きな存在だ。
「余命二年の限られた時間のなかで二千花はボランティア活動をやっている。世之介にとって、誰かのために何かをやってあげられるって贅沢なことなんだと教えてくれたのが、二千花なんですよね。そもそも一作目に登場する祥子ちゃんもボートピープルの人たちを助けられなかったことがきっかけとなってか、国連で働くようになっている。この物語の人たちって〝人のため〟というつもりもなく、自然とそういうふうに身体が動く人が多いですね」
人と人との出会いが生み出した物語
世之介シリーズは出会いの物語だと思う、と吉田さん。
「たとえば一作目で隣に住んでいた室田さんからライカを貸してもらったことが遠いきっかけとなって、世之介はその後カメラマンになっていく。すぐに結果は出なくても、誰かと出会うことがその人になんらかの意味をもたらしたり、何かが繫がったりしていく。自分もたぶん、心のどこかでそう感じていて、それが特に世之介シリーズには表れていますね」
本作の過去パートでは世之介の両親だけでなく、あけみの祖母で芸者だった秀千代のことや、戦争孤児だった二千花の父親や、母親との出会いのエピソードなども盛り込まれていく。まさに、人と人とのさまざまな出会いがあって、それが繫がっていると実感させられる。
ドーミーに一時期滞在したブータン人のタシさんが、印象的なことを言う。
〈私が誰かに生まれ変わる。そしたらその生まれ変わった誰かは、きっと今、私が愛している人たちの生まれ変わりにとても愛されるんだと思います〉
「他の作品で書くとちょっとクサくなりそうですが、世之介の話にはハマるというか。世之介を見ていると、それを信じたくなりますよね。たとえば二千花のお父さんが戦争孤児となった時に面倒を見てくれた女性がいて、その女性が新橋の芸者さんに助けてもらう場面がある。あの芸者さんがあけみの祖母の秀千代だったとまでは思わないけれど、きっと彼女は秀千代のことを知っていますよね。そうしたことを考えていくと、タシさんが言うことも説得力があるなという気がしています」
世之介との出会いは、著者にとっても大きかった。そもそも書くつもりのなかった第二作を執筆したのも、ハードルの高い雑誌連載を始める際、並走してほしい主人公像を考えて浮かんだのが世之介だったからだという。もはや、吉田さんにとって相棒のような存在だ。
「世之介を書くたびに自分がリセットされる気がします。見ている世界が変わってくるというか。ギスギスしなくなるし、優しくなれるんですよね」
世之介自身も、「この世で一番カッコいいのはリラックスしてる人ですよ」と語っている。
「これも、自分がもとから思っていたことではなく、世之介が言いそうなものとして出てきた台詞です。でも、そうだなと実感しましたね。どんなお金持ちでもどんな有名人でも、苛々している人って全然魅力がないじゃないですか。どこかで、自分が〝この人いいな〟と思うのはリラックスしている人だと感じていたんでしょうね。それが、世之介を書いたことで言葉として出てきました」
読者も、世之介の世界にいるとリラックスできる。三部作になってくれてよかったという気持ちでいっぱいだ。それでもまだまだ読み終えたくなかったと思ってしまう。著者自身も書き終わるのが寂しかった、という。
「完結編とは言いつつ、〝少年横道世之介〟もいつかどこかのタイミングで書いてみたいんですよ。長崎時代の話になります。こうなるともう、ライフワークですよね(笑)」
長崎時代のお気楽極楽少年時代のエピソード、これはぜひ読みたい。待ちます。
吉田修一(よしだ・しゅういち)
長崎県生まれ。1997年「最後の息子」で文學界新人賞を受賞し、デビュー。2002年『パレード』で山本周五郎賞、「パーク・ライフ」で芥川賞、07年『悪人』で大佛次郎賞と毎日出版文化賞を受賞。10年『横道世之介』で柴田錬三郎賞、19年『国宝』で芸術選奨文部科学大臣賞、中央公論文芸賞を受賞。16年より芥川賞選考委員を務める。
(文・取材/瀧井朝世 撮影/浅野剛)
〈「WEBきらら」2023年7月号掲載〉







