小田雅久仁『禍』
幸せな人生は退屈?
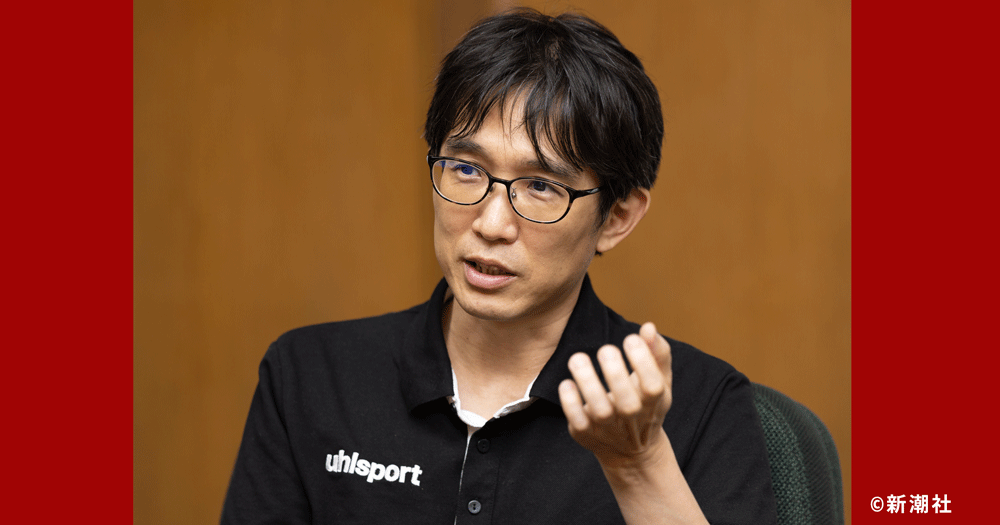
実に九年ぶりとなった三作目の著作『残月記』で昨年吉川英治文学新人賞、今年日本SF大賞をW受賞した小田雅久仁が、早くも新著『禍』を発表した。恐るべき、驚くべき想像力で「もう一つの世界」へと連れ去られる全七編には、書き手自身の切実な思いがすみずみにまで込められていた。
全三編収録の『残月記』では、古今東西の物語作家たちが想像力を競い合ってきた「月」が共通テーマとなっていたが、『禍』もまたとあるテーマのもとに編まれている。
方向性を定めたのは、第二編として本作に収録された「耳もぐり」だ。行方不明になった恋人・高坂百合子を探して、中原光太は恋人が暮らしていたアパートの隣人の部屋をノックする。行方を知っているという隣人の男が語り出したのは、「耳もぐり」という奇妙な能力の話だった──。第二一回日本ファンタジーノベル大賞受賞のデビュー作『増大派に告ぐ』の刊行からしばらくして、「小説新潮」のファンタジー小説特集のために執筆した短編だ。
「僕は三五歳でデビューしましたが、ちょうど人生がつまらなくなってきた時期だったんです。若い頃はやろうと思えばなんでもできる、と思えていましたが、人生の可能性が徐々に狭まってきて、自分にはできないこともはっきり見えてきた。自分の人生、自分の日常があまりにも退屈だから、他人の人生を味わいたい。もしも透明人間になれたら誰かについていって、その人の家にも入り込んで、どういうふうに生活しているか見てみたい。そういう気持ちが、この短編には反映されているんだと思います」
透明人間になる代わりに、耳から他人の中へ入り、当該人物の内側で生活を送る。その体験を語る男の語り口は異様に生々しく、その先には暗闇も待ち構えていた。
「結果的にファンタジーというより、怪奇小説になりました。であれば将来的に短編を一冊にまとめて出すにあたって、怪奇小説というジャンルに統一して書こうか、と。せっかくなら体の一部をモチーフにした作品集にしてみたら面白いんじゃないかなということで、耳、目、鼻……と二本目以降を発想していきました」
読前・読後で世界が変わってしまう体験
次に執筆された「食書」は、本書の冒頭に置かれ、全体を象徴する短編でもある。三八歳の誕生日を迎えつつある小説家の男が、書店のトイレで奇妙な出来事に遭遇する。ドアのカギもかけず便器の蓋の上に腰を下ろしていた四十がらみの小太りな女は、膝に置いていた本のページを破り取り、丸めた紙を喰っていた。唖然とする男に、女は言う。「絶対に食べちゃ駄目よ!」「一枚食べたら……」「もう引き返せないからね」。やがて男は、自宅アパートで試しに一枚食べてみる。
「口をテーマに、食べる、という行為を書こうと思ったとき、食べるものは本にしたら面白いかな、と考えました。僕自身の願望が出ていると思うんですよ。僕も若い頃は、もっと没頭して本を読んでいたようなイメージがあります。読前・読後で世界が変わってしまうような体験をしていたはずなんですが、単純に本をたくさん読みすぎたり自分でも書くようになったりしたことで読み方が分析的になってしまった。本に書かれていることをあるがままに受け入れて、ほんまの意味で心揺さぶられるみたいなことがなくなってしまいました。そうなったら、摂取方法を変えてみるしかない。本を食べたら本の世界の中に入ってしまうことにして、そしたらどうなるかを考えてみたんです」
それをやったら、やり続けたら、〈もう二度と戻れない。これを喰う前の世界には……〉。
「奇妙なものを書いたぞという気持ちはありますけど、怖いものを書いたぞみたいな感覚はあまりないですね」と作家は言うが、いや怖い怖い! ただし、目を背けたくなる怖さではない。いっそ行き着くところまで行きたい、と蠱惑される怖さだ。
第三編「喪色記」の主人公は〝滅びの夢〟を見るようになったことから身辺で奇怪なことが起こり始め、第四編「柔らかなところへ帰る」の主人公は太った女に痴漢されたことから妄想に支配され、第五編「農場」の主人公はハナバエと呼ばれる実験的な作物を育てる農場で働き……。
第六編「髪禍」では髪の長さを評価されアルバイトの斡旋を受けた女性主人公が、謎の宗教団体の儀式に参加する。クライマックスに現れるのは、正真正銘の地獄絵図だ。
「絵面的に激しい場面をまず思い浮かべて、そこに向かって話を組み立てていくことが多いんです。小説よりはむしろ映像作品のほうが、自分の書くものへの影響が大きいからかもしれません。自分の中にたくさんの映像が入っていて、そこから僕なりのフィルターを通して作り出した光景を、文章でどうにか表そうとしている」
そう語る小田に、具体的な「映像」を問うと、意外なアニメの名前がかえってきた。
「例えば、『髪禍』もそうだし『柔らかなところへ帰る』も、元を辿れば自分がファンタジーを好きになるきっかけの一つになった、『BASTARD!!─暗黒の破壊神─』(萩原一至)なんかのファンタジー漫画のイメージがあるんじゃないかと思うんです」
第七編「裸婦と裸夫」では、パンデミックならぬ「ヌーデミック」、人々が次々と裸になっていく黙示録的世界を出現させた。
「電車に乗っていて、急に裸の人が現れたらどうかなっていうことをずっと前から思っていました。そのアイディア自体がバカバカしいので、シリアスな感じでは書けずコメディにしてしまいました。映画で言えば〝ゾンビパニック〟的な要素もありますね」
僕が書く主人公はたいてい普通の人
主人公の日常の延長線上に「もう一つの世界」が現れる感触について、その起源を探ると、またしても意外なアニメ・キャラクターが現れた。
かの国民的アニメ『ドラえもん』である。物語のダークな感触は確かに、藤子・F・不二雄のSF・異色短編に通じるものがある。言い換えるならば、着想自体はものすごくポップなのだ。体の一部をモチーフにするという企画性も含め、すんなりと作品世界に入り込める作りとなっている。が、その先には二転三転、暗転する展開が待ち構えている。そこで腐心しているのは、意外な展開の構想だけではない。異物を読者に飲み込ませるための、文章の説得力を高めることだ。
「僕が書く主人公はたいてい普通の人で、不満とか劣等感を抱えていたり、孤独を感じていたりする。そういう人の日常風景から始まって、最終的に全然違う景色を読者に見せることができたらいいなと思っています。あり得ないことばっかり起こる荒唐無稽な話だからこそ、まずは主人公の日常をしっかり書くようにしているんです。そこがふわっとしていたら、日常が崩れる臨場感は出ないですから」
さらに小田は続ける。
「突拍子もない展開が始まっていってからは、読者に対してというよりも、僕自身がその世界にのめり込んでいけるような文章を一生懸命、頭をひねり散らかして書いています。どうも肌身に迫ってこないみたいな感覚になってしまうと、その世界から自分が弾き出されて書き継いでいけないんです」
濃密な文体は、主人公の「もう一つの世界」への移行を、書き手自身が納得するための手段だったのだ。
「どの短編も結局、僕自身の願望が反映されているんですよね。退屈な日常に、何かが起きてほしいんです」
そうなのだとしたら、なおさら疑問に思う。なぜ「もう一つの世界」は地獄によく似た様態をしているのか。
「もちろん本音で言えば、何かハッピーなことが起きて欲しいんです(笑)。でも、そっちの方向では全然想像が膨らまないんですね。根がネガティブ思考というのもあるし、幸せな人生って退屈じゃないかな、みたいな気持ちがたぶんあるんだと思うんです」
そこにはもう一つ、切実な感情が上乗せされていた。
「タイトルの通りの〝禍〟が自分の身に降りかかった時、その衝撃をやわらげるために小説を書いているのかもしれません。〝禍〟は起こり得るんだと前もって書いておくことで、心構えをしているのかもしれない」
小田は現在、本誌「STORY BOX」で短編を不定期掲載中だ。今年二月号に掲載された YouTuber が題材(!)の「フィッシュウェルの初恋」に続き、今号では「仮面」を発表している。
「自分の小説や本が爆発的な広がりを見せてくれたら、それこそが自分にとっての非日常で、退屈さがまぎれるかなと思っています。自分の人生にこんなことが起こるんだ、と感じられるのではと期待している。ただ、今のところ全くリアルに想像できないんですけどね(笑)」
いやいやいや! 実はポップで、人間存在にまつわる切実さで貫かれた小田作品は、多くの人の手に渡る可能性を秘めているはずだ。
恋人の百合子が失踪した。彼女の住むアパートを訪れた私は、隣人を名乗る男と遭遇する。そこで語られる、奇妙な話の数々。果たして、男が目撃した秘技・耳もぐりとは、一体(「耳もぐり」)。とある便所。女は、本を貪り食っていた。彼女が残した言葉に導かれるように、家の蔵書に手を伸ばした男が視る光景とは(「食書」)──ほか、全七編の悪魔的絶品集。
小田雅久仁(おだ・まさくに)
1974年宮城県生まれ。関西大学法学部政治学科卒業。2009年『増大派に告ぐ』で第21回日本ファンタジーノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『本にだって雄と雌があります』で第3回 Twitter 文学賞国内編第1位。『残月記』で第43回吉川英治文学新人賞、第43回日本SF大賞を受賞。
(文・取材/吉田大助)
〈「STORY BOX」2023年8月号掲載〉





