源流の人 第52回 ◇ 高野 寛(ミュージシャン)

憧れを追って、距離を置いて「YMOチルドレン」は続いていく
「これまでも5年おきにアニバーサリーの企画をやってきたんです。5年経つと『また来たな』と。ただ今回、30周年と35周年の間の時期は、コロナ禍と重なってしまった。以前とはかなり違う気持ちになりました」
高野は一言ずつ確かめるような口調で、そう語り始めた。
これまでの「周年」アニバーサリーでは、ベスト盤を出したり、縁のあるゲストを呼びイベントを開催したり、新譜を出したり。それが彼の定番だった。だが「30周年」直後に世界はコロナ禍に突入し、「35周年」が近づいてもなお、ライブ開催の見通しは不透明だった。計画の立てようのないまま、新譜の準備を黙々と続けていた頃、辛いニュースが立て続けに報じられた。2023年1月、高橋幸宏、3月、坂本龍一の訃報だった。
「その衝撃を受け止め、アルバムをどういう作品にするのか考えつつも、(2024年の)年が明けるまでビジョンが見えなかった。そんなときに、『エッセイを書きませんか』ってご提案をいただいたんです。そして、自分の振り返りを、今回はベスト盤としてではなく、エッセイでまとめてみようと考えました」

こつこつと綴り続けたものが一冊のエッセイ集『続く、イエローマジック』になった。その巻末に彼はこう記している。
YMO、そして幸宏さんと出会わなければ、この人生は全く違うものになっていたはずだ。ミュージシャンとして歩んできたこの道は、スタートラインから想像を遥かに超えていた。自分はなんて幸せなYMOチルドレンだったのだろう。
そしてYMOは永遠になった。もうチルドレンは卒業して、大人にならなければいけない。だがそんな決意も虚しく、還暦を迎えたら赤ん坊に戻ってしまうのか……。それならば、ずっとYMOチルドレンのままで構わない。
「Yellow Magic Orchestra(YMO)」──。元「はっぴいえんど」の細野晴臣の提唱によって坂本龍一、高橋幸宏の3人で結成し、「イエロー・マジック・オーケストラ」(1979年)でデビューした。2作目「ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー」(1979年)が大ヒットとなり、「テクノ・ポップ」ブームの立役者に。欧米でも高評価を得たが、1983年、活動を停止。数々の後進アーティストに絶大な影響を与えている。
YMOは、高野自身の音楽人生の始まりと、強い繋がりがある。
大阪芸術大学芸術学部に在学中の1986年、高橋幸宏、鈴木慶一が主催する「究極のバンド」オーディションに出場し、合格を果たす。このオーディションの目的であった「バンド結成」こそ流れてしまったものの、高野は、高橋、鈴木の音楽ユニット「THE BEATNIKS(ザ・ビートニクス)」のツアーにギタリストとして参加することになった。そして「ミュージシャン」としての高野の人生が始まった。ところがすぐに、プロの腕との差を見せつけられた高野は自信を喪失。そんな矢先、高橋幸宏は高野に言い放つ。
「高野君は個性的な声をしてるね。自分で歌ってみたら?」
こうして、思いがけずシンガーソングライターとして高野自身のソロデビューが決まる。そのプロデューサーは、高橋幸宏だった。
新刊のエッセイでは、YMOをはじめ、高野が出会い、共演してきた数々のアーティストとの交流の日々が綴られている。フリッパーズ・ギター、オリジナル・ラブ、忌野清志郎、宮沢和史、星野源、中村佳穂……。坂本龍一と世界を旅したワールドツアーや、高野がMCを務めたNHK教育テレビ(現・Eテレ)の番組『土曜ソリトン SIDE-B』について振り返る章もある。高野自身の思い出にとどまらず、ここ30年においての日本の音楽シーンを振り返ることのできる、クロニクル的な役割も同書は果たしている。
コロナ禍を生き延びろ
湾岸戦争、アメリカ同時多発テロ、東日本大震災。エッセイを読み進めていると、世界的大事件の起きるたび、高野は心を深く痛めてきたことが窺い知れる。
「東日本大震災のときは、本当に打ちのめされてしまって、約1か月間、音楽も聴けないし、歌も歌えないほどショックだったんですね」
ただ、このたびのパンデミックが起きた瞬間に高野の脳裏をよぎった言葉は、「使命感」だったと言う。
「2020年の2月下旬までライブをやっていたんですが、緊急事態宣言が発令されて、翌週からすべてのライブがキャンセルになりました。その瞬間、震災のときとは違い、使命感みたいなものを感じたんです。みんな今のポジションでできることを何かやらないと、ミュージシャンは大変なことになると。そんな気持ちを Web に綴ったら、協力してくれる人がすぐに現れ、配信ライブを早い時期からスタートすることができたんです」

90年代初頭からコンピュータを使って「宅録」で楽曲を創作してきた彼にとって、「Zoom」「Slack」などのツールに何ら抵抗はなかった。高野は振り返る。
「本当に突き動かされるようにやっていましたね、2020年は」
音楽シーンが特にこの十数年は、ライブを中心としたムーブメントに変わっていった。配信の時代に変わり、CDを買わずに YouTube で音楽を無料で聴く。そういう中で、アーティストたちはライブに活路を見出していった。リスナーにとっても、ライブはみんなで音を楽しむ特別な祝祭の空間だった。ところが「会ってはいけない、集まってもいけない」、そんな状況になり、世界のどこでもライブができなくなった。
「初めて無観客配信ライブをやったときの、何とも言えない違和感。今でも忘れられないですね。ライブって、エネルギーの循環だと思うんですよ、演者が発したものをお客さんが受け取って、声を出したり、拍手してくれたり笑ってくれたりする。それをリアルタイムで僕らが受け取ることで、またインスピレーションが生まれていく。その循環こそがライブの醍醐味。無観客だと、自分の発したエネルギーがどこに向かっているのか、本当にイメージできなくて」
それでも、くよくよしてはいられない。高野は当時を振り返る。
「収録された映像を見たら、自分の演奏のアラが見えてきたんですよね。ライブがしばらくできないのなら、この配信の演奏クオリティを上げていくことが、今の自分の一番のテーマだ。そう気持ちを切り替えたんです」
スマホ画面越しに聴いてくれる人、大画面で観てくれる人。あらゆるシーンでのアウトプットを想像し、どんな形でも楽しめる音楽を映像に込めようと決めた。彼は語る。
「それは普通にライブをやる感覚とは全然違いました。演奏を客観的に見つめ直すことは、すごくプラスになりましたね。この状況でできることは、これしかない。追い詰められた中での『あがき』でもありました」
今回の本を執筆中、高野は「ずっと着地点を考えていた」そうだ。
「どういう形でこの本を終わらせるかずっと探っていたんです。そうするうち、自分自身が還暦を迎えるということと、『YMOチルドレン』という言葉が結びついて、それが今のタイミングだ、と思い至ったんです」
そう閃いた途端、自身のつくるべき新しいアルバムのイメージが、はっきりと固まっていったのだった。
「自分が通ってきた道の『まとめ』になるような新しいアルバムができるかもしれない。結果的に、今までにないかたちで、周年の作品としてうまく収まったと思っています」
「Modern Vintage Future」
海外でも著名な電子音楽ミュージシャン・AOKI takamasa(あおきたかまさ)が、今回のアルバムのミキシングを担当している。やり取りしながら仕上げていく過程で、AOKI がアナログの機材を使ったことで、高野の想像とは異なる太い音として仕上がってきたという。
「自分のスタジオでの作業は、『宅録』と呼ばれる、ラップトップPCの中で完結するやり方でやってきたんですけど、そうすると現代的な音、悪く言えば、平面的な仕上がりになるんです。ところが AOKI 君にミックスしてもらった音は、一昔前のスタジオ録音のエレクトリック・ポップのような、太くて立体的な質感になって返ってきたんです」

それは80~90年代、まだ「宅録」が一般的になる前の頃、音楽マニアがスタジオに集まって作っていたような質感だった。質感はヴィンテージで懐かしい手触りだが、当時こんな音楽はなかった。そこで「Modern Vintage Future」というタイトルが浮かんだ。高野は語る。
「たとえば1970年の大阪万博、1985年のつくば科学万博の頃に、人々が夢見ていた未来像がありますよね。もし鉄腕アトムや万博やドラえもんの未来が今、順調に現代に繋がっていたら、こういう感じなのかもしれないな、と。そんな夢のある未来感が浮かんできました」
とはいえ、キラキラした夢や希望だけでは、現代にはリアルに響かない。そこで彼は各曲の歌詞を冷静沈着なトーンに抑えて整えていった。彼は言う。
「それが『Modern』ということかもしれません。タイトルを直訳すれば、現在・過去・未来。自分の中の時間旅行みたいなところがあります。中高生の時、こういう音を聴いていてワクワクしていたよね、っていう。自分に対する問いかけみたいなところもあるんです」
出会ったYMO、未来の音楽
1964年、高野は静岡県の長閑な町に生まれた。彼は振り返る。
「今と異なるのは、昭和の時代は、地方と東京との情報格差がとても大きかったこと。Amazon もネットもないあの頃、地方では楽器もレコードも手に入れるのが難しかった。ある程度恵まれた環境がないと、音楽も聴けないし、演奏することもできない」
手先が器用で工作好きな彼が、YMOと出会ったときの衝撃については、ぜひエッセイを参照されたい。高野は彼らのことを「奇跡の3人」と称している。
「東京都心の、恵まれた環境に生まれ育った早熟な3人だった。他にも、才能ある若いミュージシャンが、同時多発的に彼らの周りに集まって、切磋琢磨していた。YMO以前にも十分にキャリアがある3人なんですよ。実は、坂本さんがポップスのフィールドでは一番後発だったんだけれども、それでも教授と呼ばれるぐらい、いろんなことに造詣が深くて、シンセサイザーの第一人者でもあった」
当初YMOは、国籍も人種も不明な匿名ユニットをイメージして結成されたという。プロデューサー・細野晴臣のアイデアの下、「戦略的に売れるものをつくろう」と活動を開始。海外発売の直後、ワールドツアーを行うという、今では信じられないような大掛かりなプロジェクトを展開していった。
「巨大な機材を積んで世界ツアーに出る。その賭けに勝算があったのが凄いですよね」

のちに高野自身がプロのミュージシャンになって、共演の機会などを通じ、彼らから当時の話を聞くこともあった。高野は振り返る。
「最初はかなり実験的だったし、自分たちがフロントマンとして出るわけじゃないから、純粋な遊び心でワクワクしながらつくっていたんだと思います。(大ヒットして)自らの存在が矢面に立つことになり、不本意なところもあったと聞いたことがあります」
高野は続ける。
「世界に認知された理由のひとつには、高橋幸宏さんのファッションセンス、ビジュアル戦略が功を奏していることは間違いないでしょう。3人の役割分担の絶妙な配分があったんです」
当時、日本のみならず世界的に絶賛を浴びたYMO。今から40年も前にどうしてそんなに世界を熱狂させたのだろうか──。高野はこんな見解を聞かせてくれた。
「当時は、コンピュータミュージックというのは主に楽器を演奏しない人がやるジャンルだったんです。演奏の代わりにプログラミングしてコンピュータにやらせるっていう発想だったと思うんですよ。YMOは楽器を生演奏できる一流プレイヤーの集団なのに、敢えてコンピュータを道具として遊ぶように使ってみた。適材適所でコンピュータも使い、人力で演奏もする。初期はそういうバランスだった」
それに加え、ロック、ジャズ、クラシックの音楽的素養を、3人が持ち合わせている。巷のポップスよりも遥かに高度な曲づくりをしていた。
「細野さんは世界の音楽に精通し、ユーミン(荒井由実)のプロデューサーとしても大成功していたし、坂本さんの編曲能力も評価が高かった。東京藝大で培ったアレンジのセンスは、当時のポップスの世界に新風を吹き込んだんですね」
坂本がDJを務めていたNHK-FMの伝説的番組「サウンドストリート」。高野は熱心なリスナーだった。番組のいちコーナー「デモテープ特集」では、リスナーから創作曲を募集し、放送の波に乗せていた。槇原敬之、テイ・トウワら、今となっては錚々たる面々の投稿者も含むそのコーナーに高野は耳が釘付けになった。彼は振り返る。
「アマチュア作品の自由な発想に笑わされたり、感心したり、感動したりしました。坂本さんの選曲も本当に幅広くて、とにかく刺激を受けました。番組を聞いて新しい発想を得た若者たちが、自分でも何かをつくりたいと思うようになる。すごく理想的なコミュニケーションが生まれたんです。『教授』ってあだ名はダテじゃない。坂本さんが若者に与えた影響を、僕は『YMOの通信教育』って呼んでいるんですけど、それは本当に、日本のアートのレベルを底上げしたと思います」

あともう一つ。大事な時代背景として、その頃の音楽ファンたちの認識では、「邦楽は洋楽に比べ劣っている」という共通認識があったということだ。高野は分析する。
「最近でこそ『日本人離れしている』と言わなくなりましたが、昭和の時代は、音楽に限らず、欧米へのコンプレックスがまだとても強かった。ヒットチャートを聴いていても、洋楽のロックの勢いとか洗練された感じに比べると、日本の曲は何か、違う。当時は日本のドメスティックな湿度、歌謡曲的なものが根底に強くあった」
そんなときに、コンピュータと人間が共存するYMOの斬新な音楽が、みるみるうちに世界に広まって、世界じゅうのアーティストがYMOへの称賛を叫ぶようになった。日本人にしか作れない、テクノロジーを駆使した新しい音楽。YMOのヒットは、ウォークマンが世界中で大ヒットし、「メイド・イン・ジャパン」が世界のトップに躍り出た時期と重なっていた。名だたるミュージシャンがYMOとの共演を望むというムーブメントは、高野ら日本の若者にとって、希望だったという。
「日本の音楽がこんなに世界中でリスペクトされて、お互いに影響し合って、どんどんアップデートしていく。その80年代前半の様子は、本当に誇らしかった。洋楽コンプレックスを完全に払拭してくれた初めての日本のバンドだと思うんですよ。今の若い人は、J-POP が海外に比べて劣っているなんて微塵も思ってないはずですけど」
もっとも、その光の強さは、ときとして高野の創作活動に影を落とすこともあった。
「YMOの影響が大き過ぎたがゆえに、自分自身の音楽をつくらなきゃという課題をずっと抱えながらやってきているんです。だから、テクノをまったく忘れてアコースティックギターだけでツアーをしていた時期もあります」
高野がデビューした翌年、平成に入って、テレビ番組に由来する「イカ天ブーム」、「バンドブーム」がやって来た。そして「J-POP」というジャンルが定着し、高野がこよなく愛した80年代前半のテクノ・ポップのムーブメントは途絶えてしまった。「J-POP」のミリオンセラーの時代。そして「渋谷系」。高野はその潮流を少し離れたところから眺めていた。
「色んなところに片足だけ踏み入れて、『あ、ちょっと違うな』と出ていく。いつもそういう感じなんですよね。ヒット曲が出たことで、ヒットした自分にどう対峙していくべきなのか、葛藤した時期も長かった」
後進の背中を押して見えてきたもの
そんな折、高野に転機が訪れる。京都精華大学のポピュラーカルチャー学部で、教鞭を執ることになったのだ。2013年のことだった。
「創作の時間が圧倒的に奪われる。毎週、東京から京都に通うなんて信じられない。ところが、相談した友人が、誰一人として、反対しなかったんですよ。みんな『いいじゃん、やってみれば』『向いてると思うよ』って」
思い切って飛び込んだ学び舎では、10年間にわたり、後進アーティストの卵たちと対峙し続けた。
「本当にやって良かった。大学で、自分の価値観が完全にリセットされました」
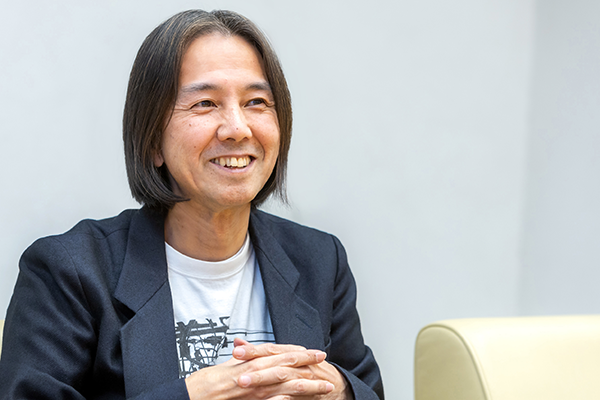
リセット、とはどういうことか。長い間、音楽を続けていると、往年のファンが支えてくれる。その存在は高野にとってありがたい。ライブには必ず集まってくれて、拍手してくれて、喜んで帰ってくれる。ただ、彼らだけを相手に音楽活動を続けていると、「それ以外の人」に自分の音楽がどう届いているのか、見えているのか、わからなくなってくる。
「テクニックや完成度を突き詰めるあまり、自分の中の基準がものすごく高くなっていたんですね。ところが学生たちは不器用で、創作に時間もかかる。一所懸命つくった作品もまだ拙い。けれども、完成度とは関係のない、作品としてのメッセージがそこにはあるんです。学生の作品に触れることでそのことに気づきました」
自分の拘っていたものが、いったんリセットされた。意味のない拘りも多かった。高野はそう振り返る。
だからだろうか、高野がここ最近、同世代のミュージシャンたちと話していると、「大人っぽいなあ」と感慨深く思ってしまうことがあるそうだ。京都の学び舎で、未熟だけれども純粋な創作の世界にどっぷり浸かり続け、そこですべてをリセットされたからだ。
高野は続ける。
「手塚治虫さんが生前、若い漫画家に本気で嫉妬していたって話が大好きなんです。実力のある若手が出てくると本気で悔しがる。劇画調の漫画が流行り始めたら、手塚さんはそれまでの作風からアップデートしていく。自分もそれを見習って、守りに入らないようにしていきたい」
教壇に立っていた頃、高野は一人ひとりの学生と、交換日記のようにやり取りしながら、「1か月に1曲仕上げる」といった目標に向かって伴走していった。
「東京に戻ってから全員にメールで一つずつ『こうしたらいいんじゃない?』『ここはいらないんじゃない?』みたいなことをやり取りする。今まで漠然と捉えていた音のことを言語化するのは初めてで、自分自身が勉強になりました」
エンタメを楽しむツールが多様化の一途をたどる今、これまで自分が意識していた音楽の世界が、いかにニッチだったかを再認識した、という高野。
「その気づきは本当に重要。だからこそ、漠然とどこかに向けて作品をつくるのではなく、確実に、それを求める、刺さるところに向けて発信していくしかない、と思っています」
「宅録」と音楽の未来
ネットの波に乗り、いま、多くの若者が自作の音楽を自由に発信する。彼らの多くは、三十数年前に高野たちがやっていた「宅録」と同じように一人きりで、音楽をつくる。でもそれはライブで一体感を得ることで生まれるカタルシスのような、音楽の本来の持ち味を、生かせてはいないのではないか──。そう問うと、高野は首を大きく横に振った。
「最近の若者たちは、僕らの時代とは別のつながりを求めていると思います。彼らは常にネットの向こう側を想像しながら、誰かに届くように発信しているんですよね」
つくる過程は一人でも、その先のコミュニケーションを意識している人々が世に出てきている。
「僕らが昭和にやっていた本当のひきこもりの『宅録』とは意味が違う。壁はあるけど距離がない。それを可能にしたのがインターネットです。そんな開かれ方、つながり方は羨ましく思うときもあります。パーソナルをすごく大事に持ちながらも、みんな決して一人じゃない」
加えて、一発撮りの演奏動画を撮り続けている人は、ライブ感覚も持ち合わせている。それまでステージに立ったことがほとんどないにもかかわらず、デビュー直後から堂々としたライブができる人も多い。高野は語る。
「本当に僕が幸せだったなと思うのは、90年代は人と一緒に集まって作業するしか方法がなくて、ライブもバンドでやるしかない。当たり前ですが、誰もがスタジオに集まって、大勢でつくっていました」

ちょうど音楽が産業として栄えていた時期にもあたる。予算や時間があって、音響設備の整った立派なスタジオにプロ用機材をセッティングし、プロのエンジニアが録音し、それをみんなで聴きながら、あれこれ話し合いながら、つくる。
「すべてが自分の思い通りにはならない。もどかしさもあるけれど、先輩に音を通じて教えてもらったものは本当に、かけがえのない宝物だった。今は大きなスタジオがどんどん潰れていってしまって、バンドで録音する場所を探すのも大変なんです」
特にポップミュージックはテクノロジーの進歩と不可分だ。コロナ禍の与えた影響は計り知れない。「宅録」や配信ライブも広まって、音楽のつくり方、楽しみ方はコロナを境に、劇的に変わった。一方で、コロナがスタジオ消滅の動きを加速させてしまった。バンド全員で録音できるスタジオが減り続け、「やりたいな」と思っても、場所も予算も、それから教えてくれる人もいない。高野は言う。
「若い世代が現場で先輩から学ぶ機会は、年々少なくなっているように感じます。その代わり、フェスの現場などでは、世代を超えた交流も増えてきているのは良いことですね」
最後に、高野自身の「次のアニバーサリー」に向けて、その将来像を尋ねた。
「もっと世界中に届いてほしいですね。そのイメージは、ずっと強い理想として持っています。日本にはまだまだ面白い作品がいっぱいあるし、やっと日本の音楽が日本語のままで世界中に聴かれる時代になった。自分のつくってきたものは、ちゃんと時代を超える力があるという自負はあるので、それがもっと世界に届いていくといいなと思っています」
高野のエッセイも近頃、外国のファンに読まれることが増えてきた。翻訳アプリを本にかざし、高野の語り継ぐ日本音楽史の葉脈を感じ取り、彼らは新しい音楽として高野の世界観に入り込んでいくという。高野の音楽は世界に確実に届きつつある。

高野 寛(たかの・ひろし)
1964年静岡県生まれ。1988年、高橋幸宏プロデュースによるアルバム『hullo hulloa』でソロデビュー。ほとんどの楽曲の作詞・作曲・編曲・ギター・プログラミングを自ら手掛けるスタイルで、20枚を超えるソロアルバムを発表。宮沢和史らと結成した GANGA ZUMBA、高橋幸宏・原田知世らと結成した pupa、BIKKE・斉藤哲也と結成した Nathalie Wise などのバンドでも活動。2013年に京都精華大学ポピュラーカルチャー学部・音楽コース特任教授に就任、2018~23年に同学部客員教授を務めた。24年にはエッセイ集『続く、イエローマジック』(mille books)を刊行、さらにデビュー35周年記念アルバム『Modern Vintage Future』をリリースするなど、幅広い活動を続けている。







