著者の窓 第13回 ◈ 望月衣塑子『報道現場』

安倍政権時代、菅官房長官への鋭い質問で注目を集めた東京新聞記者・望月衣塑子さん。昨年十月に刊行された著書『報道現場』(角川新書)は、コロナ禍以降さまざまな変化にさらされている報道の現場のリアルを、日本学術会議への人事介入や入管問題などのトピックを交えながら綴ったノンフィクションです。変わりゆく時代、報道はどうあるべきか? 米倉涼子さん主演の Netflix ドラマ『新聞記者』の劇場版原案者である望月さんにインタビューしました。
記者会見から締め出されて
──『報道現場』、拝読しました。報道を取り巻く環境の変化に記者としてどう向き合うべきなのか、率直な思いが描かれていて印象的でしたが、この本の狙いやテーマを教えていただけますか。
二〇一七年に『新聞記者』という本を出しましたが、書いた当時は菅義偉官房長官(当時)とのバトルが注目されていた時期でした。会見場で菅さんとやり合っている記者がいるけど何者なんだと。そういった疑問に答えるために、記者としての姿勢を半生を交えつつ書いたのが『新聞記者』でした。ところが二〇二〇年四月以降、コロナ禍で官邸の定例会見に参加できなくなり、結果、社会部記者本来の市民の声を聞く仕事に立ち戻ることになりました。さまざまな現場に足を運び、苦しむ人々の声をすくい上げて、それを記事にする。社会部は本来、権力者とは距離のある仕事が多い。今回の本では『新聞記者』以降、一社会部記者のわたしが何に関心を持ち、どんなことをしてきたのかを、記事に表れない舞台裏も含めて書いてみました。
──冒頭では、定例会見から望月さんが締め出されていった過程が克明に描かれていて、ショックを受けました。
もともとわたしを締め出す機会を狙っていたんでしょうが、コロナ禍が後押しをした形になりました。二〇二〇年四月に内閣府職員のコロナ感染が判明して、いよいよコロナが身近なところまで近づいてきたなという危機感が高まっていた時に、会見への出席を一社一人にしたいと、官邸広報室が内閣記者会に要望してきました。官邸広報室は「長くても一、二か月のことだから」と説明していたそうですし、状況的にコロナ感染の拡大がどうなっていくかが見えず、こればかりは仕方がないと内閣記者会側が判断したのも分かります。でも常時記者を二名会見に出していたのは東京新聞だけだったので、狙い撃ちにされたなというモヤモヤした思いはありました。事実あれから一年半以上が経ち、スポーツ会場や映画館などは人数制限が撤廃され、飲食店に人が戻っているのに(取材時二〇二一年十二月)、官邸の記者会見だけいまだに人数制限がある。なし崩し的にコロナ禍が利用されたわけで、記者クラブとしても「こんなはずじゃなかった」と思っているのではないでしょうか。実際、何度か記者クラブとして、正常の形に戻すよう申し入れをしたようですが、官邸広報室からの回答は「ノー」なようです。
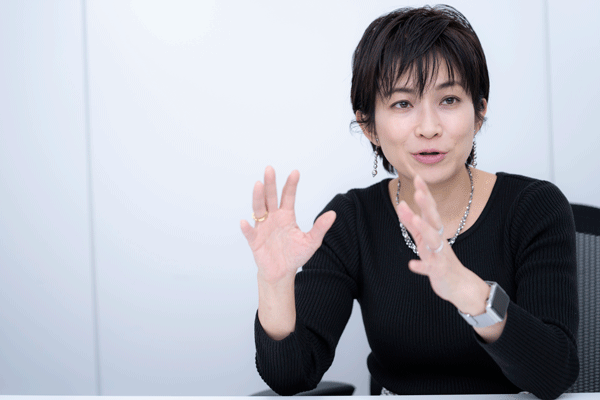
──長期政権において、メディア内での同調圧力も強くなっていったとお書きになっています。望月さんの質問に対して、菅さんに追従笑いする記者もいたとか。
二〇二〇年九月、菅さんの総裁選出馬会見の時です。あの時は五か月ぶりに菅さんに質問することができたんですが、わたしの質問に正面から答えず、「(あなたの)質問が短ければ、それだけ長く答えられるっちゅうことです」と、質問時間の話にすり替えた。暗にわたしの質問が長いと言いたいのは、すぐわかりました。その嫌味に対して、前方に座っていた番記者の一部男性たちが笑ったんです。これまで菅さんの会見に出ていた番記者やわたしからすると、おなじみの光景なのですが、普段の会見に出ていないフリーの記者たちにはショックだったようで、お笑いジャーナリストのたかまつななさんが違和感があると表明してくれました。記者会見のおかしさが伝わったので、逆に公開の場でやってくれてよかったと思います。
SNSによって記者も見られる時代に
──記者の世界で常識とされていた価値観が、あらためて問われる時代になってきたのでしょうね。
SNSの発達によって、質問する側のスタンスも問われるようになってきました。これまでは事前質問を投げて、それに答えをもらう、いわば権力とメディアのあうんの呼吸がありました。特に安倍政権はメディアの一部を抱え込んで、会見をコントロールしてきたわけですが、会見の様子がネットにアップされるようになり、空気が変わってきたと思います。政治部の記者には「オフ懇」といってオフレコ前提で政治家に話を聞く機会があるのですが、わたしが会見で目を付けられたせいで、ある一時期、菅さんのオフ懇が中止になった時がありました。重要な菅さんの生の声が取れなくなり、それで他社の一部政治部記者は「あいつをなんとかできないのか」と、プレッシャーをかけるわけです。うちの政治部記者は、板ばさみになり大変だったと聞きます。それでも会社が守ってくれたのは、ネットで会見の様子を見た読者部の方々の後押しがあったから。誰がどういう質問をしているのか、会見場での質疑が、記者や政治家のなれ合いになっていないかなど、市民が注視し、記者もチェックされる時代になったように思います。
──「フェイクとファクトの境界線」と題した章では、日本学術会議に関する虚偽情報の拡散について探っていますね。たとえ火の粉が飛んできても、情報の真偽を伝えるのがメディアの仕事、と望月さんはお書きになっています。
日本学術会議の存在そのものが問題なんだ、という論調が菅さんの任命拒否とほぼ同時に一部の有識者やメディアから発信されて一気に拡散した。あれは不可解でしたね。官邸主導でやってるのではないかと思われても仕方がない。ただ早い段階で一部の有識者や記者の説明で、フェイクであることが判明したのはよかったと思います。わたしが書いた橋下徹氏や甘利明氏に対するファクトチェック記事も、多くの方に読んでもらえましたし。橋下氏のような発信力のある人に「おかしいのではないか」と声をあげるのはパワーがいるし大変なことですが、誤った情報の拡散を防ぐためには誰かがやらないといけない。れいわ新選組の大石あきこさんが橋下さんらとのバトルで注目されているのも、多くの人の日本維新の会への怒りや疑問を代弁してくれているからではないでしょうか。

──フェイクニュースは一度拡散すると消し去ることが大変ですし、一定数信じてしまう人も出てきます。難しい問題ですね。
琉球新報や沖縄タイムスが、フェイクやデマに対するファクトチェックを二〇一八年の沖縄県知事選をきっかけに始めました。あの試みはすごく新鮮で、その後、他のメディアのファクトチェックにも広がりました。沖縄の知事選には二、三億円の官房機密費が投じられているとも言われています。米軍基地反対派についても「金で買収されているのではないか」などのフェイクが飛び交っています。そこを逐一検証し、フェイクがあった場合は反論して、オールドメディアの存在感を示したことに大きな刺激を受けました。ネット上のデマや誹謗中傷にしても、これまでは言ったもの勝ちのような空気がありましたが、開示請求をすれば匿名の投稿であっても発信者を明らかにできるようになった。フォトジャーナリストの安田菜津紀さんも差別的なツイートに対する開示請求を行い、名誉毀損で提訴しましたし、ジャーナリストの伊藤詩織さんをはじめ、誹謗中傷や悪意ある記事やツイッターの投稿に屈しない、という流れが生まれてきました。ここ数年でネット空間は、まだまだ問題もありますが、やや健全化したように思っています。
若い世代の怒りにハッとした
──第二章「取材手法を問い直す」では、取材対象の懐に深く入り込んでいくような従来の取材のあり方が時代に合っているのか、と問題提起されています。
本にも書きましたが、黒川弘務東京高検検事長(当時)と記者の賭け麻雀問題は他人事で語れる話ではありませんでした。わたし世代の記者はわたしを含め、ある種の「抱きつき取材」と言われる手法をとっていた。あくまで、取材対象者に接近し、情報を取るためで、提灯記事を書くためではないと信じていたつもりでした。しかし、実際には、黒川氏と麻雀をしていた記者は、黒川氏や法務省を擁護するような記事を書いていました。ショックでした。しかし、ある種の「抱きつき取材」をしていた自分も常に批判的に検証し、記事を書いていたのか、と問われるとやはり振り返って疑問符がつく所がありました。わたしより若い二十代、三十代の記者たちの方が、こういうやり方は恥ずかしい、変えないといけないと怒っていました。ジェンダー差別の問題にしても同じです。森喜朗氏の「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」という失言でも、真っ先に声をあげたのは若い世代です。わたしは「またいつもの森さんの失言だ」とスルーしかけていたのですが、若い人たちは、真剣に怒っていて、組織委会長を続投させるなんてあり得ないと声を上げ、ハッとさせられました。わたしたちの世代も変わることを恐れずに、価値観を日々アップデートさせていかなければいけないと思います。
──武器輸出問題、外国人労働者と入管法改正の問題などさまざまな調査取材を続けているそうですが、取材テーマはどのように見つけているのですか。
相談を受けることもありますし、会見に行って興味を抱いて調べ始めることもありますね。外国人問題については、関心はありつつも、なかなか取材に行けずにいたのですが、二〇二一年の元日に困窮者向けの「大人食堂」に外国人が列をなしていることに驚いたんです。その直後、安倍政権下の家事支援事業で来日したフィリピン人女性が、雇い止めにあって困窮していることも知りました。そこから外国人の労働問題を取材するようになり、名古屋入管で死亡したスリランカ人女性ウィシュマさんの取材に繋がっていくんです。うちの会社はあれをやれと言われることが少なくて、記者それぞれが関心のあるテーマを追いかけられる。そういう環境に助けられていると思います。

──本のあとがきにはご家族からも力をもらっている、と書かれていましたね。取材や執筆と子育ての両立は大変なのでは。
大変は大変ですけど、『新聞記者』の頃に比べると子供たちが少し大きくなって、留守番もお風呂も子供たちだけでしてくれるようになりました。執筆の時間は、真夜中含めて何とか確保できています。夫が単身赴任から帰ってきてからは、子育ての面では私よりもむしろ夫が中心になってやってくれています。夫は元教師なので勉強でも遊びでも子供に物事を教えるのがとてもうまいんですよね。わたしは短気ですぐ怒っちゃうから(笑)、家族にはいつも支えてもらっています。
新たに生まれ変わったドラマ版『新聞記者』
──一月十三日より Netflix で『新聞記者』が世界同時配信されています。二〇一九年に公開されて話題を呼んだ劇場版とはまた違った切り口の『新聞記者』が楽しめそうですね。
赤木俊夫さんの自殺をめぐり、妻の雅子さんが国を訴えた裁判を、岸田政権は認諾という形で終わらせてしまった。到底納得できることではありません。主演の米倉涼子さんとは撮影現場でお会いしましたけど、気配りの中にも情熱を秘めた方でした。今回のドラマ版には横浜流星さん演じる大学生が登場して、新聞なんて全く読まなかった学生が、社会問題に目覚めていくというドラマにもなっています。若い世代の方々にも共感してもらえるんじゃないでしょうか。

──望月さんは「記者の仕事は、権力者が隠したいと思っている事実を明るみに出すということ」とお書きになっています。つい忘れられがちですが、大切なことですね。
七年八か月におよぶ安倍政権において、メディアはすっかり権力に手なずけられてしまいました。あるテレビ局の一年生記者から「メディアは権力に批判的じゃないと駄目なんですか?」という質問をされたとデスクの方から聞いたこともありました。ジャーナリズムは権力と対峙するもの、という前提が崩れているんですね。これは教育の問題もあるかもしれない。アメリカでは、ジャーナリストを志望する学生は、まずジャーナリズムが権力を監視する役割を担うということを徹底的に学ぶそうです。だからCNNの記者がトランプ大統領から記者証を取り上げられた際も、右左の思想信条は関係なく各メディアが一丸となって抵抗した。トランプ寄りと言われていたFOXニュースまで抵抗しましたから、日本とは全然違います。日本では記者クラブ制度を完全になくすことは難しいでしょうが、たとえば官邸や政府の側が流してきた情報をそのまま発信するのではなく、裏取りや追加取材を重ね、常に疑問視して見るようにしなければ、メディアは、いいように利用されて終わってしまう。鵜呑みにしない。疑問があったら自分で調べる。報道の現場がどれだけ変化しても、そこは変えてはならないと思います。
望月衣塑子(もちづき・いそこ)
1975年東京都生まれ。東京新聞記者。慶應義塾大学法学部卒業後、東京・中日新聞社に入社。千葉、神奈川、埼玉の各県警、東京地裁特捜部などを担当、事件を中心に取材する。経済部などを経て社会部遊軍記者。菅官房長官の会見での姿勢が注目され、その時のことを記した著書『新聞記者』が映画、ドラマの原案となる。現在は、入管法や外国人労働者問題などをテーマに取材を続ける。著書に『武器輸出と日本企業』、『同調圧力』(共著)、『自壊するメディア』(共著)など多数。
(インタビュー/朝宮運河 写真/藤岡雅樹)
〈「本の窓」2022年2月号掲載〉


