【著者インタビュー】砂原浩太朗『黛家の兄弟』/代々筆頭家老を務める黛家の三兄弟の命運と絆の物語
直木賞候補作『高瀬庄左衛門御留書』に続く、「神山藩シリーズ」第二弾! 二転三転するお家騒動とともに、しみじみとした人生模様を描く時代小説の著者にインタビュー。
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
お家の未来を揺るがす大事件 その顛末に三兄弟は翻弄されていく 道は違えど、思いはひとつ――躍動感あふれるシリーズ第二弾!
黛家の兄弟
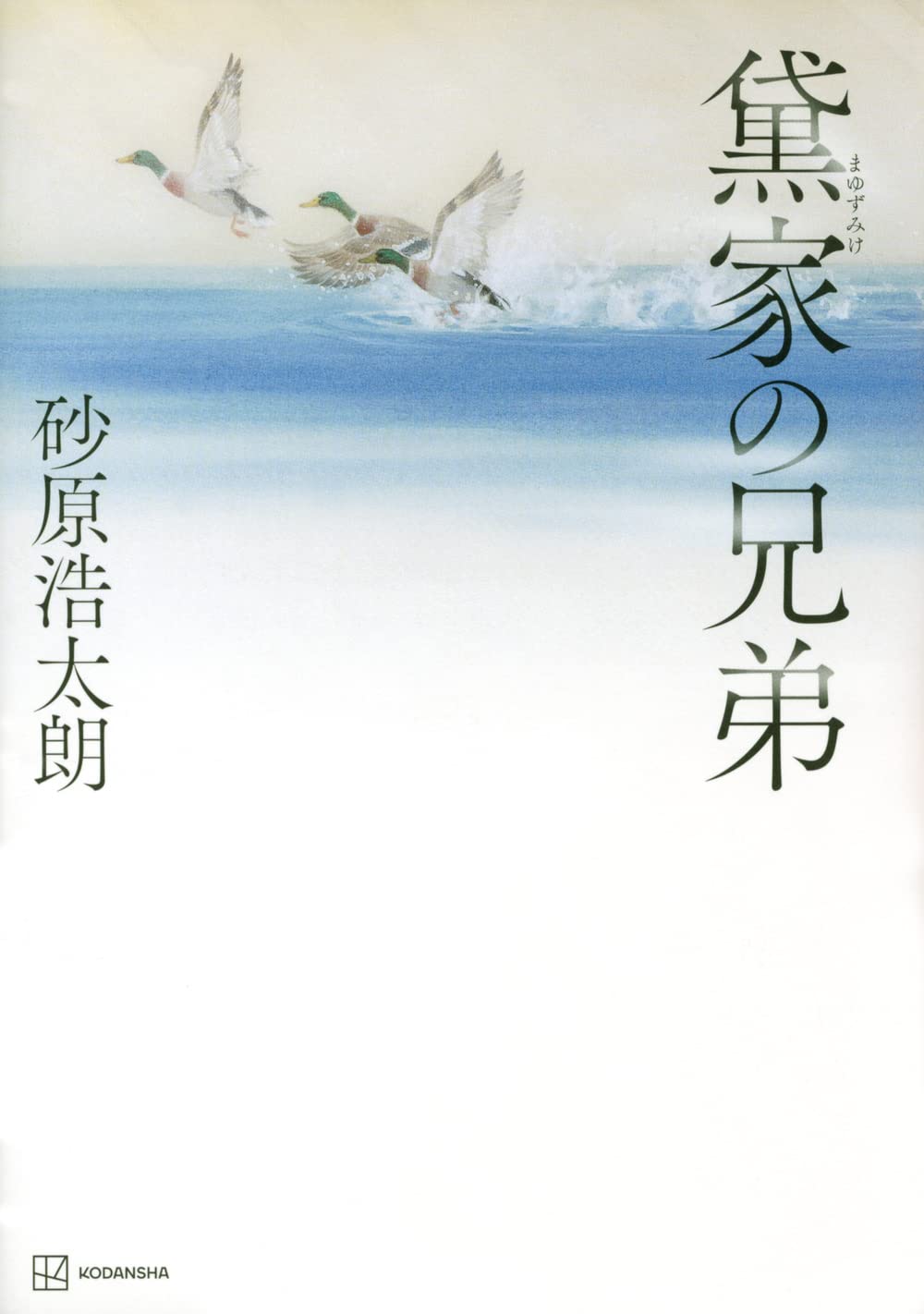
講談社
1980円
装丁/芦澤泰偉 装画/大竹彩奈
砂原浩太朗

●すなはら・こうたろう 1969年生まれ、兵庫県出身。早稲田大学第一文学部卒。出版社勤務やフリーのライター等を経て、2016年に第2回「決戦!小説大賞」を受賞、18年『いのちがけ 加賀百万石の礎』で単行本デビュー。昨年1月刊行の『高瀬庄左衛門御留書』は直木賞、山本周五郎賞の候補や『本の雑誌』21年上半期ベスト10でも第1位に選出されるなど、目下最も注目される時代小説家のひとり。177㌢、63㌔、AB型。
拒むにせよ取り入れるにせよ、出会った人の思いに向き合い生きてゆくのが人間
舞台は前回の直木賞候補作『
前作で幅広い層の読者を獲得し、「これぞ令和の時代小説」と注目された著者・砂原浩太朗氏は現在52歳。中学生の頃から藤沢周平や『三国志』を愛読し、「
「例えば現代で人が殺されると、警察が来てDNAも調べるとか、本題でなくても書かなければいけないことがたくさんありますよね。一方で、『罪と罰』のような古典文学には、指紋の発見以降は成り立たない話も多いですが、作品の価値が損なわれるわけではない。僕の場合、書きたいテーマを鮮明に打ち出すには、時代小説というジャンルが合っているのかなと思います」
*
物語は藩主の信頼も厚い父〈清左衛門〉が50を迎え、代替わりを考え始めた矢先、花見客で賑わう鹿ノ子堤で三兄弟が質の悪い酔客と喧嘩になりかけた、新三郎17歳の春の出来事から始まる。
この時、新三郎の傍には道場仲間の〈由利圭蔵〉がいた。黛三千石、由利二十石と家格は違うが、肩身の狭い三男同士、2人は妙に気が合った。その圭蔵があまりの美貌に頬を赤らめたのが、同じ場所で花見をしていた大目付〈黒沢織部正〉のひとり娘〈りく〉だ。
新三郎は、栄之丞から文を託されたため、りくと兄の間には何らかの通い合いがあると感じている。ところが、兄には藩主の息女と、そして新三郎には、こともあろうに、当のりくとの縁談が舞い込んで……。結局、新三郎は圭蔵を側近として召し抱えた上で黒沢家に婿入りするのだが、本人たちの思いとは別の次元で家というものが営まれる時代でも、決して失うものばかりではない、というように、終始フェアな視線を注ごうとする著者の姿勢がいい。
「以前、高名な映画監督が人間は何も選べない、人生というのは不自由なものなんだとおっしゃっているのを読んだことがあります。たしかに、生きることって、制約だらけですよね。一見、自由に見える現代でも、当然、自分の親も生まれる場所も選べないわけですし。
時代小説は制限が多いように見えますが、そもそも人間は今も昔もずっと不自由なものですから、それが分かりやすい形で表れているだけだと思うんです。
ただ、それでも幸せや生き甲斐といったものを求めてしまうのも人間ですよね。それこそ望むと望まざるとに拘わらず婿入りし、舅から大目付の心得を伝授される新三郎のように、不自由を受け入れた上で異なる世代や世の中と良好な関係を築けたりと、得るものも必ずあるはずですから」
件の花見の席で、兄弟やりくに絡む酔客を〈やめい〉と一喝で制したのが次席家老〈漆原内記〉だった。折しも娘〈おりうの方〉が藩主との間に男子を儲け、勢いに乗る漆原はある陰謀を画策するが、そんな中で事件が起きる。
漆原の嫡男〈伊之助〉は、仲間と花街に入り浸っており、やはり家に居つかず、〈花吹雪〉なる無頼集団を率いる壮十郎と対立していた。ある日、料亭で伊之助ら〈雷丸〉が狼藉を働く現場に新三郎たちが踏み込んだ折、弟に襲いかかった伊之助を壮十郎が斬り殺してしまったのだ。
むろん非は伊之助にあるが、壮十郎は仲間の名を頑として語らず、罪を被ろうとする。そんな兄を目付役筆頭の〈久保田〉は〈強情なやつ〉〈つまり、いい漢だといっている〉と評するが、弟からすれば、なぜ罪を免れようとしてくれぬのかと、承服しがたい思いだった。
その久保田も漆原の策略に搦め取られてしまう。辛酸を嘗めた新三郎が黒沢家と織部正の名を継いだ十数年後、思いもよらないドラマが幕を開けることとなる。
今いる自分だけがまことという思い
「古風な言い方になりますが、僕はビルドゥングス・ロマン(成長小説)の信奉者なんです。前作『高瀬庄左衛門御留書』にしても、中高年下士の変化と成長の物語だと思って書きました。
特に今回は10代の少年が30代の青年になる王道的な物語。その間、新三郎は周りの人から様々なものを受け継ぎ、自分というものを形成していく。父や舅はもちろん、敵役の漆原内記でさえ、彼の成長に寄与しているというのは最も描きたかったことのひとつです。敵役はいても、一方的な悪役は存在しない。拒むにせよ取り入れるにせよ、出会った人々の思いに向き合いながら生きてゆくのが人間だと思うので」
だからだろうか。〈ひとの心もちには応えよ〉〈応えんとしているうちに、多くを得る〉など本作には数々の金言がちりばめられている。二転三転するお家騒動を描きながら、しみじみとした人生模様も堪能できるのだ。
「二転三転ということでいえば、元々ミステリーも好きなので、伏線を張ったり、読者を驚かせたりすることが性に合っているんだと思います(笑)。映画でも、『十二人の怒れる男』のような裁判物は特によく観てきました。もちろん時代小説ではありますが、ミステリータッチと言われることも増えてきましたね」
〈未熟は悪〉という人と〈正だの義だのを人へもとめるには、いろいろなものを見過ぎた〉という人の生き方が何ら矛盾せず、醜いまでに生にしがみつく人も、生き急ぐ壮十郎のことも、両方肯定するのが砂原作品だ。中でも象徴が〈こうとしかならぬ〉という台詞だろう。
「僕の作品によく登場する、
〈だれかの夢を見るのは、そのひとがおのれのことを思うているから〉というある人の言葉が、別の誰かを救いもする。人は自分が思うより、はるかに多くの言葉のバトンに支えられて生きているのかもしれない。
●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト 2022年1.28号より)
初出:P+D MAGAZINE(2022/02/03)

