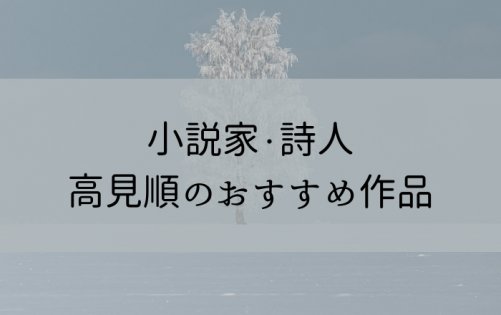【『いやな感じ』など】小説家・詩人 高見順のおすすめ作品
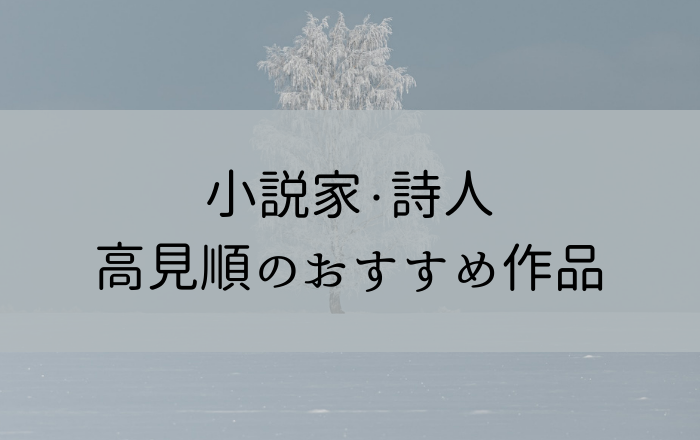
『いやな感じ』『故旧忘れ得べき』といった代表作を持ち、小説家・詩人として活躍した文士、高見順。その小説や詩集の中から、おすすめ作品のあらすじと魅力を紹介します。
小説家として自身の出生に関する記憶や左翼運動の挫折にまつわる作品を多く残したほか、詩人・文芸評論家としても活躍した高見順。作品のなかで昭和という時代を生々しく描写した高見は、“最後の文士”とも謳われました。
今回は、代表作『いやな感じ』や第1回芥川賞の候補ともなった『故旧忘れ得べき』といった小説を中心に、高見順作品の魅力をご紹介します。
『故旧忘れ得べき』

出典:https://www.shogakukan.co.jp/books/09352432
『故旧忘れ得べき』は、高見順が1935年に発表した中編小説です。大学時代、左翼運動に献身していた自身の体験を元に書かれた本作は、同年に石川達三の『蒼氓』や太宰治の『逆行』と並び、第1回芥川賞の候補作にもなりました。
物語は、安月給の出版社に勤務する小関健児という男を中心に進みます。現在はサラリーマンとして家庭を持ち、凡庸な日々を送っている小関ですが、彼は時折、左翼運動に熱中していた自身の学生時代に思いを馳せます。
希望があってこそ夢想は楽しい。しかし彼の現在には何の夢があり希望があろうか。しがない勤めに味気ない家庭。何を目当てに一体生きているのだろう。なんのための生活か。そう思うと、今はとめどなく涙も出て来てしまうのである。──楽しかったのは学生時代だけである。あの時分には夢があった。
小関が抱えている虚無感は、彼だけでなく、学生時代の左翼運動の仲間にも共通する思いでした。実家が金持ちであるが故に生活には困ったことのない篠原辰也や、同居している女性に養ってもらっている松下長造といった小関のかつての仲間たちも、皆、左翼運動に熱中していた過去の記憶が、現在に暗い影を落としています。
本作は“饒舌体”と呼ばれる、言葉数の多い、軽妙洒脱な文体で書かれています。また、文中にはしばしば“筆者”の名で、高見自身が登場します。たとえば、
思えばなんとした愚かな廻り道を筆者はしたことであろう。筆者が饒舌を弄しているうちに、われわれの主人公たる小関健児はとっくに散髪をおえ、彼の所謂味気ない家庭へ既に帰っているではないか。(中略)彼は一時自分は病気なのではないかと心配したが、いろいろ考え合わせてみるとそうでないことが分り、そうなると、自分の異様な気の弱さの自覚と甘えから、一層嵩じた振舞を演ずる始末になり、冒頭で述べた所がつまりそれなのであった。
というような形で、筆者の登場人物たちに対するまなざしが垣間見られるのです。高見はこういった文体のあり方について、自身の評論『描写のうしろに寝てゐられない』の中でこのように述べています。
作家は黒白をつけるのが与へられた任務であるが、その任務の遂行は、客観性のうしろに作家が安心して隠れられる描写だけをもつてしては既に果し得ないのではないか。白いといふことを説き物語る為だけにも、作家も登場せねばならぬのではないか。作家は作品のうしろに、枕を高くして寝てゐるといふ訳にもういかなくなつた。作品中を右往左往して、奔命につとめねばならなくなつた。
高見は、“客観”の体裁を守った描写のみを是とするのではなく、筆者自身も積極的に物語に介入していくべきだと考えていました。この筆者の介入こそが、ときに読者を強く物語に共感させたり、反対にどこか突き放されたような心地にさせたりと、本作を読み進める上でのユニークなアクセントになっています。
アナーキストの若者の生と死──『いやな感じ』
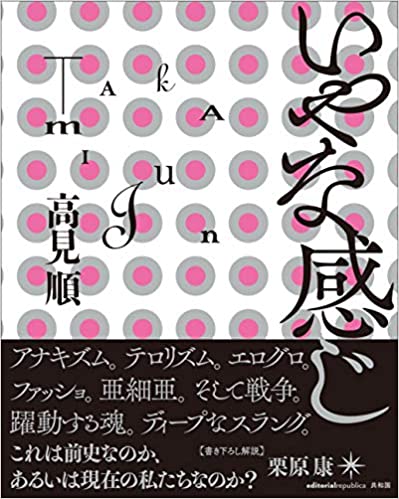
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4907986572/
『いやな感じ』は、高見が最晩年の1963年に発表した長編小説です。アナーキストの加柴四郎という男を主人公に、関東大震災、満州事変を経て日中戦争が泥沼化するまでの日本の姿を描いています。
加柴は学生時代にアナーキストの社会運動家・大杉栄の思想に惹かれ、福井大将の狙撃事件に関わった経験を持っています。しかし、加柴らの代わりに余罪を引き受けて死刑となった一派に沈黙を命じられ、生き延びていました。そんな加柴は自分のことを、“死にぞこないのテロリスト”だと感じています。彼は資本主義国家の転覆を謀ってさまざまな仲間たちと結託し、闘いを続けるものの、どの計画も失敗に終わってしまいます。
本書のタイトルにもなっている「いやな感じ」とは、作中で加柴がしばしば覚える違和感や生理的な嫌悪感を指しています。たとえば、加柴はテロを実行しようと決心し、見えない後援者から莫大な金を受け取ったりしたときに、この“いやな感じ”を体感します。
後援者というのは、相当の金持ちでないと、俺のふところにあるような金を、ぽいと出したりはできないだろうから、おそらくはブルジョアにちがいない。ブルジョアは俺たちの敵だ。敵の金で俺は……それも、まあ、いいだろう。毒をもって毒を制すで、それはいいとしても、ブルジョアが金を出すというのは、それが何か自分の利益になるのでなかったら、そうと分ってなかったら金輪際、そんなことはしないだろう。となると、俺の生命は、しょせん、そのブルジョアの私利私欲のために献ささげることになるのか。これもいやな感じだった。
言葉にできない嫌悪感は、終始加柴の人生につきまといます。この“いやな感じ”は、昭和の激動期に日本を覆っていた暗雲そのものとも解釈できるのです。
また、本作の特徴として、独特なスラングが多用されていることが挙げられます。
下から女が戻ってきた。俺は椅子を立った。
「どこへ行くんだ」
「ちょっと」
「ちょっと、なんだ」
「フントウバだ」
監獄の便所のことで、ムシニン(囚人)の言葉だが、ムシ(監獄)に縁の深い俺たちはズバチョオ(手水場)なんて言葉よりもっぱらこれを使っていた。
「ジュウロク……?」
と女が言った。シシ(四四)十六で小便のことである。
登場人物らのこういった言葉遣いからは、死に直結するアンダーグラウンドな世界を生きている若者特有の高揚感や団結感、選民意識が感じられます。本作は重厚な長編ではありますが、加柴の行動や心境が活き活きと鮮明に描かれ、一度読み始めたら目が離せなくなるような力を持っています。
病床の高見が記した詩集、『死の淵より』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4062901854/
『死の淵より』は、1964年に発表された詩集です。高見は晩年、食道癌に冒され、4度の大手術を伴う闘病生活を送っていました。本書は、高見が“死の淵”で記した詩をまとめたものです。
食道ガンの手術は去年の十月九日のことだから早くも八ヵ月たった。この八ヵ月の間に私が書きえたものの、これがすべてである。まだ小説は書けない。気力の持続が不可能だからである。詩なら書ける――と言うと詩はラクなようだが、ほんとは詩のほうが気力を要する。しかし持続の時間がすくなくてすむのがありがたい。二三行書いて、あるいは素描的なものを一応書いておいて、二三日おき、時には二三週間、二三ヵ月おいて、また書きつゞけるという工合にして書いた。
という序文の通り、高見は本書に収録された詩を数行ずつ、数ヶ月にわたって書き進めていました。
高見が綴る病床の記録は、どれも強く“死”の匂いを感じさせる、痛切なものばかりです。ときに、彼は詩の中で悲鳴をあげたり、泣いたり、疲れ果てて眠ったりします。
何事かがはじまろうとしている
カラスどもは鋭いクチバシを三階の部屋に向けている
それは従軍カメラマンの部屋だった
前線からその朝くたくたになって帰って
ぐっすり寝こんでいるはずだった
戦争中のラングーンのことだ
どうかしたのだろうか
おれは三階へ行ってみたカメラマンはベッドで死んでいたのだ
死と同時に集まってきたのは
枝に鈴なりのカラスだけではなかった
アリもまたえんえんたる列を作って
地面から壁をのぼり三階の窓から部屋に忍びこみ
床からベッドに匍いあがり
死んだカメラマンの眼をめがけて
アリの大群が殺到していたおれは悲鳴をあげて逃げ出した
そんなように逃げ出せない死におれはいま直面している
──『三階の窓』より
耳へ
愚かな涙よ
まぎれこむな
それとも耳から心へ行こうとしているのか
──『愚かな涙』より
高見は、家族や周囲の文人たちからも「繊細すぎる」と評されるような人物でした。本書に収録された詩の数々は、彼の鋭敏な精神性を感じさせるとともに、死のリアリティを克明に表現しています。
おわりに
饒舌で読みやすい文体を駆使し、“恥”の意識を感じさせる生々しい人間の心境を緻密に描くのが、高見順の作品の大きな魅力です。高見の作品を知ることは、激動期の昭和という時代を深く知ることにも繋がります。
太宰治や坂口安吾らといった同時期の作家に比べると、高見は現在、スポットを当てられることが少ない作家です。しかし、高見が描く若者の胸中には、現代を生きる人々にも共感できる部分が多いはずです。高尚で難解な作品にはあまり手が伸びない──という方にも、ぜひ手にとってみてほしい作家のひとりです。
初出:P+D MAGAZINE(2022/02/03)