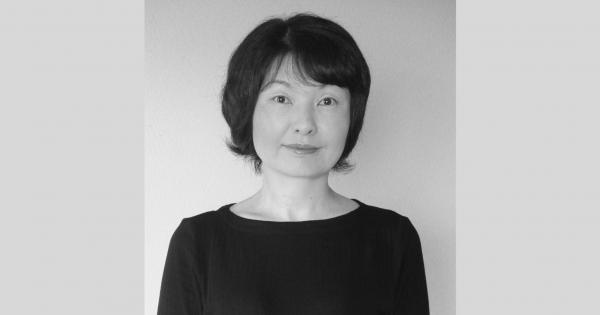翻訳者は語る 中谷友紀子さん
デビュー作ながら、本国イギリスでの刊行直後、十五か国で翻訳が決定したという、注目のサイコスリラー『邪魔者』。厄介な事情を抱えた姉妹の複雑な心理描写がズキズキと刺さる前半から、家族の秘密が暴かれる後半へ。読む者を釘付けにする本書の読みどころについて、翻訳を手掛けた中谷友紀子さんに聞いた。
〈『邪魔者』の魅力〉
初めて原書を読んだとき、おお! ドロドロしたのが来たぞと興奮しました。ギリアン・フリンの『ゴーン・ガール』以来、心をグサグサ刺されるダークなサイコスリラーを訳すのは久しぶりでした。
三歳のときに叔母に預けられた主人公アイリーニが、約三十年ぶりに生家に戻って自分が捨てられた理由を探るというストーリーです。自分はいらない子だというコンプレックスを抱えたアイリーニの屈折ぶりが生々しくて、痛々しくて。おまけに、親元に残された姉のエルがそんなアイリーニの弱点を熟知し、容赦なく傷つけたり、逆に巧みに懐柔したりして、心を操ろうとするんです。胃が痛くなるようなしんどい姉妹関係ですが、それでも、二人にしかわからない絆のようなものもある。愛憎入り混じる姉妹の複雑な感情が濃密に描かれ、読ませます。
前半はそんなふうにじわじわと緊迫感の高まるサスペンス、後半はさらにひねりが加わって見えているものがころころと変わる展開になり、ミステリーとしての面白さが際立ってきますね。
〈著者はどんな人物?〉
献辞に、この本を「自分を無価値だと感じたことのある方々に贈ります」と書いているように、著者は拒絶される惨めさや、認めてもらえない悔しさを知っている人なんだろうと思います。もしかすると、デビューまでの十年に七つの長編を書きあげたものの、出版には至らなかったという経験のせいなのかもしれません。わたしも翻訳者になれるまでに長い時間がかかったので、そのなんともいえない焦燥感はよくわかるなあと。そこに通じるものを感じて、惹かれます。
著者の第二作は、早くも来年七月に刊行が予定されています。こちらも家族がテーマのサイコスリラーとのことで、楽しみにしているところです。
新聞社勤務から翻訳家へ
〈翻訳との出会い〉
大学卒業後、新聞社の広告局で働いていたとき、のちに師匠となる田村義進先生が訳されたウォーレン・マーフィーの『二日酔いのバラード』と、浅羽莢子さん訳のジル・チャーチル『ゴミと罰』に出会ったんです。面白くて面白くて、大笑いしながら読みました。広告の仕事が向いていないかもと悩んでいた時期だったので、救われたような気がしたものです。翻訳ってすごい、自分もこんなことができたら、と思うようになりました。
まずは通信・通学講座を受講しながら、翻訳新人賞や試訳に応募しました。運よく賞をいただき、ミステリーの短編や実用書の翻訳の仕事につながりました。その後、関西で開かれていた田村先生の翻訳勉強会に参加して、数年後に先生から版権エージェントをご紹介いただいたんです。それがきっかけで、念願の長編の訳書が出ることに……とまとめると、すんなりいったみたいですが、下積み時代は本当に長かったです。最初に翻訳者になりたいと思ってから、長編の訳書が出るまで、十五年以上かかりました。
〈翻訳家としての転機〉
翻訳者としての長編デビュー作となった、ギリアン・フリンの第二作『冥闇』です。原書を読みだした瞬間からしっくりくる感覚があって、この作品を訳したいと思いました。訳者に選んでいただいたときは、夢かと思うほどうれしかったです。『邪魔者』は、主人公の人物造形や、過去に家族に起きた事件の謎を探る設定といった点が、『冥闇』を感じさせるなあと思いながら訳していました。フリン作品がお好きなかたには、特にお楽しみいただけるのではと思います。
以前、ある編集者のかたに、「物語を目の前にぽんと置いてくれるような訳ですね」と言っていただいたことがあります。その言葉がとてもうれしくて、お守りのように大事にしています。なるべく雑味のない、作品世界のなかにすっと入っていけるような訳ができればと思っているので。「ぐいぐい物語に引きこまれた」という感想を目にすると、訳者として最高に幸せですね。
(構成/加古 淑)