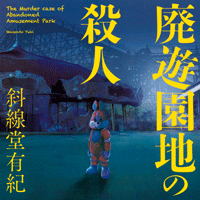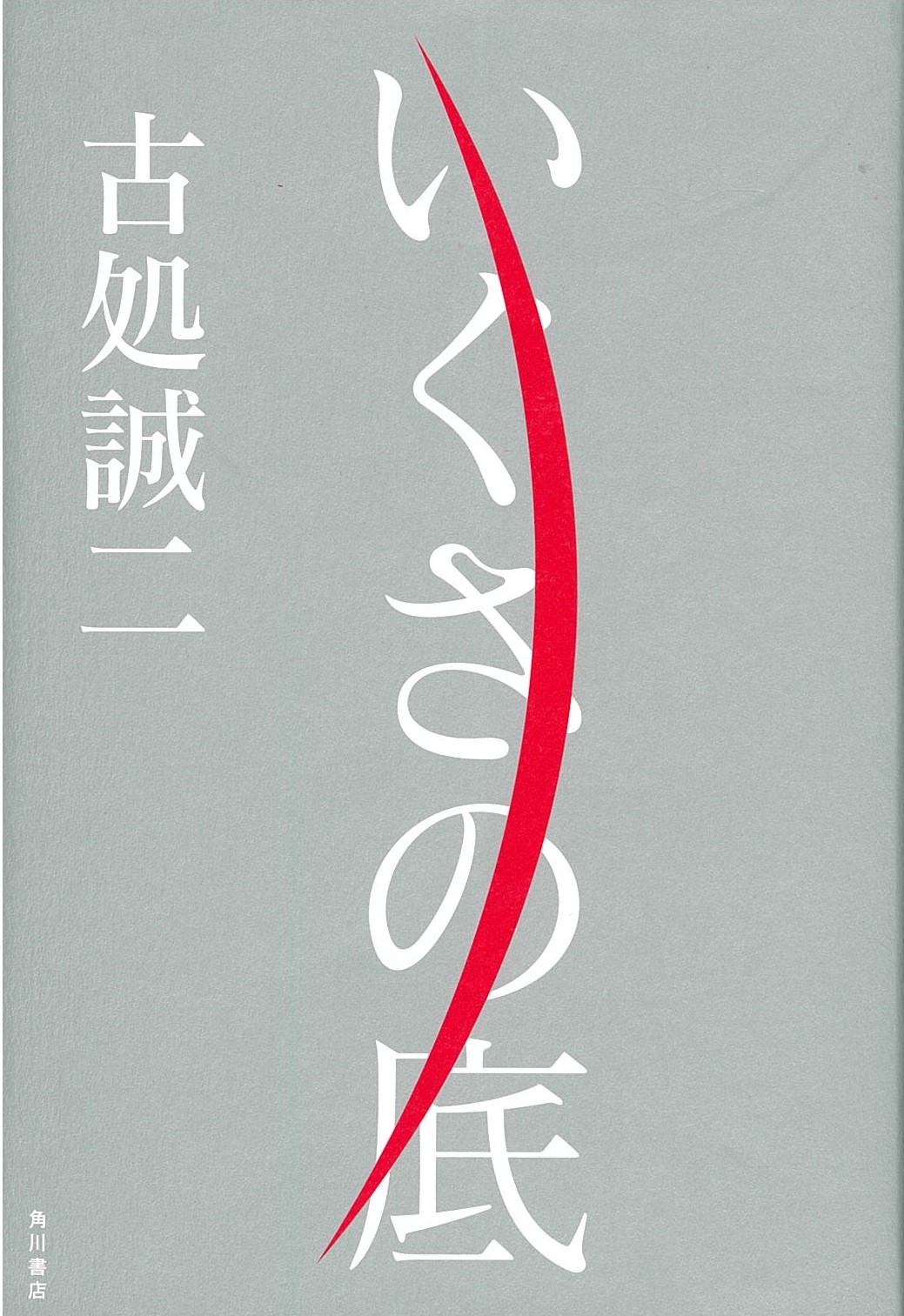今月のイチオシ本 ミステリー小説 宇田川拓也

そうです。賀川少尉を殺したのはわたしです。──という犯人の独白から幕が上がる、古処誠二『いくさの底』の舞台となるのは、太平洋戦争の真っ只なか、戡定後のビルマの山村だ。
民間人である依井は、賀川少尉率いる警備隊に通訳として同行。村に到着後、順調に駐屯準備が進められたその夜、依井は肩を揺さぶられて目を覚ます。准尉の「隊長殿が死んでいます」という信じ難い言葉を受け、厠まで急ぐと、そこには首から大量の血を流して倒れている賀川の無惨な姿があった……。
いったい誰が、なぜ賀川を殺したのか? 約二百ページの分量と、いたってシンプルな謎の提示に、一見すると引き締まったパズラー的な内容を予感させる。しかし本作は、そうした要素を研ぎ澄ませたうえで、さらに・戦争ミステリの金字塔・という帯の惹句に偽りのない真相へと熱を抑えた筆致で読む者を誘う。
苛烈な戦闘場面や目を覆いたくなるような戦場の痛ましい情景が克明に描かれているわけではないが、終盤で犯人の口から語られるのは、明らかに戦争が招き、現在の事態を生じさせてしまった大いなる不幸だ。シンプルと思われた謎の向こう側に、まさかこれほどの深い懊悩と譲れない決断が秘されていたとは、おそらくほとんどの読者は思いもしないだろう。と同時に、あえて太平洋戦争中のビルマを選んだのが単に効果的な特殊設定を狙ったものではなく、また山村という舞台が単なるクローズドサークルとして機能させるための選択ではなかったことに大きくひざを打つはずだ。なぜ本作は、この時間と場所でなければならなかったのか? なぜ犯人は自らの手を血で汚すことに踏み切ったのか? 本格ミステリの手法で、これらの問いにいささかも揺るがない強固な説得力を見事に持たせたことで、本作はまぎれもなく・戦争ミステリの金字塔・と称えられるべき作品である。
毎年夏になると、大岡昇平『野火』、井伏鱒二『黒い雨』が平積みで書店に並び、読み継がれているように、本作もまた、ミステリファンに限らず、広く永く読み継がれることを願って止まない。