渡辺裕『感性文化論〈終わり〉と〈はじまり〉の戦後昭和史』斬新な視座で見つめ直す戦後昭和史
「やらせ」に違和感を抱く現代人の感受性は、いつどのように形成されたのか。人のものの見方や価値観について、感性の変容を解き明かします。井上章一が解説。
【ポスト・ブック・レビュー この人に訊け!】
井上章一【国際日本文化研究センター教授】
感性文化論〈終わり〉と〈はじまり〉の戦後昭和史
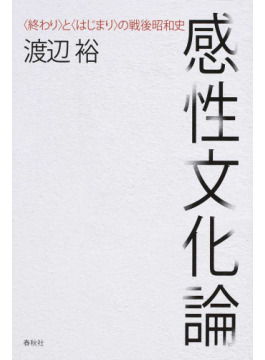
渡辺 裕 著
春秋社
2600円+税
装丁/芦澤泰偉
「やらせ」に違和感をいだく感受性はいつ形成されたのか
市川崑の映画『東京オリンピック』は、オリンピック映画の傑作とされている。政府筋からは、日本人の活躍をあまりとりあげていない点などが、批判された。それで、文部省も、一度はきめた推薦をとりけしている。だが、芸術としての評価はゆるがない。
そんな作品に、著者は今日的な観点から、注文をつけていく。
たとえば、開会式の入場シーン。映画は、その場でながれた音楽も収録しているかのように、画面を構成した。しかし、じっさいの入場行進では、べつの音楽がひびいていたことを、著者はつきとめる。競技の映像についても、オリンピック終了後にあとで撮影した箇所が、あるという。
今ふりかえれば、とうていドキュメントとは言いがたい。一種の「やらせ」ではないかと、著者はいう。だが、批判をするために、映画の作為をいちいちあばいているわけではない。
著者は、画面に虚偽があると感じてしまう自分自身を、問いつめる。どうやら、一九六〇年代の人びとは、自分がひっかかったところをうけいれていたようだ。なのに、なぜ自分はわだかまりをおぼえてしまうのか。「やらせ」に違和感をいだく現代人の感受性は、いつどのように形成されたのだろう。こうして、著者は歴史の古い層をさぐっていく。
戦前のスポーツ実況と称するラジオ放送には、今だとありえないものがあった。たとえば、電波のとどかない遠隔地の野球中継。電話で知らされた試合の様子を、原稿用紙に書きとめる。それをアナウンス室へもちこみ、実況風にラジオでつたえたりもしていたらしい。「第一球、なげました。ボール!」というように。
いっぽう、一九六〇年代末期には、フォーク・ソングのソノシートで、新しい試みがはじまった。ライブの場で聞こえるヤジ、怒号なども、レコードにおさめる録音が。夾雑物もまじってこそ、リアリティがある。そんな感受性のめばえを、著者はそのあたりにかぎとっているようである。
(週刊ポスト2017年6.9号より)
初出:P+D MAGAZINE(2017/10/05)

