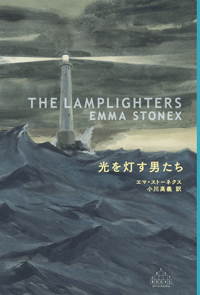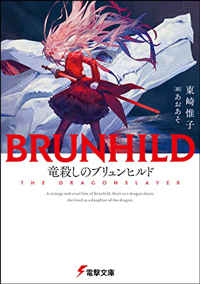採れたて本!特別企画◇BEST BOOK OF THE YEAR 2022
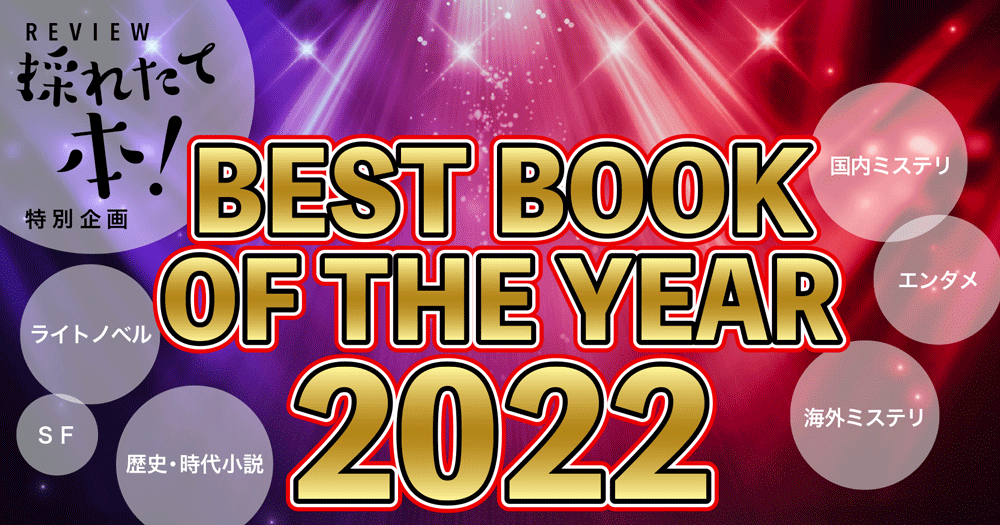
新たな年に期待がふくらむ、この季節。振り返ると、2022年も素晴らしい文芸書に恵まれた一年だった。本誌「STORY BOX」のフルリニューアル以来、「採れたて本!」で紹介してきた本は39冊。毎号ハズレなしのフレッシュな作品に出会えると人気の本コーナーでは、特別企画として、各ジャンルの年間ベスト本を7人の評者に選んでいただいた。必読の傑作7冊、読み逃している人は今すぐチェックを!

評者︱末國善己
長浦京は、殺し屋の小曾根百合が陸軍に消された一家の生き残りの少年を守って戦う『リボルバー・リリー』など、派手なアクションが魅力の作品を発表している。『プリンシパル』のヒロインも暴力を使うが、自らが武器を手にするよりも、命知らずの男たちを死地に送る方が多いので戦闘指揮官に近くなっている。
関東最大級のヤクザ水嶽本家の娘・綾女は、家業を嫌い教師になっていた。終戦の日、父が重態との連絡を受けた綾女は、疎開先から東京の実家に帰るが、その夜、父が亡くなった。多量の軍需物資を隠匿し、長男と三男は戦地、次男は病気療養中の水嶽本家は、敵組織に襲撃される。綾女は無事だったが、拷問されても綾女の隠れ家を口にしなかった乳母一家が殺され、幼馴染みは重症を負う。この襲撃で腹を括り、兄が復員するまでの代理として水嶽本家のフロント企業の社長代行になった綾女は、父が戦中に請け負った仕事を利用して堅気の巻き添えも辞さない殲滅戦で複数の敵組織を壊滅させ、残酷な方法で裏切り者を粛清した。
ヤクザを主人公にすることで、物資が不足し流通網も破壊された終戦直後は、ヤクザの闇市が庶民の生活を支えていたなど、戦後の裏面史が活写されるのも面白い。闇市を成功させた綾女は、不動産、建設、運輸といった従来の事業に加え、GHQの不良軍人相手の商売、新たな公営ギャンブルの立ち上げ、関西の大物がバックにいる天才少女歌手・美波ひかり(モデルは美空ひばり)の東京でのマネジメントなどの興行にも参入する多角経営で、水嶽本家をさらに発展させる。
GHQのウィロビーやダレス、保守政治家の旗山市太郎(モデルは鳩山一郎)や吉野繁実(モデルは吉田茂)らも金と力を求めて水嶽本家に近付くが、綾女は大物政治家はいつヤクザを切り捨てるか分からないと警戒する。互いに相手を利用しても利用されないよう立ち回るギリギリの駆け引きを、虚実の皮膜を操りながら活写した著者の手腕は圧巻である。
部下の男たちの命を使い捨てる壮絶な戦闘で不利を覆す綾女だが、愛した男との結婚は許されず、復員した長男とは骨肉の争いになるなど人並みの幸福が許されずヒロポンに溺れる。唯一の救いは美波ひかりの成長だったが、それもダークな結末になるだけに、綾女の血みどろのサクセスストーリーは殺伐としていく。
成功と引き換えに心身をすり減らす綾女は、男性社会で働く女性が直面している諸問題の戯画のように思え、裏社会のフィクサーが戦後政治に食い込んでいた事実を踏まえるなら、本書で描かれた世界は現代とも無縁ではないのである。

評者︱阿津川辰海
2022年のマイ・ベストとくれば、謎解きミステリーとしても少女の成長小説としても一級品のクリス・ウィタカー『われら闇より天を見る』、ジュブナイル・ミステリーの雄編、シヴォーン・ダウド『ロンドン・アイの謎』、全編メールのみで構成された企み満載の本格ミステリーであるジャニス・ハレット『ポピーのためにできること』なども外せないが、今回は偏愛ベスト1という視点で挙げてみたいと思う。
新潮クレスト・ブックスから刊行されたエマ・ストーネクス『光を灯す男たち』は、刊行レーベルゆえミステリーとしては注目されていないが、ミステリーの枠組みをうまく取り込んだ文学作品の逸品である。灯台を描いた作品には、トニー・パーカー『灯台』、ケン・フォレット『針の眼』、ヨハン・テオリン『冬の灯台が語るとき』、大阪圭吉「燈台鬼」(中編)、三津田信三『白魔の塔』など、傑作が目白押しだ。『光を灯す男たち』は、なぜ灯台小説がこれほど魅力的なのかを探る手掛かりになる一作である。
本作は一九〇〇年にスコットランド沖フラナン諸島の中のアイリーン・モア島で起きた、三人の灯台守が行方不明になった事件をモチーフにしている。イギリスでは有名な実際の事件だ。直前まで生活をしていた痕跡がちゃんと残っているのに、理由も分からず人が消えてしまうという事態には、「メアリー・セレスト号事件」に似たうすら寒さを覚える。
本書は事件の舞台をあえて一九七二年に設定し、三人の灯台守を描く「一九七二年パート」と、彼らに取り残された妻たちと、彼女らにインタビューを試みながら真相に迫ろうとする海洋冒険小説家を描いた「一九九二年パート」を交互に描きながら、あの夜、あの灯台で、何があったのか、に少しずつ迫っていく。灯台のぼんやりとした灯りを頼りに、謎めいた霧の中に少しずつ分け入っていくような読み心地が、本書の最大の魅力である。事件そのものだけでなく、「残されてしまった」妻たちの視点も取り入れることで、「灯台」という主題の書きぶりも、現代小説としてのテーマ性も一段と研ぎ澄まされた。
新潮社のホームページには、著者エマ・ストーネクスによるエッセイが掲載されている。灯台への思い入れが語られたよい文章だが、その中に「去年(2020年)から今年にかけて、ある意味で、私たちはみな灯台守になったのではないかと思えてきた」という一節がある。
これこそ、この小説の感動の核心だと、私は思う。先の見えない状況の中、この小説が持つ灯台のような暖かな光が、私たちの孤独を癒すのだ。

評者︱前島 賢
今回は年間ベストというお題を頂いたものの、評者の担当であるライトノベルというジャンルで「ベスト」を決めるのはなかなか難しい。この枠にはファンタジーからラブコメからミステリ、SFと様々なジャンルが内包されているし、年間の刊行点数も二千点余。人気作なら既刊数十冊を数えることも珍しくはなく、さらにウェブ小説の動向も重要と、その全貌を掴むのさえ容易ではない。そこで勝手ながら、対象を2022年デビューした新人に絞り、連載中に惜しくも取り上げられなかった作品から選んだ。
『竜殺しのブリュンヒルド』は第28回電撃小説大賞にて銀賞を受賞した東崎惟子のデビュー作だ。科学技術の進歩が、絶対的強者だった竜を凌駕し、人類が竜を狩る側にまわり始めた時代。エデンと呼ばれる楽園の島で、白銀の竜に拾われた少女ブリュンヒルドは、竜を父に、深い愛情を注がれて育つ。だが、島は人間に侵略され、竜は無惨にも殺害される。義父を殺し、竜の娘を捕らえたのは竜殺しの英雄シギベルド・ジークフリート。彼こそブリュンヒルドの本当の父親だった。
これは父の仇を討つために父を狙う、ひとりの娘の復讐譚である。力では叶わない男を殺すため、少女は従順な仮面を被り、密かに狡猾な陰謀を巡らせる。仇の長年の友人や、仇の息子……すなわち自分の弟と親しくなったのも、その一環のはずだった。だが人と交われば、彼らの事情もわかってしまう。彼女の島が襲われたのは、帝国の存続のためにエデンの資源が必要だったからだ。義父を惨殺した男は、しかし弟の目からすれば、憧れてやまない目標だった。そして何より彼女の仇自身が、「竜殺し」であるのと同時にひとりの父親であった……。
本作の主要登場人物に根っからの悪人はいない。むしろ、皆が皆、己の意思で、自分の生きる道を切り開こうとする、英雄的とさえ呼べる者たちである。だが、彼らが信念を貫こうとすればするほどに、運命の歯車は、逆に彼らを逃れられない結末へと導いていく。その様は、ギリシャの古代演劇をも連想させてくれる。
11月には、続篇となる『竜の姫ブリュンヒルド』も刊行された。蛇足になるのではと、いささか心配もしていたが、本作の七百年ほど前を舞台に、身分も性別も異なる四人の若者の、竜と愛を巡る群像劇というまた違った語り口から、しかし本作同様の、「劇的」なカタルシスを見せてくれた。
はたして3作目は何を読ませてくれるか。できればこの調子で、ライトノベル界のソフォクレスやシェイクスピアなんて呼ばれる存在を目指してほしいと思う。

評者︱三宅香帆
ハリウッド映画を舞台にした、女性クリエイターたちを主人公に据えた物語──そんなモチーフだけでもう「こ、この話、好きかも」と期待が高まる。しかし本書はその想像をはるか超えた遠い場所に私たちを連れていってくれる。だからこの本を読んでよかった、と素直に思えるのだ。
主人公は二人いる。一人めの主人公は特殊造形師として働くマチルダ・セジウィック。戦後ハリウッド映画のとりこになった彼女は、やがて一体のクリーチャーを創り上げた。しかし時代は変わる。マチルダが熱中していた特殊造形の仕事は、コンピューター・グラフィックスに取って代わられてしまう。そして登場する二人めの主人公は、2017年にイギリスで活躍するアニメーター、ヴィヴィアン・メリル。彼女は将来を嘱望されるアニメーターだが、スランプに悩んでいた。そんな時、ある大きな仕事が舞い込んでくる。それは30年以上前に天才特殊造形師・マチルダが作り上げたクリーチャーを、CGによってリメイクするという依頼だった。
まだ女性のスタッフが少なかった戦後ハリウッド映画界で活躍した叩き上げのマチルダと、周囲から期待されている割に自分自身に対して自信を持てない現代のアニメーター・ヴィヴ。ふたりのクリエイターは、常に自分たちの創作に対して真摯で、そして迷っている。それは、創りたいものだけ創っていても、自分の創りたいものを創り続けることができないからである。
マチルダもヴィヴも、共通して「時代や世間が求めるものを創らなくてはいけないのか?」という点に悩んでいる。そしてその葛藤の末、マチルダは自分の創りたいものを創り、ヴィヴは自分が創りたいものが分からなくなってしまう。しかし自分の創作物を売って生活している人間で、世間が求めるものと自分が創りたいもののバランスに悩まない人間などいるのだろうか。きっと誰しもが悩むところなのだろう。自分の創りたいものはたしかにある。しかしそれだけ創っていても、求められることはない。ふたりのクリエイターの姿を通して、創作する人間の普遍的な苦悩を、本書は描く。
しかし悩んでいるだけで物語は終わらない。ふたりは創作の葛藤の果てに、読者も思いがけないラストシーンを見せてくれる。遠い場所に連れていってくれるもの、自分の予想もつかない場所に辿り着かせてくれるもの、それが創作なのだと、作者が自ら説いているようにも見える。クリエイターが悩み抜いた先の景色を、ぜひ堪能してほしい。
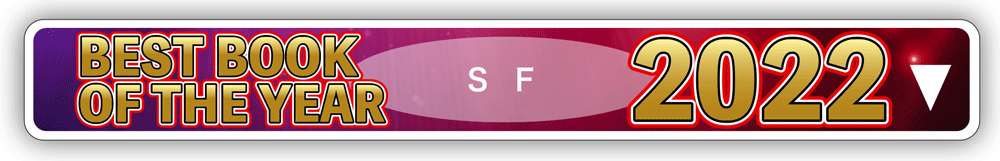
評者︱大森 望
本書は、TVアニメ化もされた大ヒット作『BEATLESS』以来、長谷敏司にとってなんと10年ぶりの新作長編。人間とテクノロジーの関わりを描く点は前作と同じだが、今回は人間の肉体と精神にスポットを当て、より生々しく切実に〝人間性のありよう〟に迫る。
もともとコンテンポラリー・ダンスのカンパニー「大橋可也&ダンサーズ」の公演(2016年)のために書き下ろした同名の中編が原型なので、本来の主軸はダンス小説だ。
時は2050年代。主人公は27歳のコンテンポラリー・ダンサー、護堂恒明。恵まれた体躯と鍛え上げた筋肉で身体表現の極限を追い求める注目の若手だが、バイク事故で右足を切断。AIで精密に制御される義足を装着し、過酷なリハビリとゼロからの訓練を経て、じょじょにダンサーとしての動きをとり戻していく。ロボットと共演する新作舞台でダンスに復帰することも決まり、新たな表現を切り開くべく、必死に模索と思索と練習をつづける恒明。
──と、ここまでなら王道の現代的サイボーグSF。テクノロジーと人間の共生は、現代SFの中心となるテーマのひとつだから、ダンスと組み合わせた作品も、過去にいくつか例がある。
ようすが変わってくるのは、コンテンポラリー・ダンスのレジェンドである父の護堂森が交通事故を起こしてから。同乗していた母は死亡。父も重傷を負う。しかも、回復の途上で、父が認知症を患っていることが判明。生活費を稼ぐためのアルバイト、父の介護、家事、あらゆる面倒が恒明にのしかかってくる。そしてその間にも、恒明にとって〝超えられない壁〟だった伝説のダンサーだった父がダンスを失い、人間性を失っていく。
危ないからやめろというのに一日に何度も風呂に入りたがり、入ったら出てこない父親と激しく口論する、まるでコントのような場面が恒明の絶望を浮き彫りにする。ダンスの練習がしたい、ダンスのことだけ考えていたいのにそれができないつらさ。身体表現における人間性とは何か? ロボットと人間が同じ舞台で踊ることにどんな意味があるのか? 哲学的・思弁的な問いかけを介護の現実がすべて押し流していく。排泄物の処理、掃除、洗濯、金策、兄との諍い、そして認知症患者との果てしない口論……。
八方塞がりの絶望的な状況の中で、恒明はそれでも公演実現のためにあがきつづける。介護パートがリアルすぎて小説のバランスを危うくしかねないくらいだが、だからこそクライマックスの舞台が深く胸を打つ。

評者︱マライ・メントライン
特にロシア軍のウクライナ侵攻以来、日本の国内世論・言論シーンで急激に明確化してきたのが、冷戦時代を引きずった戦争/平和観の陳腐化、そして大規模パワーゲーム的リアリズム思考の不足だ。パワーゲーム的思考の優位性は昔から保守論壇では大いに論じられていたが、得てして左派リベラル業界への愚弄挑発とセットで主張されるクセの強さがあり、重要な観点でありながら、一般層への強い訴求力を持てなかった印象がある。
だがこれは文芸界にとってテーマ化のチャンスであり、例えば、貴族→武家時代の移行期に生じたパラダイムシフトの内面性を鮮烈に描き、直木賞候補にもなった永井紗耶子の『女人入眼』は、この機を一見それとわからない形で活かした傑作といえる。そして、このムーヴに強烈な一撃を打ち込む、現時点での最強作と思われる逸品が『地図と拳』だ。
愛と怨念と執念と諦念が渦巻く本作の何が凄みの核心かといえば、19〜20世紀的な地政学に基づく列強パワーゲームのリアリズムと、南米文学の相貌も窺える大胆なマジックリアリズムの融合だろう。繊細にして剛毅、細部への執着を見せつけつつ広壮。単なる大風呂敷でない心身のスケールの大きさがホンモノだ。
人物設定もいい。例えば「異能」系のキャラクターに、いわゆる発達障害的な才人として解釈可能な余地を残してあるのは大きなポイントで、伝奇系とリアル系、どちらの嗜好の読者にも満喫可能な仕様となっている。ここには著者のジャンルクロスオーバー的な知的素養の強みが存分に活きているように感じる。
そして何より、史観と人間観。
大日本帝国の大陸進出をテーマとする物語には通例、当時の日本の国策の是非・善悪・好嫌についての見解表明を行うお約束的ステップが存在するが、本作の場合はそういった味付けを抜きに、帝国主義のリアルとはこういうものだという観点から、冷徹にそして熱く、列強の野望に満ちる浪漫と傲慢を矛盾なく描き抜いている点が素晴らしい。
真に重要なのは、後知恵めいた思想的イデオロギー的「正しさ」の主張よりも心的社会的メカニズムの掘り下げなのだ。ゆえに、陸軍の密偵も満鉄の技師も、宣教師も田舎町の顔役も、抗日パルチザンも憲兵将校も、想像力豊かな者も乏しき者も皆ひとしく、その内面の世界観や行動の動機がしっかりと魅力的に描かれる。脇役なのにこいつが次に何をするか、私は見たいと思わせる筆力こそ、小川哲という作家の凄さ、恐ろしさだ。人間の内奥に対する真摯な知的好奇心の結実。私は本作を二〇二二年のベスト小説に推す。

評者︱千街昌之
既に私があちこちの媒体に書評を寄稿している作品ではあるし、恐らく年末に発表される各種年間ベストテンでも上位を席巻していると予想されるのだが、二○二二年のベスト国産ミステリは何かと問われれば、これを挙げないわけにはいかない。白井智之の『名探偵のいけにえ 人民教会殺人事件』である。
一九七八年、探偵の大塒宗は、ニューヨークで消息を絶った助手の有森りり子が、新興宗教「人民教会」の教祖ジム・ジョーデンについて調査するため教団に潜入したことを突き止める。ガイアナにある教団の本拠地ジョーデンタウンに乗り込み、りり子と再会した大塒に対し、教祖は自らの「奇蹟」の力を誇り、信者たちは絶対に治るわけがないような大怪我を教祖に治してもらったと主張する。そして翌朝、鍵のかかった部屋の中で他殺死体が見つかる。これも「奇蹟」なのか、それとも巧妙なトリックか。
一九七八年にガイアナで実際に起きた「人民寺院事件」をモデルにしているが、この事件に関する予備知識を持たずに読んでも差し支えない。著者の作風の大きな特色だったグロテスク趣味は極力控え目にしているし(そのぶん、読者を選ぶ内容だったこれまでの作品よりも広い層に受容されそうだ)、今までと違って特殊設定ミステリでもないが、教団側の登場人物がみな奇蹟を信じているというシチュエーションは相当に特異ではある。そして、そんな登場人物たちの世界観を踏まえて、ラスト百数十ページに亘って繰り広げられる多重解決は圧巻そのもの。多重解決ミステリはダミーの解決がつまらないと白けるし、かといって真の解決よりダミーの解決が面白すぎても興醒めだが、本書の場合はどの解決にも力が籠もっており、多重推理を知り尽くした著者ならではのエキサイティングさに溢れている。著者が本格ミステリ作家としての自己の力量を全開にしたことが伝わってくる、掛け値なしの傑作だ。
因みに、私にとって二○二二年の国産ミステリの二位は小川哲の『君のクイズ』。あるクイズ番組の最中、問題文が一文字も読み上げられないうちに解答者が正解を出した……というユニークかつ不可解極まる謎を解き明かす物語である。『名探偵のいけにえ 人民教会殺人事件』が複雑な構成の大作なのに対しこちらはシンプルで分量もコンパクト、書き手も本格ミステリ一筋の白井に対し、小川はこの作品でミステリ界に初参入……と、何から何まで対蹠的な二作品だが、それだけ本格ミステリというジャンルが幅広い可能性を持っているという証明になりそうだ。
〈「STORY BOX」2023年1月号掲載〉
関連記事
未曾有のパンデミックで、自由に外出することがままならなかった2021年。人に会えず、家で過ごす時間が増える中で、あらためて本の魅力を実感した人は多いのではないだろうか。果てしない空想の世界へと誘ってくれる壮大な物語、弱った心や孤独に寄り添ってくれる優しい物語、怒涛の展開や謎解きに没入させてくれるスリリングな物語。