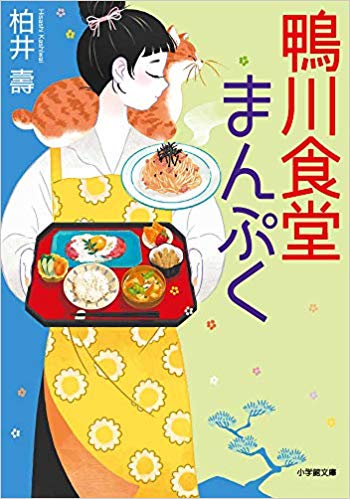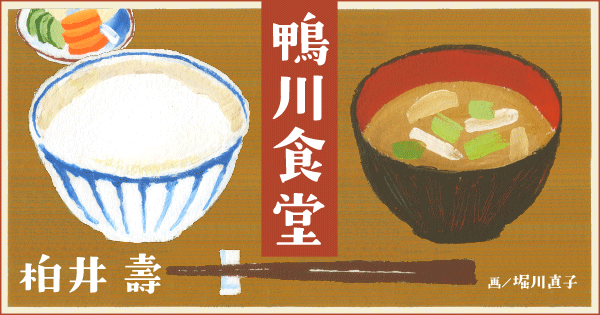「鴨川食堂」第1話 鍋焼きうどん 柏井 壽

第1話 鍋焼きうどん
「おめでとう。女性からプロポーズされたんやね」
こいしが小さく拍手をした。
「息子も賛成してくれよったから、そのつもりになったんやが、問題は食べ物や。ナミちゃんは関東の人間やさかいにな」
窪山が顔を曇らせた。
「それが鍋焼きうどん?」
「のろけるわけやないんやが、ナミちゃんは料理上手やねん。肉じゃがやとか炊き込みご飯、和食もええけど、カレーやとかハンバーグ作らせても玄人はだしや。餃子やら肉まんも手作りしよるしな。たいていの食いもんには何の文句もない。ヘタな店よりよっぽど旨い。せやのに、なんでかわからんが、鍋焼きうどんだけはアカン。一所懸命作ってくれよるんやで。けど、昔食べた味とは雲泥の差がある。鍋焼きうどんはわしの一番の好物やねん。それが……」
「わかった。お父ちゃんがなんとかしてくれる。まかしとき」
こいしが胸を叩いた。
「まかしとき、て言うといて、お父ちゃん頼りかいな」
窪山が苦笑した。
「もうちょっと詳しいに教えて。どんなお出汁で、具はどんなもんが入っていたか、とか」
こいしがペンを持って構えた。
「出汁はまあ、京都のうどん屋でよう出て来る味や。具かて、そない変わったもんは入っとらなんだ。鶏肉、ネギ、蒲鉾(かまぼこ)、麩、椎茸、海老天と玉子。そんなとこや」
「うどんはどうなん?」
「今流行りのさぬきうどんみたいな、あんなコシはない。くにゃ、っちゅうか、くたっ、というのか」
「京の腰抜けうどん、ていう、あれやね。だいたいわかった。けど、おっちゃん。ナミちゃんにも、このレシピていうか、どんな鍋焼きうどんか、て伝えたんやわね。それでも別モンになってしまうんやろ。案外難問かもしれんな」
こいしが顔をしかめた。
「材料が昔とは別なんか、味付けが違うのか。ようわからんけど」
「亡くなった奥さん、何か言うてはらへんかった? どこそこの店のうどん玉やとか、具はどの店のもんやとか」
「こっちがあんまり食いもんに興味なかったさかい。……そや、桝がどうとか、鈴がどやとか、藤ナントカと言うとったな」
「桝、鈴、藤。後は?」
ペンを持ったまま、こいしが窪山に顔を向けた。
「買いもんに行く前に念仏みたいに唱えとったさかい、それだけは今でも耳に残ってるんやが」
「他には? 味の記憶とか」
「最後に苦いな、と思うた記憶がある」
「苦い? 鍋焼きうどんが?」
「うどんが、というのやのうて、食い終わるときにいつも苦い……、いや、違うかもしれん。別のもんを食うてたときとゴッチャになっとる」
「鍋焼きうどんが苦いはずないと思うんやけどなぁ」
こいしがパラパラとノートを繰った。
「最後にもう一回だけ、あの鍋焼きうどんを食べたら、気持ちよう高崎に行けると思うんよ。郷に入っては郷に従え。あっちに行ったら向こうの味に馴染まんとな」
「よっしゃ。期待しとって」
こいしがノートを閉じた。
窪山とこいしが姿を現すと、流はリモコンでテレビを消した。
「あんじょうお聞きしたんか」
「ばっちりや、と言いたいとこやけど」
流の問い掛けに、こいしが自信なげに声をしぼませた。
「難事件っちゅうとこやろ。お宮入りにならんように頼むわ」
窪山が流の肩を叩いた。
「おっちゃんの第二の人生がかかってるんやから」
こいしが追い打ちをかけるように、流の背中をはたいた。
「せいだい気張らせてもらいます」
顔をしかめて、流が腰を折った。
「お勘定してくれるか」
コートを羽織って、窪山が財布を出した。
「何を言うてはりますねん。ようけお供えいただいたのに、何のお返しも用意してまへん。せめてメシ代くらいは」
「なんや、気付いたんかいな。線香立ての下に隠したつもりやったんやが」
「挙動不審は見逃しまへん」
顔を見合わせて、ふたりが笑った。
「次なんやけど、おっちゃん。再来週の今日でもええやろか」
こいしが窪山に訊いた。
「二週間後か。仕事が休みやさかい、ちょうどええ」
開いた手帳に舐めた鉛筆で窪山が印を付けた。
「聞き込みしてはったころを思い出しますな」
流が目を細めた。
「長年のクセは抜けんもんや」
窪山は内ポケットに手帳を仕舞い表に出ると、トラ猫が逃げ出した。
「どないしたん、ひるね。コワイ人と違うよ」
「飼い猫か? さっきは居らなんだが」
「五年ほど前から居ついてるんよ。いっつも昼寝してるみたいやから、ひるねて名前付けたんやけど、可哀そうなんよ。お父ちゃんにいじめられてばっかり」
「いじめてるわけやないがな。人さんに食いもんを出す店の中に猫が入って来たらアカンと言うとるだけや」
流が口笛を吹いても、道のむこうで寝そべるひるねは知らんぷりを決め込んでいる。
「ほな、頼むで」
窪山は西に向かって歩いて行った。
「今回も難問か?」
後ろ姿を見送って、流が隣に立つこいしの顔を見た。
「難しいんと違うかなぁ。どういう料理か、窪山のおっちゃんはわかってはるのに、再現出来ひんて言うてはるんやから」
こいしが引き戸を開けた。
「ものは何や?」
店に戻って、流が椅子に座る。
「鍋焼きうどん」
こいしが向かい合って腰かけた。
「どっかの店のか」
「亡くなった奥さんが作ってはった」
こいしがノートを広げる。
「そら間違いのう難問や。千恵子はんは料理がじょうずやったし、そこに想い出という調味料が効いとるさかいな」
流がページを繰る。
「どう考えても、普通の鍋焼きうどんやろ? せやのに再現出来ひんて言わはるんよ」
「千恵子はんは生粋の京都人やったさかい、味付けはだいたいわかる。住まいが寺町やから……」
流が腕組みをして考え込んでいる。
「亡くなった奥さんのこと、よう知ってるん?」
「知ってるどころか、なんべんも手料理を食わせてもろたがな」
「それやったら話が早いやん」
「けど、この鍋焼きうどんは食べさせてもろた記憶がない」
流がノートの字を丹念に追う。
「今度のお相手な、ひと回りも若い女の人なんやて。うらやましいやろ」
「アホ言え。お父ちゃんは掬子ひと筋やて、いつも言うとるやろ。それより、そのナミちゃんという女性は上州人なんやな」
流が顔を上げた。
「実家が高崎やて言うてはったから、たぶんそうやと」
「高崎か」
流が首をひねる。
「なんや鍋焼きうどんを食べたなって来た。今夜は鍋焼きうどんにしよか」
「今夜だけやない。当分は毎晩鍋焼きうどんや」
ノートから目を離さずに流が言った。
2.
一年で最も寒いのは節分過ぎだと、多くの京都人が言う。その言葉を実感しながら、窪山は夕暮れ迫る正面通を東に向かって歩いていた。
どこからか豆腐売りのラッパが聞こえて来る。家路を急ぐランドセルがすぐ横を通り過ぎて行く。ひと時代前に戻ったような錯覚を覚える。長い影を斜めに伸ばして窪山は『鴨川食堂』の前に立った。
顔を覚えているのか、トラ猫のひるねが足元に擦り寄ってくる。
「流にいじめられとるのと違うか」
屈みこんで頭を撫でると、ひるねがひと声鳴いた。
「えらい早かったやん。おっちゃん早ぅ中に入りいな。寒いやんか」
引き戸を開けて、こいしが背中を丸めた。
「入れてやらんと風邪ひきよるで」
「猫は風邪ひかへん。お父ちゃんに見つかったら、えらいこっちゃし」
「こいし。ひるねを店に入れたらアカンで」
厨房の中から流が大きな声を上げた。
「言うたとおりやろ」
こいしが目配せした。
「毎年ふたりでやっとるんか」
コートを脱ぎながら窪山がぼそっと言った。
「ふたりで? 何のことよ」
茶を出しながらこいしが訊いた。
「豆まきしとるんやろ。〈鬼は外、福は内〉と流がまいて、こいしちゃんが〈ごもっとも、ごもっとも〉と後ろを付いて歩く。今でもちゃんと、京都らしいしきたりを守っとるんやな」
「なんでわかったん?」
こいしが目を白黒させる。
「敷居の隙間に豆がはさまっとる」
窪山が鋭い視線を床に走らせた。
「ホンマに昔のクセが抜けへんのですな」
白衣姿の流が厨房から顔を覗かせた。
「ちょっと早かったか。待ち切れいでな。歳取ると忙しのうていかん」
「昼を抜いて来てくれ、てなご無理を言うて申し訳なかったですな」
カウンター越しに流が頭を下げた。
「流の言いつけはちゃんと守ったで。朝早うに喫茶店でいつものモーニングを食べたきりや」
空腹をまぎらすように、窪山は茶を一気に飲んだ。
「もう十分ほどくださいや」
流が声をかけた。
「ナミちゃんとは順調なん?」
テーブルの支度を整えながらこいしが訊いた。
藍染のランチョンマットを敷き、柊を模(かたど)った箸置きに杉箸を並べる。唐津焼の呑水(とんすい)を中央に、右端に青磁のレンゲを置いた。
「先週退職しよってな、もう高崎へ帰ってしもた。社長が残念がってたわ」
窪山は、マガジンラックから夕刊紙を抜き出した。
「外食ばっかりなんと違う?」
「昼も夜もコンビニ弁当と外食ばっかりじゃ、ええ加減飽きるな」
広げた新聞を下げて窪山が笑った。
「もうちょっとの辛抱やんか。向こうに行ったらバラ色の生活が待ってる」
こいしが目を輝かせた。
「この歳になって、舅(しゅうと)を抱えるんやで。そない甘いもんと違うわ」
「楽あれば苦あり。人生すべて甘辛です」
流はわらで編んだ鍋敷きを、ランチョンマットの左上に置いた。
「いよいよ登場やな」
新聞をたたんで窪山がパイプ椅子に座り直した。
「新聞はそのままにしとってください。昔食べてはったときと同じように」
言い残して、流が背を向けた。
「なんでわかった」
今度は窪山が目をしばたく。
「わしも昔のクセが抜けまへんのや」
振り向いて、流が小さく笑った。
「こんな映画を観たような気がするなぁ。昔は相棒やったふたりの老刑事が再会する、いう話」
こいしがふたりを交互に見る。
「老だけ余分や」
窪山が舌を打った。
「こいし。ちょっと来てくれるか」
厨房に入って流が手招きした。
「仕上げはわたしがするみたいよ」
「しっかり頼むで」
窪山がこいしの背中に声をかけた。
厨房に入ったこいしに、流が何ごとかの指示をしている。窪山は流に言われたとおり、新聞を広げて読むともなく、紙面に目を落とした。やがて馨(かぐわ)しい出汁の香りが漂って来て、窪山は思わず鼻をひくつかせた。
「時間帯は違いますけど、こんな感じやったと思います」
窪山と向かい合って腰かけた流がリモコンを操作すると、神棚の横で夕方のニュース番組が映し出された。
「仕事が終わって家に帰る。着替えるのも面倒くさい。上着を脱いでネクタイだけ緩めて、ちゃぶ台の前に座る。新聞広げて、テレビ点けて、と台所の方から出汁のええ匂いがして来る」
流が言葉を紡ぐと、目を閉じて窪山が顔を天井に向けた。
「あのころは、うちでも同じでした。家に帰ったらヘトヘトで何もしとうない。口もききとうない。腹は減っとる。〈早ぅメシにしてくれ〉と掬子に怒鳴って……」
流がため息を吐いた。
「〈テレビ観てへんのやったら消したらどうやのん〉て千恵子にどやされてな」
窪山が繋ぐ。
「〈テレビ観るのも仕事のうちや〉て言い返す」
「刑事の家てなもん、どこも一緒やったんやろな」
流と窪山の掛け合いが続く。
「そろそろ玉子入れてもええかな」
厨房からこいしが声を上げた。
「その前に豆壺(まめつぼ)に入ってるヤツを鍋に入れてくれ」
流が厨房に声を向けた。
「全部入れるん?」
「全部や。按配(あんばい)よう振りかけて、お玉でよう混ぜる。そこで一気に強火や。ぐつぐつと煮立ったら玉子を割り入れて、火を止める。すぐに蓋をせい。きっちりしたらアカン、ちょっとだけずらすんやぞ」
流が指示を出す。
「タイミングが大事なんやな。鍋焼きうどん、っちゅうやつは。出て来てしばらく、新聞を読み耽っとって、よう千恵子に怒られたわ」
「〈早よ食べてえな。うどんが伸びるやんか〉ですやろ」
流が合いの手を入れる。
「さあ出来ました」
ミトンをはめた両手で、湯気が立ち上る土鍋を、こいしが運んで来た。
「どうです? 昔と同じ匂いですやろ」
流の言葉に、窪山は鼻を鍋に近付けて、湯気の勢いに負ける。
「ナミちゃんの鍋焼きうどんは、この匂いがせんのや」
窪山が首をかしげる。
「ゆっくり召し上がってください」
立ち上がって、流はこいしと厨房に引っ込んだ。
合掌して窪山が土鍋の蓋を取ると、湯気は一段とその勢いを増した。
青磁のレンゲを取って、まずは出汁をひと口飲む。窪山は大きくうなずいた。箸でうどんを掬(すく)う。音を立てて啜り込もうとして、その熱さにむせる。鍋底からネギを取り出し、うどんに絡めて口に運ぶ。鶏肉を噛みしめる。蒲鉾を齧(かじ)る。その度に窪山は、うんうんとうなずく。
ついさっきまで冷え切っていた身体が、一気に熱を帯び、額にはじんわりと汗が滲み出した。上着のポケットからハンカチを取り出して窪山が額と頬に当てる。
思い出したように海老天をつまみ上げ、箸でふたつに切った窪山は、頭の方だけを口に入れた。
「尾っぽの方は玉子と絡めるんやが、問題はその玉子やな。黄身をいつ崩すか。それを考えながら食べるのが、鍋焼きうどんの醍醐味っちゅうもんや」
窪山は笑みを浮かべて、ひとりごちた。
「どないです」
遠慮がちに、流が窪山の横に立った。
「不思議やなぁ。昔の味そのままや。ナミちゃんにも同じように伝えたんやが」
窪山は箸を止められずにいるようだ。
「ものの味てなもんは、そのときの気分で大きく左右されます。きっと窪山はんは、そのナミちゃんの料理を食べはるとき、緊張してはるんやと思います」
流がやわらかな眼差しを向けた。
「身構えとるのは間違いないな」
窪山がまたハンカチを使った。
「多少の違いはあるかもしれまへんけど、気を楽にして食べたら、昔食べてはったんと、ナミちゃんが作らはる鍋焼きうどんも大差はおへん」
流が窪山と向かい合って腰かけた。
「けど、やっぱり味は全然違うで。どんな手品使うたんや」
窪山が不服そうに言った。
「推理と言うて欲しいですな」
「未だに取り調べのクセが出よる」
笑みを浮かべて窪山がうどんを啜る。
「まず出汁です。というより、千恵子はんがどこへ買い物に行ってはったか。そこから始めました。お住まいの十念寺辺りへ行って来たんですわ。昔から秀さんは近所付き合いが苦手やったみたいですが、奥さん連中は親しいしてはったみたいで、ご近所さんに尋ねたら、千恵子はんのことをよう覚えてはりました。一緒に買い物にも行ってはったそうです。それがこの『桝方(ますがた)商店街』ですわ。出町にありますやろ」
地図を広げて、流がペンで指した。
「豆餅(まめもち)を買うのに、ようけ行列が出来とる餅屋のとこやな」
箸を持ったまま、窪山が首の向きを変えた。
「それは『出町ふた葉』です。その横の道を入ったとこが『桝方商店街』。錦市場と違うて、地元の人が通う商店街ですわ。たいていの買いもんは、ここで済ませてはったようです。いろんな業種が揃うてましてな、昆布と鰹節(かつおぶし)やら、出汁の材料はこの『藤屋』、鶏肉は『鶏扇』、野菜は『かね康』と、千恵子はんは決めてはったそうです。今でも奥さん連中は浮気せんと、ここで買うてはります」
流が商店街のパンフレットを見せる。