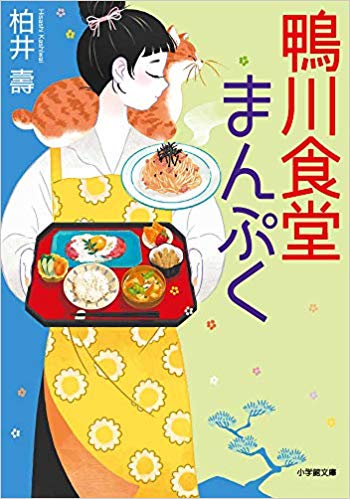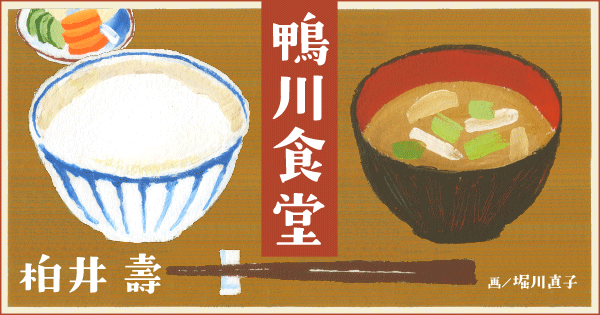「鴨川食堂」第1話 鍋焼きうどん 柏井 壽

第1話 鍋焼きうどん
1.
東本願寺を背にした窪山秀治(くぼやまひでじ)は、思わずトレンチコートの襟を立てた。寒風に枯葉が宙を舞う。
「比叡颪(ひえいおろし)か」
信号が青に変わるのを待ちながら、窪山は両眉を八の字にした。
〈京の底冷え〉という言葉どおり、真冬の京都盆地には三方の山から寒風が吹き下ろす。窪山が生まれ育った神戸でも六甲颪が吹き渡るが、寒さの質が違う。
正面(しょうめん)通を歩きながら、遠くに目を遣ると、東山の峰々が薄らと雪化粧していた。
「すんません。この辺に食堂ありませんか。『鴨川(かもがわ)食堂』という店なんですが」
赤いバイクにまたがる郵便局員に窪山が訊いた。
「鴨川さんのお宅なら、その角から二軒目です」
郵便局員は至極事務的に、通りの右側を指した。
通りを渡った窪山は、しもた屋の前に立った。
店の体をなしていない二階建てのしもた屋には、かつて看板とショーウィンドウがあったようだ。外壁に二箇所、白いペンキが四角く乱雑に塗られている。とは言え、空き家のような寂寞(せきばく)感はなく、人の温もりを持つ、現役の店らしき空気に包まれている。
無愛想な構えで遠来の客を拒んでいる一方、辺りに漂う飲食店特有の匂いが客を誘うようでもあり、中からは談笑の気配が漏れて来る。
「流(ながれ)らしい店やな」
窪山はかつての同僚、鴨川流と過ごした日々を思い出していた。今は共にリタイアしているが、先に職を辞したのは後輩の流の方だった。
店を見上げて、窪山がアルミの引き戸に手をかけた。
「いらっしゃ……窪山のおっちゃんやんか」
丸盆を持ったまま、こいしの顔が固まった。
流のひとり娘であるこいしを、窪山が初めて見たのは、まだ赤子だったころだ。
「こいしちゃん、ますます、べっぴんさんになったな」
窪山がコートを脱いだ。
「秀さんやないですか」
聞きつけて、厨房から、白衣姿の鴨川流が出て来た。
「やっぱり、ここにおったんか」
目を細めて窪山が、流に丸い笑顔を向けた。
「よう見つけてくれはりましたな。ま、どうぞお掛けください。汚い店ですけど」
流が手拭いでパイプ椅子の赤いシートを拭いた。
「俺の勘もまだ衰えとらんな」
かじかんだ指に息を吹きかけて、窪山が腰かけた。
「何年ぶりですやろ」
流が白い帽子を取った。
「奥さんの葬式以来と違うかな」
「その節はありがとうございました」
流が一礼すると、こいしがそれに続いた。
「なんぞ食わしてくれんか。ごっつ腹が減っとるんや」
若い男性客が丼(どんぶり)を掻き込んでいるのを横目にして、窪山が言う。
「初めてのお客さんには、おまかせを食べてもろてますのやが」
流が言った。
「それでええ」
窪山が流と目を合わせた。
「すぐに用意しますわ。ちょっとだけ待っとってください」
帽子をかぶって流が背を向けた。
「鯖はアカンで」
窪山が茶を啜った。
「わかってますがな。長い付き合いですさかい」
振り向いて、流が言った。
窪山が店の中をぐるりと見渡す。厨房との境にある五つのカウンター席には男性客がただひとり。四組のテーブル席に客はいない。壁にもテーブルにも品書きと思しきものはない。柱時計は一時十分を指している。
「こいしちゃん、お茶をお願い」
男性客が空になった丼をテーブルに置いた。
「浩さん、もうちょっとゆっくり食べんとアカンよ。消化に悪いやんか」
こいしが清水焼(きよみずやき)の急須を傾けた。
「その様子やと、まだヨメには行っとらんみたいやな」
窪山が浩と呼ばれた男とこいしを交互に見た。
「高望み、っちゅうやつやと思いまっせ」
盆に載せて料理を運んで来た流を、こいしがにらみつけた。
「えらい、ごっつおやないか」
窪山が目を見張る。
「ご馳走てなもんやおへん。今の流行り言葉で言う、〈京のおばんざい〉ですわ。昔はこんなもん、人さまからお金をいただいて出すようなもんやなかったんですけどな。秀さんはきっと、こういうのを食べたいんやないかと」
盆から小鉢や皿を取り、流が次々とテーブルに並べる。
「ずばりや。流の勘も衰えとらんがな」
皿を目で追う窪山に、流が言葉を加えてゆく。
「あらめとお揚げの炊いたん。おからのコロッケ。菊菜の白和え。鰯の鞍馬煮。ひろうす。京番茶で煮た豚バラ。生湯葉の梅肉和え。それに、こいしが漬けとる、どぼ漬けです。どれも大したもんやおへん。強いて言うたら、固めに炊いた江州米(ごうしゅうまい)と、海老芋の味噌汁が一番のご馳走やと思います。ゆっくり召し上がってください。味噌汁には粉山椒をたっぷり振ってもろたら、身体が温たまります」
流の言葉にいちいちうなずき、窪山は目を輝かせる。
「おっちゃん、熱いうちに」
こいしに急かされて、窪山は粉山椒を振ってから、味噌汁の椀を手にした。
先に汁を啜ってから、海老芋を口に入れる。噛みしめて、二度、三度窪山がうなずく。
「ほっくりと旨いなぁ」
薄手の飯茶碗を左手に持った窪山は、迷い箸をしながら、次々と小鉢に手を伸ばす。タレの染みた豚バラを白飯の上に載せ、口に運ぶ。噛みしめると、口の端に笑みが浮かんだ。サクッと衣を噛みくだき、おからを味わう。ひろうすを舌に載せると薄味の煮汁が滲み出て来て、唇から溢れる。窪山は箸を持った手で顎を拭った。
「ご飯、お代わりしましょか」
こいしが丸盆を差し出した。
「こんな旨いメシ、久しぶりや」
相好を崩して窪山が、茶碗を盆に載せた。
「たんと召し上がってくださいね」
盆を持って、こいしが厨房へ駆け込んだ。
「こんなんで、よろしおしたかいな」
こいしと入れ替わりに出て来た流が、窪山の横に立った。
「大したもんや。わしと一緒に地べたを這いまわってた人間が作った料理やとは思えん」
「その話は堪忍してくださいな。今は、しがない食堂のオヤジですさかい」
流が目を伏せた。
「窪山のおっちゃん、今は?」
茶碗にこんもりと飯を盛り付けて、こいしが差し出した。
「一昨年、定年になってな。今は大阪の警備会社で役員をしとる」
窪山が艶々の白飯に目を細めて、箸をつけた。
「天下りっちゅうやつですがな。よろしいやないか。けど、昔とちょっとも変わってはりまへんな。相変わらず鋭い目付きや」
流が窪山と目を合わせて笑った。
「菊菜の苦みがよう効いとる。京都ならではの味やな」
窪山は、菊菜の白和えを飯に載せてさらえた後、どぼ漬けの胡瓜(きゅうり)に歯を鳴らした。
「よかったら茶漬けにしてください。鰯の鞍馬煮も載せてもろて。こいし、熱いほうじ茶を」
流の言葉を待っていたように、こいしが万古焼(ばんこやき)の急須を傾ける。
「京都では鞍馬煮と言うんか。山椒の実と一緒に煮たもんを、わしらの方では有馬煮と言うんよ」
「お国自慢っちゅうやつですかな。鞍馬も有馬も山椒の名産地ですさかい」
「知らんかったわ」
こいしが言った。
さらりと茶漬けを食べ終えた窪山は、楊枝を使って、ひと息吐いた。
カウンター席の右手横には藍地の暖簾が掛かり、厨房への出入口になっている。流が出入りする際に垣間見ると、厨房の一角には畳敷きの居間が設えてあり、壁際には立派な仏壇が鎮座していた。
「ちょっとお参りさせてもらえるか」
奥を覗き込んだ窪山を、こいしが仏壇に案内した。
「おっちゃん、なんか若返ったんと違う?」
両肩に手を置いて、こいしが窪山の顔をぐるりと見回した。
「からかいなや。おっちゃん、もう六十を越えたんやで」
線香を上げて、窪山が座布団を外した。
「ご丁寧にありがとうございます」