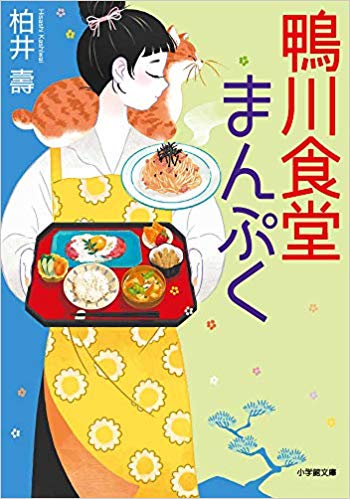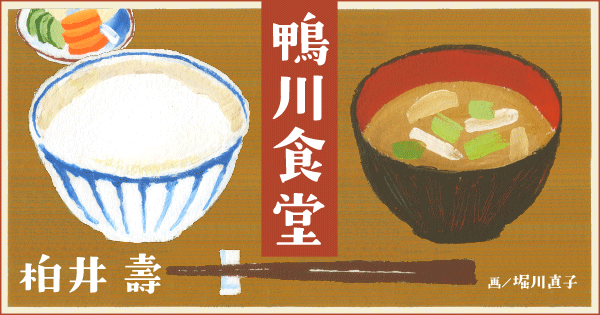「鴨川食堂」第1話 鍋焼きうどん 柏井 壽

第1話 鍋焼きうどん
流がきっぱりと言った。
「わかっとるわい。けど、最後にこの鍋焼きうどんに出会えてよかった。しっかり味おうとかんと」
窪山がていねいにレンゲで出汁を掬う。
「冬場は三日にあげず食べてはりましたやろ」
「わしの好物やと千恵子はよう知っとったし、寒いときには手っ取り早うて旨いさかいな」
「昼も夜もない暮らしに、千恵子はんも、掬子もよう付き合うてくれよった。突然家に帰って来て、すぐにメシにしてくれ、て無茶言うてたのに」
流がテーブルに目を落とした。
「湿っぽい話はやめときいな。おっちゃんの第二の人生が始まるていうのに」
瞳を潤ませて、こいしが水を差した。
「苦いな」
窪山が口の中から黄色いかけらを取り出した。
「柚子(ゆず)の皮です。香り付けに入れてはったんでしょう」
流が言った。
「そうか、これが苦かったんか」
窪山がまじまじと見る。
「上に散らすのが普通ですけど、それやと秀さんはポイと捨てはるに決まってる。千恵子はんは鍋底に柚子皮を忍ばせてはった。秀さんが〈苦い〉と言わはったら、最後までお出汁を飲んだしるし。千恵子はんに伝わるんです」
「大した推理や。地取りも完璧やしな。思うてたとおりの鍋焼きうどんやった」
窪山がレンゲを置いて合掌した。
「よろしおした」
「これで気持ちよう高崎に行けるね」
こいしの言葉に、窪山は黙ってうなずいた。
「探偵料は幾ら払うたらええんや?」
窪山が財布を出した。
「お客さんに決めてもろてます。お気持ちに見合うた金額をここに振り込んでください」
こいしがメモ用紙を渡す。
「せいだい気張って払わせてもらうわ」
窪山がトレンチコートを羽織った。
「どうぞお元気で」
引き戸を開けて流が送り出す。
「年に何度かは墓参りに帰ってくるさかい、そのときは覗かせてもらうわ。旨いもん食わしてくれ」
外に出た窪山の足元に、ひるねが擦り寄って来た。
「ナミちゃんと仲良ぅせんとアカンよ」
こいしがひるねを抱き上げた。
「上州名物は何かご存知ですか」
流が窪山に訊いた。
「空っ風とカカア天下」
「知ってはるならよろしい」
流がにやりと笑う。
「おっちゃん、風邪ひかんようにな」
「早ぅヨメにいかんと、流も後添えをもらえんで」
「言われんでもいきます」
こいしが口を尖らせる。
「流。ちょっと気になってるんやがな」
立ち去りかけて、窪山が流に顔を向ける。
「なんです?」
「たしかに昔のままの味で旨かったけど、ちょっと塩気が濃いように思うたんやが」
「気のせいですやろ。千恵子はんが作ってはったお出汁、そのままやと思います」
流がきっぱりと言い切った。
「そうか。気のせいか。おおきに。しっかり味は覚えさせてもろた」
窪山が口元を指した。
「お元気で」
青い闇に包まれ始めた正面通を、西に向かって歩く窪山にこいしが声をかける。
「末永ぅ、お幸せに」
振り向いた窪山に、流が深々と頭を下げた。
「喜んでもらえてよかったなあ」
店に戻って、こいしが片付けを始める。
「あの歳になって馴染みのない土地に、しかもお舅さん付きで住む。苦労も多いと思うで」
流が白衣を脱いで椅子の上に置いた。
「ええやんか、甘い新婚生活が待ってるんやし」
「さあ、どうなんやろな。わしはもう要らん。生涯掬子ひとりや」
「お父ちゃん、肝心のレシピ渡してあげるの忘れたやんか。まだ、その辺に居はるやろから、持って行って来るわ」
「いつまでも京都を引きずったらあかんやろ。千恵子はんの料理は忘れて、向こうに行ったらナミちゃんの作る料理を味おうたらええ」
「けど、窪山のおっちゃん、取りに戻って来はるかもしれんやん」
「秀さんは、ようわかってはる」
「それやったらエエんやけど」
「そろそろ夕飯にしよか。腹減って来たで」
「また今夜も鍋焼きうどんやろ?」
「違う。今夜はうどん鍋や」
「似たようなもんやんか」
「浩さんから電話があってな、明石のええ鯛が入ったんやそうな。それを持って来てくれるんやて。鯛鍋しよう言うて」
「ホンマ! 鯛鍋して、あとからうどん入れるんやね。そや。思い出した。さっき最後に入れたんは何やったん? あの豆壺に入ってた」
「即席のだしの素や。向こうに行ったときのために、そういう味に慣れとかんとあかんやろ」
「それで味が濃いて言うてはったんや」
「これが千恵子はんの味や。秀さんがそう思い込んでくれはったら、向こうに行って多少濃い味やっても納得出来る。同じ味やと思えるはずや」
「それやったら、最初から入れといたらエエんと違うの」
「そんな濃い味で鯛鍋出来るかいな」
「さすがお父ちゃん」
こいしが流の背中をはたいた。
「雪やな」
流が窓の外を見た。
「ほんまや。降ってきた」
「今夜は雪見酒や」
「ぴったしのお酒を買うてあるんよ」
こいしが冷蔵庫から酒瓶を取り出す。
「『雪中梅』やないか。ちょっと甘口やが鯛鍋にはよう合うやろ。掬子の好きそうな酒や」
流がやさしい眼差しを仏壇に送った。