SPECIALインタビュー ◇ 八木詠美『休館日の彼女たち』
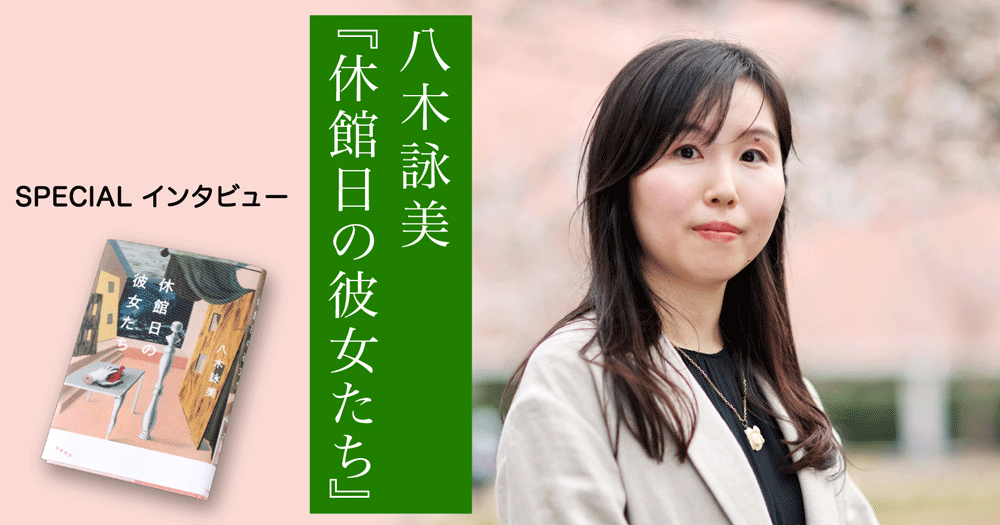
2020年、八木詠美は『空芯手帳』で第36回太宰治賞を受賞した。主人公の柴田が「偽装妊娠」によって、社会の凝り固まったジェンダー規範から離れ、身も心も生まれ変わっていく物語は、大きな驚きをもたらした。あれから3年、2作目となる『休館日の彼女たち』を書き上げた八木に、話を聞いた。
『空芯手帳』はデビュー作にして、アジアや欧米の18の国と地域で翻訳された。日本のみならず、世界に驚きを持って迎えられた新人作家の八木だが、小説を書くようになったのは社会人になってからだという。
「『太宰治賞』は2回目の投稿で受賞しました。学生時代から何か書いてみたかったんですが、書き方がわからなかった。社会人になって、急に書けそうだなと思ったんです。というか、学生時代は書くことに憧れていただけで、書く必要がなかったのかもしれません。社会人になって、会社勤めをしたり、結婚したり、自分のいる環境が変化し、理不尽な出来事に直面する機会が増えた結果、現実とは異なる世界を描くことに救いを求めたのかもしれませんね」
『空芯手帳』のあらすじはこうだ。会社員の柴田は、自分には無関係な打ち合わせが終わった後、コーヒーの片付けをすることに嫌気がさし、発作的に妊娠を偽る。その後も「偽装妊娠」を続け、やがて彼女の体型は妊婦のごとく変化し、妊婦が集うエアロビクス教室に通いだして、〝ママ友〟まで作ってしまう。そんな奇想天外なストーリーだが、あくまでも八木は自身の実感から小説を書き始めているというのだ。ちなみに、八木が体験したイヤなこととはなんだったのだろうか。
「会社では『空芯手帳』みたいな露骨なハラスメントはなかったんですけど、普通に働いているだけで、イヤなことって誰にでも起こるじゃないですか。例えば仕事をしていると『八木さんはおっとりしてるよね』とよく言われるんですが、『なんでそういう風に決めつけるんだろう』って私は思うんです。仕事場だから必要最低限のことしか喋らないだけで、普段の私は、好きな女性アイドルのことを興奮して話したりするんですよ(笑)。誰かの一面だけを見て、性格を決めつけるのはおかしい。小説を書くときにも、他者のことを知ったような顔をしないということは、心がけています。また、『空芯手帳』はちょうど結婚する直前に書き始めたんですが、夫の親類に初めて会ったとき『少子化だから、子供は3人産みなさい』と言われたんです。そこで私は子供を3人産まない代わりに、小説というフィクションを妊娠して出産しようと決めました」
八木の小説では「他者のことを知ったような顔をしない」という不可侵の倫理が貫かれる。一方で、徹底的に無視されてしまう存在も登場する。例えば、『空芯手帳』では、柴田の同僚である〝東中野さん〟がそうだ。彼は、妊娠を偽る柴田の体調をいつも過剰なまでに気にかけ、会社ではほぼ毎日誰かに謝っている。気弱で、コミュニケーションが不得手な東中野に対して、社内の誰も興味を抱かない。
「私の同僚にも、すごい勢いで謝ってみんなをびっくりさせる人がいました。その人が会社を辞めたとき、『どこの部署だったんだろう』と気になり同僚たちに聞いたんですが、そもそも彼の名前を知っている人がいなかった。コミュニケーションがうまく取れないことで、〝居ない〟ものとして扱われてしまう人がいるんですよね。でもそういう人は内面をうまく出せないだけで、当然何か考えているし、感情も持っている。そういうことを書きたいとは思っていました。それに誰しもがコミュニケーションの取り方に独特の癖とか偏りがあるはずで、それを極端にしたのが、東中野さんなんだと思います。私自身、子供の頃は誰かと友達になる方法がわからなくて『友達になろう』と宣言してから、仲良くしてもらう不器用な子だったんですが、あの頃の自分がそのまま突っ走っていたら、東中野さんになっていたかもしれません」
誰もが抱えているコミュニケーションの難しさや、人間関係の居心地の悪さを、見事にすくいとるからこそ、八木の小説は海を越えて読まれるのだろう。それにしても、デビュー作がいきなり翻訳される感覚というのは、いかなるものだろうか。
「翻訳された本が届くと知っている人の知らない一面を見るというか、同僚の休日を垣間見るような感じでした。私は10〜20代の頃から、友人も多い方ではなくて、周りの人とどう繋がっていいかよくわからないタイプの人間でした。今でも人と人がわかりあうことはないと思って生きています。でも、会ったこともない海の先にいる方々が、自分の小説を読んでくれるのは、希望だなと思います」
小説のヒントはモーニング娘。に
日本だけでなく世界の読者を獲得した『空芯手帳』は、フェミニズムの文脈で読まれることも多い。そのことについて八木自身はどう考えているのだろうか。
「私はフェミニズム小説を意図して書いたわけではないですが、結果的にフェミニズム小説として読まれることは意識していて、翻訳されて再認識しました。ただ、私の出発点はあくまでも『妊娠した、と嘘をついたらどうなるか』であって、ジェンダー構造への問題意識ではないんですよね。最初の一節を書いてみてはじめて、『こんな嘘をつく人は、会社でハラスメントを受けているのかもしれない』と気づいたんです。今の日本でまったくジェンダーの問題と無縁で過ごせる女性はいないですしね」
『空芯手帳』の面白さはもちろん「偽装妊娠」というスキャンダラスなテーマにもあるが、一方で、柴田はごく普通の女性でもある。彼女の趣味は音楽鑑賞で、ライブやフェスにも行く。トルコ旅行に一人で出かけるようなアクティブさもある。友達もいる。読者の身の回りにもよくいるタイプ。というか、読者自身がそうであってもおかしくない。そんなごく普通の女性だから、おかしなことをしていても、真実味が増してくる。
「普通の人を書くのが好きで、生活の描写を重ねていく癖はありますが、それは裏を返すと、物語を動かすのが下手ということでもあるんですよね。プロットをきちんと組み立てて、物語で読ませることができない。それよりも描写していくうちに『こういう女性が働く会社はこんな場所なんじゃないか』と気づき、言葉が連なっていく。人物や生活の描写に引っ張られて、物語が生まれていく感覚なんです」
八木は、尾崎翠や松田青子、津村記久子といった女性作家の作品に親しんできたという。特に津村の作品に対しては「お仕事小説なのに、全然働いていないのが好き」と語る。一方で、学生時代にずっと読んでいた村上春樹の小説には、違和感を覚えるようになったとも言う。
「あるときから、真っ先に女性の登場人物の外見的な美醜を描写するところが気になってきて。私自身、人の顔を見て『綺麗だな』と無意識に思うことはあると思うんですが、わざわざ言葉にはしたくないんですよね。私はモーニング娘。がすごく好きなんですが、それも見た目に惹かれてるわけじゃないんです。彼女たちはたしかにすごくかわいいですが、見ているうちに、顔がかわいいかどうかってどうでもよくなるんですよね。彼女たちのパフォーマンスはすばらしく、存在そのものが気高い。そこに美醜は関係ないんです。モーニング娘。の話題になると、『今、かわいい子いるの?』と聞かれがちなんですが、そういうときは『外見とかの問題じゃなくて、モーニング娘。は気高い存在なんだよ』と答えてます。そういえば『空芯手帳』を書き終わってから、『泡沫サタデーナイト』という楽曲を改めて聴くと、その歌い出しがこの小説のテーマだったんだなと気づきました。小説の世界のヒントになっている、と言ってもいいかもしれません」
わかりあえなくても、つながることの意味
この春、八木が3年ぶりに発表した2作目『休館日の彼女たち』は、「博物館のヴィーナス像とラテン語で喋るバイト」を題材にした前作を上回る突拍子もないものだ。それについて八木は「1作目で『偽装妊娠なんてできるわけない』という批判があったので、だったらもっとありえない話を書こうと思ったんです。彫刻が話す小説ならありえないことが嫌な人は最初から読まないかなって」と笑う。そんな〝ありえない話〟でも、八木ならではのユーモアと五感に訴えかける描写によって、グイグイ読ませる。奇妙なバイトに就いたホラウチリカは、普段は冷凍倉庫で働き、目には見えない〝黄色いレインコート〟に長年苦しめられている。しかし彼女はヴィーナスとの交流を通して息を吹き返す。そして博物館に留め置かれたヴィーナスもホラウチを通して、誕生から2000年来抱えていた〝諦め〟と向き合うことになる。一方的に鑑賞者から見られるだけの存在だったヴィーナスは語る。「決めた。今度から私も見ることにするの、来館した人たちを。博物館だからってこっちばかりが見られているのも癪だから」と。
「着想を得たのは、彫刻のヴィーナス像ではなく、マネキンからでした。コロナ禍で人がまばらなデパートで見た裸のマネキンが妙に気になったんです。もし自分があのマネキンだったら、何を喋るんだろうって。また、小田原のどかさんの『近代を彫刻/超克する』という論考集を読んで、女性の彫刻について考えるようになりました。小田原さんは「裸の女」の彫刻が公共空間に「量産」されていると指摘されているんですが、たしかに思い返してみると、私が通っていた図書館にも『自由』というテーマの裸婦像があるんですよ。男性の場合、西郷隆盛とか大隈重信みたいな名前のある偉人が服を着て像になるけれど、女性は匿名で服を脱がされる。そんな裸婦像のどこが『自由』なんだろうと疑問を感じるようになりました」
ヴィーナス像が徹底的に脱がされている一方で、彼女の話し相手になったホラウチは〝黄色いレインコート〟を常に羽織っている。他者には見えないが、ホラウチにとっては実体として感じられるレインコート。セックスをしているときも脱げず、ホラウチと他者を完全に隔てるそれは、もともとひとつの比喩に過ぎなかったという。
「最初は『レインコートで外界を遮断し、目の前にいる人と親しめない』という比喩だったんです。でも書いているうちに『ホラウチリカは本当に黄色いレインコートを着ている』と気づいて物語を考え直しました。ここも描写に引っ張られて物語が生まれていきましたね」
レインコートから逃れられないホラウチが、ラテン語を習得したのは大学時代のこと。教授とふたりきりで、現代社会では使われなくなったラテン語で日常会話をするときだけ、息を吹き返せるのだった。
講義中、私は何度かレインコートのことを忘れた。膜のように絶えず私を覆うそれを。私は言葉を交換することができた。教授と私は多くの人の口もとから絶えつつあるその言葉で会話をし続けた。フランケンシュタインの怪物に息を吹き込まんばかりに。
──『休館日の彼女たち』より
ホラウチがラテン語によってヴィーナスと濃密な関係を築く中、博物館に住み込みで勤めるハシバミは言葉に失望している。
「言葉はいつだって最後には果てしない差異を浮かび上がらせます。言葉で橋をかけて、橋の長さに彼岸を知る。僕はそれがさびしいんです。許せないといってもいい。(後略)」
──『休館日の彼女たち』より
彼はヴィーナスの美しさに魅了されながらも、ラテン語を使ってヴィーナスと語らうのではなく、その外面的な美しさにとどまろうとする。ヴィーナスとホラウチ、そしてハシバミの三角関係が、クライマックスに向けて小説をドライヴさせていく。
「主人公のホラウチリカはコミュニケーションが苦手で、職場とか身近にいる人とはうまく喋れない。でもラテン語というすごく昔の、とても難しい言葉だったらなぜか話せるとしたら楽しいお話になりそうだなと思いました。ホラウチはわかりあえなくてもヴィーナスと一緒にいたいと思うんですよね。対照的にハシバミはどうせわかりあえないなら、もう喋る必要はないと拒絶する。ハシバミはすごく寂しくて、その孤独に耐えきれない人だから、わかりあえなさを認められないんです」
ここでも八木は、コミュニケーションの不可能性と、それでも交わろうとすることの意味を考えている。わかりあえなくても、言葉を紡ぐ。その先で、人と人は出会い直せる。ヴィーナスはハシバミに言い放つ「あなたが怖がっているものは言葉。あと連帯」という言葉は鮮烈だ。
「その言葉を帯に書いてもらえばよかったかな?(笑)たしかに、わかりあえなくても話したり、人と人が繋がったりすることが、この小説のテーマでした。実際に生きていると、ハシバミのように、わかりあえない相手の異論をじっくり聞くんじゃなくて、黙らせてしまうようなコミュニケーションしか取れない人っているんですよね。SNSだと〝アンチ〟という言葉に象徴的で、アンチの言うことは聞かないっていう人は少なくない。それは違うよなと私は思うんです」
『休館日の彼女たち』は、人間同士の「わかりあえなさ」を丹念に描きながらも、その読後感が極めて爽やかだ。また、エンディングで語り手の視点が変わることによって、味わい深さも倍増している。ここには八木の好きな映画のエッセンスが、はからずも入っているという。
「ラストシーンはパク・チャヌク監督の『お嬢さん』のイメージがあるかもしれません。あと小説を書き終わってみると、トッド・ヘインズ監督の『キャロル』もイメージが重なるなと思いました。『キャロル』では、裕福な奥様(ケイト・ブランシェット)と、カメラマンになりたいけど消極的な若い女性(ルーニー・マーラ)が出会う。若い女性は奥様に憧れるけど、そんな奥様も不自由でままならないものを抱えている。その構図は『休館日の彼女たち』と同じですよね。だから、私の中でヴィーナス像の顔は、ケイト・ブランシェットなんです(笑)」
前作の発表から、『休館日の彼女たち』が書き上がるまで、3年近くかかっている。会社員として働きながら小説を書く八木だが、なぜこの月日が必要となったのだろうか。一読者として八木にしか書けない小説をもっと読みたいと思ってしまうが、この3年は環境の変化も大きく苦労したという。
「コロナ禍になって、今まで小説を書いていた図書館が閉鎖されて、書くペースが掴めなくなってしまったんです。最近引っ越して自宅で書けるようになったんですが、前は夫と二人暮らしの部屋では書けなくて。いろいろ書ける場所を探している頃は苦しくて、一時的に不眠症にもなりました。『休館日の彼女たち』は苦労しましたが、これからは短編も長編もいろいろ書きたいです。『空芯手帳』で、ニューヨーク公共図書館の2022年の Best Books の一冊として取り上げてもらった際リストを眺めていたら、世界には本当にいろんな小説があるんだなと知りました。自分が小説を出すことに『こんなものを出して大丈夫か』というためらいが拭えなかったのですが、こんなに奇妙な小説がいっぱいあるなら、自分もあんまり気にせずたくさん書けばいいんだと思えるようになりました」
八木の手によって、世界に奇妙な小説が一つでも多く増えることを切に願いながら、『休館日の彼女たち』を味わいつくしたい。
八木詠美(やぎ・えみ)
1988年長野県生まれ。早稲田大学文化構想学部卒業。2020年『空芯手帳』で第36回太宰治賞を受賞。世界18の国と地域で翻訳され、特に2022年8月に刊行された英語版(『Diary of a Void』)は、ニューヨーク・タイムズやニューヨーク公共図書館が「今年の収穫」として取り上げるなど話題を呼んでいる。
(取材・文/安里和哲 撮影/横田紋子)
〈「STORY BOX」2023年5月号掲載〉



