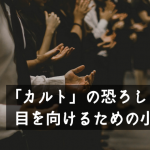アジア9都市アンソロジー『絶縁』刊行記念対談 ◆ 村田沙耶香 × チョン・セラン

アジア文学という冒険がはじまる
昨年12月、刊行された『絶縁』は、村田沙耶香、ハオ・ジンファンをはじめとするアジア9都市の作家9名が参加するアンソロジーである。多くの作品が書き下ろしで、韓国でも老舗出版社・文学トンネから同時刊行された。この異例プロジェクトは、テーマや参加作家の枠組みも含め、韓国の人気作家チョン・セランの次の発案から始まったという。「アジアの若手世代の作家たちが同じテーマのもと短編を書く―そんなアンソロジーを作ってみませんか?」昨年9月末、ソウル国際作家フェスティバルに出席するため渡韓した村田沙耶香は、イベントの合間を縫ってチョン・セランのもとを訪ねた。日韓を代表する作家の初対談は、「絶縁」に込めた思いにはじまり、お互いの作品講評、創作論にまで多岐に及んだ。
絶縁という言葉には「中間」がない
──お二人が実際に会うのは今日が初めてということなので、まずはこの場に参加された感想をお聞かせください。
村田
(チョン・セランから)この小説のアンソロジーの「絶縁」というテーマをいただいたことにすごく感銘を受けていて、お会いできるのをとても楽しみにしていました。
チョン
私もずっと村田沙耶香さんの小説を読んできたので、実際にお会いできる今日という日を、春からカレンダーに印を付けて指折り数えていました。先日、他の小説家と集まる機会があったのですが、村田沙耶香さんにお会いすることを話したら、みんなにうらやましがられて。本当に私はラッキーで、貴重な機会に恵まれたんだなと実感しました。
──こうした多国籍のプロジェクトは、言語や契約関係といった実務的な難しさが伴うせいもあり、非常にまれなことだと思います。チョン・セランさんに質問ですが、このプロジェクトを始めることになったきっかけや、「絶縁」というテーマを選んだ理由についてお聞かせください。
チョン
日本の文学界の方々との交流は、いつも意義深くて楽しいものだったので、日本の出版社(小学館)から今回ご提案をいただいたときもぜひやってみたいと思いました。最初は韓国と日本の作家がそれぞれ半分ずつ執筆するというプロジェクトでしたが、調整がなかなか難しくて。それなら(一作品あたりの)分量を少なくして作家の負担を減らし、これを機に韓日文学界の友情をアジアの他の地域にも広げられたらいいなと考えたんです。
アジア各国の作家さんに余裕を持って原稿依頼をするために、テーマを早めに決定しなければならなかったのですが、この数年間を振り返ったとき、長い付き合いだった人、好きだった人、憧れていた人との別れを経験してきたことに気付きました。
その現象が私だけではなく、周囲の多くの人に起こっていたのです。この時代は人と人が別れる時代なんだな、そのことについてアジアの作家のみなさんと語り合ってみたいと思い、テーマを決めました。ここまでが私がやった仕事です。私はアイデアを提供しただけで、その後の執筆依頼などはすべて出版社の方々がやってくださったので、とても感謝しています。参加してくださった作家のみなさまにも御礼申し上げます。

村田
私の記憶が正しければ、最初に小学館の編集者さんからメールを頂戴したとき、そこには「日韓それぞれの作家たちの競作のような形で原稿を執筆・掲載できないか、とチョン・セランさんにご依頼しました。するとセランさんから、『同じテーマでそれぞれ違う短編小説を書いたアンソロジーを出してみたいです。今、思い浮かんでいるテーマは「絶縁」です』とご提案いただきました」という内容が書かれていました。その規模の大きさとテーマにぞくりとしました。セランさんの視野の広さと発想に痺れるような気持ちでした。
日本語では〝ぜつえん〟と発音しますが、各言語で意味も少しずつ違っているでしょうから、それを知ることもすごく面白いだろうし、他の言語で作家さんがどんなふうに書くのかも楽しみでした。私自身もたくさんの別れとか、いろんな形での絶縁、人とは限らない絶縁を感じることがあったので、とても深く刺さるテーマでした。
──韓国では〝絶縁〟というと、悲壮な感じがしますよね。友達関係や恋人関係ではあまり使われません。
チョン
この〝絶縁〟という単語が面白いなと思ったのは、すごく重いか、あるいは軽いノリで使われて、中間がないという点です。家族関係で絶縁と言ったら、それこそもう戸籍から抜いてしまうぐらいの局面で使われますが、友達同士でふざけて「私たち、もう絶交よ!」みたいに(「絶縁しよう」と)冗談めかして言うことはあっても、それ以外に日常生活で使われることがあまりないんです。それが興味深くて、極端な言葉だなと思って、このテーマを選びました。
村田
とても面白いですね。日本語でも〝絶交〟という言葉は友達同士で、それこそ冗談めいて使ったりする言葉ですが、〝絶縁〟は、縁という見えないつながりをすべて断ち切るというような印象とインパクトがある言葉だと思います。お互いが向かい合って崖に立っていて、双方の間には真っ暗な闇しかないような。そういうものすごく壮絶なイメージを持つ言葉だと思います。
──コロナ禍では、人と会うことや海外との交流が難しくなりました。表面的にはそういったことも絶縁のきっかけになっていると思いますが、他にも私たちが絶縁を経験することになった原因があるとしたら、それは何だと思いますか。
村田
個人的には、〝絶縁〟と言うと、ただ縁が途切れるというだけではなくて、そこに〝絶望〟があるような感覚があります。あくまでも私の想像ですが、たとえばコロナが原因で誰かとの連絡が途切れるとか会えなくなるということではなく、その人が自分の人生から消滅するというだけのことでもない。人間同士の〝絶縁〟という言葉からは、何らかの個人的な大きな絶望が、(絶縁の)きっかけになるのではないかという想像が私にはあります。
チョン
村田さんがおっしゃった、絶縁に内包された〝絶望〟について、私ももっと深く掘り下げてみたいなと思いました。というのも、絶望が訪れた後には〝転換〟が可能となるのではないかとずっと考えていたんです。私たちが通過している今の時代が、これまでの生き方に疑問を抱かせている気がします。個人であれ集団であれ、ひたすら成長を重視して駆け抜けてきたけれど、はたしてその方向性は正しかったのか? 他の方向性を模索すべきではないか? という思考の転換が生じ得る。このところの混乱は、これまでの時代に別れを告げる過程なのかもしれません。だからこそ、村田さんの作品に惹かれたのだと思います。直線的な成長とは異なる方向性のミニマリズムが感じられるというか。今回の作品を読んで、私も(村田の作品「無」に登場する)〝無街〟に帰依しそうになりました(笑)。
──〝アジア〟というエリア、あるいはアイデンティティについてはどう思われますか。
村田
私は大人になるまで日本を出たことがありませんでした。「無」という作品では特権の中を生きている主人公を書いているのですが、学生の頃の私は、日本という国の中で、誰にもルーツを聞かれることがなく、見た目も言語の発音も日本人だと認識されながら生きたことは、恐ろしいほどの特権の中を生きることなのだという点について、とても無自覚だったと思います。自分が透明だった。透明でいられる特権をずっと持っていたわけですが、日本という国を飛び出していろいろな方と交流するようになり、少しずつ、アジア人という自分のアイデンティティを自覚するようになりました。気付くのが遅くなってとても恥ずかしいのですが、そういう恐ろしい透明さの中に自分がいたことについてよく考えています。そういう意味でも、アジアの作家が集まった本に参加できて、とても嬉しいです。
チョン
私も韓国人として享受している透明な特権について、見つめ直してみなければいけませんね。確かに、外の世界を経験すればするほど、アイデンティティを意識するようになります。ちょっとしたエピソードですが、シンガポールのガーデンズ・バイ・ザ・ベイというホテルで光のショーがあって、最後に映画『ラヴソング』(ピーター・チャン監督、1996年)でテレサ・テンが歌う「甜蜜蜜」が流れると、アジア人だけが感傷的な表情になるんです。私もそうでしたが、ぐっときて涙ぐむ人もいたり。欧米や他のエリアの観光客はそれを「なんでかな?」という表情で眺めていました。そのとき気づいたんです。人の心、内面を構成する文化的な要素は、自分の国だけではなく、隣接した文化圏から浸透するものも多いですよね。文学や映画、ドラマ、音楽、美術、ダンス、ファッション、建築……さまざまな分野において、境界を超えて流れ込んでくるものについて考えさせられました。ですから、アジア人は自分で思っている以上に繫がっているという気がします。こういう交流がもっと増えて、お互いのつながりを発見できる機会になればいいなと思います。
いつか本当の〝無〟まで到達した世界を描いてみたい
村田が今回書き下ろした「無」は、「絶縁」に正面から取り組んだ作品だ。グリーン・ギャル、喪服ガール、リッチナチュラル……さまざまなブームの流行り廃りの末に、若者の間で〝無〟が流行し、世界各地にそのライフスタイルを実践する〝無街〟が出現した。無か、混沌か、人々が翻弄される世界を描いている。
──村田さんは以前から「絶縁」というテーマに深い関心をお持ちだったように思いました。今回の「無」は、どのように生まれましたか。
村田
最近すごく興味があるのが、同じ場所にいても、人それぞれ違う光景を見ているということです。絶縁という言葉は、そうした繫がっている断絶を私にイメージさせました。「無」では、同じ時代に生きているけれど、違う世界を生きている三人を三つの視点から描いてみました。〝無〟ということに最近すごく興味があって、自分が空っぽなのではないかと思うときが増えています。自分の言葉はどこからきたのか? 今、発している言葉も本当に自分から湧き出たのか、自分に入ってきた文化から発生したものなのか? それとも他者の模倣なのか? どこまでが私のオリジナルの言葉なのかわからないまましゃべっていることがあって、自分に対して空っぽのコップのようなイメージを持つことが増えました。それで、みんなが無になろう、空っぽになろうとしている光景を自然に想像しました。私は小説の結末がどうなるかをまったく決めないで書くのですが、この小説の中では語り手は本当の意味では空っぽになりませんでした。彼らが〝無〟と呼んでいるものは暗い穴のようなもので、その穴はどす黒いうめきのようなものを孕んでいました。語り手が空っぽになろうとしても、その空洞が叫び声をあげ、なかなかそれは消去できませんでした。いつか本当の〝無〟まで到達した世界を描いてみたいです。
──「無」の中には「安定志向シンプル世代」「リッチナチュラル世代」など、さまざまな表現が出てきますが、こうした世代に対する意識はどのように生まれたのでしょうか。
村田
小説を書き始めた頃はわかっていませんでしたが、時代が変容していく小説を何本か書いているうちに主人公が見ている光景よりさらに引いた場所に、もう一台カメラが置いてあって、時の流れを見つめている感覚を抱くようになりました。たとえば、親世代が使っている言葉が消えたり、私たちの世代から新しく言葉が発生して、意味を変えながら消えていったり。または昔は食べていたものを今は食べなくなったり、絶対に食べなかったものを喜んで口にするようになったり。世界は少しずつグラデーションで変わっていくのだと感じ、そのことに強い興味を持つようになりました。世代が違う人物が自分とは違う文化をごく自然に味わっている。彼らからなにげなくその文化の破片がこぼれ落ちてきたときに、自分や同世代の友人がまったく違う感覚を抱く。その光景に惹かれるのです。私はいつも小説を書くとき、自分の無意識を攻撃しているような感覚があります。語り手が見ている時の流れとは違う時間の流れやそこに広がる光景の存在を強く感じるようになったのは、自分が無意識では知っていた光景を小説を通じて思い知らされたからかもしれません。
──ご自身はどの世代に属していると思われますか。
村田
私は、この小説を書きながら〝無〟の世代のような気がしていました。空っぽの世代。なぜそう思うのかわからないのですが。ただ、世代は完全に分裂しているわけではなく、グラデーションで繫がっています。そこが面白いところだと思っています。
──チョン・セランさんはこの作品をどのように読まれましたか。
チョン
まずは母娘関係、あるいは親子関係について、言葉にするのが難しい部分が実に鋭く解釈されていた点が本書のテーマにぴったりでした。何と言っても、作品全体に本当に奇妙な揺らぎがあるところが魅力的でした。この人の視点から見たとき、あの人の視点から見たときに発生する揺らぎの中で、読む人も一緒に揺れることになるという特別な体験でした。振動と混沌をもたらしてくれるこの作品を愛しています。先ほどお話ししたように、私はこの〝無〟という概念にすっかり魅了されたのですが、少しでも苦しさを感じている人であれば、同じように魅了されるのではないかと思います。でも、先ほど村田さんがこの作品を執筆したとき、空っぽのコップみたいな感じがしたとおっしゃったので、苦しさからこういうテーマが生まれたわけではないことがわかりました。だとしたら、この〝無〟というアイデアにたどり着くまでに、村田さんが抱き続けてきた問いはどのようなものなのでしょうか。
村田
私が繰り返し自分に投げかけている質問ですが、人間ではない生き物から見た人間の姿というか、宇宙人から見たエイリアンとしての人間みたいなことをずっと考え続けています。苦しさという観点から言えば、私は子どもの頃から本当に内気で、しゃべるのが得意ではなくて、おどおどしていて、早く普通の人間になりたいと思いながら過ごしていました。それは命を脅かすほどのものすごい苦しさで、ずっと私を切り刻んでいたと思います。でもいつからか、その〝普通の人間〟ということ自体が、とても奇妙で、いびつで、興味ぶかい虚構なのではないだろうかと、小説の語り手たちが感じ、呟くようになりました。私は小説の中で、人間の目を捨てたいと願うようになりました。その眼差しで見たとき、どんな光景が広がっているのか、少し異常に思えるほど知りたくて、固執しています。脳の外に出たいのです。それは大きな問いとしてずっと私にあるように思います。〝無〟というイメージも、その問いとかなり密接に接続しているように感じています。
ねじ曲がった論理がもっともらしい顔をする
チョン・セランが書き下ろした「絶縁」は、放送作家を巡るジェンダー問題を扱っている。6人の女性放送作家に甘い言葉を囁いて近づき、あげくインターネットで行状を告発された男への処遇を巡って、主人公佳恩(カウン)が親しい先輩夫婦と対立する。映像制作会社に勤める佳恩は、恋人の横暴なふるまいに悩んでいた自分を救ってくれた先輩夫婦を、家族のように慕っていたのだが――。
──チョン・セランさんの「絶縁」という作品では、人間関係におけるはっきりとした絶縁が描き出されています。この物語は、主人公の佳恩が友達の善貞(ソンジョン)、亨祐(ヒョンウ)との縁を切る物語でもありますが、不道徳な行為をした人物が社会からどのように縁を切られるか。その明確な基準というのは存在するのか、という問いを投げかけているようにも見えました。この作品はどのように構想したのですか。
チョン
いろいろなきっかけがあったと思います。表面的には文学界で問題を起こした人物が復帰する際に繰り返されるパターンについて書きたいという気持ちがありました。たとえば、ある人は信頼を得るために大変な苦労をするのに、またある人の言葉は実にたやすく共感と同情を得て、二度目、三度目のチャンスを得るということがありますよね。同じ人間であっても、心の通じ合う回路がねじれているということについて書かなければと思ったのです。小説に書いた内容とは違いますが、同じ経験に関する記憶が家族と異なっていたこともモチーフになりました。どうして私の記憶だけが違っていたんだろう、と驚いたんです。ここ数年、精神的に参っていた時期があったのですが、もしそんな時期にどこかで証言をするようなことが起こったら、どんな目に遭っただろうか?
そういう過程もまた、さまざまな出発点の中の一つでした。そしてまた、私は今まで葛藤や摩擦は抑制されるのではなく、表に溢れ出てきたほうが健全であり、時が過ぎれば回復や治癒が可能だと信じていたのですが、その考えが変わったこともきっかけの一つです。回復も治癒もできない、分裂と破裂だけが残る葛藤もあるんだなと思うようになったんです。単純に不愉快なだけの出来事と完全に違法な出来事の間には、とても広くて複雑なスペクトラムがありますよね。包丁でスパッと切るようには分けられない、あいまいな事件の場合、それを解釈する人々の意見もバラバラになりますが、ねじ曲がった論理がもっともらしい顔をすることがあります。この小説はそれぞれにゆがんだ面を持つ人物がでてくる不快な小説です。全員を、すべての文章を疑っていただけたらと思います。読む人がピンボールのようにぶつかり、はねながら、自分ならではの答えに行きつく小説を書きたかったです。私はふだん不快な小説は書かないタイプですが、今回のテーマには合うだろうと判断しました。私としては新しい試みでした。
──作品中の「現代の結婚とは結局、一つの画面をずっと一緒に見続ける行為ではないか」という文章が印象的でした。伝統的な観点から離れて、共同体の形を再定義するという面で興味深かったです。そこから派生して、「現代の友達とは些細な日常生活だけではなく、モラルを共有する関係」と言うこともできるでしょうか。
チョン
その部分は、コロナ禍で私が画面を眺める時間が長くなった経験をもとに書いた文章なので、それほど深い意味はありません(笑)。ですが、さまざまな活動が遮断された状態で、人間関係の骨組みがあらわになったのではないかと感じることはありました。コロナ禍の前までは、人と会って一緒に食べたり飲んだり、スポーツをしたり、映画を見に行ったりしながら、深い会話をしなくても人間関係を維持することができましたが、それらが消えた結果、会話だけが残ったわけです。じっくり見てみると、真剣な会話ができるグループと、長い付き合いだからお互い諦めて関係を続けていこうというグループに分かれていました。モラルというところまでいかなくても、会話の時点で枝分かれする地点があって、人間関係のレントゲンのようだなと感じました。
村田
(「絶縁」を)静かで深い痛みを感じながら読みました。私自身の人生の記憶から、似た痛みが蘇ってくるような感覚もありました。価値観による、こういう形の絶縁がいろんな人の記憶にあるような気がしています。私自身も誰かを静かに諦めたことが何度かありました。諦めたままその人と人間関係を続けていくということもあったと思います。その人の前で心の扉を開くことはもう絶対にないと思いながらも縁は切らず、その人が人生に存在し続ける。でもこの小説に描かれていることは、そこから一歩踏み出すということ。すごく悲しいことでもあるけれど、主人公の勇気や力のようなものを感じました。諦めつつも絶縁はしないという選択ではなく、それをちゃんと伝えて生きていくことを選んだというのは、ものすごく大きなことに思えます。主人公は、自分を裏切らないで生きていくことを選択していると感じました。それで、痛みもあるけれど、とても大切で力強い一歩の物語でもあると、自分の魂の声、叫びから耳を塞がず進んでいく、そういう美しさもある作品だと思いました。
チョン
私にはできないことを主人公にやらせたような気がします。現代は、言葉にしない〝絶縁〟のほうが多い時代だと思います。「あんたとはもう会わない」「あなたとは仕事はもうしません」と思っても、それを口に出すことは少ないですよね。フィクションの小説の中だから、爆発できるのだと思います(笑)。
- 1
- 2