『翡翠色の海へうたう』刊行記念対談 深沢 潮 × 内田 剛
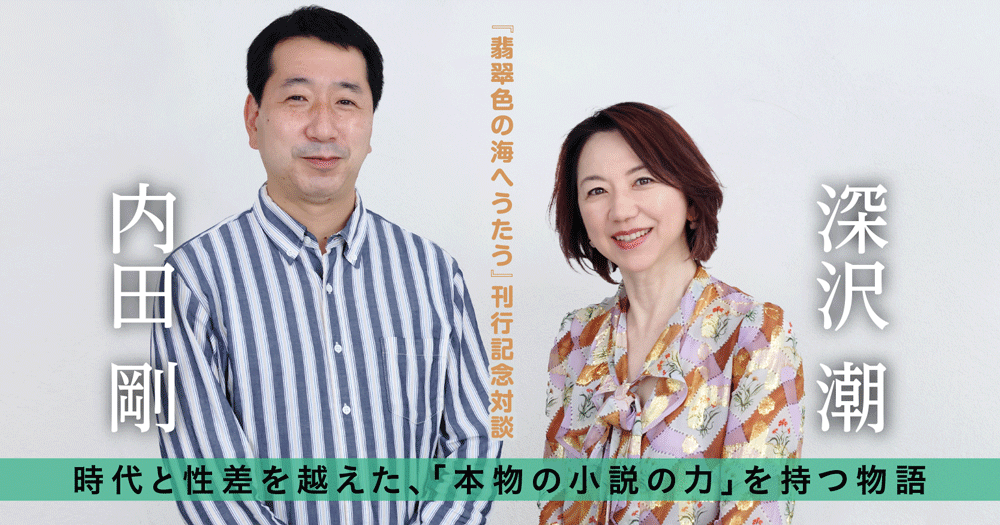
「深沢潮の到達点であり、出発点の物語」。最新作『翡翠色の海へうたう』をそう絶賛するブックジャーナリストの内田剛さん。小説家を目指してもがく契約社員の葉奈と、戦時下の沖縄で名前を奪われ「穴」として扱われる女性。時代を越えて交差する2人の物語から見えてくる希望とは? 深沢さんと内田さんが語り合いました。
当事者でなければ書く資格はないのか?
内田
僕は昨年まで30年間、書店勤めをしていたので、店頭でどう売ろうかも含めて気になっている作家が何人かいるんです。深沢さんはその筆頭株。新作が出るたびに、今度は何をどう書くんだろうといつも楽しみにしていました。『翡翠色の海へうたう』も相当ハードルを上げて読み始めたのですが、期待はまったく裏切られなかった。「これが本物の小説の力だ」と感じましたし、作家・深沢潮の到達点であり、新たな出発点だと思っています。
深沢
ありがとうございます。確かに私はよく他の人が避けるテーマを書く作家だと言われるのですが、自分としてはそういった気負いがあるわけではないんですよ。在日コリアンの問題もそう。周囲のマジョリティには馴染みがなくても、私にとっては日常であり、親しみのある感情を書いているつもりです。
内田
本作は2人の女性を軸に物語が進んでいきます。小説家を目指す契約社員の葉奈と、戦時中に沖縄に連れてこられた韓国人女性。沖縄をテーマに選んだきっかけは?
深沢
沖縄のことや慰安婦の問題は、ずっと気になってはいました。小説に書こうと考え始めたのは6年くらい前。遠いきっかけはそれより前の家族旅行で沖縄の戦跡を訪れたことです。それから徐々にこのテーマで書きたいという気持ちが湧いてきて。その後、取材で訪れた阿嘉島で、慰安所のお世話をしていたおばあさんにお話を伺うことができました。その方は韓国から連れてこられた女性たちが歌っていたアリラン(韓国の望郷の歌)を記憶していて、実際に私の前で歌ってくださったんですね。それを聴いた瞬間、パーッと頭の中に構想が浮かんできました。
内田
主人公の葉奈は、深沢さんと同じく沖縄に何の関わりもなく、慰安婦のこともほとんど知らなかった女性です。「当事者じゃないと書いてはいけないのだろうか」と悩む彼女の姿には、深沢さん自身が投影されているのでしょうか。
深沢
自分を託している部分はありますね。でも最初はもっと私に近い人物だったんです。在日コリアンで、すでに作家デビューしているけど、何かブレイクスルーが欲しいと思っているような。でも編集さんと相談していく中で、「もっと読者に近い人物に」と提案されて、自分が作家志望だった頃を振り返りながら葉奈という人物をつくりました。あの頃の私は、「今、ウケるテーマは貧困だろうか」「婚活かな」と社会問題を切実に考えるよりは、ネタとして見るような傾向があったんですよ。そんな当時を思い出しながら書きました。
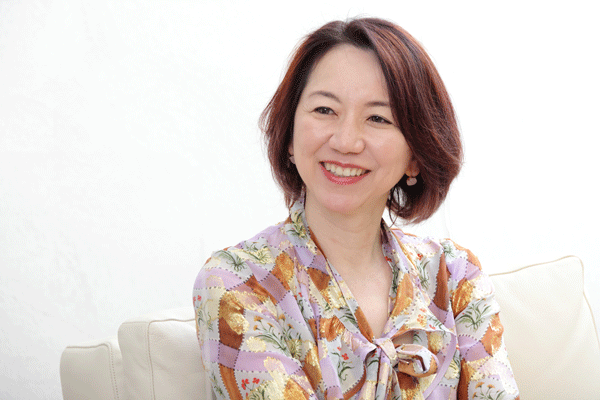
内田
「当事者でなければ書いてはいけないのか?」というテーマって難しい問題ですよね。深沢さんが普段から考えていらっしゃる作家としての在り方や目指すところが、葉奈というキャラクターを通して言霊のように伝わってきました。
深沢
知らないことそれ自体は、別に責められることではないと思うんです。何かのきっかけで知ることができたら、そこから頭の片隅に置いておいてくれればいいことですから。かつて戦争が起きて、慰安婦として扱われた女性たちがいた。それは男性と女性の間に起きた悲劇でもありますから。
内田
戦中のパートは、読んでいてやっぱりつらい部分もあって。僕は男性ですから、こうはありたくないと思う男の残酷さも描かれていて。でもこの本の感想をフェイスブックに投稿したら、女性のベテラン書店員から「こんなに残酷な物語なのに美しく感じた。読んでいてもつらくなかった」というコメントをもらったんですね。彼女はこの物語から、きちんと美しさを掬い取っていた。性差を越えて届くものがある、いい作品だとあらためて実感しました。
深沢
自分でも執筆しながらつらい部分はやっぱりあるんです。性的に搾取されたり、モノとして見られたりする経験は、ほとんどの女性が持っていますよね。でも私が苦しみながら書くと、読むほうもつらくて読めなくなってしまう。だからこそ、少し距離を置いて、伝わるように書こうという点は意識しました。
そこに確かにいた人のつらさを届けたい
内田
深沢さんの小説はいつも光が当たってできる影や闇の部分に踏み込んで書かれていますよね。残酷な事実も、なかったことにはしていない。本作ではそのすごさが極まっているし、戦時中に繰り広げられた暴力の問題は、実は今の時代とも繫がっている。僕たちの周囲にはセクハラやパワハラのような暴力がいまだにあって、声を上げられずにいる人も大勢いますから。
深沢
そう、普遍的な問題なんですよ。不幸にも植民地にされてしまった国があり、そこから連れてこられた女性たちがいて、男性が女性を性的に搾取するという問題が起きた。これは時代と形を変えて、連綿と続いている普遍的な問題でもある。私はこの作品で慰安婦の方を描きましたが、慰安婦問題を描いたわけではないんですね。そこを一面的に捉えてほしくない、という思いはあります。
内田
組織やシステムの問題ですよね。根本的なシステムが変わらないから、時代が変わっても繰り返されてしまう。
深沢
慰安婦を買う兵士の中には、いい人も優しい人もいるんです。でも優しい兵士がいるからといって、彼女が救われるわけではないんですよね。たまに男性から「男はみんな悪いとでも言うのか」と誤解されることがあるのですが、決して男性をひとくくりにして責めているわけではありません。
内田
ただ、システムを変えていくためには、僕たち男性がもっと声を上げなければならない気がしています。男らしさを履き違えて、偉そうに見て見ぬ振りをするのではなく。そのためには、まず「知る」ことが入り口になる。過去にこういう出来事があって、地続きで今があるんだ、とまずは理解する。その上で一緒に考えていく。『翡翠色の海へうたう』はその入り口となる小説だと僕は感じました。過去作の『緑と赤』もそうですよね。
深沢
『緑と赤』は大学や高校の授業でも結構採り上げられる機会が多いんです。
内田
日本と韓国、2つの民族とその狭間でアイデンティティを持つ人の気持ちを知るためのきっかけになる、格好のテキストでもありますよね。10代の読者には特に、教科書を何百冊も読むよりずっと多くが伝わる作品だと思います。
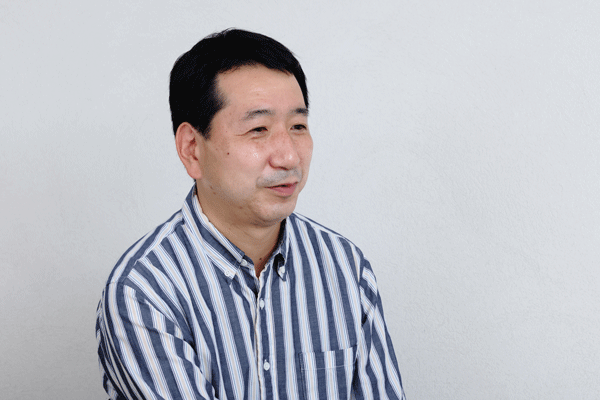
深沢
小説は感情移入して自分が追体験するかのように感じられますからね。だからこそ、誰かや何かを糾弾する書き方はしない、という点にも気をつけました。私は物語を通じてそこに確かにいた人の苦しみや悲しみ、つらさを感じとってほしいのであって、告発したいわけではまったくないんです。
内田
ちを犯してしまうのが人間ですよね。だからこそ、文学が必要になる。深沢さんは今回の作品の中でも、小説でしかできない表現をされています。主人公の1人である韓国人の女性が、砂を吐くアサリを見つめながら、「追い詰められて生きる半島の民のようだ」と自らを重ねるシーンはとても象徴的でした。
深沢
嬉しい。あそこは誰かに気づいてほしいなと思いながら書いていたんです。
翡翠と「うた」に込めた思い
内田
二枚貝のアサリは、向き合って重なる2つの民族のようでもありますよね。他のシーンで出てくる金平糖もそうだし、翡翠もまた海や時代、国境を越えていくものの象徴とも思える。そんな風にいろんなことを考えさせられるシーンがたくさんちりばめられています。タイトルはいつ決まったのでしょうか。
深沢
早い段階で決まりましたね。翡翠はチマチョゴリの胸から垂らす飾りである「ノリゲ」によく使われる宝石で、翡翠の指輪も古代朝鮮からの定番なんです。と同時に、沖縄のエメラルドグリーンの海の色でもある。沖縄と韓国を象徴するものとしてタイトルに入れようと思いました。
内田
日本でも翡翠は古代から勾玉の石として崇められていました。翡翠色って一色ではなくて、黄緑から深い青緑まですごくバリエーションがある色なんですよね。多様な美しさを醸し出すこの物語にふさわしいタイトルだなと感じました。そしてもうひとつ、アリランもまたタイトルと物語を貫く重要な要素です。
深沢
アリランは日本でいうところの「夕焼け小焼け」に近いかもしれない。みんなが知っていて、郷愁を搔き立てられる歌。私の祖父もしょっちゅう歌っていましたし、今でもBTSなどの K-POP アイドルがコンサートで歌ったりしています。
内田
この物語の軸にも歌がずっと流れていますね。2つの言語でずっと歌が聴こえてくるし、エンディングも歌によって深い余韻がもたらされています。決して長くないボリュームであるにもかかわらず、何冊分も読んだかのような充足感があります。
深沢
戦後の話をもっと厚く書くこともできたのですが、そうすると焦点がぼけてしまいそうで。重い話だからこそ、大長編にはしないでおこう、という気持ちもありましたね。
内田
書店員っていつもは無口で、黙々と仕事をしているような人たちばかりです(笑)。一方で、いい作品を発信していきたいという強い気持ちはみんな持っている。社会的にきちんと波紋を呼べるような、雄弁な作品を棚で推したいと書店員なら誰もが思っているはずです。『翡翠色の海へうたう』は間違いなくそういう作品のひとつだし、多くの読者の手に届けていきたいですね。
深沢
そう受け取ってくださるのはすごく嬉しいです。私はデビューも遅いですし、正直に言うと作家という職業をいつまで維持できるのだろうという思いは強くあります。そして毎回、「もしかしたら、これが最後になるかもしれない」と考えて書いています。それにこの先は年齢を重ねるにつれて、ベストパフォーマンスができる時期も限られてくるでしょう。だからこそ、今の自分が書けるものを自由に書いていきたい。『翡翠色の海へうたう』を書き終えた今、あらためてそう思っています。
深沢 潮(ふかざわ・うしお)
東京都生まれ。2012年「金江のおばさん」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞を受賞し、受賞作を含む『ハンサラン 愛する人びと』でデビュー。他の著書に『ひとかどの父へ』『緑と赤』『乳房のくにで』など多数。
内田 剛(うちだ・たけし)
1969年生まれ。約30年の書店員勤務を経て2020年よりフリーに。本屋大賞実行委員会理事。文芸書レビューから販促物アドバイス、学校や図書館でのPOP講習会など活躍の場を広げている。著書に『POP王の本!―グッドセラー100&ポップ裏話』がある。
(構成/阿部花恵 撮影/浅野 剛)
〈「WEBきらら」12月号掲載〉





