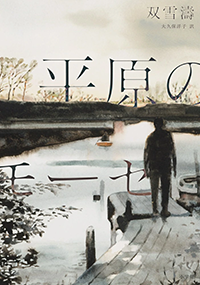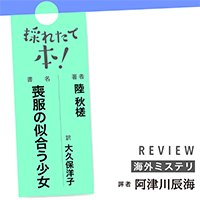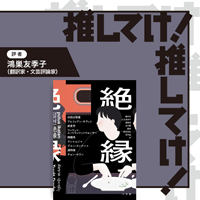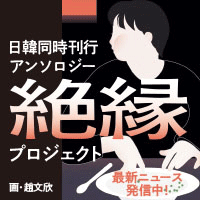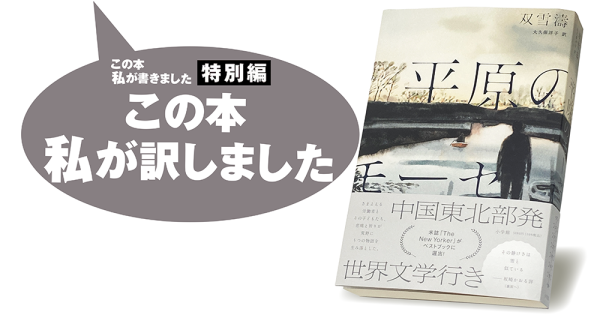大久保洋子『平原のモーセ』
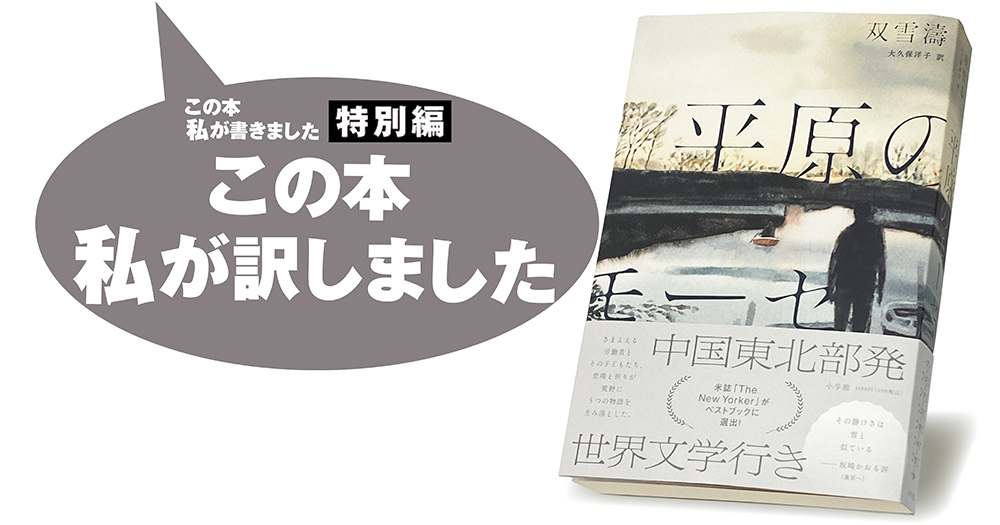
灰の中に黒く輝く小さな石炭
初めて訳した双雪濤の小説は、2022年の春に『中国現代文学』という翻訳誌に載せた「平原のモーセ」だった。それから短編集を翻訳刊行する運びとなり、作者や編集者と相談しながら収録作品を選び始めたのが2023年の秋ごろ。今、ようやく本の形にすることができた。「平原のモーセ」の訳稿を準備し始めた2020年秋から数えると、実に5年の歳月だ。原文を繰り返し読み、訳文に手を入れるうち、登場人物たちは作品世界ごと私の中で暮らすようになった。
作品に哲学めいた言葉をあまり書かないのは、双雪濤の特徴の一つだ。彼が語るのは物語、人物の言葉と行動である。
たとえば「グラードを出る」で、中学受験を控えた大人しくまじめな小学生である「僕」は、炎天下で露店の商いをする母親ともうすぐ町を離れる自分を思い、授業をさぼって石炭工場へ向かう。道連れの不良少女と口論の末、一度は彼女を見捨てて帰ろうとするものの、刑務所にいる父を想起し、薄暮の工場へと戻っていく。
「光明堂」で、両親のいない柳丁が門番の趙さんと打ち解け、将来の約束をして握手をする場面。趙さんの手の感触の短い描写に、粗暴な問題児の柳丁がよるべなさを抱えながら生きてきた時間の長さが伝わる。
「飛行家」の「僕」は、年老いて奇矯な言動をする伯母に戸惑う一方、室内の清潔さや彼女の身だしなみにさりげない視線を向ける。
彼らの言葉も印象的だ。成長し再会した荘樹に対して、過去の時間を抜け出せない李斐が放つ一言。柳丁はまだあどけないほおずきに母への思いを語り、ほおずきは母へのゆるぎない信頼を短い言葉にこめて、暗い力に抵抗する。
紆余曲折の人生を経た李明奇は、幼い頃に父に言われた言葉を、旅立ちの瞬間に「僕」に残す。
どんなに卑小で愚かに見えても、双雪濤の描く人物には、やむにやまれぬ思いに根差した人生があり、心の中に譲れないものを持っている。大きな流れに踏みにじられる人生で、声高に叫ぶことこそないものの、彼らは自分の核を大切に、手放すことなく温め続ける。灰の中に燃え残った黒く輝く石炭のように。作者は彼らをジャッジしない。飾らない文章を通して、ただすくいあげる。
5年間、時々途切れながら、彼らの人生や言葉に耳を傾けてきた。今、本の形になって、彼らが手元から旅立っていくのを感じている。一人一人の人生が作者のもとから日本の読者のもとへ届いてゆく途中の一時期、彼らと語り合い、向き合うことができた幸せを、その時期が過ぎ去る寂しさとともに感じている。
何かを代表しようとしているのではなく、ただ個人を描こうとしている、と双雪濤は語ったことがある。人物の中の小さいけれど確かな核に触れる時、彼らの姿は読む者の中で像を結ぶだろう。彼らがそれぞれの背景を持った個人として、本を閉じた後も生命を持ち続けていくことを、訳者として願ってやまない。
大久保洋子(おおくぼ・ひろこ)
1972年東京生まれ。中国文学翻訳者。主な訳書に、陳春成『夜の潜水艦』、陸秋槎『喪服の似合う少女』、郝景芳「ポジティブレンガ」(『絶縁』)、同『流浪蒼穹』(共訳)、李夏「長安ラッパー李白」(『長安ラッパー李白』)。