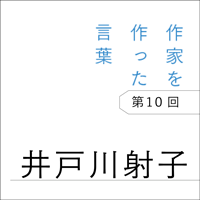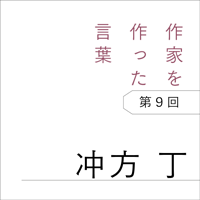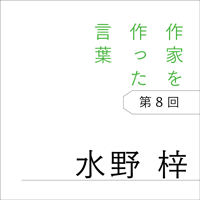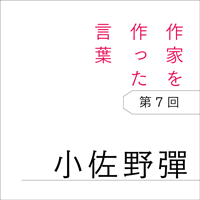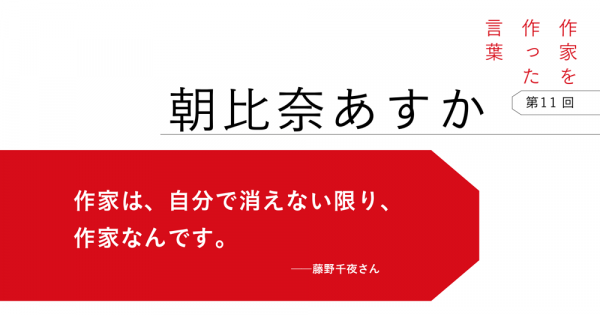作家を作った言葉〔第11回〕朝比奈あすか
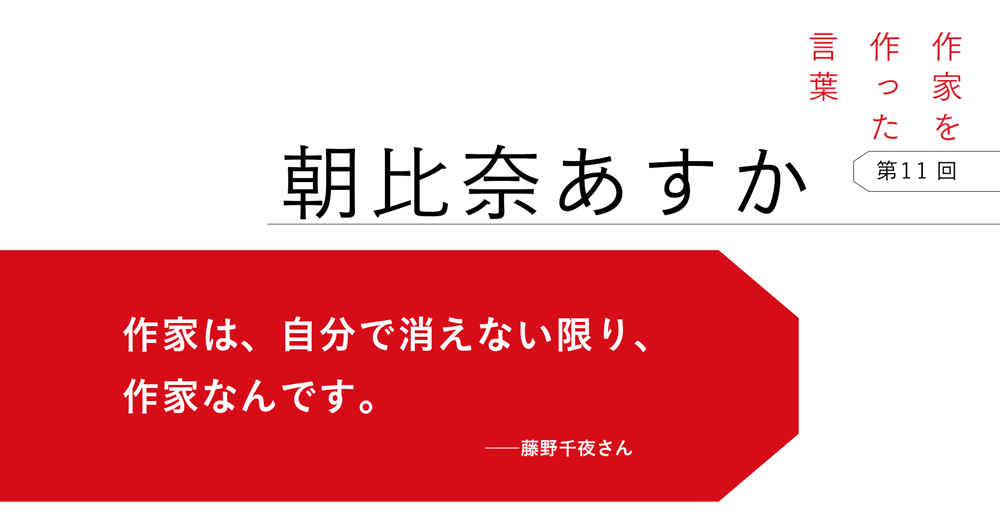
16年前、新人賞授賞式の後に歓談の時間があり、選考委員の藤野千夜さんとお話しする機会をいただいた。大ファンの私はどぎまぎし、「せっかく選んでいただいたのに、すぐ消えるかもしれません」と、場違いな自虐をした。すると藤野さんは優しく微笑み、「作家は、自分で消えない限り、作家なんです。本が出ようが出まいが、書き続けていれば作家ですよ」とおっしゃった。
当時、私は不安でいっぱいだった。次の小説が書けるか、分からなかった。どうにかこうにか形にしたものも、編集者から何度も突き返された。運よく単行本を出せても増刷には繫がらなかった……。といった回顧録は、大ブレイクした後ならばさまになるだろうが、実際のところ16年後の私の作家としての立ち位置も心持ちも、当時とそれほど変わっていない気がする。逆に言えば、(自分で言うのもナンですが)毎年きらめく才能が現れ書棚を争う厳しい文芸界で、デビュー当時からほぼ同じ感じで16年間書き続けている私もなかなかではないかと、(自分で言うのは本当にナンなのですが)思ったりもする。
新人賞をもらっても消えてしまう作家は多いというのは編集者からよく聞く話だが、その多くは、書けなくなるというより書かなくなるんじゃないかと思う。時間をかけて書いた原稿がボツになったり、作品にネガティブな感想がついたりしたら、自分に力があるのか分からなくなる。それでも、自ら消えない限り、作家は作家でいられるのだ。デビュー時に藤野さんに大切な言葉をもらえて、本当に運がよかった。私はずっと作家であり続けたいから、ずっとずっと書き続けていこうと思う。
朝比奈あすか(あさひな・あすか)
1976年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。2006年、第49回群像新人文学賞受賞作『憂鬱なハスビーン』で小説家としてデビュー。主な著書に『君たちは今が世界』『翼の翼』『ななみの海』など。
〈「STORY BOX」2022年11月号掲載〉