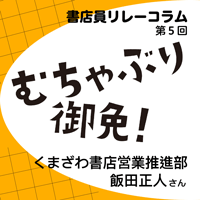「拾う人」森絵都

そんな大昔の恩が孫の代まで通用するのか謎だったが、車で五分ほどの鎌竹さん宅を訪ねて事情を説明したところ、「そいづは大変なごっだな」と二つ返事で軽トラを貸してくれた。
「河井(かわい)のじいぢゃんが荷車でなんか運んどるどご、俺も見だごどある。そーだらごどになっどっだがあ。河井さんどこには昔お世話になっでっがら、なんでも出来るごどがあったら言っでくれ」
ありがたく拝借した年代物の軽トラで、その日、俺と尚行は運転を交代しながらじいちゃんちと処理場を行ったり来たりした。自治体の定めたその場所までは片道約四十分。運びだしや積みこみの時間を加えると、じいちゃんが帰ってくる夕方までには二往復が限度だった。汗をかきかき俺たちが撤去したゴミはせいぜい全体の四分の一で、俺は虚脱感をおぼえるのと同時に、これだけ大量のゴミをたった一人で収集したじいちゃんの馬力に脱帽した。
尚行も似たようなことを思っていたらしく、日が暮れて鎌竹さんに軽トラを返したあと、筋金入りのじいちゃんっ子ぶりを発揮して言った。
「じいちゃん、やっぱすげーわ。あの年であの体力は超人的だ。さすが山歩きで鍛えてきただけある。見直した」
見直している場合ではなかったのだが、疲れきっていた俺には言い返す気力もなかった。「じいちゃんがボケた」と考えるよりも「じいちゃんは超人」と考えたほうが精神衛生上いいのは言わずもがなだ。
気がかりだったのはじいちゃんの反応だ。「じいちゃんはじいちゃんの理由があってゴミを拾っている」というばあちゃんの説が正しいとするならば、留守中にその四分の一が失われたことをじいちゃんはどう受けとめるのか。
「おっ、なんだ。めんずらしい顔だな。来でだのが」
そわそわと帰りを待っていた俺たちに対して、六時すぎに帰宅したじいちゃんは拍子抜けするほど前と変わらない様子だった。その表情にも、声にも、わかりやすい病の証(しるし)は見てとれない。そのぶんよけいにその筋張った手がぶらさげていたおんぼろの座椅子が異様なねじれを感じさせた。
「せっかぐだがら、ごはん食べでいってもらうべど思って、じいぢゃん待ってだんだよ。さ、座って、座って」
ばあちゃんに居間へうながされたじいちゃんは、ゴミの撤去によって開かれた空間に復活したちゃぶ台をしげしげとながめ、落ちくぼんだ目を瞬いた。
気づかれた。そりゃそうか。じいちゃんの混乱や怒りを覚悟して俺は身構えた。
しかし、聞こえてきたのは小さなつぶやき一つだった。
「そうが、土に還っだが」
たった一言。それで終わりだった。それきりじいちゃんはゴミの喪失について一切口にしなかった。
安堵と困惑の中で囲んだ夕食のあいだも、じいちゃんは普通といえば普通だし、普通じゃないといえば普通じゃないし……という「普通」と「じゃない」のあわいを漂っていた。
「おめら、いぐづになった?」
「家族は丈夫でやっでっか」
「尚行はちゃんとメシ食ってげでるのが」
俺と尚行の存在はしっかり孫と認識し、ぼそぼそと短い問いを投げてはくるものの、それに対する俺たちの答えがどこまで届いているのかはわからない。会話が長く続かない。もともと無口な人だから、それもまた普通といえば普通なのだが。
じいちゃん、なんでゴミなんか拾ってるの? 機会をうかがいながらも、俺にはとうとうその問いを口にすることができなかった。言ったが最後、そこにある危うい均衡が一気に崩れそうな気がして怖かった。結局のところ、俺もじいちゃんの闇に立ち入りたくなかったのかもしれない。
尚行は端からじいちゃんのメンタル問題にきっぱり背を向けている。
結果、何一つはっきりしないまま食事は終わり、俺たちはなんとも中途半端な事の収め方をした。
「じいちゃん、わりと普通だったよ。たとえ認知症が始まってたとしても、今はまだ日常生活に支障を来すほどではないって感じ」
その夜、俺はおふくろに電話で報告した。
「ゴミは拾ってくるけど、集めたゴミに執着はしてないみたいだし。そのあたり、テレビでよく見るゴミ屋敷の主とちょっと違うんじゃないかな」
「そう? だったら、しばらく様子を見たほうがいいかしら」
「うん。とりあえず、俺と尚行で何回かじいちゃんちに通って、あそこにあるゴミをぜんぶ片づけちゃうよ」
「え、いいの? 悪いわねえ」
おふくろはいつになく殊勝な声を出したが、俺にしてみれば妻との冷戦下で週末をすごすより、じいちゃんちのゴミと格闘しているほうが遥かに健やかだったのだ。
「大丈夫。週末ごとに通えば、ひと月もかからないよ」
しかし、結果的にはひと月どころか、翌週の一度きりで片が付いた。
亜純という助っ人が登場したのだ。
〈じいちゃんちがゴミ屋敷になりかけているの巻〉はあっという間に親戚中へ広まって、俺と尚行の活躍も皆の知るところとなった。結果、長男家と長女家が孫を派遣しているのなら、次女家からも一人――みたいな流れになったのだろう。二人姉妹の孫のうち、三つ子を育てていない亜純の方に白羽の矢が立ったのは想像に難くない。
「うぎゃー、これぜんぶおじいちゃんが拾ってきたゴミ?」
次の日曜、約束の午前十時にバイクを走らせてきた亜純は、まだ所狭しとガラクタが詰めこまれていた広間を前に絶叫した。
「こんまりが見たら卒倒する!」
その一日、亜純の口から何度「こんまり」の名を聞いたかわからないが、ともあれ、二人よりも三人のほうが遥かに作業ははかどった。鎌竹家から借りた軽トラに加え、その日は俺の車にも小物を積んで処理場へ運んだため、一往復で持ちこめるゴミの量も増えた。結果、三往復を終えたころにはあらかたのゴミが消えていた。
敢えて完全には撤去せず一部を残したのは、じいちゃんへの配慮だ。数ヶ月がかりの収穫物がたった一日で跡形もなく消えてなくなったら、さすがにじいちゃんもがっくりするだろう、と。
事実、帰宅したじいちゃんはすかすかになった広間と対面しても「土に還った」とはもう言わなかった。ただ何度も目を瞬きながら長いことその場に佇んでいた。
その後、夕食中に見せたあわいの漂い方は前週と同様で、消えたゴミについてじいちゃんが何を思っているのか、そもそも何を思ってゴミを拾っているのか、あいかわらず俺にはじいちゃんの頭の中がまるでわからず、もはやわかろうとする意欲すらも失いはじめていた。
ただ一つ、時おり綻ぶその口もとから伝わってきたのは、俺たち孫がそこに集っているのをじいちゃんが快く思っている、ということ。食卓狭しと並んだ料理の数々からは、ばあちゃんの高揚も立ちのぼっていた。
「なんかわかんないけど、また来るか」
「そだな。どうせまたゴミも溜まるだろうし、月いちくらいで集まっか」
「じゃ、どうせなら土曜日に来て、泊まっちゃわない? そしたら宴会できるし」
かくして「ひまな孫トラッシュバスターズ」が結成されたのだった。
三回忌の法要がつつがなく終わり、最後までノリまくった住職が立ち去ると、広間には静けさのあとの嵐が再び舞いもどった。会食に残った三十人弱による喧々たる酒盛り。正座の足を崩した解放感も手伝い、昼日中からつぎつぎとビールや日本酒が空いていく。
「ねー、なんでもっとがんばってくれなかったの?」
「あたしたち、三つ子より五つ子がよかった」
「パパのがんばりが足りなかったせいだってママが言ってたよ」
三つ子から難癖をつけられている須和さんを横目に、俺は隅の席で仕出し弁当をつまみに日本酒をちびちびやっていた。座卓の対面には説教予備軍のおやじどもから逃げてきた亜純と尚行がいた。喋っていたのはもっぱら亜純だ。
「ね、年をとればとるほど、どんどん時間が経つのって速くなっていくじゃん。少なくとも速く感じるようになるじゃん。それってなんでかわかる? こないだテレビでやってたんだけど、ポイントは脳への刺激なんだって。人生経験の浅い子供にとっては、毎日が刺激に満ちてるでしょ。初めて見るものがたくさんあって、その一つ一つに驚いたり、ときめいたりすることで、同じ五分でも脳はそれを長く感じるんだって。逆に、大人になるといろいろマンネリになって脳への刺激が減るじゃない。たとえばこのお弁当のからすみ大根、これって食べたことない子供にとっては刺激なわけよ。鴨の燻製、これも刺激なわけよ。ね? でね、私、思ったんだけど、私たちもからすみ大根を生まれて初めて食べるみたいな初心にもどれれば、脳をだませるっていうか、どんどんスピードアップする時間の流れに抗えるんじゃないかなって……」
亜純は昔から男運が悪く、別れた夫はギャンブル好き、今の同棲相手は女好きでその種の苦労が絶えず、しかも二十代から続けている派遣の仕事すらいつ首を切られるかわからないのに、会えばいつもどこか浮き世ばなれした話に興じている。
「ちょっと待て。俺、白状するとからすみ大根って今日初めて食ったんだけど、ってことは、俺にとってのからすみ大根的刺激は、ほかの大人たちのそれよりも数段激烈で、つまりここ、ここ、ここ、今俺のいるここだけがスローな時間の流れ方をしてるわけで……」
それにまた尚行がいちいち乗っかるものだから、この二人といるとときどき若干かったるい話の展開になる。こうなると俺には入っていけない。
とはいえ、この地に足を付けない二人の存在あらばこそ、俺がシビアな現実を直視せずにすんでいるのも歴たる事実である。対岸の親戚たちがくりひろげている子供の出世自慢、旅自慢、ペット自慢、投資自慢、健康自慢、終活自慢などをうかがうに、この岸は遥かに平和だ。
「つまりさ、こういうことになんない? からすみ大根の刺激によって俺の時間は膨張する。膨張しない君たちの時間とのギャップがそこには発生する。時空の歪みってやつだ。そこ、そこ、そこ、その歪みこそタイムトリップの入口になるんじゃねえか?」
「なる、なる、なるっ」
しかし、意味不明の会話が小一時間も続くとさすがにきつく、俺は「ちょっと、しょんべん」とさりげなく中座した。
ビール瓶をよけながら廊下をめざす足が心なしか頼りない。普段あまり飲まない日本酒で酔いがまわったのかもしれない。
風を浴びようと外へ出ると、遮蔽物のない空には朝よりも多くの雲がかかり、天頂の太陽を朧にかすませていた。
いろいろあった気がするが、まだ真っ昼間か。やっぱり長い一日だな。あれ? ってことは、ここでの時間を俺の脳は刺激的と認めたことになるのか? まさか。
からすみ大根妄想から逃れるため、俺は広間の喧騒が届かない離れの裏側へまわり、軒下のベンチでひと息つこうとした。河井家の食糧庫ともいえる野菜畑、そしその背後に広がる山脈を見渡せる特等席だ。
と、そこに予期せぬ先客の影を見た。
とうに帰ったと思っていた夕子おばさんがベンチで煙草を吸っていた。
「え……あれ。なんで?」
へんに裏返った声を出してすぐ、黙って回れ右すればよかったと後悔した。俺に気づいた夕子おばさんと目が合ってしまった。
恰幅のいい四きょうだいの中でただ一人細身の彼女は喪服姿も様になり、常に倦怠感を湛えた目には妙な凄味がある。白い胸元を飾る大粒の黒真珠も威圧的だ。
「座れば?」
表情とは逆の言葉をかけられ、俺は瞳を泳がせた。
「ああ……はい」
仕方なく、少し離れた横に腰かける。今さら去るに去れない。
「まだ宴会終わってないの?」
「はい」
「よく飲むよね、あの人たち」
「はい」
「誰もお父さんの話なんてしてなかったでしょ」
「はい……はい?」
流れでうなずき、ハッとした。
「あ、そうですね。そういえば」
「そんなもんだよね、法事って」
赤い唇から煙を吐きだしながら、夕子おばさんが目を細める。昔は一重だったと親戚中が噂する二重まぶた。
まさかと思いつつ俺は尋ねた。
「あの、夕子おばさんは、その……ここで、一人で、じいちゃんのことを偲んでたとか?」
「まさか」
間髪入れずにおばさんは返し、足下へ捨てた吸い殻をピンヒールの踵で踏みつけた。
「ジャフを待ってるのよ」
「ジャフ?」
「車が田んぼに落っこったんだって」
「……」
夕子おばさんの顔を見るに見られず、俺は遠い山稜へ目を馳せた。東京の空では見かけない大きな鳥の影がある。
「あの、なんかすみません」
「なんであんたが謝んのよ」
「俺が運転手さんに、その、車を移動してもらったんで」
「どうせお姉さんたちの差し金でしょ」
「え」
「つまんないことでいちいち親戚の目とか気にしちゃって、ほんと田舎ってめんどくさいよね。ばかばかしい」
そこまで見抜いているのならば話は早かった。
森 絵都(もり・えと)
1968年生まれ。90年、『リズム』で第31回講談社児童文学新人賞を受賞しデビュー。95年『宇宙のみなしご』で野間児童文芸新人賞、産経児童出版文化賞ニッポン放送賞、98年『アーモンド入りチョコレートのワルツ』で第20回路傍の石文学賞、『つきのふね』で第36回野間児童文芸賞、99年『カラフル』で第46回産経児童出版文化賞、2003年『DIVE!!』で第52回小学館児童出版文化賞、06年『風に舞いあがるビニールシート』で第135回直木賞、17年『みかづき』で第12回中央公論文芸賞を受賞と、数多くの文学賞を受賞している。他の著書に『いつかパラソルの下で』『クラスメイツ』『出会いなおし』『カザアナ』『できない相談』など多数。
関連記事