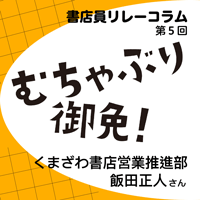「拾う人」森絵都

それでも俺が抵抗せずに表へ向かったのは、柱の陰からこちらをうかがっている典子おばさんの高圧視線を察知したからだ。ここでおふくろに逆らったところで、結局、大奥の誰かにねじふせられて終わるのである。
「おい。座布団、足りないんじゃないか」
「ちょっと、お供えの柿を食べたの誰よ」
「仕出し屋が来たぞー」
「おばあちゃん、住職さんに出すお茶どこ? っていうか、おばあちゃん、どこ?」
高低さまざまなノイズが乱れ飛ぶ現場を離れ、俺は庭先の通りでひときわ目立っているベンツへ歩みよった。
助手席の窓から覗くと、三十代半ばとおぼしき運転手が深く倒したシートに背中を埋めてスマホの操作をしている。彼をここで待たせておくということは、夕子おばさんは葬式のときと同様、法要後の会食をパスして帰る気なのかもしれない。
「あの、すみません」
窓をノックしながら呼びかけると、運転手が気づいて身を乗りだし、助手席のドアを開けた。
「悪いんですけど、ここにほかの車を停めたいみたいなんで、ちょっと移動してもらえませんか。できれば山の裏手の方へ」
「山の裏手?」
「その……このへんに車を置いとくと、子供にいたずらされる恐れがあるんです。野蛮な三つ子がいるもんで」
「はあ」
首をひねりながらも運転手が車を発進させるのを見届け、俺は再び家の中へ引き返した。
と、今度は階段の下でおやじと鉢合わせた。
「武、おまえまだ喪服に着替えてないのか。何やってんだ。早くしろ」
言い返す気力もなく、俺は吐息を一つ残して階上をめざした。
一階の喧騒とは対照的に、二階には人いきれのない無臭の静けさが立ちこめていた。開けっ放しの窓から吹きこむ涼風を浴びながら、俺はシャツとデニムを脱ぎすてて喪服のスーツに着替え、壁の鏡でヒゲの剃り残しがないのをチェックした。
一人になると落ちつく。なのに、どこかで苛立っている。胸の奥にある異質なざらつき。それはおふくろに不条理な仕事を押しつけられたせいでも、運転手に妙な噓をついたせいでも、おやじに小言を言われたせいでもなく、「親戚の多くが家族連れで来ている」という現実に当てられたせいだろう。結局、妻子がここにいないことを誰より俺自身が気にしている。
聡美との関係をどうするか。それはこの三回忌を機にがぜん深刻さを増したテーマである。じいちゃんの法事よりも息子の模擬テストを優先させた妻の強硬姿勢は、これまで延ばし延ばしにしてきた決着を俺に迫るに足るものだった。
しかし、のんびりそのテーマを追っている間もなく、
「武、何やってんの。早く、早く。住職さん、いらしたわよ」
階段を駆けのぼってきたおふくろにせっつかれ、俺は再び親戚たちの渦の中へと引きずりもどされた。
住職が到着したせいか、一階のドタバタ劇はすっかり幕を閉じ、参加者たちはみな行儀よく広間に着座していた。畳を埋める座布団はほぼ満席で、縁側に続く廊下にまで予備の数枚が溢れている。
「おーい」
噓くさいほど厳粛な空気をひっかくように、最前列の昭雄おじさんが大きく手招きをしているので、誰を呼んでいるのかと思ったら、俺だった。
「武、こっち座れ」
同じ並びの左端を指さして言う。
最前列には施主であるばあちゃん、昭雄おじさん、典子おばさん、良樹くんとその妻子、尚行が肩を並べていて、本来ならば尚行の妹一家あたりがそれに続くはずが、なぜだか尚行の横には本家筋ではない亜純の影がある。その横に俺も座れと言う。
昭雄おじさんの胸中に思いをめぐらせながら、俺は窓寄りの最前列へと進み、亜純の横でひざを畳んだ。
横目でそっとうかがうと、小麦色の首元に真珠を垂らした亜純も、喪服がぜんぜん似合わない尚行も、最前列の縁者らしく神妙にうつむいている。俺もそれに倣って目を伏せた。窓から差しこむ秋の陽が黒一色の参加者たちにほのかな色を添えていた。
いともしめやかなムードに変化が兆したのは、物々しい沈黙の中で住職が入場し、遺影の前でお経を唱えはじめてからだった。
第一声からしてぞくっとした。「むらっ気のある坊主」という先入観を裏切り、五十前後の住職は落ちついた物腰の二枚目で、じつに麗しい声の持ち主でもあった。低音にして艶のあるオペラ歌手のような美声。いや、むしろロックか。ビート感に富んだ木魚の叩き方もまさしくドラマーのそれだ。
よかった。彼はノッているのだ。
この法要は成功する。そう確信した俺がひじで突くと、亜純はこくんとうなずいて親指を突きたて、その奥で尚行が小さく拳をふりあげた。
長く退屈なお経の時間はかくして聞きごたえのあるショーと化し、途中から順番に焼香を始めた人々の動きにも心なしかキレがあった。まずは最前列の俺たちから仏前へ進み、じいちゃんの遺影に一礼、刻み香を香炉へ移してまた礼をする。不器用な俺はこの所作が苦手なのだが、BGMのおかげか今回はスムーズにいった。
――じいちゃん。夕子おばさんの車を山の裏に隠してよかったよ。
心でじいちゃんに呼びかけてから元の席へもどる。
二列目、三列目――順に席を立つ参加者たちは皆、焼香が終わると最前列の遺族へまなざしを滑らせ、無言で一礼してから捌けていく。その面々の多くが、俺と亜純に気づくと寸時動きを止め、「なんでおまえらがそこに?」という顔をした。
無理もない。俺と亜純は長女次女の血筋。序列からして最前列にはふさわしくない。
一方で、序列を度外視してまでも昭雄おじさんが俺たちをここに座らせたのには、やはりそれなりのわけがある。
少年期や青年期、中年期などをぜんぶ脇へよけて最晩年のじいちゃんだけをふりかえると、やはり俺と亜純はここに堂々といてもいいような気がするのだった。
一人だけ、俺と亜純に気づいてもへんな顔をせず、むしろ深々と頭を垂れてくれた老人がいた。
鎌竹(かまたけ)さんだ。
俺と亜純、そして尚行は同時に「あ」という顔をし、深々と頭を垂れかえした。
白髪頭のボリュームが多少減ったのをのぞけば、鎌竹さんはじいちゃんの葬式で会ったときとさほど変わっていない。初めて会った三年前とも変わっていない。人間はどこかで老け止まり、老人として完成する。
長い永続の中にいる鎌竹さんを見たら、なんだか無性にじいちゃんの不在がくやしくなった。鎌竹さんがここにいるのなら、じいちゃんも生者としてここにいて然るべきだ、と。お経なんか唱えてもらっている場合じゃない、と。
俺はきょろきょろと首を回してみたけれど、もちろんそこにじいちゃんの影はなく、住職のノリをありがたがっているのは正真正銘の生者たちばかり。じいちゃんが好きだった庭の紅葉までもが、もはやじいちゃんではないほかの誰かの手で刈り込まれているのだった。
「茨城のおじいちゃん、どうも調子がおかしいらしいのよ」
約三年前におふくろからの電話で不吉な知らせを受けたとき、まず俺が思ったのは「ついに来たか」だった。当時すでにじいちゃんは九十も近かったから、それが体の不調であれ心の不調であれ、別段驚くには値しなかった。
にもかかわらず、おふくろの話は俺を驚かせた。
「なんかね、おじいちゃん、いろいろ拾ってくるようになっちゃったらしいの。私もよくわからないんだけど、物を……たぶん廃棄物とかだと思うけど、あれこれ拾い集めて、家に溜めちゃうみたい」
ゴミ屋敷。瞬時頭をかすめた一語に俺は戦慄した。
「なにそれ、ヤバいじゃん」
「そうなの、だから心配で。おばあちゃんはああいう人だから、家の物を捨てられるよりは拾ってきたほうがまだいい、みたいなのんきなことを言ってるんだけど、やっぱり放っておけないじゃない。で、今度の日曜日、尚行くんがちょっと様子を見に行ってくれることになったのよ。ほら、兄さんはアレだし、私も佳美もアレだし」
「ああ……」
昭雄おじさんはそのころ腸閉塞やら初期の胃癌やらで入退院をくりかえしていて、おふくろはおふくろで父方のばあちゃんの介護に追われ、佳美おばさんは三つ子を産んだ娘のヘルプで大忙しだった。結果、誰もしばらく茨城へ足を運んでおらず、そのせいでじいちゃんの異変発覚が遅れたともいえる。
「じゃ、俺も行こうか」
言下の期待を嗅ぎとった俺が先まわりをすると、
「ええっ、行ってくれるの?」
待っていましたとばかりにおふくろは声を弾ませた。
「そうよね、尚行くんだけに任せるわけにいかないわよね。じゃ、私から尚行くんに伝えとくから、くれぐれもよろしくね」
おふくろがさっさと電話を切った十分後、今度は当の尚行から電話があり、翌週の日曜日、埼玉の浦和からはるばる電車でやってくる彼を最寄りの駅で俺がピックアップし、じいちゃんちまで乗せていくことになった。
田園の稲が青々とまぶしい季節だった。ほかのいとこたちと同様、成長とともに顔を合わせる機会が減った尚行と会うのは数年ぶりで、田舎道を走る車の中で俺たちは互いの近況をぽつぽつと報告し合った。放送作家としてまだ低迷していた尚行はバイトで食いつないでいると言い、俺は家電会社の営業としてそこそこ仕事はうまくいっていたものの、家庭はうまくいっていないと白状した。ふいに持ちあがった茨城行きを、少なくともこの時点での俺たちはちょっとした息抜きの小旅行的に捉えていた節がある。
しかし、じいちゃんちに到着した俺たちを待っていたのは、庭に面した一階の窓が透かす恐怖の情景だった。
仕切りを開放した一階の広間+廊下。横にも縦にも広いその空間を大量のガラクタが埋めに埋めつくしていた。自転車。三輪車。ミシン。机。椅子。カート。傘。長靴。棚。壺。水槽。籠。タンス。電気スタンド。壁時計。ジョーバ。ステレオ。ゴルフバッグ。洗濯機。ポリバケツ。植木鉢。モップ。なんでもある。どれもこれも見るからに古い廃棄物だ。
「……」
限りなくホラーに近い現実を容易に受けいれられず、かといって目をそらすこともできずに、俺は呆然と立ちつくした。
気がつくと、尚行はへなりと地面に座りこんでいた。生まれて初めて腰を抜かしたとのちに教えてくれた。
「あんれ、いづ来でだの?」
俺たちに気づいたばあちゃんの声がするまで、いったいどのくらい庭で固まっていたことだろう。
「ばあちゃん、これなに? どうなってんの?」
「じいちゃん、どうしちゃったの?」
二人して質問攻めにしたばあちゃんの返事を圧縮すると、おおよそこんな話になる。
「何ヶ月が前がら、じいぢゃんが毎日、毎日、一生懸命に物を拾ってぐるようになってさ。ちゃーんときれいに洗っでるし、家は広いし、まあええがなど思っでたんだけど、だんだん場所がなぐなってぎて、ちゃぶ台も置げなぐなっちゃって。しょうがねえがら、今は二階でごはん食べでるんだけど、やっぱりごはんは一階で食べたいさ。二階までお皿運ぶの大変なんだわ。そんだがら昭雄に相談したんだ、どうしたもんだっぺって」
どこまで本気で困っているのかよくわからないばあちゃんは、持ち前の擬態能力のせいか背後のゴミと妙になじんでいて、すでに体の一部が廃棄物化しつつあるようにも見えた。
俺はますます焦った。
「ばあちゃん、じいちゃんは? どこ?」
「今日も荷車引っぱってなんが拾いに行っださ。朝がら夕方まで、遠ぐまで。よぐ働ぐ人だ」
「ばあちゃん、止めないの?」
「止めたよう。けんど、私の言うごどなんか聞ぐ人じゃねえもん」
「って言ったって……」
「しょうがねっぺ。じいぢゃんにはじいぢゃんの理由があってやってるごどだ」
「どんな理由だよ」
「それはじいぢゃんにしかわがんね。けんど、じいぢゃんはよぐ言ってるよ、無駄死にはいげねって。拾ってぎだもん洗いながらよぐ言ってるよ」
無駄死にはいげね。たしかにじいちゃんにしかわからない理由だ。やはり認知症の萌芽と見るべきか。
「一度、病院に……」
診てもらったほうがいい、と言いかけた俺をさえぎって、そのとき、長らく呆けていた尚行が言った。
「それより、まずはゴミをどうすっかだ。じいちゃんが夕方まで帰らないんだったら、その前に片づけられるだけ片づけちまおうぜ。自治体の処理場に直接持ちこむのが一番てっとり早いな」
思えば、この時点からすでに尚行はじいちゃんのメンタルに立ち入らない姿勢を明確にしていた。彼は一貫してじいちゃん内部の問題には目を向けず、そこにあるゴミだけを問題として捉え、その処理に全精力を傾けた。
「けど、こんな大量のゴミをどうやって運ぶんだよ」
「んー。軽トラでもレンタルするっきゃないかな」
「レンタカーなんてあるのかな、このへんに」
「そこだな」
渋く黙りこんだ俺たちに、「ほんなら」とばあちゃんが提案した。
「鎌竹さんどごの軽トラ、借りればいっぺ。じいぢゃんの孫だって言っだら、きっど貸してぐれるさ。うんと昔な、鎌竹さんどごの豚が逃げたどぎ、じいぢゃんの家族みんなで追っがげて、捕まえてやったって言うがら」
森 絵都(もり・えと)
1968年生まれ。90年、『リズム』で第31回講談社児童文学新人賞を受賞しデビュー。95年『宇宙のみなしご』で野間児童文芸新人賞、産経児童出版文化賞ニッポン放送賞、98年『アーモンド入りチョコレートのワルツ』で第20回路傍の石文学賞、『つきのふね』で第36回野間児童文芸賞、99年『カラフル』で第46回産経児童出版文化賞、2003年『DIVE!!』で第52回小学館児童出版文化賞、06年『風に舞いあがるビニールシート』で第135回直木賞、17年『みかづき』で第12回中央公論文芸賞を受賞と、数多くの文学賞を受賞している。他の著書に『いつかパラソルの下で』『クラスメイツ』『出会いなおし』『カザアナ』『できない相談』など多数。
関連記事