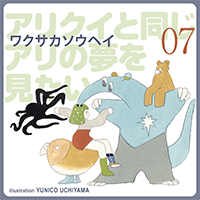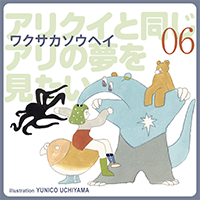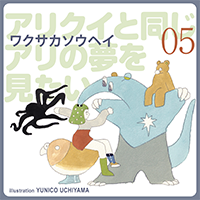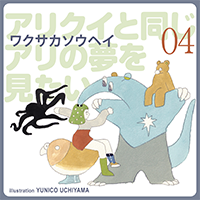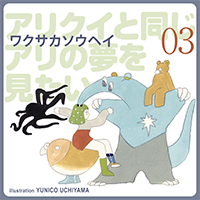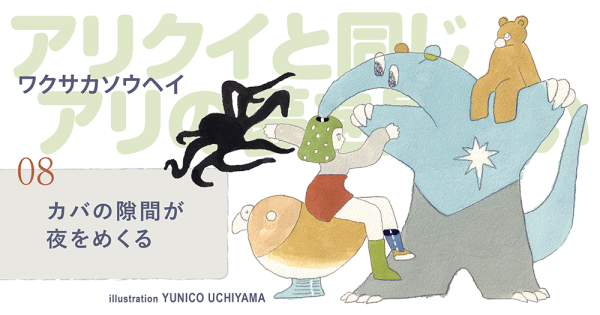ワクサカソウヘイ「アリクイと同じアリの夢を見たい」#08
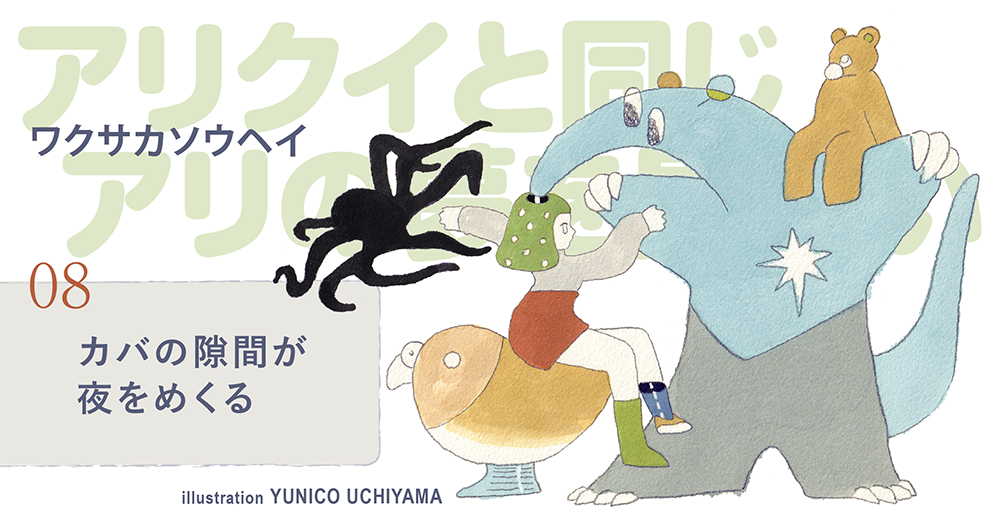
08 カバの隙間が夜をめくる
コンビニに立ち寄ると、「しあわせバター風味」を謳うポテトチップスを見つけた。その瞬間、意地悪な思いが頭に浮かぶ。本当に幸せなのかどうかは、こっちが決めることだろう、と。
「幸せ」という言葉を、どうにも信じきれない。響きとしては温かく和やかなものであるはずなのに、それはどこか作り物めいた違和感を耳に残す。
「幸せ」には、規格的な匂いが強く纏わりついている。自分の知らない誰かが、裏側で「幸せとはこういうものですよ」と基準を決めているような感じ。いつの間にか「しあわせバターは幸せの味がするんですよ」と定義されているような感じ。
おそらくだが、私たちのまわりにはびこる「幸せ」には、正解とされるフォーマットが縫い込まれている。恋人と寄り添う、結婚する、子どもを持つ、家を建てる、車を持つ、はちみつが含まれたバターを食べる。そういったテンプレートをなぞれば、「幸せ」というスタンプが押されていく仕組みだ。なんて胡散臭い話なのだろう。
私は、「幸せ」を信用していない。しかし、本当の幸せを求めないわけではない。だから、誰かに勝手にスタンプされる前に、自分で自分の幸せを定義する。
それは、「野生のカバと添い寝をする」というものである。
大勢のカバに埋もれて眠ることは、自分にとって幸せ以外のなにものでもない。バターではなく、私はカバにまみれたい。カバとカバの隙間で横になりたい。
そう、隙間。
幸せがどうにも見落とされがちになってしまうのは、それがちょっとした隙間の中に点在しているものだからだ。
たとえば、昨日も休みで、そして明日も休みだという、三連休の中日。その安息の隙間にいる私たちは、確かな幸せを感じているはずである。
エレベーターで最後の一人として乗り込むことができた時。アラームが鳴る前に布団の中で目覚めて「起きる時間まであと三十分も余裕がある」と気がついた時。新品の靴にぴったりと自分の足が収まった時。仕事が予想外に早く終わって夕方の明るいうちに帰宅している時。好きな人と肩を並べて歩いている最中にふと手が触れ合った時。そこには、必ず歓びの情緒がある。幸せはいつだって、隙間の中にある。
そこから私は、とある日の幸福な時間を思い出す。
いまからもうずっと前。私は、お金がなく、やることもなく、何者でもなく、時間だけを大量にあり余らせている、実家暮らしで、モラトリアムな、つまりどこにでもいる二十代の若者であった。
親の小言から逃れるために自分の部屋に閉じこもり、布団の中で天井ばかりを見つめ、「がぶぶ」とか「ごもごも」などと、濁点混じりの無意味な呻きを漏らすだけの、空虚な毎日。それは鉛色の時間であった。端的に、不幸の真っ只中だった。
夜が訪れるたび、無性に孤独を感じた。人が恋しかった。しかし、自分を抱きしめてくれるような恋人や友人はいなかった。いたとしても、いまは草木も眠る丑三つ時だ。玄関の戸を開けて外に出るような時間ではない。この強烈な寂しさは、どうにか実家の中で処理しなければならないのである。
闇に覆われた自室の布団の中で、ふとこんなことを思った。
「そういえば、大人になったら親と寝てはいけないなんて、誰が決めたのか」
気がついたら、両親の寝室のドアをそっと開けている自分がいた。父と母の静かな寝息で満たされたその空間に、忍び足でもって、踏み入っていく。そして、ポイントを定め、父と母の布団、その隙間に静かに潜り込み、横になる。
その瞬間、懐かしい温かさに包まれた。無上の多幸感が、そこにあった。すべてが救われたような心地だった。柔らかな静寂に包まれながら、私はうっとりとした眠りへと誘われていく。
「ぎゃっ」
母の短く太い叫び声が、寝室に響いた。隣に成人男性である息子がいつの間にか横たわっていたことに、気がついたのだ。その声に、ハッと目を覚ます。
「何をやってるんだ?!」
続いて目覚めた父が問い詰めてきた。本当に自分は何をやっているのだろう。我に返った私は明確な言い訳もできず、「がぶぶ」とか「ごもごも」などといった、なんの解決にもならないうわ言を口走ることしかできない。両親の寝室にパニックが巻き起こる。私は隙間から立ち上がり、自分の部屋へと退散した。
あのどん底の季節で瞬間的に触れた感覚は、私にひとつの確信をもたらした。
誰かと誰かの隙間に入って、そこで眠りに落ちること。それ以上の幸福など、この世には存在していない。
実家を出てからも、私はあの時の残像に囚われ続けた。
時が経つ中で、誰かと一晩を過ごすこともあったし、誰かと暮らすこともあって、添い寝の機会には恵まれた。しかし、それは片側だけに人がいる状態であり、隙間に挟まっているわけではない。足りない。幸福には、まだ足りない。隙間への渇望は、日を追うごとに深度を増していった。
で、そこにカバが現れた。
書店でなんとはなしに立ち読みした、自然科学雑誌。その誌面には、野生のカバたちが水中で睡眠をする様子が、グラビアで掲載されていた。
それは、現実離れした光景であった。
カバ、カバ、カバ。数えきれないほどのカバたちが密集し、体を寄せ合いながら、半眼でうたた寝をしている。
日中のほとんどの時間を沼などの中で暮らしているカバだが、実は彼らは泳ぐことができない。水中で移動する際は、水底を蹴り、まるで月面をジャンプする宇宙飛行士のようにふわりふわりと進んでいく。つまり彼らは、泳いでいるのではなく、歩いているのである。
そして睡眠中は、水深のあるところで浮かぶこともできない。カバの体は水よりも比重が大きいため、何もしていないとそのまま沈んでしまうのだ。
ゆえに彼らは、沼の中で眠る時、浅瀬へと向かう。そして足のつくところで水面から鼻を出し、呼吸を確保して、うつらうつらと夢の底に落ちていく。
沼における浅瀬のエリアは限られている。そしてカバたちは群れでの生活を基本としている。だから休息のひとときを過ごす際、彼らは互いの体を寄せ合って密集することになる。巨大な背中と背中で、水面を埋め尽くす。それはさながら、満員状態のエレベーターである。
私はその写真を眺めながら、こんなことを思った。
このエレベーターの隙間に乗り込めたら、どんな幸せを感じることができるのだろうか。
カバとカバの隙間に収まって眠れたら、どれほど幸福な夢を見ることができるのだろうか。
ああ、埋もれたい。密集するカバの中に、埋もれてみたい。
それは荒唐無稽な願いであったが、しかし本当の幸せはその隙間の中にしかないのだという揺るぎない思いでもあった。
「父と母の隙間」に代わるもの、それは「カバとカバの隙間」であったのだ。
そんな妄言を誰かに漏らすこともなく、自分の中でひっそりと抱えながら、いくつもの年月を見送った。かつてのモラトリアムだった時期が懐かしいほどに、私は都会で馬車馬のように働き続けていた。仕事が終われば、また別の仕事が待ち受けていて、隙間などは一ミリもない日々。生活を織りなすことはできていたが、しかし幸せに潜り込む機会などはどこにも存在していなかった。
ふと、足を止めた。このままでは、幸せを感じ取ることができずに、生涯を終えてしまうような気がする。一時、ここで休息をとってもいいのではないか。自らに隙間を与えてもいいのではないか。そこで私は、仕事を整理して、二週間のバカンスをとることにした。
さて、貴重な長期の休みである。いったい、どこで過ごそうか。私は口元を緩めながら、頭の中で行き先の候補を転がした。
そこで浮かび上がってきたもの。
それは、野生のカバが密集する、アフリカ大陸の、あの景色だった。
そうだ。いまこそ、自分にとっての本当の幸せを叶える時ではないか。
「あのですね、死にますよ」
旅行会社の担当氏は、苦虫を噛み潰したような表情で、私にそう伝えてきた。
そりゃそうだ。目の前にいる客は、「カバとカバの隙間で眠る旅にしたいんです」と真っ黒な目で寝言を唱えているのである。「死にますよ」以外のコメントなんて、できるはずもない。
カバは地球上で最も危険な哺乳類として名高い。一説によれば、アフリカ大陸では年間に約三千人もの人々が、カバに襲われて命を落としていると推定されている。
そんなカバに埋もれようものなら、幸せになるどころか、確実に不幸せな結末を迎えてしまう。
私だって、カバが凶暴であることは知っていた。でも、もしかしたらワンチャンあるんじゃないか、どこかに隙間はあるんじゃないかと、あえて感覚を麻痺させて旅行会社のテーブルで思惑を述べてみたのだが、あっという間に希望のプランは立ち消えとなった。
「ただ、まあ、それに近いことであれば可能かもしれません……」
担当氏はそう言って、ある提案を示してきた。それを聞き、私は迷うことなく頷いた。なるほど、そんな手があったのか。そのプランであれば、もしかしたら幸福の景色を叶えることができるかもしれない。
「でも、野生のカバの姿を見たら、一緒に寝たいだなんて気持ちは吹っ飛びますよ。あれは布団じゃなくて、戦車ですから」
本当に、戦車だった。
太陽の光が降り注ぐアフリカ大陸、その赤道付近の正午過ぎ。時差ボケを抱えつつ、私は現地のガイドに導かれ、大きな沼の前にいた。泥水が淀んだその水溜まりの浅瀬には、何百頭ものカバたちが群れをなしていて、そして互いに大きな口を開けながら、大乱闘を繰り広げていた。
カバは家族単位での大きな群れを作る習性を持ち、縄張り意識が非常に強い。隣に馴染みのないカバが近寄ってこようものなら、「おいおい、いま肩がぶつかったよな?」という感じですぐさま喧嘩が勃発する。しかもこの争い、一度始まると、かなり長引く。一回は負けを認めたと思われたカバが「やっぱり上訴します!」といった感じで相手に体当たりをしたり、傍聴席で成り行きを見守っていたと思われた第三者的なカバが突然闘争の中に「異議あり!」といった感じで割って入ってきたりする。泥沼の中で展開される、泥沼劇である。
まごうかたなき戦車と戦車のぶつかり合い。相手に突進するカバがいて、相手に噛みつくカバがいて。沼の水面には、真っ赤な血が浮かんでいる。北野武とかが監督していないと辻褄が合わないほどに、バイオレンスな景色が目の前には広がっていた。
私は、引いていた。
むき出しの自然の姿に、引いてしまっていた。
無理だろう。こんな動物の隙間に潜り込んで、幸せな眠りを得ることなんて、できるはずがない。「死にますよ」の指摘は、まったくもって、正しかったのである。
ここに来るまで、少しだけ、泡のような期待を持っていた。カバは危険だとか凶暴だとか謳われてはいるが、それはもしかしたらデマなのではないか、という。だって動物園で見るカバはなんだか穏やかな印象で、瞳には優しげな色が浮かんでいる。カバをマスコットに仕立て上げるならば、淡いピンク色で、ニコニコ笑いながらこっちに手を振ってきて、「やあ、ボクの名前はヒポポくん。ビスケットが大好きなのさ」みたいなセリフが似合うキャラクター像が自然と浮かんでくるわけで、どう考えてもそこに暴力的なイメージを結びつけることができなかったのである。
ああ、それは本当に、泡のような期待でしかなかった。
野生のカバは、ヒポポくんなんかではなかった。
凄惨な光景を目の当たりにして、時差ボケによる眠気なんかは吹っ飛び、その沼から無言で引き下がった。
それでも夜になれば、眠気は再び、訪れる。
足場のしっかりとした、高床式のテント型ロッジ。私はそこに据えられている簡易的なベッドの上で、瞼を重くしながら、ぼんやりとした時間を味わっていた。
がぶぶ、ごもごも、がぶぶ、ごもごも。
その時、重低音の呻き声のようなものが聞こえてきた。
来た……! 私はベッドから立ち上がり、忍び足でロッジの出入り口へと向かい、そこのジッパーをそっと下ろして、隙間から外の様子を窺った。
わずか数メートル先。そこには一頭のカバがいた。月光でぬらりと照らされている背中。地面に生えている草を、がぶぶ、ごもごも、と音を立てながら、勢いよく食んでいる。
旅行会社の担当氏が、「カバとカバの隙間で眠りたい」とのたまう私に差し出した、安全で合法的な提案。それは、「カバの生息地の周辺にあるロッジに宿泊して、その巨大な野生動物の存在を近くで感じながら眠ること」であった。
近い、本当にカバが、近い。
隙間に埋もれることはできてはいないが、まあ、ここまでカバに肉薄しながら夜を過ごせる機会というのも稀である。自分で自分をそう納得させて、その野生のカバを、あぐらの姿勢でじっと観察した。薄闇の中から視線を送る私のことなど気にも留めず、カバは猛然と食事を続けていた。その咀嚼音は、静かな闇の中に滲んでいく。それを聞いているうち、私はゆっくり、安堵の緩みへと誘われていく。
がぶぶ、ごもごも、がぶぶ、ごもごも。
私はハッと、目を覚ました。気づけばジッパーの手前の床板の上で、寝落ちをしていたようだ。よだれを拭き、外の様子を確認する。カバは、もうそこにはいなかった。
しかし。
がぶぶ、ごもごも、という音は、まだどこからか聞こえる。どこからか、というよりも、さっきよりもずっと近くで聞こえる。なんだ、もしかしてあのカバ、私が寝ている間に、「やあ、眠くなっちゃった。ビスケットの夢でも見ようかな」とばかりに、ロッジの中へと入り込んだのか。これは、ベッドの上でヒポポくんがいびきをかいているサウンドなのか。
ミシミシ、とロッジが揺れた。
まさか、と思い、意識を床下へと向ける。
がぶぶ、ごもごも、がぶぶ、ごもごも。
ぐしゃぐしゃ、もぎゅぎゃふ、ぐっちゃぐっちゃ、ばりばり、むっしゃり、もっしゃもっしゃ、ごりゅっごりゅっ、ぶりゅんもぎゃ。
大群だ。カバの大群が、この高床式ロッジの、すぐ真下で蠢いているではないか。草を食む音が洪水のようにして、この宿泊小屋を震わせているではないか。
私は床にべったりと耳を押し当てた。
ああ、カバだ。カバたちだ。
カバたちが折り重なるようにして、私の横にいる。
その密集するカバたちの咀嚼の響き、その隙間に、身をよじるようにして潜り込んでいく。息遣いがあり、体温がある。
それは、幸福だった。私はその幸福な夜に、耳を傾け続けた。
カバたちの音が、遠ざかっていく。
ゆっくりと意識を失っていくその最中で、幸せとは、喧騒の隙間にある静けさのことなのだと思い知りながら、私はバターのように眠りへと溶け込んでいった。
ワクサカソウヘイ
文筆家。1983年東京都生まれ。エッセイから小説、ルポ、脚本など、執筆活動は多岐にわたる。著書に『今日もひとり、ディズニーランドで』『夜の墓場で反省会』『男だけど、』『ふざける力』『出セイカツ記』など多数。また制作業や構成作家として多くの舞台やコントライブ、イベントにも携わっている。