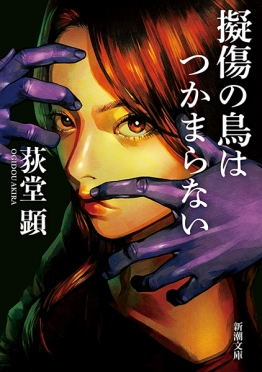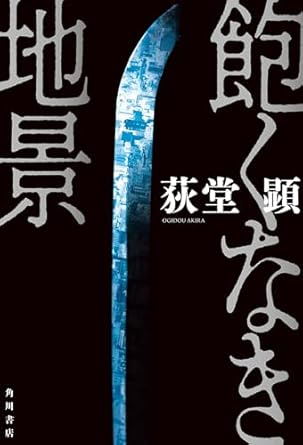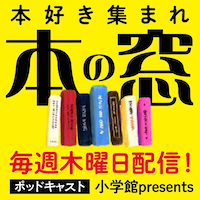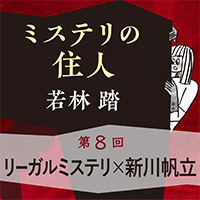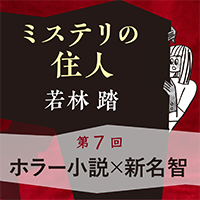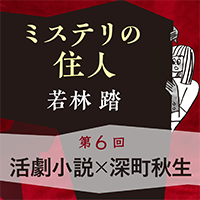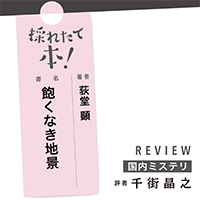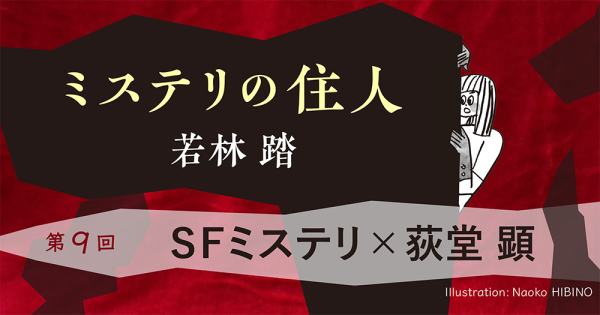ミステリの住人 第9回『SFミステリ × 荻堂 顕』
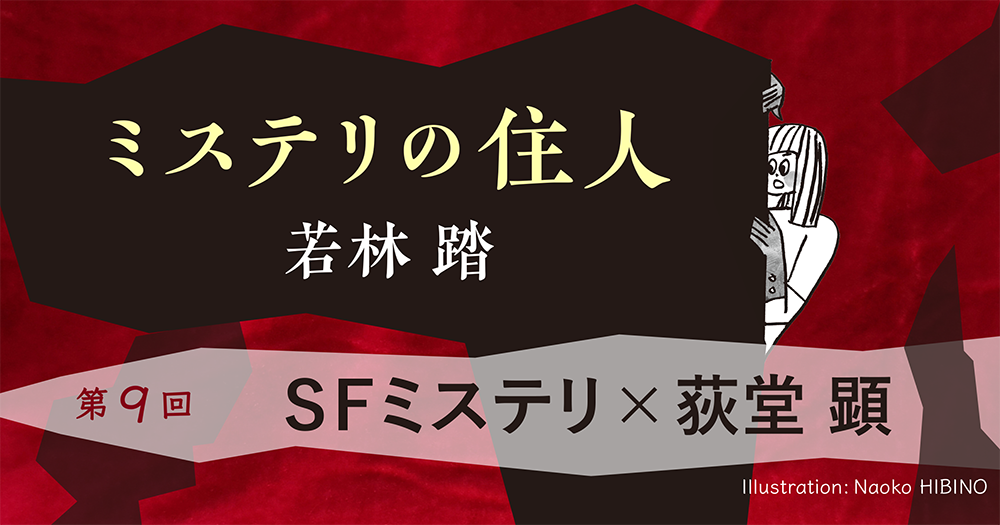
若林 踏(ミステリ書評家)
方丈貴恵も〝SFミステリ〟については「作者が自ら作った世界を、ミステリの切り口から眺めてみようと思って書いたのがSFミステリ」と述べており、〝SFミステリ〟については「構築された社会そのものを見渡すことへ関心が向かう」ことに力点を置くジャンルという共通認識がどの作家にも朧げにある印象を受けた。上記のような視点に立って「独自に構築された社会を見渡す犯罪小説」=SFミステリの書き手として思い浮かんだのが荻堂顕だった。
世界の認知が歪んだ人物を描くため
荻堂が第77回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門を受賞した『不夜島 (ナイトランド)』(祥伝社)は、電脳技術が発達した第二次世界大戦後の沖縄を舞台にした犯罪小説だ。科学技術によって身体を拡張した人間が存在するサイバーパンクSFの要素がある作品と言えるだろうか。語り手である武庭純は身体をサイボーグ化した台湾人で、密貿易によって生計を立てながら暮らしている。
現実とは異なる歴史を辿った世界を描く歴史改変SF、あるいは並行世界SFとも『不夜島(ナイトランド)』は読むことが出来るが、そうした要素がある作品の魅力を荻堂は「現実の世界をどのように改変したのか、というところに作者の価値観が反映されている」ことだと、今回のインタビューでは述べていた。後述する『ループ・オブ・ザ・コード』(新潮文庫)も架空の歴史を辿った土地を巡るSF小説の要素があるミステリだったが、そうした要素がある作品で特にお気に入りのものを挙げてもらったところ、マイケル・シェイボンの『ユダヤ警官同盟』(2007年、新潮文庫、黒原敏行訳)の名前が出てきた。米国で実際に計画されていたというユダヤ人特別区の話を基に書かれた小説で、同作は優れた歴史改変SFに贈られるサイドワイズ賞も受賞している。
『不夜島(ナイトランド)』の武庭純は殺人を繰り返す元憲兵の日本人の捜索と、〝含光(ポジティビティ)〟と呼ばれる正体不明のものを探すことを物語の前半部で行う。人探しと物探しの模様を一人称視点から書くという、私立探偵小説と似た興趣が『不夜島(ナイトランド)』にはあるのだ。武庭純という社会の片隅で生きる人間の視点から見えるものは、密貿易によって栄え夜は華やかなネオンが輝く与那国島の姿である。戦後の混沌が生み出した清濁併せ呑む社会の様子を浮かび上がらせるという、都市小説の側面も同作は持ち合わせている。まさに「独自の社会を構築しながら、その社会全体を見渡す」小説なのだ。
主人公の武庭純をはじめ、『不夜島(ナイトランド)』の登場人物の多くは故郷喪失者というべき存在として描かれている。アイデンティティを喪失し、自分が自分であることの証を立てられない人間たちが、己の存在意義を取り戻すために捨て身の闘いに投じる姿を壮絶な活劇場面とともに描き切った終盤にこそ、この小説の醍醐味があるのだ。
インタビューで、SF的な世界観の中で故郷喪失者と呼べる登場人物を描くことへの拘りがあるのではないか、という話をふった時に「世界に対する認知に歪みを持ってしまった主人公を描くことに関心があると荻堂自身は述べていた。『ループ・オブ・ザ・コード 』で語り手を務めるアルフォンソ・ナバーロは家族や故郷と呼べるものを持っておらず、「生まれてこなければ良かった」という思いを抱いている人物だ。世界に対する不信が常にある語り手と言い換えても良いだろう。
『ループ・オブ・ザ・コード』の舞台となる〈イグノラビムス〉は生物兵器によるジェノサイドを行った罪で国連から歴史を抹消された土地だ。現在は多数の欧米企業が進出し、米国の風景そのものを写し取ったかのような外観を持っている。その〈イグノラビムス〉からジェノサイドで使われた生物兵器が盗まれ、「世界生存機関」の現地調査員であるアルフォンソ・ナバーロが兵器を奪い去った犯人たちを追跡するという冒険活劇の要素が織り込まれている。
いっぽうで〈イグノラビムス〉では200名以上の児童が原因不明の発作を起こし、体を丸めたままの姿勢で動かなくなるという奇妙な事態が発生していた。この謎の奇病の原因を突き止める任務にもアルフォンソは就いているのだ。患者の関係者を尋ねて回り、会話を重ねて謎を追うという形式は『不夜島(ナイトランド)』でも効果的に使われていた一人称私立探偵小説に近い。
〈イグノラビムス〉を歩き回りながら語り手のアルフォンソ・ナバーロが問い続けるのは、故郷や家族を持たない人間がどのように自分の存在理由を立てれば良いのか、ということである。歴史が抹消された国家、というSF的な設定は上記のような問いを語り手に持たせるための媒介であり、不安定なアイデンティティを抱えてしまった人間の苦悩や葛藤を描いていくことにこの小説の主眼はある。終盤においてアルフォンソが導く一つの答えが感慨深いのも、そうした自分の証を立てられないことへの不安という普遍的な問いに真っ向から向き合ったものだからだろう。荻堂の書くSFミステリは社会全体を見渡したうえで、そこから更に個人のアイデンティティへと焦点を絞って物語が綴られていく。
言い換えればSFのガジェットや設定を書くこと自体に荻堂自身はそれほど強い関心があるわけではない。インタビューでも「SFというジャンル自体に強い拘りはない」と述べているように、SFの要素は「世界の認知が歪んでしまった語り手」がどのように世界と折り合いを付けていくのか、という姿を描くための媒介に過ぎないと言って良いだろう。『ループ・オブ・ザ・コード』や『不夜島(ナイトランド)』に感じるのは、どのような人物が社会を見渡しているのか、という視点への拘りである。インタビューでも触れているが、荻堂は日本推理作家協会賞翻訳部門の予選委員を務めるなど翻訳ミステリへの関心が非常に強い作家で、一人称視点の犯罪小説や活劇小説に親しんでいる書き手でもある。 そのことは新潮ミステリー大賞を受賞したデビュー作『擬傷の鳥はつかまらない 』(新潮文庫)から既にはっきりと表れていた。同作の語り手である〝サチ〟こと沢渡幸は、新宿の歌舞伎町でネイルサロンを営む傍ら、「アリバイ屋」という偽物の身分を用意する稼業を営み、更には「雨乳母(あめうそば)」という異名で所謂「逃がし屋」のようなこともやっていた。その「雨乳母」としての役割を求めてやってきた二人の少女に出会ったことからトラブルに巻き込まれ、サチはある人物を捜索することになる。
物語の導入部は人探しを主眼とした一人称私立探偵小説の構造に極めて近しい。ただし、ここに1つだけ特殊な設定が持ち込まれる。先ほど敢えて書かなかったが、実は「雨乳母」としてのサチは、ある特異な力を使うことによって逃亡を考えている人間を逃がしているのだ。その力とは異世界につながる「門」によって逃がすというものである。外観は歌舞伎町を舞台にしたリアルな犯罪小説でありながら、そこに一点だけファンタジー的ともいうべき非現実的な設定を入れる。冒頭に紹介した阿津川辰海の〝特殊設定ミステリ〟観に沿っていえば、『擬傷の鳥はつかまらない』はSFミステリやファンタジーミステリではなく〝特殊設定ミステリ〟に属する作品ということになるだろうか。
そうした細かいジャンル定義はさておき、『擬傷の鳥はつかまらない』は一人称の語りを持つ犯罪小説の魅力が詰まった小説になっている。荻堂自身は「自然と一人称視点を選択してしまう傾向がある」と語っているが、グレーゾーンの側で生きる主人公が目の前の複雑な厄介事をどう対処しながら自分自身が抱える問題にも向き合うのかという、かつて海外私立探偵小説で幾度となく書かれてきた光景がここにはあるのだ。
荻堂は、同作の執筆に当たって意識した小説にギャビン・ライアルの『深夜プラス1』(1965年、ハヤカワ・ミステリ文庫、鈴木恵訳)と桐野夏生の〈村野ミロ〉シリーズの名前も語っている。『深夜プラス1』は命を狙われる大富豪を車に乗せて逃亡する主人公たちを一人称視点で描く冒険小説の名作で、〈村野ミロ〉シリーズは日本における女性私立探偵ものの里程標と呼べる作品だ。この二つの作品が根底にあるということを聞いて、深く納得した次第である。
SFやファンタジー的な要素がない小説でも一人称視点への拘りは感じられる。第46回吉川英治文学新人賞を受賞し、直木賞候補作にもなった『飽くなき地景』(KADOKAWA)は昭和期を舞台に土地開発で財を成した一族の模様と、その一族の守り神と呼ばれる宝刀に魅入られた語り手の人生を描く大河小説である。過去の三作に比べるとジャンル小説の要素が控えめになっているが、昭和史と重ね合わせる形で親子の相克を一人称視点から描く点に、社会と個人の軋轢を一人称で描いてきた過去作との繋がりを思わせる部分があるのだ。
再びSF要素を犯罪小説へ持ち込むことに話を戻すと、荻堂は「メタファーとしてSF要素を作品内に描く」と語っている。繰り返しになるが荻堂の関心は世界の認知にどのような歪みを抱えた人物を視点に置き、物語を描くのかにあり、「SF要素はそのための手段である」と荻堂は捉えているのだ。冒頭で〝SFミステリ〟は「独自に構築された社会を見渡す犯罪小説」と書いたが、誰が見渡すのかに注目してSFミステリは鑑賞すべき、ということを荻堂との会話で改めて痛感した。
※本シリーズは、小学館の文芸ポッドキャスト「本の窓」と連動して展開します。音声版はコチラから。
若林 踏(わかばやし・ふみ)
1986年生まれ。書評家。ミステリ小説のレビューを中心に活動。「みんなのつぶやき文学賞」発起人代表。話題の作家たちの本音が光る著者の対談集『新世代ミステリ作家探訪 旋風編』が好評発売中。