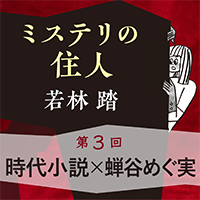ミステリの住人 第7回『ホラー小説 × 新名智』

若林 踏(ミステリ書評家)
謎解き後もすっきりとさせない
第41回の大賞受賞作である『虚魚』はこんな話だ。語り手の“わたし”こと怪談師の三咲は、呪いか祟りで死にたいと願っているカナちゃんと共に暮らしている。ある日、「釣り上げた人が死んでしまう魚がいる」という話を聞いた三咲は、その真偽を確かめるために怪談の起源を辿っていく調査をカナちゃんと始める。いわゆる実話怪談を題材にしたホラーミステリであり、怪談の起源を辿る過程にミステリの興趣を感じ取ることができるだろう。ただ、物語はそれだけでは終わらない。序盤は単線に思われた展開が、中盤から大きくうねり出すのだ。このうねりこそが、同書の魅力である。
新名が実話怪談というジャンルに触れたのは、小学校時代に読んだ講談社KK文庫の〈学校の怪談〉シリーズなど児童書だったと「本の窓」でのインタビュー内では語っている。〈学校の怪談〉シリーズは民俗学者である常光徹が執筆した児童書で、全国の学校などに伝わる怪異の体験談を収集して記す形式で書かれている。1990年から2014年まで続いたシリーズは対象読者である小学生を中心に大ヒットし、同書を原作とした映画が4本製作されるなどメディアミックスの面でも話題を呼んだ。この〈学校の怪談〉シリーズのヒットを皮切りにテレビドラマ、アニメ、漫画作品でもタイトルに“怪談”を冠する若年層向けの作品が1990年代に多く制作され、実話怪談というジャンルが人口に膾炙するきっかけの1つとなった。また、新名は高校生の頃に読んだ木原浩勝・中山市郎の<新耳袋>シリーズの名前もインタビュー内で挙げている。第1作である『新・耳・袋-あなたの隣の怖い話』が扶桑社より刊行されたのは1990年のことで、後にテレビドラマや映画化もされているロングヒットシリーズだ。怪談・オカルト研究家の吉田悠軌は編著『ジャパン・ホラーの現在地』(集英社)で実話怪談ブームを3つのフェーズに分けているが、その第1フェーズに当たるのが<新耳袋>や<学校の怪談>といった活字メディアを中心とした1990年代から2000年代前半であるという。近年ではインターネット上の配信コンテンツから実話怪談に触れる人も多いだろうが、新名は活字の文化から怪談の世界に入った人間だといえる。
さて、怪談に触れた原体験は〈学校の怪談〉シリーズや<怪新耳袋>シリーズだったと語る新名だが、『虚魚』を執筆する上で最も影響を受けた作品としては、小野不由美の『残穢』(新潮文庫)だという。2012年に刊行された『残穢』は小野自身を思わせる語り手が読者から寄せられた恐怖体験の出所を辿っていくという話で、平山夢明や福澤徹三といった実在の作家も登場する疑似的なドキュメンタリーの手法で描かれている。怪談の起源を語り手が追うという形式が、まさに『虚魚』の展開にも受け継がれていることは明らかだろう。映像作品ではオリジナルビデオ作品の〈ほんとにあった!呪いのビデオ〉シリーズなど、フェイクドキュメンタリー形式のホラー作品は存在したが、それを小説の形で表現するとどうなるのか、ということに挑んだのが『残穢』である。現在のホラーブームの特徴としてフェイクドキュメンタリー形式の作品が目立つことが挙げられるが、それらの作品に『残穢』が与えた影響は少なくないだろう。
とはいえ、新名へのインタビューからは、『残穢』についてはフェイクドキュメンタリーという部分以外に惹かれるものがあったことがわかる。興味深かったのは、『残穢』のような怪談を追う作品が持つ魅力として、新名が「私立探偵小説のような面白さがある」と指摘しているところである。ここで新名のいう私立探偵小説とは主人公の一人称視点で調査の過程や事件の顛末が描かれていく形式のミステリを指す。新名は怪談=事件を追うプロセスが1人の視点人物から描かれる点にミステリとしての核があると捉えているのだ。
この点をもう少し踏み込んで考えたい。一人称私立探偵小説を構成する重要なものとして、インタビュー小説の要素がある。視点人物が事件の関係者を訪ね歩き、断片的な情報を拾い集めて事件の構図を自らの手で再構築するというのが、私立探偵小説の基本的なプロットだ。無論、関係者は常に正確な証言をするとは限らない。意図的に虚偽の情報を紛れ込ませることもあれば、証言者の勘違いや記憶の風化などによって証言が歪められることがある。会話というコミュニケーションにおいて生じた歪みをただしていく過程を追うのが私立探偵小説である、という言い方もできる。
新名はこうした私立探偵小説というジャンルの有り様と、実話怪談というジャンルの有り様が似ていると感じたのではないだろうか。『ジャパン・ホラーの現在地』(集英社)に収められた作家・黒史郎との対談の中で怪異体験とは「なんらかの体験をした人が、誰かに自分の『体験談』として語ったその時に初めて生成されるもの。体験者が取材者に話すという行為抜きには、そもそも生成も発生もしないんです」と、実話怪談がコミュニケーションに着目することで成り立つジャンルであることを述べている。人から人へ伝わったこと、あるいは伝わらなかったことを整理しながら怪異を集める実話怪談のスタイルに、私立探偵小説というジャンルの興趣を重ね合わせる点に新名の面白さがある。
ここでようやく思い至る。新名智の書くホラーミステリは「伝える」という行為について考えさせる小説でもある、と。
例えば第2作『あさとほ 』(KADOKAWA)は、題名や内容の一部が後世に残っていながら物語そのものは失われた状態にある散佚物語が大きな要となる。小説の冒頭で語り手が子供の頃に体験した怪異が描かれ、さらに大学生となった主人公の周囲で失踪事件が起きていることが綴られていく。大学関係者の失踪には「あさとほ」と呼ばれる散佚物語が関わっているらしく、主人公は怪異を解くための手掛かりを得るためにこの「あさとほ」の謎に挑む、というのが同書の内容だ。物語について語る小説であるため、必然的に作品内には物語論が展開することが、これが寄り道ではなくミステリとしての趣向にもきちんと関わっているところが秀逸である。物語が伝わる、あるいは伝わらないとはどういうことか、というテーマがミステリとして結実するのだ。
また、第3作長編の『きみはサイコロを振らない 』(同)では「遊ぶと死ぬゲーム」による呪いを解く方法を主人公達が探すという、前2作以上に本格謎解きミステリの要素が前面に出た作品になっている。現代的なアイテムが呪いを伝播させる、という趣向は国内現代ホラーの金字塔である鈴木光司『リング』(角川ホラー文庫)以降にポピュラーなものになったが、『きみはサイコロを振らない』では呪いが発動する人間としない人間の違いは何か、という謎を論理的に解き明かしていく過程に工夫が施されている。これも呪いが伝わる、あるいは伝わないことの差異が鍵となる点で“伝わる/伝わらない”をテーマにした小説だと言えるのだ。
第4作長編の『雷龍楼の殺人 』(KADOKAWA)はどうだろうか。本作の帯や版元サイトの惹句を見ると「完全なる密室」「衝撃不可避の本格ミステリ」などという文字が目に飛び込んでくる。インタビュー内でも度々触れられているが、新名自身の創作姿勢はあくまでミステリに向けられており、これまでの作品でも謎解きの要素が物語を駆動する力として書かれてきた。『雷龍楼の殺人』はその本格謎解きミステリへの拘りを過激なまでに前面へと押し出したものだ。それが端的に表れているのが冒頭に挿入された「読者への挑戦」だろう。
通常の謎解きミステリでは「読者への挑戦状」というものは読者に対して謎を解くための手掛かりがすべて提示される。つまり物語の終盤に挿入されるものなのだ。しかし『雷龍楼の殺人』では「読者への挑戦」は小説の始まりから20頁ほど進んだ段階で提示されるのである。しかも「読者への挑戦」にもかかわらず、そこには犯人の名前が堂々と宣言されているのだ。このような挑発的な趣向が盛り込まれた本格謎解きミステリとして、読者は本作を読み進めるはずだ。新名自身も「正面から本格ミステリを書こうと思った」とインタビューで述べている。そもそも「ミステリ的なフォーマットが一番面白いという感覚が自分の深いところにあり、エンターテインメント小説を書くとどうしてもミステリの構造を持ったものになる」そうだ。ミステリ作家としての新名の姿が際立つ形で露われているのが『雷龍楼の殺人』なのだ。
とはいえ、これまでの新名智作品とは全くテイストが異なるかといえばそうではない。確かに本作は論理的な推理が展開する本格謎解き小説ではある。しかし、論理によって真相が開示された後に飛び込んでくる光景は、霧が晴れるようなものではない。その不条理な感覚はむしろホラーと呼ぶべきものに近いのではないのか。インタビュー内で新名は『雷龍楼の殺人』を書くに当たって念頭に置いていた、ある現代海外ミステリ作品について語っている。ここでは敢えて作品名は伏せるが、気になる方は是非ともポッドキャストの後編を聴いていただきたい。その題名を聞いた時に筆者はなるほど、と感心した。ミステリとしての趣向は違えども、謎が解かれてもすっきりとしない、という意味では確かに通ずるものがあるのだ。ならば「伝える」というキーワードはいずこに、と思った方もいるだろう。この点については、主要登場人物の2人が極めて特異な状況下でコミュニケーションを図って謎解きに挑まねばならないところに現れているだろう。どのような状況下なのか、ということは詳しく書かないが、読者の不安を増幅させる演出として秀でたものだ。
論理性を重んずるミステリを軸にしながら、あらゆる形でホラーに通ずる要素が滲み出る作風。そして、「伝える」という行為にまつわる小説であること。こうした強い芯で貫かれているのが、新名智という作家の作品なのだ。
※本シリーズは、小学館の文芸ポッドキャスト「本の窓」と連動して展開します。音声版はコチラから。
若林 踏(わかばやし・ふみ)
1986年生まれ。書評家。ミステリ小説のレビューを中心に活動。「みんなのつぶやき文学賞」発起人代表。話題の作家たちの本音が光る著者の対談集『新世代ミステリ作家探訪 旋風編』が好評発売中。