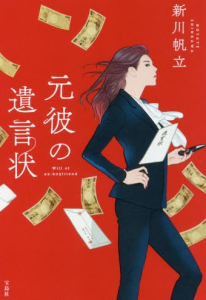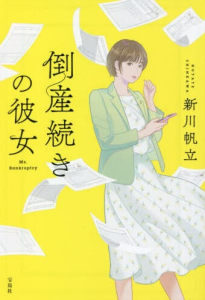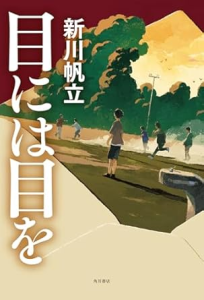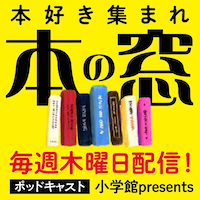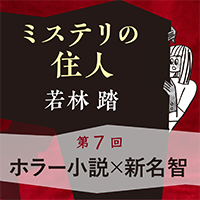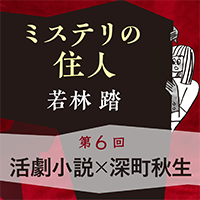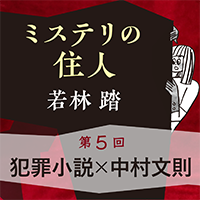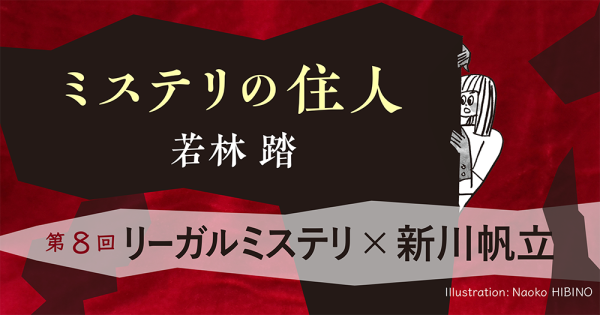ミステリの住人 第8回『リーガルミステリ × 新川帆立』
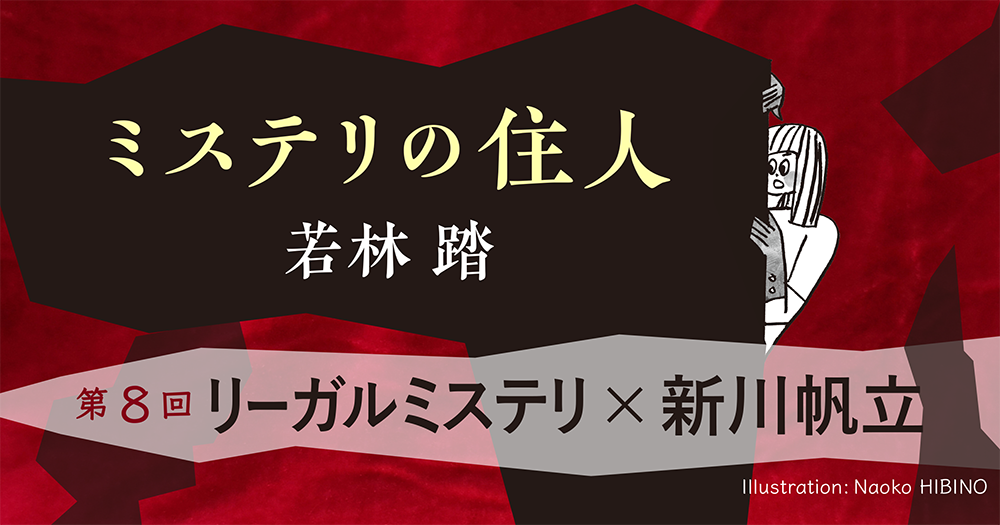
若林 踏(ミステリ書評家)
それが新川帆立にインタビューして思ったことだ。
第19回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞したデビュー作『元彼の遺言状』 (宝島社文庫)は破天荒な弁護士・剣持麗子が活躍するミステリで、綾瀬はるか主演のテレビドラマ化も手伝い大ヒット作となった。剣持麗子のシリーズによって、おそらく大半の読者は個性的なキャラクターを主眼にした小説の書き手、という印象を新川に抱いたことだろう。
だが新川作品の魅力は本当にキャラクターなのだろうか。そのような疑念を抱いたのは2023年に刊行された『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』 (集英社)を読んだ時だった。ひょっとして新川帆立はキャラクターよりも、法そのものを主題とした小説を書きたいという思いが強い作家なのではないか。今回のインタビューでは、その答えを得ることが出来た。
キャラではなく法そのものを描く
新川の言うリーガルミステリの定義は至って明快である。「ミステリとしての謎解きや犯人の動機といった部分に法概念や法の仕組みが関わってくる小説」だ。そして新川はこのようにも言っている。「弁護士が出てくるだけで“リーガルミステリ”と括るのは、ちょっと違うのでは」と。非常にシンプルではあるが、実はこれこそが現在において“リーガルもの”と呼称される作品の課題を鋭く突いている。新川が抱く懸念は“リーガル小説”が“キャラもの”として消費されることで、法そのものの形を問うというリーガル小説本来の読みどころが見逃されてしまうことにあるのだろう。話を聞いていて「なるほど」と思ったのが、ジョン・グリシャムの作品に対する新川の評価である。グリシャムといえばリーガルスリラーの大御所として日本でも知られている作家だが、新川は「法制度や法概念がミステリの根幹に関わっておらず、『弁護士を主人公にしたスリリングなサスペンス』と呼んだ方が良い作品も多い」と述べる。確かにグリシャムの小説を弁護士の成長物語として鑑賞する向きも多い。“キャラもの”ではないが、グリシャム作品を一種の教養小説として受容しているのではないか、というのが新川のグリシャム評の意図だろう。
では、新川が唱えるリーガルミステリ観に則って〈剣持麗子〉シリーズを振り返るとどうなるか。剣持麗子の強烈な個性に目が行きがちではあるが、実は第一作で法そのものの有り方がミステリの趣向にしっかりと結びついていることが分かる。デビューの段階から新川は自身のリーガルミステリ観に対して忠実だったのだ。また、新川がキャラクターではなく法そのものを描くことに重きを置く作家であることは、シリーズ第二作『倒産続きの彼女』(宝島社文庫)を読めば明確に見えてくる。同作では剣持麗子は登場するものの、主要視点人物は剣持の後輩弁護士である美馬玉子が務める。『倒産続きの彼女』は倒産法を題材にした小説であるが、読んでいくと作品の視点人物を美馬玉子というキャラクターに設定した必然性が浮かび上がってくるのだ。デビュー作で人気を勝ち得たキャラクターを主役に据えず、小説の題材に相応しい視点人物を置くことを重要視している。第三作である『剣持麗子のワンナイト推理』(宝島社文庫)はタイトル通り、再び剣持を主人公にした連作短編集となっているが、これも謎解き連作としての企みを成立させるために固定化した探偵役として剣持の出馬が要請されたと見るべきだ。現にインタビュー内で新川自身も『剣持麗子のワンナイト推理』について「名探偵が登場する本格謎解き短編集」と語っている。
こうして明確なジャンル定義を持ちながら創作を続ける新川が、自身のリーガル小説観を最も鮮明に打ち出したのが先ほど挙げた『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』だ。これは6つの異なる“レイワ”日本を舞台にした、パラレルワールドSFの要素を持つ短編集である。それぞれの世界の日本には架空の法律が制定されている。例えば6篇目の「接待麻雀士」では認知症予防のために賭け麻雀が合法化されており、接待麻雀専門の雀士が存在している世界が描かれている。そうした架空の法律によって生まれた社会の歪みを書くことで、既存の価値観に対する違和を炙り出す風刺小説としての側面がこの連作集にはあるのだ。
ミステリの要素が核にある短編も多く、その意味では同作はれっきとしたリーガルミステリ短編集と呼べる。だが、法曹関係者が主人公だったり法廷が舞台になっている作品は一編目の「動物裁判」のみで、大半の読者が想像するリーガルものとは違う趣きになっていることが面白い。ここで主題となるのは法律の概念がその社会にどのような影響を与え、歪みを生んでいるのかということである。つまり新川の唱える「法概念や法の仕組みそのものを主眼とした」リーガル小説なのだ。
リーガルミステリの範疇に入ると書いたが、その趣向も多彩である。賭博小説であり立派な麻雀ミステリである「接待麻雀士」も素晴らしいが、筆者のお気に入りは「最後のYUKICHI」だ。キャッシュレスが過度に進んだ日本で現金を廃止する法律が制定され、一万円紙幣がマネーロンダリングの手段として重宝されるようになった社会が舞台の小説である。現金の無い世界でしのぎを削る犯罪者たちの悲喜こもごもを描いており、ドナルド・E・ウエストレイクの書くようなクライムコメディになっているのが楽しい。かと思えば「健康なまま死んでくれ」という作品は「労働者保護法」という過剰な健康管理を義務付ける法律が敷かれた世界での本格謎解き小説になっているなど、幅広いミステリの興趣を盛り込んだ短編が揃っている。リーガル小説とウエストレイクのような犯罪小説の組み合わせなどと聞くと面食らうミステリファンがいるかもしれないが、ここもまた新川の言うリーガルミステリの定義から1ミリもぶれていない。つまり法概念や法解釈が結びついていれば、必ずしも法廷ものや法律家を主役に据える必要は無く、様々なミステリのサブジャンルと融合させることが可能である。『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』とはリーガルミステリが如何に豊饒なジャンルであるのかを示した作品集なのだ。
更に言えば『令和〜』は新川がキャラクターの造形よりも、ミステリの技法と小説の主題を結びつけることに関心を寄せる作家であることが良く分かる作品でもある。今回のインタビューで新川は〈剣持麗子〉シリーズの印象が強すぎる故に、個性的なキャラクターを主人公に据えた仕事小説を求められることが多かったと述べている。いわゆる“キャラもの”を書いて欲しいという要望が強いことに新川自身が悩んでいるようにも見受けられたが、これを作家としてのイメージが固定化されてしまうのを恐れていると捉えるのは早計だろう。新川が危惧しているのは、ミステリあるいはジャンル小説の鑑賞が“キャラ読み”、すなわちキャラクターの魅力だけに収斂されてしまうことである。逆に言えば技法や趣向の組み合わせ方にどのような工夫を施しているのかに目を向けると、ジャンル小説の読み方がより豊かになると新川は信じているのだ。
そこで2025年1月末に刊行された『目には目を』(KADOKAWA)の話である。発売前につきインタビュー収録時には言及できなかったが、同作は新川のジャンル小説観が明確に打ち出され、かつミステリとしての完成度は過去作を含めて随一のものになっている。
かつて傷害致死の罪に問われた元少年が被害者遺族に殺されるという事件が起き、語り手を務めるライターが関係者に証言を聞いて回る、という形で小説は進行する。少年犯罪を題材にしたミステリはこれまでも多く書かれてきたが、本書の特徴は中盤から変則的なフーダニットの趣向が持ち込まれる点にある。加えて引っ繰り返るような大仕掛けがさらりと書かれ、終盤は畳みかけるような展開に圧倒される。同作はミステリの技巧をつなぎ合わせることによって読者を物語の中へと引きずり込んでいく小説なのだ。登場人物の造形をはじめ作品内で描かれることは、すべて技巧を成り立たせることへ奉仕するようになっている。ここではミステリの技法から逆算される形でキャラクターが作り上げられているのだ。技法や趣向の組み合わせの工夫に目を向けて欲しい、という新川の声が聞こえてくる。
着目すべきは、中盤以降に仕掛けられるミステリの技法が小説全体を貫く主題を浮かび上がらせることに繋がっていることだろう。作品内で書かれていることのすべてが技巧に貢献している、と述べたが、それは物語としての豊かさまで犠牲にしているわけではない。むしろ同作ではミステリの技法があるからこそ扱われている題材が鮮明に浮かび上がるようになっているのだ。そこには『目には目を』という小説の題名が意味するものも含まれている。目には目を、歯には歯を。ご存じの通り、バビロニアのハンムラビ王が制定した、世界最古の法典と呼ばれる「ハンムラビ法典」のなかにある条文である。この作品もまた、新川の言葉に則れば紛れもなくリーガルミステリなのだ。やはり新川帆立はどこまでもリーガルミステリの本質に迫ろうとする作家なのである。
※本シリーズは、小学館の文芸ポッドキャスト「本の窓」と連動して展開します。音声版はコチラから。
若林 踏(わかばやし・ふみ)
1986年生まれ。書評家。ミステリ小説のレビューを中心に活動。「みんなのつぶやき文学賞」発起人代表。話題の作家たちの本音が光る著者の対談集『新世代ミステリ作家探訪 旋風編』が好評発売中。