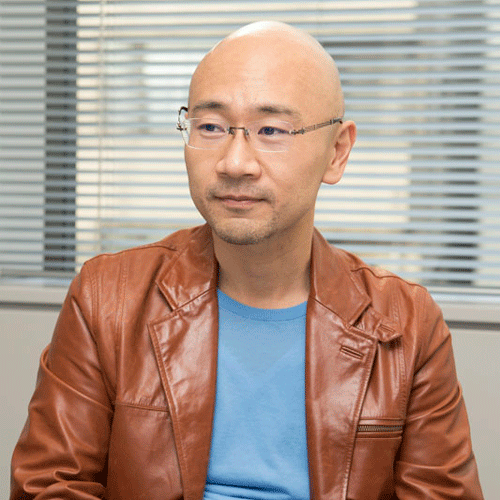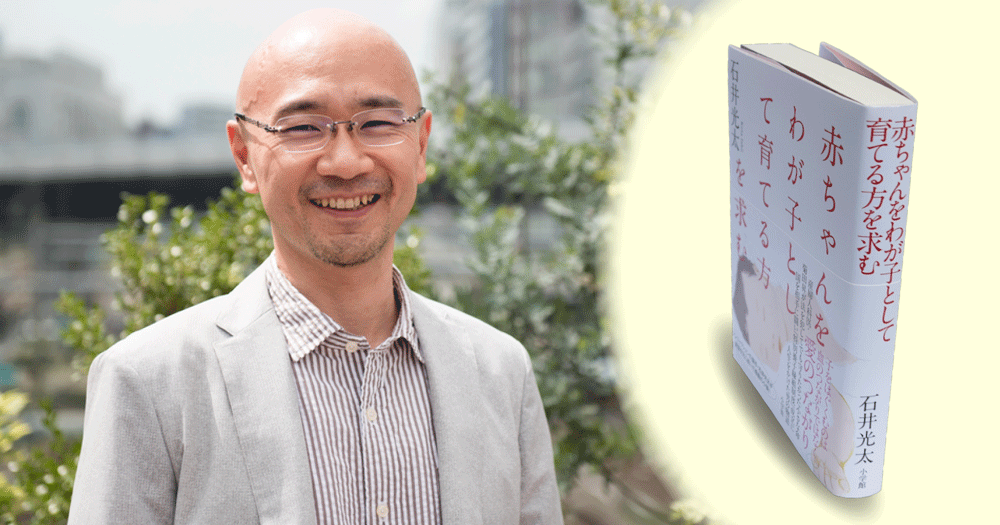◇自著を語る◇ 石井光太『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』
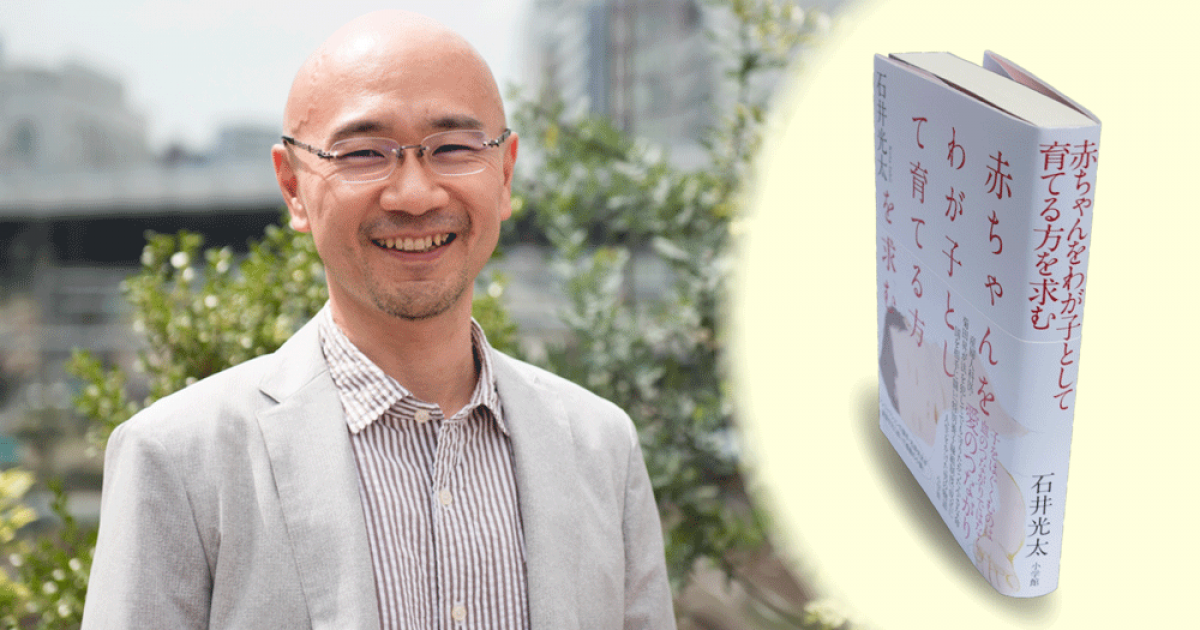
「宮城県石巻市の遊郭で育った一人の産婦人科医がいた。彼は中絶手術に嫌気が差し、出産させた上で赤ちゃんを不妊の夫婦にあげる斡旋をはじめた。そしてその事実を公表した上で、国や医師会を敵に回して闘い、勝ち取ったのが特別養子縁組の法律だった」
その医師の名が菊田昇だと聞いたのは、東日本大震災が起きてから少し経ってからのことだった。
私は東日本大震災の取材をする中で、石巻が東北有数の漁港としてにぎわい、遊郭まであったという話を方々で聞いていた。そのため、あの時代のことかと思うと同時に、菊田昇が何のために国や医師会に反旗を翻してまで赤ん坊の命を守ろうとしたのかを知りたいという気持ちが膨らんだ。
石巻の歴史と菊田昇の人生を追う旅は、非常に深いものだった。
昭和初期の石巻の遊郭で、菊田昇が目にしたのは、東北の貧しい農村から集まってきた遊女たちの哀しい人生だった。彼が進学し、医者になれたのは、彼女たちが体を売って稼いでくれたからだ。
三十歳を過ぎてから石巻にもどって産婦人科医院を開業した時、昇がもっとも苦しんだのが妊娠後期の堕胎だった。
当時は妊娠二十八週までの人工妊娠中絶が認められていた。陣痛促進剤を打って早産させるのだが、中には命を宿して生まれてきてしまう子もいた。そんな時、医師は自ら嬰児の首を絞めたり、濡れたタオルを顔に置いたりして葬り去り、「死産」と偽って処理した。
昇もこうすることで、長者番付に載るほどの名士になった。だが、彼の心には、赤ん坊を殺害することの罪悪感があった。やがてその思いは、母親を説得して赤ん坊を産ませた上で、別の不妊の夫婦に与えるという「赤ちゃん斡旋」へとつながっていく。
だが、斡旋の数が増えれば増えるほど、引き渡す夫婦も必要になってきた。そこで昇は決心し、新聞に次のような広告を打つ。
《赤ちゃんをわが子として育てる方を求む》
公然と赤ん坊の親となってくれる人を募集したのだ。特別養子縁組をめぐる国との闘いが幕を開けたのは、ここからだった。詳しいことは本書を読んでほしい。
ただ、この時代の産婦人科医であれば、昇と似たような思いを抱いていたはずだ。その中で、なぜ彼だけが国や医師会を相手に人生をかけて闘うことができたのだろうか。
資料を調べたり、親族に話を聞いたりして確信したのは、彼が過ごした遊郭での幼少期の記憶と無縁ではないだろうということだった。
彼は、遊女たちが客の子供を孕み、堕胎してきた姿を見てきたはずだ。さらに言えば、その無数の屍のおかげで医師になることができた。そう考えた時、赤ん坊の命を奪うより、助けることを選択したのだろう。これは石巻という町が背負ってきた業でもある。私が小説という形をとることでしか、この物語を描き切ることができないと考えたのは、そのためだ。
現在、特別養子縁組は、様々な事情で実親に育ててもらえない子供たちを別の家庭に預ける手段として重宝されている。法律ができてから三十年ほどの間で、一万四千人以上の子供が養親のもとに引き渡され、実子同然に愛情を注がれて育てられてきた。
私たちが手にしている権利は一朝一夕にできたものではない。多くの人々の苦悩と努力の末に勝ち取ったものなのだ。こんな困難な時代だからこそ、菊田昇という医師の人生を通して、私たちが手にしているものの大切さを噛みしめてほしい。