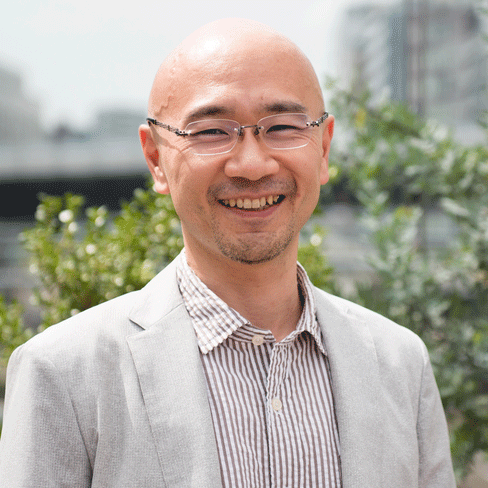石井光太さん『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』
貧困層の実態など、社会に一石を投じる作品を多数発表してきた、ノンフィクション作家の石井光太さん。近年は小説家としても活躍中です。4月には最新刊『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』を発表しました。特別養子縁組の法整備を目指し、医師団体や国家と闘った産婦人科医・菊田昇を主人公にした長編です。多くの命の実像を見つめてきた石井さんが、卓越した人間洞察と想像力で、法律を変えた異端の医師の素顔を、現代に蘇らせます。本作にかけた思いを、石井さんに語っていただきました。
栄えていた昭和の石巻を書けるチャンス
きらら……『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』は、特別養子縁組制度ができるまでの壮絶な人間ドラマを描いた、実話ベースの小説です。構想はいつ頃、考えられたのでしょうか。
石井……2011年に東日本大震災が起きたとき、僕は取材で宮城県に入っていました。そのとき石巻の人たちに「ぼろぼろに壊れた町じゃなく、自分たちが生きていた町の状況を描いてほしかった」と言われたのが、ずっと印象に残っていました。
その2年後ぐらいに、子どもの虐待をテーマに取材を進めていました。特別養子縁組が虐待の予防策として非常に有効で、多くのケースの解決策として利用されている事実を知りました。いろいろ調べていくなかで、養子縁組の法律をつくったという、石巻の産婦人科医・菊田昇の存在に行き当たりました。
昇は地元で生まれ育ち、望まれずに生まれた赤ちゃんを救うため、養子縁組の法整備に力を尽くしました。僕が震災取材で石巻の人たちから聞いた「昔は遊郭がたくさんあった」「すごく栄えていたんだ」という話と、彼の人生の背景に、つながるものを感じたのです。
被災地で破壊された景色は、ノンフィクションで徹底的に書き尽くした記憶はあるんだけれども、それより以前の景色を自分は書いていない。昇と出会ったのは、書けるチャンスかもしれないと思い、構想をまとめていきました。
きらら……小説の形で書くことは、最初から想定されていたのですか?
石井……正直、ノンフィクションでいけるならノンフィクションの方がいいと、最初は考えていました。しかし昇の話で、いちばん僕が面白いと感じたのは、遊郭で生まれ育った出自です。
彼が地元で産院を開業した昭和30年代は、妊娠8ヶ月の胎児の中絶も認められていました。倫理的に中絶したくない医師は、きっといたはずでしょうけれど、表だって法改正を唱える人は、いませんでした。たったひとり、声を上げたのが昇です。赤ちゃんや妊婦を取り巻く理不尽な環境の改善を求め、医師会など組織から攻撃されながらも、信念を曲げずに闘いました。
彼を突き動かしていた強い動機は、中絶や流産を日常的に見ていた、遊郭育ちの生い立ちによるものでしょう。昇はそんな遊女たちを哀れに感じ、深く愛情を感じていました。実際に著書で、子どもの頃は遊女たちに、家族のように大事に育てられたと明かしています。
当時の遊女は、戦前の貧しい東北の田舎から集められた少女たちでした。過酷で惨めな暮らしを、強要されました。彼女たちの稼いだお金で、菊田は一流の大学を出て、医師の資格を取り、産院を開業したのです。遊郭育ちで自分ひとりだけ、社会的成功を得てしまったという後ろめたさを、抱えていたと想像されます。
遊郭育ちの部分を深掘りして書けば、昇が医師として赤ちゃんの斡旋を手がける動機が、明確になるのではないかと思いました。けれど昭和初期の遊郭の記録が、ほとんど残っていません。その部分を省いてノンフィクションにまとめることもできますが、妊婦を救った立派な医師の話になり、誰も共感してくれないでしょう。
昇の実像に迫るためには、遊郭で育った生い立ちを想像で補完するしかありません。この物語は、小説で書くことを選ぶよりなかったと思います。
母と息子が同じように抱えた後ろめたさ
きらら……昇は幼少期、遊女のカヤとアヤの姉妹を、実の姉のように慕っていました。彼女たちは昇の原風景となる、重要な存在として書かれています。
石井……彼女たちは僕の完全な創作です。昭和初期に東北から集められた遊女たちが置かれている状況を、体現させるキャラクターとして登場させました。若くて働けるうちはいいけれど、年を取ったり病気になると、遊女は無残に打ち棄てられました。そんな実態を凝縮させた人物が、アヤとカヤです。
姉妹は昇が幼い頃は、ある程度、幸せに暮らしていました。しかし結局、姉妹ふたりとも惨い最期を迎えます。小説だからというわけでなく、事実に照らしても、多くの遊女たちの運命は、そうだったでしょう。もし昇が幸せな人生を歩めた遊女に接していたなら、後に語っていただろうし、リスクを冒してまで赤ちゃんの斡旋に心血を注ぐ道を選ばなかったと思います。小説ならば、カヤとアヤのどちらかの人生をハッピーエンドで終わらせることもできました。でも、そうじゃないだろうと。昇の闘ってきた軌跡を見れば、カヤとアヤの哀れな生涯は必然でした。
彼女たちの思いは、住職のもとで育った文子に託されました。文子はずっと、法の壁に挑み続ける昇の味方であり続けます。もしアヤとカヤが、大人になった昇の近くに居たら、こんなふうに彼を支えていたでしょうね。
きらら……もうひとり、菊田の母親のツウにも注目したいです。女手ひとつで遊郭を経営し、菊田と他の兄弟たちを育て上げました。やり手である一方、昇の気持ちは聞かず、自分の意思を押しつけます。ツウが生涯を閉じる晩年まで、母子の確執は残りました。
石井……ツウに関しては昇の息子さんほか、ご存命の関係者の方々に取材して聞いた人物像を、そのまま書きました。あの時代に遊郭の稼ぎで、子ども5人を食べさせようとしたのです。並大抵の胆の据わり方ではなかったでしょう。
実は、昇以外の姉兄は、昇よりも勉強ができました。しかしツウは経済的に、全員は高校に行かせられませんでした。母親としては無念だったと思います。それが末っ子の昇にかける責任感の大きさとなり、接し方は厳しくなってしまったのでしょう。
きらら……ツウは昇に、必ず産科医になって、地元で開業しろと強要します。
石井……遊郭で多くの遊女たちを酷使した、彼女の罪滅ぼしだったのかもしれません。勉強をさせてやれなかった他の子どもへの申し訳なさ、遊女の供養など、いくつもの責任感のようなものが、昇の教育に集中したといえます。
反抗しながらも、昇はツウと同じように後ろめたい感情を抱え、結局は母の願ったとおり地元で医者になります。ツウは何としてでも生きていく、子どもたちを育てるというエネルギーにあふれていました。そのエネルギーは、医師として法律を犯してでも、周りに敵をつくってでも赤ちゃんを救いたい、昇のエネルギーと重なります。
苦しいけれど、人間にはやらなくてはいけないことがある。理解し合うことは難しかったけれど、昇は間違いなく、ツウから大事なものを受け継ぎました。
きらら……信念に生きた医師の物語である一方、愛憎によって繋がった母と子の物語でもあると思います。
石井……親父と息子だったら、また違う話になっていたでしょうね。
人間オタクだから人間を見ることに飽きない
きらら……行き場のない新生児を、実子として育ててくれる親を探す昇の活動は、医師会から激しく批難されます。人を助けるはずの正論が、逆に反感を買うという、現代に通じる日本社会の縮図をあらわしているようです。
石井……信念を持って行動した人を批判する側って結局、人間を見てないんですね。社会のなかで、面子やしがらみに揉まれているうちに、人ではなく社会の方ばかり見るようになる。社会が何のために存在しているのか、忘れてしまうのです。
人間は、人間を見るのが本質のはず。昇はそのとおりに動いているのですが、社会を見ている側は間違っているととらえ、昇のような姿勢の人を叩こうとします。
社会の側が、人間を大切にする個人を攻撃し、服従させようとする。いつの時代にもありますね。社会というものが形成された大昔から、繰り返されている現象でしょう。
ただ、昇のように、人間の味方でいる姿勢を崩さず、闘い抜いた者たちがいたから、社会は動きました。制度改革が行われ、たくさんの人が救われました。僕たちがふだん何気なく享受している福祉やサービスは、無数の努力と犠牲のうえで、成り立っています。そういう事実を、忘れてはいけないんですね。
特別養子縁組は、昇や支援者たちの血を吐くような努力と、歴史に埋もれた悲劇によって実現しています。あるのが当たり前ではない。この制度を活かし、未来を生きる子どもたちを助け、どのように社会を良くしていくべきか、深く考えなきゃいけないのではないか? そんな問いかけを、今回の小説が果たしてくれたらいいと考えています。
きらら……石井さんがノンフィクションでも追究されている、生ききろうともがく人間をありのまま描写した、胸に刺さる小説です。
石井……僕は実は社会派ではなくて、人間を書くのが好きなんです。どこか人間オタクなところがあります。昆虫オタクが時間を忘れて、虫ばっかり観察しているように、人間をいつまでも見ているのが楽しい。まるで飽きませんね。人間は見れば見るほど、魅力にあふれてきます。
菊田昇は晩年まで闘い続け、最期は病に侵されました。彼の人生は、逆境の連続だったでしょう。けれど自分も他人の命も、諦めなかった。苦しかろうとも生きるのだという、人間としての力強い姿を見たとき、僕は理屈にならない感動を覚えます。
僕が感動することは、多くの読者も感動してくれると信じています。それを書き続けるのが、最もやりたいことで、作家である僕の役割だろうと思います。
小学館
石井光太(いしい・こうた)
1977年東京生まれ。『絶対貧困─世界リアル貧困学講義─』『遺体─震災、津波の果てに─』『「鬼畜」の家─わが子を殺す親たち─』ほか多数のノンフィクションを手がける。小説に『蛍の森』『砂漠の影絵』『世界で一番のクリスマス』『死刑囚メグミ』など。