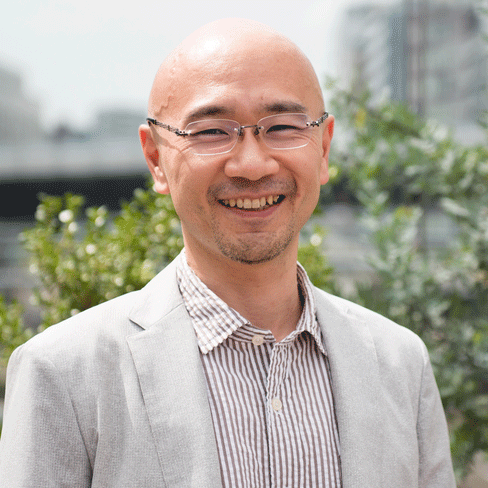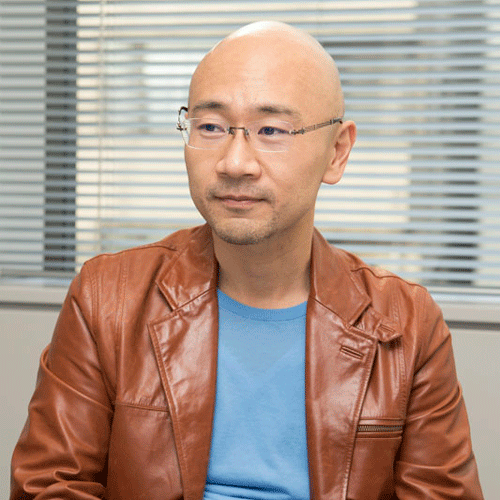石井光太『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』

〝嬰児殺し〟と戦いつづけた男
近年、特別養子縁組制度は、虐待を受けたり、親がいなかったりする子供たちを助ける命綱として注目されている。
この制度ができた一九八八年以前は、母親はどんな事情があれ、産んだ赤ん坊をすぐに他人の家に特別養子に出すことができなかったため、人工妊娠中絶を選ぶしかなかった。しかし当時は妊娠七カ月までの中絶が認められていたことから、失敗すれば、死産にならず、赤ん坊が命を持って出てきてしまうこともあった。医師は母親の人生を慮り、赤ん坊を分娩室内で殺めて「死産したこと」にしなければならなかった。
そんな状況に疑問を呈したのが、宮城県石巻市で生まれ育った菊田昇医師だった。
かつて石巻は東北でも指折りの栄えた漁港だった。日本中から船が押し寄せ、港町には遊廓が立ち並び、競馬場まであった。歓楽街は、海の男たちが夜通し遊ぶための場所だったのだ。
菊田医師は遊廓で育ち、自ら「遊女たちに育てられたようなもの」と述べている。戦前から戦中にかけての遊廓たちの悲しい現実を嫌というほど見て育ってきたのだろう。そんな彼が医師になり、東北大学附属病院などを経て、石巻にもどって産婦人科医院を開業したのは、昭和三十年代のことだった。
当時の私立の産婦人科医院の経営を支えていたのは、原則として公立病院では行っていなかった中絶手術だった。大きな港町には、一夜の遊びで孕んだ女性だけでなく、強姦された女性、だまされた女性、客の子を身ごもった娼婦などがたくさんいた。開業医はそんな彼女たちに中絶手術を施し、時には先述したように誤って生まれてしまった赤ん坊を殺害してあげた。石巻の闇を背負い、闇に葬るのが、仕事だったのだ。
周りの医師たちはそれを産婦人科医の宿命として受け入れていたが、菊田医師は遊女の苦しみを間近で見てきたこともあるのだろう、違う考え方をした。
──赤ん坊たちを養子に出して、何とか命を守りたい。
そう思い立ち、開業から二十年以上もの間、自分がやってきた後ろめたい過去を公表し、これは日本全国の産婦人科医が背負っている業であり、日本の暗部なのだと訴え、特別養子縁組制度の設立を訴えたのだ。
命をつくることは何なのか。
命を守るとはどういうことなのか。
本書の主人公である菊田医師の人生にはそうした問いが全てつまっている。日本政府が特別養子縁組制度を赤ん坊の命綱として力を入れている今だからこそ、多くの人に彼の人生を通してそのことを考えてほしいと思う。