丸山正樹『ワンダフル・ライフ』
素晴らしい人生であれ
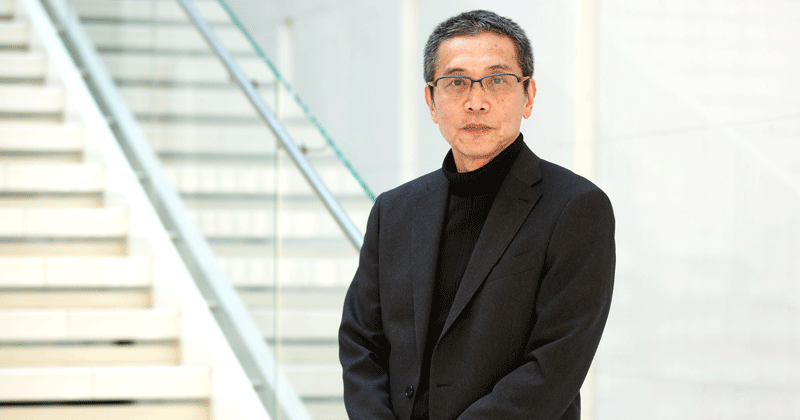
聴覚障害を題材にした社会派ミステリー「デフ・ヴォイス」シリーズで知られる丸山正樹が、作家デビュー一〇年の節目となるタイミングで渾身の勝負作『ワンダフル・ライフ』を発表した。
四組の男女からなる物語の内側に、自身の実人生をも取り込んだ本作は、ミステリーの要素が盛り込まれながらも人間ドラマとしてかつてない高みに到達している。
外側からではなく内側から探りたい
二〇一一年のデビュー作『デフ・ヴォイス』の主人公は、聴覚にハンディキャップを持った人々を支える手話通訳士であり、耳が聞こえないろう者の親から生まれた耳が聞こえる子供──コーダ(CODA/Children of Deaf Adults)だった。作家自身は健聴者であり、作家の身内にろう者がいたわけではない。資料に当たり取材を重ねることによって、同シリーズ三作を書き継いできた。
「当事者の視点からは書けない、少なくとも聞こえない人の立場では書くべきではないと考え、それでもなんとか成り代わり得る存在はないだろうかと探したところで出合ったのが、コーダでした。当事者性を重んじるがゆえに、当事者を回避するというのが、これまでの私の書き方だったんです。ただ、その選択は、当事者について深く考えないことに繋がりかねないという疑念もありました」
そんなおり、二〇一六年七月に「相模原障害者施設殺傷事件」が発生した。
「やまゆり園で一九人が殺害され二七人が重軽傷を負った事件そのものにも衝撃を受けましたが、〝重度障害者は生きている意味がない〟として犯行に及んだ容疑者に対し、その動機を擁護する声がネット上で多数あがっているのを見て二重に衝撃を受けたんですね。そうしたネットの反応を目の当たりにしながら、〝あぁ、自分はこの問題の当事者だな〟と思ったんです」
あとがきでこう記している。〈私自身、作中人物と同じく頸髄損傷という障害を負った妻との生活を三十年続けておりますが、小説内の設定と異なり、いたって円満に過ごしております〉。
「今回の『ワンダフル・ライフ』では、当事者性に初めて向き合おうと思いました。障害を持つ妻を介護する私自身の生活を、男性主人公の一人称で、なまなましく書く。それだけでなく、脳性麻痺で全身が動かない男性を、当事者が読めば〝違う〟と言われるかもしれないことを恐れずに、当事者に成り切り深く深く考えて書いていく。そうした作業を積み重ねることで、この社会に存在する問題を、外側からではなく内側から探っていきたいと思ったんです」
切なさという感情は障害者も変わらない
四組の男女が登場する、四編の物語から構成されている。まず現れる「無力の王」という章タイトルの物語は、事故による頸髄損傷でほぼ全身が動かない妻を、自宅で介護する中年男性(「わたし」)の日常とその心理がドキュメントされていく。
ありがとうとは決して言わない、高圧的な妻の言動により無気力になりかけていたが、深夜に一人でできる密かな趣味と出合ったことで、息抜きを超えた充実を得る──。
「私の妻はもっと愉快な性格ですが(笑)、介護当事者としての細かな描写はすべて、私自身の経験であり本当のことです。介護をしながらこう思った、こう感じたという心理の部分に関しても、自分の中にあるものを大きく膨らませたりしながら書いていきました。私がこれまで意識してきたのは〝障害者を題材にエンターテインメント小説を書く〟ことでしたが、今回はエンターテインメント性をほとんど考えていなかった。
小説とは言えないものを書いてしまっているんじゃないか、という不安はずっと拭えませんでしたが、ここを書き切らなければ作家として前に進めないと腹を括りました」
誤解を招く言い方かもしれないが、「知らなかった現実を知る」「他者の人生を内面込みで追体験する」という意味で、この一編も十分にエンターテインメントだ。
続く「真昼の月」では、三〇代後半の夫婦が一年限定で不妊治療に臨む様子が描かれる。
三番目に現れる「不肖の子」は、不倫相手である上司の子を身ごもった広告代理店勤務の二〇代の女性が、別の男性と距離を近づけていく物語だ。それぞれのカップルの間に横たわる秘密が、少しずつこぼれ出ていき、やがて後戻り不能な展開へと至るプロセスにサスペンスが宿る。
「一編目の『無力の王』の夫婦の話があまりにも自分の現実に近く、自分自身と対話しなければいけなかったために、書き進めるのがしんどかったんです。気分転換の意味も込めて、自分の現実からは離れた、年代も異なるいろいろな男女の物語を書いていきました」
四番目の物語「仮面の恋」では、脳性麻痺の青年が、ネットで知り合った健常者の女性と恋に落ちる。やむを得ぬ事情により、自分は健常者であるという偽りの身分をまとって彼女とデートをすることになったのだが……。強烈な片思いを描く、ロマンチックかつリアルな恋物語となっている。
「妻が通う障害者通所施設で、脳性麻痺の青年と出会いました。彼は足の指でパソコンのキーボードを一文字ずつ押してプログラムを書き、スマホアプリの開発者として生計を立てていたんですね。見た目からは想像もつかない……と私自身が人を外見で判断したり差別意識を持ってしまっていたことも含めて、障害者を巡る一つの現実として書いてみたかった。恋愛をクローズアップすることになったのは、自分を理解してもらうことなどできないし相手を理解することも難しい、といった状況で生じる切なさが、恋愛という関係の中で一番強く出せると思ったからかもしれません。障害を持った方々と普段あまり接したことがない方たちにも、その気持ちは自分も知っている、と通じ合えるような話にしたかったんです」
読んで心が動いたなら社会を変える力になる
本作の特徴は、四つの物語が「無力の王(1)」「真昼の月(1)」「不肖の子(1)」「仮面の恋(1)」という順番で現れ、それぞれが「(3)」まで進んでいった先で、「エンドロール」と題された章が現れる点にある。
「一編ごとに結末まで書いていく、わかりやすい連作短編にすることも考えたんですが、悩んだ末にこの構成に落ち着きました。そもそもがこの構成でというか、初期設定だけは固めて結末をはっきり決めず、四つの物語を同時進行で書いていったんです。そういう書き方をしたからこそ、内容が自然と反響し合っていったんですよね。例えば『真昼の月』は他の三編とは異なり、障害者の問題が絡んでくる予定はありませんでした。
ですが、話を進めていったところで、特別養子縁組制度を取り上げることになった。その制度を活用する夫婦は、子供を選ぶことができないのは知っていたんですが、子供に障害があるか否かも選べない、ということは知らなかったんですよ」
障害者にまつわる問題を筆頭に、この社会に存在する「知らない(ふりをしていた)現実」や「知っているつもりでいた現実」を知る、感じる。そうした営みの先で、四つの物語は「エンドロール」でひとつに繋がる。驚愕必至のラストには、まぎれもなくミステリーの興奮が宿っている。
「私自身は今回、ミステリーを書くという意識はあまりなかったんです。とにかく自分の中にあるモヤモヤを、小説の形にして外へ出すことが優先順位としては第一でした。ただ、エンドロールを書くうえで唯一意識していたのは、落差です。読み手の感情をぐっと高めていったところで、思いっきり落とす」
そう聞くとバッドエンドが描かれているように思われるかもしれないが、読み心地はまったく違う。
「果たして自分の人生が素晴らしいものかどうかは、分かりません。けれど、誰かに対して〝素晴らしい人生であれ〟と願うことができているならば、それは人生にとっての光であり希望なのではないかと思うんですよ」
現在は「デフ・ヴォイス」シリーズ第四作となる『わたしのいないテーブルで』を、「しんぶん赤旗」で連載中だ。コロナ禍における障害者の現実を描くことになる、と言う。
また、このインタビューの直前、『ワンダフル・ライフ』の重版が決定した。丸山正樹の物語は、今、時代に求められている。
「相模原事件の容疑者に共感を抱いてしまう人々が一定数いるこの社会に対して、私ができることは、小説を書くことぐらいしかありません。その小説を読んで、心を動かされたと言ってくださる方々が少なからずいる。それはもしかしたら、社会を変える微かな力になっているのかもしれないなと思うんです」
四組の男女が織りなす人生ドラマ。頸髄損傷で寝たきりの妻を介護する夫、障害を隠しながら女子大生とネットで交流する脳性麻痺男性など、いずれの登場人物もセンシティブなテーマを抱える。著者自身の介護体験に加え、日本の障害者運動の歩みも物語の背骨に組み込まれている。
丸山正樹(まるやま・まさき)
1961年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部演劇科卒。広告代理店でアルバイトの後、シナリオライターとして多くの作品を手がける。2011年『デフ・ヴォイス』(文庫化にあたり『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』と改題)で小説家デビュー。本作の続篇に『龍の耳を君に』『慟哭は聴こえない』がある。他の著書に『漂う子』など。
(文・取材/吉田大助 撮影/黒石あみ)
〈「STORY BOX」2021年4月号掲載〉




