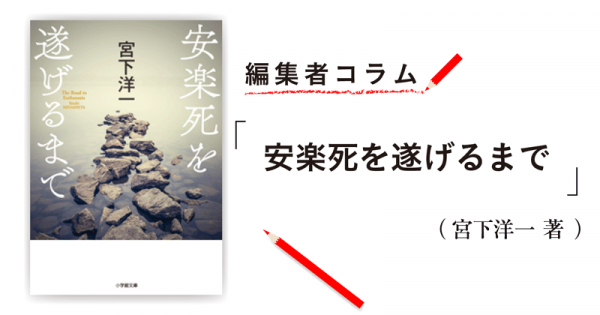◎編集者コラム◎ 『安楽死を遂げるまで』宮下洋一
◎編集者コラム◎
『安楽死を遂げるまで』宮下洋一

この作品の単行本が出たのが2017年、さらに筆者の宮下洋一氏が取材を開始したのは2015年のこと。その後、橋田壽賀子さんが『安楽死で死なせて下さい』を出版したり、実際にスイスで安楽死を遂げる日本人が現れたり(この顛末については著者の続編『安楽死を遂げた日本人』を参照ください)と、この「逝き方」について国民的な関心が高まります。しかし、取材当時は、日本人で安楽死に詳しい専門家はほとんどいませんでした。この本は、類書がほぼなきまま、走り出したのです。
著者はスペインとフランスに拠点を置く日本人ジャーナリストです。安楽死について取材したことはありません。ほぼ頭のなかは白紙でしたが、最初から抱いていた疑問は一つ。本当に安らかで楽な死に方なのか――。それを経験した人間は死を遂げているわけですから、確かめるのは困難です。ただし、そこに近づく方法はありました。死ぬ「瞬間」の患者たちの顔を間近で眺め、その心境を推察することです。
宮下氏は、スイスの安楽死団体に取材申請し、女性代表を説得し、了解を得ます。彼女は、安楽死を啓蒙したいがゆえに宮下氏の取材を許したわけですが、一方で安楽死肯定論を強いることはありません。そのかわり、ありのままをレポートしなさい、と伝えます。そして安楽死の前日に患者を取材し、当日、現場に立ち会い、その後、遺族にインタビューするといった取材工程が何度も繰り返されるのです。
さて、さきほどの女性代表の「ありのままをレポートせよ」との言葉は、私なりの解釈でいえば大いに迷え、ということです。詳しくは本書を読んでいただきたいですが、眼の前の死を止めなくていいのか、これは医療行為なのか、死ぬ間際に患者はなぜ笑顔をみせジョークを吐けるのか…と都度、記していきます。
単行本発表後、安楽死への考えを深め、時に改めていく著者の姿勢について、これだけ取材しているのに安楽死への賛否を明らかにしていない、考えがブレている、などと批判される一幕もありました。しかし、編集者からすると、これほど誠実に対象と向き合っている著者はいません。むしろ、先人なき執筆テーマを迷いなく書ける筆者がいたら、それこそ疑っていたかもしれません。
一部の批判には忸怩たる思いがありましたが、今回、文庫解説にて武田砂鉄さんがこう書いてくださいました。
〈最終的な答えは、賛成・反対の二択かもしれないけれど、そこに至るまでの過程を複数にする。迷う、というのは、迷う道ができた、ということでもある。(略)著者の迷いが、読み手の思考にいくつもの新しい層を与えてくれる〉
胸がスッと軽くなりました。そう、本書を書きながらも筆者は(もちろん編集者も)、たくさん迷いました。読者の皆さま、〈安楽死という迷宮〉にようこそ。
──『安楽死を遂げるまで』担当者より