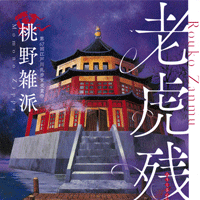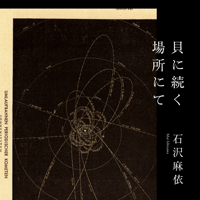今月のイチオシ本【デビュー小説】

今年結成45周年を迎えるTHE ALFEEの高見沢俊彦(64歳)が、初の長編小説『音叉』を上梓した(髙見澤俊彦名義)。
ロンドンブーツのシルエットをあしらった大久保明子デザインのシックなカバーは、キラカード風の特殊なフォイル加工が施され、すばらしく目立つ。もっとも、小説に描かれるのは、そういうキラキラ感に満ちたまぶしい青春ではない。
時は1973年。語り手の"俺"こと風間雅彦は、今春、大学に進学したばかり。高校時代からの仲間4人と組むバンドがメジャー・デビュー目前だが、小説はディレクターのこんな台詞で始まる。
「バンド名を変えてくれ。それがデビューの条件だ」
"俺"は、お約束のように、だったらデビューはやめる! と反発するが、そもそもバンド名の「グッド・スメル」は体臭ケア用スプレーの名前で、雅彦自身も"史上最低なバンド名"と広言している……みたいなズッコケ感を交えつつ、恋と音楽にどっぷりハマった70年代東京の青春が瑞々しく語られる。
実名で登場する原宿のロック喫茶「DJストーン」や渋谷の「エルシド」はじめ、喫茶店が若者の溜まり場で、学園闘争が身近だった時代。『恐竜100万年』のラクエル・ウェルチのポスター、初来日したムーディー・ブルースの武道館公演など、当時の固有名詞が無数にちりばめられ、パソコンも携帯電話もなかった"あの頃"が鮮やかに甦る。
当然、自伝的要素が色濃いものの、著者自身が「あくまでもこれは創作であり、実話でも等身大の自分でもありません」と語るように、小説的な脚色が大胆に加えられ、普遍的に読める。女性キャラの台詞には改善の余地がありそうだが、音楽用語を駆使した描写はさすがの迫力で、デビュー作としては上々の部類。60代以上の読者にとっては懐かしく、若い読者にとっては新鮮な青春小説だ。併録の書き下ろし短編「憂鬱な週末」は、本編では脇役だったディレクター(現在は外資系レコード会社の社長)を主役に、時代を現代に移し、大人の目から見た音楽業界の倦怠と憂鬱をほろ苦く描く。