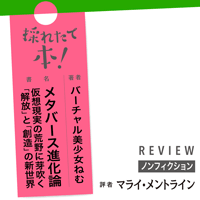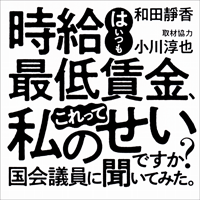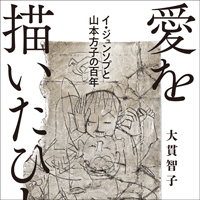今月のイチオシ本【ノンフィクション】

世の中が高齢化社会に向かってまっしぐらに進み、日本人の死因一位ががんだと目の前に突き付けられ、自分が生活習慣病の対象年齢になり、自分より年下の友人を亡くすと、否が応でも生きることと死ぬことを考えるようになってくる。
本書は終末医療に対して、綺麗ごとを一切排除した生身のルポルタージュだ。取材を行った著者は最初から最後まで弱音を吐き続ける。自分の弱さをさらけ出し、死にゆく取材対象に対して毒づくことも少なくない。だからこそ、読み終わった後、どしんと胸に響くのだ。
主人公は訪問看護師の森山文則という。彼が身体の異変に気が付いたのは京都にある渡辺西賀茂診療所に勤務していた二〇一八年の八月、四八歳のときだ。
検査の結果、すい臓がんを原発とする肺転移の疑いで、この時点ですでにステージⅣだった。こうなると手術も放射線も効かず、五年後の相対生存率は一・五%。予後は絶望的だと看護師ならすぐに理解した。
佐々涼子に連絡があったのは、その結果が出たすぐ後。死をテーマにしたノンフィクションを書いていたが、自律神経のバランスを崩し、本を書けなくなっていた時だった。森山を通して取材していた在宅医療の原稿も頓挫していた時に、彼からがんを告白され、実際に患者本人から見た実践看護の本を作りたいと共同執筆を託される。
森山が優秀な訪問看護師なのは誰もが認めるところだ。終末期の患者にとって良かれと思うことを躊躇なく行ってきた。すべてが成功したわけではないが、その時々で最善を尽くしていた。ならば自分の最期はどうするのか。
本書では森山がかつて行った訪問看護の体験と自身の経過が交互に綴られていく。そこに要介護五の佐々の母親の話が挟まれる。人生のゴールテープは目前に迫っている。
森山の最後の日々は佐々が想像していたものと全く違っていた。戸惑いつつ伴走しきった後に何を思ったのか。
この物語を書き上げたことで佐々涼子はまた一つステップアップしたと思う。