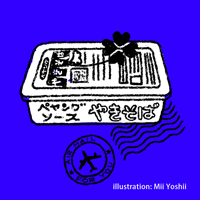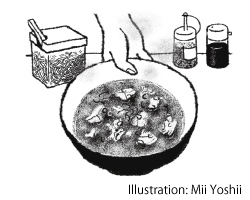思い出の味 ◈ 友井 羊
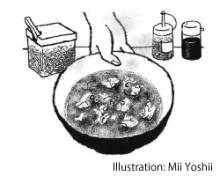
デビュー前に激務の会社で働いていた。終電で帰路につき、自宅最寄り駅に到着したときは大抵深夜一時を過ぎていた。
寒い冬の時期、ふらふらとした状態で家の近くにある某牛丼チェーンに立ち寄った。二十四時間営業の店には煌々と灯りが点いていた。
食券を買って席につく。寒さで芯まで凍え、上着を脱ぐこともできない。他の客は誰もいなくて、店員は一人だけだ。席に座った私は食券を出した後、自然とうつむいていた。心身共に疲れ果てていた。頭に浮かぶのは残りの仕事のことだけだ。期日と仕事量を計算すれば、数日間の徹夜は免れないだろう。
子供の頃からずっと、漫画家になりたかった。しかしそれに挫折した。大学時代から小説という表現方法に興味が移り、少しずつ書き進めるようになった。
小説執筆は漫画よりも手応えがあった。だが入社以降は激務に追われて一行も書けていない。仕事も好きになれず、やりたいこともできず、このまま死んでいくのだろうか。未来を想像するのは恐ろしかったが、仕事への焦りでそう考える余裕すら失われつつあった。
そこでふと、カウンターに豚汁が置かれた。湯気と一緒に味噌の香りが鼻孔に飛び込んでくる。注文していないため、私は思わず顔を上げる。すると店員が心配そうな眼差しを私に向け、牛丼を配膳した。白髪交じりの男性で、年齢は五十歳前後に見えた。店員は「サービスです」と苦笑いを浮かべてから厨房に戻った。
私はきっと酷い顔をしていたに違いない。豚汁をすすると野菜の味と豚肉の旨味、味噌の麹の香りと出汁の風味が感じられた。味自体はいつも通りのチェーン店の豚汁だが、これ以上身体が芯から温まったことはない。
店員がマニュアル違反をしてまで出してくれた豚汁は、間違いなくあの瞬間の私の心を救ってくれた。名も知らぬ店員が今、幸せであることを心から願う。