『口福のレシピ』文庫化記念 特別対談 ◆ 飛田和緒 × 原田ひ香

あの日から、25年!
小説のなかで匂いや湯気、温度感や歯触りまで感じさせるほど料理を美味しく描くことで、定評のある原田ひ香さん。『口福のレシピ』は料理学校を舞台に、さまざまなレシピが登場します。その原点は、20代の頃に料理研究家・飛田和緒さんの料理教室に通ったことだといいます。文庫化にあたり、お二人の対談が実現しました!
食を書く時は、食卓の端からすべて丁寧に描写していく
原田
私が飛田先生のお料理教室に通っていたのは二十代後半のことです。だからもう二十五年くらい前になるんですね。
飛田
料理教室には多くの方がいらっしゃいましたが、忘れられない生徒さんのひとりでした。まだ原田さんもお若くて、料理だけでなく生活全般に興味をお持ちで、たくさん質問されていましたね。
原田
飛田先生のことは、最初の著書『チャッピーの台所?お料理絵日記』の頃からずっと存じ上げていたんです。それでたまたま見た雑誌に「自宅で料理教室を始めました」と書いてあって。まだ携帯もない時代だったから、仕事の休み時間に編集部に電話をかけて、「連絡先を教えてもらえますか」と聞きました。そうしたら、先生から直接お電話をいただいて。先生のご自宅の調度品や食器がすごく素敵だったので、「どこで買ったんですか」と尋ねて、お教室の帰りに車で送ってくださったついでに、先生とお揃いの食器を手に入れたこともありました。
飛田
懐かしいですね。
原田
私、夫の仕事の関係で海外もふくめて引っ越しを何度もしましたが、お教室の日時のやり取りやレシピをファイリングして取ってあるんです。今日はそれを持ってきました。当時は連絡がファックスや手紙で、「何日にいらしてください」とお知らせが来ていたんですよね。
飛田
原田さんは熱心なのに加えて、本当に食べることが好きよね。いつも私が生徒さんに言うのは、作ることをがんばらないで、ということなんです。何より大事なのは、自分が食べたいものを作ること。そうやって自分のなかで納得してキッチンに立てばいいのよ、料理を義務だと思わないで、とはいつも話していましたね。
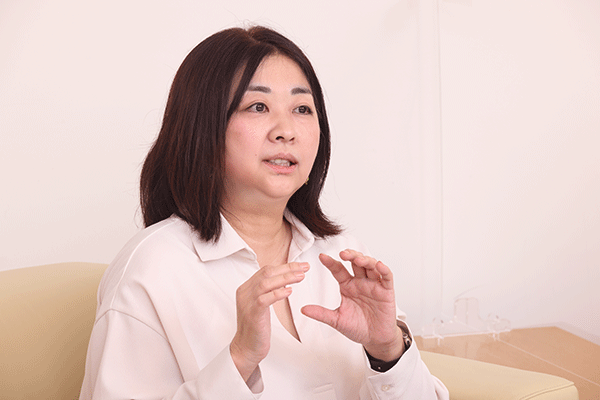
原田
今はレシピを見なくてもできるくらい、先生のお料理はもう何度も作っています。このファイルに入れてある紙にもメモしていますが、先生がおっしゃったことで印象的だったのは、「外食でおいしいものがたくさんあるので、家では素材重視、野菜中心の料理を作りましょう」ということ。それがすごく生活に即したいい考え方だなと思ったのを覚えています。
飛田
原田さんはドラマのシナリオライターから作家になられましたけれど、当時は、まだ会社勤めをしていらっしゃいましたよね。
原田
はい。秘書室に勤めていたんです。契約社員のような雇用形態だったから、三十歳を過ぎたら働けなくなるかもしれない、何か別のことをしなければと、いろんな習い事をやってたんです。アンティークの勉強をしたりとか。お料理もそのひとつという感じで。
飛田
料理を仕事にしたいと思っていたんですか。
原田
料理が好きだったので、淡い期待はありました。でも先生のところに行って、才能のある方というのは違うんだということが、まざまざとわかったんです。レシピを見て上手に作れるだけではダメで、新しい料理を考案したり、アレンジができなければいけないんだ、と。
飛田
当時はお料理教室をまだ始めたばかりだったから、失敗もたくさんありましたけれどね。クリスマス用のチキンレッグをプラムやベーコンなどと一緒に赤ワインで煮込む料理を作るときに、教室の時間内に煮詰まらなくて、「あとは家でやってください」と言ったこともありました(笑)。
原田
私がとにかく強烈に印象に残っているのは、塩むすびなんです。お料理教室の最後に、残ったご飯で塩むすびを作って、持たせてくださったんですよ。それで私が家に帰って疲れて寝ていたら、家族がそれを食べていて。もう慌てて取り返したんです。そうしたら、「ひ香ちゃん、これなに? すごくおいしいんだけど」と。冷えた塩むすびなのに、それほど食に興味のない家族ですら「なにかが違う」とわかるというのがすごい衝撃で。才能のある方がお米も塩も吟味されて、精米の仕方や炊き方、握り方も完璧に作った塩むすびはこんなに違うんだと感じました。プロになる才能というものを近くでまざまざと見ることができた、というか。それは今回の小説にも生かしています。昭和初期に生きるしずえは女中奉公に出ていますが、料理の才能がある女性として描いていますから。
飛田
そんなに誉めていただいて、お恥ずかしいです。今回は、まるでレシピ集のような小説ですね。次から次へとお料理が出てきて、私も「なるほど」と思うことがたくさんありました。まず、冒頭の「白芹」から気持ちをわっと掴まれました。もちろん、レシピを読めばどんな料理かはわかるんですけれど、「白芹ってなんだったかしら」と、思わず引き込まれてしまって。それに加えてさまざまな人間ドラマがあって、「どうなるの?」「どうするの?」と、もう夢中で読みました。
原田
私自身、そんなにレシピを考えられるわけではないので、小説のなかのレシピは、近所の和食屋さんで食べた一品を取り入れたり、留希子のような世代の人たちがどんなものを食べるかを調べたり。当初は毎月の連載だったので、その時期の旬の食材を取り入れましたが、毎回綱渡りでしたね。
飛田
レシピ作りの難しさは、よくわかります。私の場合は、自分がわかっていることをどう伝えるかに苦心します。あまり説明しすぎて長いレシピになると、どなたも読んでくださらないし、なるべく短いプロセスで、その行間に隠れたポイントがあると伝えていくようなイメージです。原田さんはこの小説で皆さんご存じの家庭的なレシピに一工夫してしっかり書いていらして、読みながらもうずっとお腹が空きっぱなしでした。
原田
料理を作るのも好きですけれど、やっぱり食べることが何より好きなんですね。そういう私の意識が、小説のなかにも滲み出ているかもしれません。
飛田
本当に、食いしん坊よね(笑)。
原田
はい(笑)。私が初めて本格的に食を書いたのは『ランチ酒』という小説なんですが、最初はどういうふうに食べるものを表現したらいいか、という迷いがすごくあったんです。食を書かせたら、うまい小説家の方というのはたくさんいらっしゃいますしね。それである時から、迷ったら目の前にある食卓を端から丁寧に描いていくようにしたんです。お刺身とお酒とお醤油があったら、まずお醤油はどんな色をしているか、どんな器に入っているかというのを丁寧に端から書いていく。そうするようになってから、有難いことに食の表現を誉めていただくことが多くなりました。
飛田
今回の物語の鍵になるのは家庭料理の豚の生姜焼きですが、それを取り上げたのもすごく納得でした。誰もが好きだし、誰もが食べたいと思う一皿なので。
原田
特にこだわったわけではなく、じつは別の料理でもよかったんです。ただ私は以前からタレにリンゴのすりおろしを使う豚の生姜焼きが好きだったから、それを生かそうと思ったのと、豚の生姜焼きを検索してみると、あまり起源がはっきりしていなかったんですね。それも決め手になりました。「このお店が発祥」とはっきりしている料理だと、少し描きづらいなというのもありましたから。
女性たちの暮らしぶりにリアリティを添える食べ物
飛田
女性の暮らしぶりに、すごくリアリティがあるなとも感じました。冒頭で留希子がスーパーへ買い出しに行くところもそうですね。

原田
私もスーパーが大好きなんです。留希子と同じように、大根とブリをカゴに入れている人がいると「ああ、今日はブリ大根か。でもあのネギはどうするのかな。味噌汁かな」とか考えてしまう(笑)。そうやって人のことをジロジロ見て、観察しているんですね。買い物が苦痛で、時間の無駄だと言う人もいますが、私はもし可能なら、何時間でもスーパーにいたいタイプなんですけれど。海外に住んでいた時も、棚の端から端まで見るのが本当に楽しくて。だから買い物とか料理への興味というのは、人それぞれで全然違うんですね。
飛田
私も買い物は大好きです。今は神奈川県の三浦半島に住んでいますが、近くに農家の方がたくさんいらっしゃるので直売所を巡ったり、魚屋さんを巡ったり。とにかく、いろんなところを巡る。都内にいる時は食材を作る方に会うこともなかったけれど、たとえば野菜を育てている農家さんにどんなふうに食べているかを聞くのも面白くて。ただ季節の旬のものしかないので、その意味では不便ではありますけれど。
原田
私は三十代の頃、夫の仕事の関係で北海道の十勝に住んでいたんです。何を食べても美味しいし、本当に食が豊かで。じゃがいもが道端にごろごろ転がっているので、地元の人に「あれは持って行っていいの?」と聞いたら、「そんな人はいない」と言われました(笑)。でも翌日、家の前にじゃがいもがたくさん置いてあって。その人が「拾うもんじゃない」と持ってきてくださったんです。
飛田
留希子が風花と一緒に住むようになってから、お酒に合うおつまみを作ったりと料理が変わりますよね。自分のレシピを崩すというのは意外と難しいんですが、誰かと暮らし始めるといった生活の変化によって料理もまた自然と変わっていく。この小説にはその部分も描かれていて、「そうそう」と思いながら読み進めました。それから、いつもは料理を担当している留希子が、疲れ果てて「ご飯を作る気がしない」と言うと、風花が作ってくれる。あれもいいですね。
原田
うちの夫は一人暮らしが長かったので、「何もできない」とは言うものの少しくらいは作れるだろうと思っていましたけれど、本当にまったく作れなくて驚きました。だから、私が料理をできない時は外食なんです。
飛田
私の夫は好きで時々、作ってくれます。娘も特に料理を教えたわけではないけれど、日頃から私の作ったものを食べているから、もちろん少しポイントなどのアドバイスはしますけれど、「作って」と言うとできますね。やはり大事なのは、食べることなんですね。食べるのが料理上手への近道です。私もどちらかというと、作るより食べるほうが好き。もし自分好みの味で、今食べたいものをイメージどおりに作ってくれる人が傍にいたら、自分ではお料理しないかも、と思ったりします。
令和らしい男女の役割を意識する
飛田
留希子はがむしゃらに料理研究家として自分の道を進んでいきますね。年齢こそ留希子のほうが若いですが、私の駆け出しの頃を見ていたのかなと思うくらい、もうそっくりでした。
原田
私が先生のお料理教室に行き始めた頃は、数人だけ通っているのどかな感じでしたけれど、それからどんどん生徒が増えて、先生がお忙しくなって。才能のある人が売れていく、メジャーになっていく過程というのはこういう感じなんだなと思ったのをよく覚えています。それは今回の留希子にも生きていますね。
飛田
料理研究家というのは女性が多いんです。それに比べて板前やシェフというのは男性社会ですよね。近年は変わってきたけれど、家庭料理は女性の領分という雰囲気が、以前はあったと思います。最初の頃の料理研究家というのはご主人の出張で海外に赴任して、そこで覚えた西洋料理などを日本で再現するというようなところから始まった。そうやって家庭に収まるだけでなく、外へ飛び出して行きたいと願う女性たちによって、料理研究家という職業が少しずつ認知されていったように思います。私は特に「男性」「女性」という考えではなくて、ただ食が好きだから、それを皆さんに伝えられれば、という思いでやってきました。
原田
この小説のなかでは、昭和初期の料理学校は男性である「旦那様」が経営に携わり、女性であるしずえがレシピを考えて、旦那様を支える形です。でも令和の時代になると、坂崎という男性が女性である留希子の才能を支えます。そのラストだけは少しジェンダーを意識しました。しかも男性が決して気負うことなく、どちらが上とか下ではなく、自然に「僕に支えさせてください」と言うような終わり方にしたいというのはありましたね。
飛田
レシピの変遷も、ここではひとつのテーマになっていますね。
原田
豚の生姜焼きのレシピが、すりおろしリンゴからリンゴジュースに変わります。リンゴをすりおろすというのは昔の人から見ると面倒ではなくても、忙しい現代では「いちいちすりおろしていられるか」というのが本音だと思います。調理器具や圧力鍋なども良質で便利なものがどんどん出てきていますし、変わっていくのが当然ですよね。
飛田
私もレシピは時代とともに変わっていいものだと思っています。たとえばお米でも、昔はしっかりお水で研ぐようにと言われていました。そうしないと、糠臭かったんですね。でも今は精米機がすごく進化しているし、美味しいお米の種類も出てきているので、研ぎすぎるとお米の味が抜けてしまう。だから軽く研げばいい、と。鶏肉だって、生姜やネギを入れて一度茹でるというレシピは、昔のお肉には臭みがあったからで、今は必要ないんですね。もちろん昔ながらのお漬物の味など、時代を超えて大事にしたいものもあります。だから、両方あっていいんですね。
原田
レシピには著作権がないというのもよく言われることで、私にはネット上で料理を発表する人たちの間で「料理法がかぶってるな」と感じることが時々あります。料理研究家の方はみなさん何もおっしゃらないけれど、多少心のなかでもやもやするところもあるんじゃないかという想像もあって、あのシーンを加えました。もちろん最後に少し物語を盛り上げるという意図もありますが。
飛田
著作権に関しては私は、全然気にしていないんです。「これは私のものです」と大きな声で言うものでもないかなと。私は最終的に、多くの人が美味しいものを食べられることが、何より大事だと思っています。
原田
今日はありがとうございました。久しぶりにお会いできてうれしかったです。先生は、初めてお会いした頃から暮らしぶりも含めて本当に素敵でした。素敵な方はずっと素敵なんだと、改めてそう感じることができました。

飛田和緒(ひだ・かずを)
1964年東京都生まれ。短大卒業後、会社員、主婦を経て30代半ばから料理家として本格的に活動を始める。2014年『常備菜』が料理レシピ本大賞を受賞し、ベストセラーに。雑誌や書籍を中心に、幅広いジャンルの家庭料理を提案。著書に『海辺暮らし 季節のごはんとおかず』『おとなになってはみたけれど』『仕込んで、使って、一年中楽しめる みその本』『料理家・飛田和緒』など多数。
原田ひ香(はらだ・ひか)
1970年神奈川県生まれ。2005年「リトルプリンセス二号」がNHK主催の創作ラジオドラマ脚本懸賞公募最優秀賞に選ばれ、07年「はじまらないティータイム」ですばる文学賞を受賞。著書に『東京ロンダリング』『母親ウエスタン』『三人屋』『ランチ酒』『三千円の使いかた』『まずはこれ食べて』『一橋桐子(76)の犯罪日記』『古本食堂』『財布は踊る』『老人ホテル』など。
(構成/鳥海美奈子 写真/浅野 剛)
〈『口福のレシピ』(小学館文庫)収録〉





