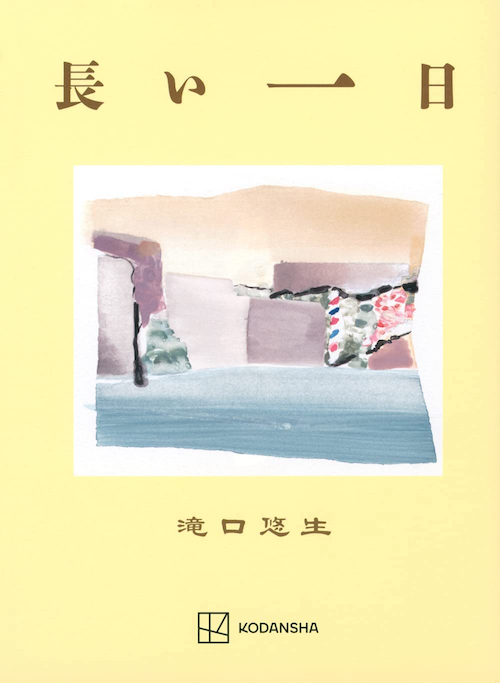週末は書店へ行こう! 目利き書店員のブックガイド vol.8 三省堂書店成城店 大塚真祐子さん

小説とは、そこに書かれた言葉とは、現在だろうか過去だろうか。読むという行為においては現在だが、言葉を主体にしたとき、書くという行為はつねに過去にある。作者を主体にすれば、書くことは現在かもしれないが、頁がひらかれなければ、書かれた言葉は無にひとしく、ひらかれるのかひらかれないのか、存在するのかしないのか、わからない未来のために数多の言葉が息をひそめる。
小説家の夫と妻が転居を決めてから引っ越すまで、というのが本作の時間軸の中心となるが、〈なにかについて話そうとすると、それ以外のことがたくさんついてきて、話がどんどん長くなってしまう〉と作中で夫が語るように、転居までの営みのなかで、契機となるような出来事、そこに付随する記憶、夫妻をとりまく人びとのいる景色、彼らの思念などが一様に交錯し、物語を流れる時間が入れ子のように重なりあう。
エッセイとして連載を開始したはずの本作が、いつの間にか長編小説となって上梓されたことを、狐につままれたように感じていたが、〈注ぎ込んだら注ぎ込んだ中身によって、自在に形を変えるようなものだと思うから〉と、小説という装置について夫が考えるように、なぜ小説なのかを思索したとき、言葉というものがそもそも、重層的な時間を内包していると気がついた。読むわたしは現在だが、言葉はわたしより過去にある。これは「思い出す」という行為によく似ている。
〈何かを思い出せば言葉になり、その先には誰とはっきりしなくとも、誰かが宛て先らしく立つ。どんな楽しいことでも、思い出すという行為のなかには、必ず少しの寂しさがあって、当たり前だが寂しさは過去形のなかにしかないし、誰かに向ける言葉も過去形のなかにしかないが、過去がなければ幸せだと感じることもたぶんなく、寂しさも幸せも思い出す愛着の影〉
序盤のこの一節から折り返すように、本作は小説としての語りを深めていく。小説という容れ物が自在であるように、思い出すという行為もまた自在なのではないか、現実には起こらなかったことを思い出してもいいし、過去だけでなく未来のことを思い出してもいい。そう考えたとき、著者の言葉は小説という可能性をえらびとり、いまわたしがそれを読んでいる。ああ今朝は子どもが学校から持ち帰った、マリーゴールドの鉢植えに水をやるのを忘れたなとか、前を行くツーブロックの少年は、やたらと襟足に触れるなとか、そんな日常の延長線上で、『長い一日』という作品がまるで自分の記憶のように入りこんでくるのを、自然と受け入れている。
あわせて読みたい本
『長い一日』が伸縮する時間を書いたものなら、『三の隣は五号室』は時間を超え結びあう空間を書く。両作家とも作中で「愛着」を語るが、愛着そのものを語る滝口さんと、愛着の対象を子細に語る長嶋さんで、作品が全く違うことに驚く。
(2021年9月10日)