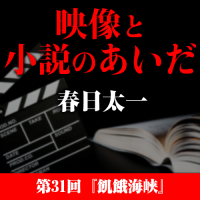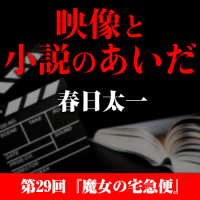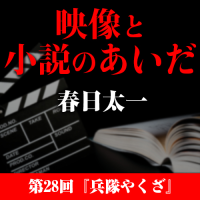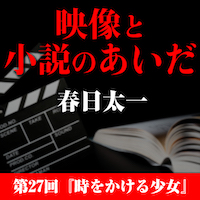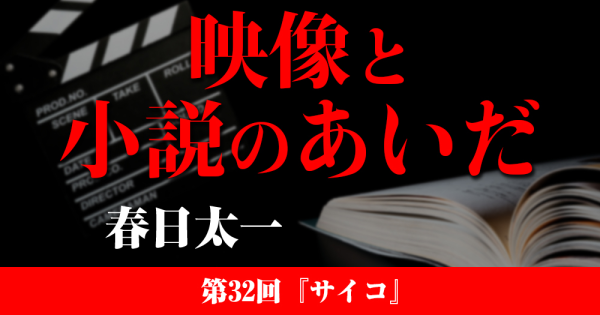連載第32回 「映像と小説のあいだ」 春日太一
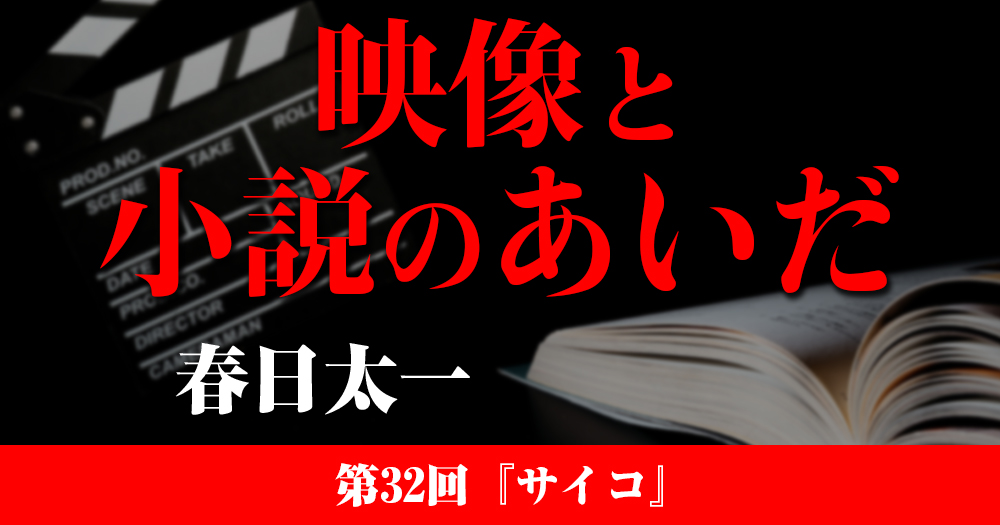
小説を原作にした映画やテレビドラマが成功した場合、「原作/原作者の力」として語られることが多い。
もちろん、原作がゼロから作品世界を生み出したのだから、その力が大きいことには違いない。
ただ一方で、映画やテレビドラマを先に観てから原作を読んだ際に気づくことがある。劇中で大きなインパクトを与えたセリフ、物語展開、登場人物が原作には描かれていない──!
それらは実は、原作から脚色する際に脚本家たちが創作したものだった。
本連載では、そうした見落とされがちな「脚色における創作」に着目しながら、作品の魅力を掘り下げていく。
『サイコ』
(1960年/原作:ロバート・ブロック/脚色:ジョセフ・ステファノ/監督:アルフレッド・ヒッチコック/制作:シャムリー・プロダクションズ)
「〝I was born in mine. I don’t mind any more.〟(吹き替え版訳:僕は生まれつき、どうにもならないんだ )」
ロバート・ブロックの同名小説をアルフレッド・ヒッチコック監督が映画化した『サイコ』は、物語展開や人物設定だけでなくディテールのかなりの部分に至るまで、原作に準拠したものになっている。まずは、ラストまで一気に物語を述べたい。もちろん、思いきりネタバレしているので、気になる方はここで引き返していただきたい。
借金に苦しむ恋人のサム(ジョン・ギャヴィン)と結婚するため、不動産会社に勤めるマリオン(ジャネット・リー)は銀行に預けるはずだった顧客の金・4万ドルを持ち逃げしてしまう。サムの元へ車を走らせたマリオンだったが、夜になり、外は大雨。彼女はモーテルに宿泊することにした。旧道にひっそりと建つそのモーテルは閑散としており、ノーマン・ベイツ(アンソニー・パーキンス)という青年が一人で切り盛りしている。ノーマンは老いた母と二人で暮らしているらしい。そして、ノーマンと食事を済ませて自室でシャワーを浴びているところをマリオンは謎の老婆に襲われ、ナイフでめった刺しにされて命を失う。翌朝、マリオンの死体を発見したノーマンは母親の仕業と確信し、彼女の死体を裏手の沼に捨てた。
マリオンの妹・ライラ(ヴェラ・マイルズ)とサム、そして不動産会社に雇われた探偵(マーティン・バルサム)はマリオンの行方を追い、探偵はノーマンのモーテルにたどり着く。だが、探偵も老女に殺されてしまった。ライラとサムは保安官に相談するも、ノーマンの母親は既に死んでいるとし、とりあってくれない。二人はモーテルに乗り込む。ライラがミイラ化した母親を発見したとき、女装したノーマンが襲いかかってくる。間一髪、サムが助けに入り、ノーマンは逮捕される。
明らかになったのは、ノーマンが二重人格だったということだ。ノーマンはかつて、母親を愛人もろとも心中に見せかけて殺害していた。その後で母親の人格が彼の中に宿るようになり、その人格が彼に近づく女性たちを殺害していたのだった――。
原作も映画も「老女による殺人」の場面を二度とも克明に描写している。つまり、受け手も犯行を目撃しているということだ。そこでキモとなるのは、その老女の正体をノーマンの母親だと思い込ませることである。「実は老女の正体はノーマンだった」とわかる終盤で驚かせることが、本作の作劇の上での最重要ポイントであり、ノーマンに対して受け手の疑いの目を向けさせることなく「犯人は母親である」と終盤までミスリードし続けなければならない。
それを成し遂げる上で、一見すると原作とほとんど同じような内容に思わせつつ、映画には細かい脚色が施されている。
まずは、ノーマンの描写だ。原作はノーマンの心情を詳細に追っている。その中には、母親が沼にいることをうかがわせるのを始め、心の中で母親が語り掛けてくるセリフ、さらに探偵殺害の場面では現場に居合わせているのになぜか声が出ない――など、「もしかしたらノーマンが犯人なのではないか」と思わせる記述は少なくない。だが、映画はそうした描写は徹底してカットしているのである。
また、こうした描写の他にも原作はノーマンの狂気をうかがわせる描写が冒頭から頻発している。特に印象的なのは女性に対するコンプレックスで、これまで女性から嘲笑されてきた反動として原作のノーマンは全ての女性を心の中で「雌犬」呼ばわりしている。それに対して映画はそうした心情描写を全てカットしており、「支配的な母親に苦しめられる、哀れな内向的青年」としてのみ印象付けさせることを徹底しているのだ。ノーマンは母親の狂気に振り回されるだけであり、彼が犯人だとは微塵も感じさせない人物像に仕上げられていた。
その印象付けをする上で、実はマリオン(原作ではメアリ)の人物設定も少しだけ変化させている。恋人のサムが金銭面で苦しんでいるのは変わらないのだが、原作は父親の遺した借金の返済が問題なのに対し、映画ではそれに加えて元妻への養育費の支払いもしなければならない。原作のサムはメアリと婚約しており二年で借金を返済できると誓っているものの、二年後には29歳になることを焦ったためにメアリは犯行に及ぶ。一方、映画の二人は婚約していない。サムが出張の度に、昼休みの合間をぬって人目を忍んで情事をするしかなく、マリオンが結婚を迫ってもはぐらかされる。つまり、映画のマリオンの方がより哀れな立場にいるということだ。
これが、ノーマンの印象付けに効いてくる。マリオンが泊った夜、ノーマンは彼女に食事をふるまう。その際にノーマンの境遇を聞いたことでマリオンは心を入れ替え、来た道を引き返す決意をする。この展開は原作も映画も変わらない。
ただ、そこに至る彼女の心情は大きく異なる。原作のメアリはノーマンを見下しており、「自分はまだマシだ」と思い至って心の安息を得たことで金を返そうという気になる。
一方、映画はそうではない。以下は原作にない、映画オリジナルのやり取りだ。
ノーマンはマリオンに尋ねる。
〝You’re never had an empty moment in your entire life have you?〟
(吹き替え訳:君は人生を空しく感じることはない?)
それに対して、彼女は「自分なりに」と答えている。作品冒頭で描かれたサムとの情事は、まさに彼女にとって「empty moment」以外のなにものでもない。つまり、ノーマンとマリオンは空しさを抱えた者同士として、今ここに向き合っているのである。そしてノーマンは、禁欲的な母親の支配下に置かれてどうにもならないこと、逃げ出すことも悪態をつくこともできないことを吐露する。その流れでノーマンが語ったのが冒頭のセリフだ。
こうした諦観を他人に語れるということは、映画のノーマンには自分の人生を冷静に見つめる目がまだあるということでもある。これは、原作にはない一面だ。そして、絶望の沼から抜け出せずにいるノーマンの苦悶を目にしたことで、マリオンは自分はまだ引き返せると気づき、改心するのである。
こうして、原作と異なり、この食事シーンでは二人の心に温かい繋がりのようなものが垣間見られる。マリオンが浴室で惨殺されるのは、この直後のことだ。となると、ノーマンが犯人であるとは、観客はよもや思うまい。しかも、殺害場面で老婆の影は映っているし、食事の場面の前には家に彼女を招くことを猛反対する母親の声をマリオンが聞いている描写も、映画は新たに加えた。衝撃の真相を隠すための、実に巧妙なミスリードを施しているのである。
【執筆者プロフィール】
春日太一(かすが・たいち)
1977年東京都生まれ。時代劇・映画史研究家。日本大学大学院博士後期課程修了。著書に『天才 勝進太郎』(文春新書)、『時代劇は死なず! 完全版 京都太秦の「職人」たち』(河出文庫)、『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』(文春文庫)、『役者は一日にしてならず』『すべての道は役者に通ず』(小学館)、『時代劇入門』(角川新書)、『日本の戦争映画』(文春新書)、『時代劇聖地巡礼 関西ディープ編』(ミシマ社)ほか。最新刊として『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』(文藝春秋)がある。この作品で第55回大宅壮一ノンフィクション大賞(2024年)を受賞。