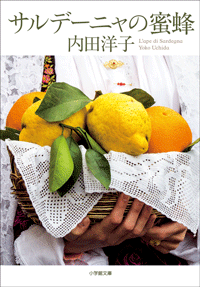週末は書店へ行こう! 目利き書店員のブックガイド vol.127 梅田 蔦屋書店 河出真美さん
- 書店員さん おすすめ本コラム
- エリザベス・ストラウト
- オリーヴ・キタリッジの生活
- オリンピア
- サルデーニャの蜜蜂
- デニス・ボック
- 内田洋子
- 小学館文庫
- 小川高義
- 書店員コラム
- 河出真美
- 目利き書店員のブックガイド
- 越前敏弥

生きている、ということは、時に、とても悲しい。
その悲しみは、近しい人を失う悲しみかもしれない。以前はなかよく暮らしていた家族が、散り散りになってしまう悲しみかもしれない。戦争の記憶を抱え続けなければならないことの悲しみかもしれない。
本書には七つの短編が収められているが、その最初の話、それも最初の一行からして、悲しみのにおいがする。それも、一晩泣いて忘れられるような悲しみではない。生きているということそれ自体とどこかで結びついてしまっているかのような悲しみだ。その悲しみの気配のようなものは、この静かな小説にひっそりと漂い続ける。
語り手のピーター、妹のルビーとその両親からなる家族を中心に据えた本書は、まず家族から一歩外側にいる人々を描き出す。二度目の結婚式をあげることにした祖父母、プールの修復を延々と続ける異国からやってきたおじ、戦争で負ったダメージを抱えて生きる祖父の兄。それぞれの物語に漂うどうしようもない悲しみは、しかし、語り手ピーター自身の悲しみというよりは、ピーターからすれば少し距離のある誰かの悲しみである。だがピーターも、いつまでも悲しみの傍観者ではいられない。やがて彼自身も深い悲しみに見舞われることになる。
ここで、本書のタイトルに注目したい。オリンピア、という言葉からたいていの人が連想するのは、オリンピックだろう。この小説の背景には、そのとおり、オリンピックがある。ピーターの祖父母と父はオリンピック選手で、妹ルビーもオリンピック出場を期待される。一家は家のテレビでミュンヘン・オリンピックを見る。彼らに何が起ころうと、あたりまえだが、世界は終わらない。四年経てばまた、次のオリンピックが開催される。そうして繰り返されるサイクルは、悲しみに見舞われた人間の目から見れば冷たいものに映りかねない。しかし本書におけるオリンピックは、再生の象徴としての顔をも持つ。四年が経ちさえすれば、それ以前に開かれたどんなオリンピックとも異なる新たなオリンピックがまた開かれるのだ。何度終わりを迎えようと、必ず次のはじまりがやって来る。そのさまはまるで死と生を繰り返しているかのようだ。
オリンピックが死と生を繰り返すように、悲しみに見舞われた人も、やがては新たなはじまりを迎えることができる。それは抱えていた悲しみを手放したその時にやってくるのだろう。失ってしまった大事なあの人に別れを告げるのは決して悲しいことではないと、この本の最後に置かれた短編は、そう語っている。
あわせて読みたい本
連作短編集、という言葉を聞くとわくわくする。その本に収められた短編がどのように「連なって」いて、「連なって」いることによって一体どんな新しい形を見せてくれるのか、というところにわくわくするのだ。
おすすめしたいのが『オリーヴ・キタリッジの生活』である。頑固で怒りっぽく、あまり人好きのする性格とは言えないオリーヴが、中心に押し出されたり背景に退いたりしながら描かれて、とてもリアルな像を結ぶ。きれいなばかりではいられない人間というもののでこぼこしていたり尖っていたりする部分がくっきりと書かれた一冊だ。
河出真美(かわで・まみ)
本が好き。文章も書く。勤め先では文学担当。なんでも読むが特に海外文学が好き。趣味は映画鑑賞。好きな作家はレイナルド・アレナス、ハン・ガンなど。最近ZINE制作と文フリの楽しさに目覚めました。