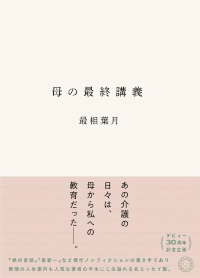週末は書店へ行こう! 目利き書店員のブックガイド vol.135 梅田 蔦屋書店 永山裕美さん

ノンフィクション作家が、その当時、取り組んでいた仕事にまつわることや、コロナ禍での日々、家族のことなどを綴ったエッセイ集。
『絶対音感』『青いバラ』『星新一』『セラピスト』などの著作に見るように、対象に深く心を通わせながらも、距離がきちんと保たれているのは、自分を相手にしても変わらない。
ただ、ノンフィクションでは常に黒子となっていた最相葉月という一人の人間が、エッセイではくっきりとした輪郭をもって感じられ、彼女が心をかたむけて書いたノンフィクションも改めて、読み返してみたくなる。デビュー30周年記念企画にふさわしい、幅広い仕事と厚みのある人生を思わせるエッセイ集だ。
47本のエッセイが集められた本書の白眉はやはりタイトルにもなった、著者が20代の時から、約30年に及んだという母親の介護について書かれたエッセイだろう。
若年性認知症のため、「母に育てられた年数よりも母を介護してきた年数が上回った」こと、「二十六年、自分の足で外出できず、友だちもおらず、買いたいものを買えず、食べたいものを食べられず、読みたい本を読めず、人の世話になるばかりの時間が続くと想像するだけでぞっとする。だが母はそのぞっとする時間を生きてきた」こと。
そんな生き方を強いられた時、人はどうなるのか。間近で見続けた著者はそれを「母の最終講義」だという。介護として向き合うよりも、「最終講義」としてそれを受けとめよう、となるまでに、どれほどの時間が必要だったのだろう。
また、別のエッセイでは、がんで闘病していた父が「不自由で長すぎる余命を生きることに疲れていく」様子がありありと描写される。
「がんの手術で舌と咽頭を切除し(中略)声と嗅覚と味覚を失い、食事は流動食、首に開けた永久気管孔で呼吸をする」 ──それはあまりにも壮絶で、言葉を失ってしまうほどだ。
そんな両親を看取った著者には、ここに書かれなかった、様々な思いがあったに違いない。その抑制された筆の運びから、多くのことが逆に浮かびあがるようだ。決して、感情のままに綴られない文章には著者の矜持を感じるし、またそれに対して、深い信頼が、読者として、自分のなかにあるのがわかる。
「ゲリラサイン会」というエッセイはとても嬉しく読んだ。著者が、出版社に任せきりではいけない、と思い、本を手売りするところに、書店員として、深く励まされた。今は著者も出版社も書店も、同じくらい力を込めて、同時に発信しないと本が売れない時代だと思う。本離れと言われる現状に、「本から近づいていくだけだ」というその潔さに、確かにそうだと、思わず笑ってしまった。
本書では、必ずしも良いことばかり書かれているわけではない。割り切ることの難しい、2匹いた飼い猫への愛情の優劣、その葛藤についての思いは、こういうことも語られるのだ、という驚きがあった。
今では言及されることの少なくなった、スポーツ選手としての橋本聖子の横顔も、あざやかで印象深い。
ページを捲っていくと、この本の為に出版社が作った「わたしと最相葉月さんの本」というペーパーが挟まれている。それは、ノンフィクション、エッセイ、対談、人生案内といった仕事をこなす著者の多面的な魅力と、その作品へのリスペクトに溢れているが、それだけではない。一冊の本を共に作り上げようとする、出版社で働く人々の情熱が感じられ、手に取った人を嬉しい気持ちにさせる。そうやって、人を巻き込んで、一冊一冊を世に送り出してきた、それこそが最相葉月の力なのかもしれない。
あわせて読みたい本
ページ数としては僅かだが、こちらも父との別れが書かれたエッセイ集。
家族のことを書くのは珍しい著者が、真正面から後悔や迷いといった気持ちの揺らぎ、怒りを表していて、心を揺さぶられる。ただ、それは全体のごく一部で、基本的には、山小屋を巡る自然について、言及したものが多く、改めて、自然と人間の在り方を考えさせてくれる。自分の身体のなかにある言葉を見つめながら、ゆっくり手探りで取り出していくような、内省的な文章は祈りのようでもある。自分の心を鎮めてくれる、心がざわついた時に手に取りたい一冊。
おすすめの小学館文庫
平易な言葉で書かれてある、ごく普通の人のエッセイ集だが、東北で詩や小説を書き続けてきたという著者のまっすぐな視線が忘れがたい印象を残す。
特に心に残るのが、義母や祖母について書かれたものだ。義母の産婆としての仕事や、義母が夢中になって仕立てた羽織のこと、そして、義母の介護について、どこか陰影のある事柄も、共感をもって、柔らかく懐深く描かれる。また、生前には祖母と知らなかった間柄の、祖母との思い出もしみじみとした趣きがある。血縁のある女性をきちんと一人の女性として扱い、自分も含めた、名もなき過去の女たちについて語る、その口調は血が通っていて、しみじみと温かい。
永山裕美(ながやま・ひろみ)
大体、何でも読みます。本当は残りの人生、本だけ読んでいたいと思う今日この頃。