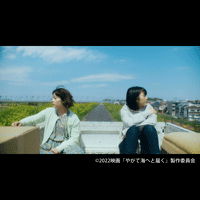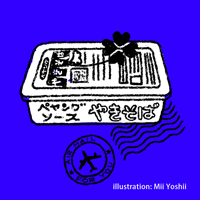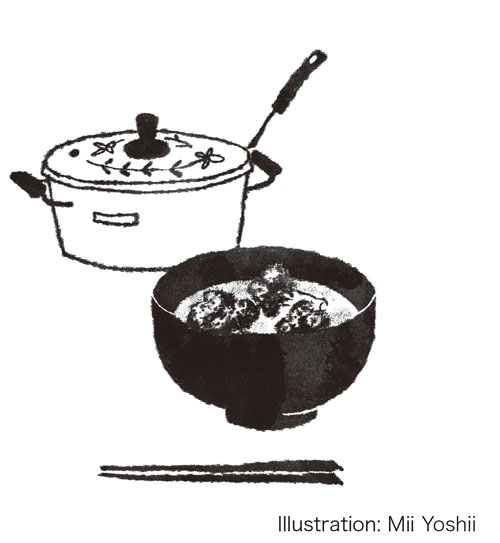思い出の味 ◈ 彩瀬まる

理不尽だなあ、と思うことがある。
私は今、三歳の子供を育てている。今のところ概ね子育ては楽しい。
楽しいのだけどストレスはある。うちの場合は食事だ。
硬すぎず、噛みちぎりやすく、味がはっきりしていて、ほどよく油分があって、酸味も辛みもない、いわゆる子供向けの食べ物を作ることに飽きた。
超飽きた!
ああ、辛い麻婆豆腐が食べたい。麺つゆで煮た茄子に生姜をきかせ、そこに素麺をぶち込んだ茄子素麺が食べたい。一人ならもっと適当に、好きなものだけ作れるのに。
母の味というのは基本的に「母が自分の嗜好よりも、家族にとっての最大公約数的な味を優先して作り続けた味」だ。我慢と譲歩と気づかいの味だ。だってそうしないと残されるし。
理不尽なのはここからだ。私は十六歳の時に母親をがんで亡くした。
そして現在、母の料理の記憶をきれいさっぱりなくしている。
なんにも覚えていない。覚えているのは一度「ブロッコリーの入った味噌汁」が出て、こりゃねえよ母ちゃんと思ったことだけだ。病が進行し、日々の買い物も億劫だったのだろう。当時の私はそんなことすら気づかなかった。
きっと母は、完璧な「母の味」を続け過ぎたのだ。たった三年で私が超飽きている我慢と譲歩と気づかいの提供を、病がそれを破綻させるまで十六年続けた。でも子供にとってはただの当たり前の食事で、水や空気と同然に流れ去った。親と子供には圧倒的な時間と経験の隔たりがある。伝わらないことは伝わらないのだ。
ただ、料理の内容を覚えていなくても私は割と味覚が確かだ。調理の際に困ったことがないし、好みに合うものを出せば家族は「おいしい」と食べてくれる。それはきっと母が適切な料理を出し続けてくれたからだろう。
とはいえ「母の味」、ぶっちゃけ頑張らなくていいんだろうなと思う。心を込めたって忘れられるかもだし。辛い時には、子供にはスティックパンとコーンスープと三角チーズ、私には茄子素麺を作っていいのだ。
母が本当はなにを食べたかったのか、我慢されるより知りたかったと、今でも思う。