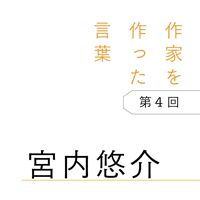宮内悠介さん『黄色い夜』
アラル海周辺を旅した経験からその地域の架空の小国を舞台にした『あとは野となれ大和撫子』を発表するなど、宮内悠介さんにとって旅と創作は密接な関係にある。新作『黄色い夜』は、カジノを一大産業としているアフリカの架空のE国が舞台。その執筆の背景とは。
きっかけは二十代の頃の旅
アフリカのエチオピアに隣接する架空のE国。そこは資源が乏しく、産業はカジノに頼り、砂漠には螺旋状の巨大なカジノ・タワーが建っている。ここにやってきた日本人青年の龍一、通称ルイは、ある目的を持って数々のギャンブルに挑んでいく──『黄色い夜』は中篇ながら、宮内悠介さんのエッセンスがぎゅっと詰まったような一冊である。
もともと各国を旅し、その体験をもとに小説を執筆することも多い宮内さん。
「二〇〇五年くらいに、転職の狭間に一か月できたのでアラビア半島のイエメンから紅海をわたってアフリカ大陸のジブチに行き、エチオピアと旅をしたんです。アルチュール・ランボーの足跡を辿ろうとして、自分もランボーと同じようにイエメンのアデンからアフリカに渡ろうとしたのですが、大きな貨物船ばかりで人を運ぶ船がなくて。結局モカコーヒーで知られるモカから沈みそうな木造の貨物船で渡りました(笑)。対岸のソマリアとエリトリアが内戦中だったので、行き先もジブチを選ぶしかなかった。そうした旅の途中で、たまたまカジノの小説が書きたくなったんです。それで、旅をしながら短篇を書きました」
本作の大本となっているのは、その時の短篇だという。その後一度長篇にして、それを削って今回の中篇にしたという。なぜカジノが舞台かというと、
「もともとゲーム性のあるものが好きで、ギャンブルも小説に書いてみたい気持ちがありました。ただ、ギャンブルものは必然的に、小さな共同体の話が多い。それをどうにか社会レベルに拡大できないかと考えました。いわば、ギャンブルものと社会派の融合です。昔、島田荘司さんが本格ミステリと社会派の融合を唱えていらしたので、その影響ですね(笑)。それで、カジノで成り立っている国家にすれば、カジノの攻略がそのまま国家の乗っ取りになるから面白いのではないかと。あの地域は石油は出そうで出ないし、海沿いとはいえ結構砂漠が多く、カジノを産業とする国としての条件がそろっていることもありました」
小説内の時期は執筆した当時のまま。今回発表するにあたって近年に置き換えなかったのは、
「その後イエメンが内戦時代に入るなど情勢が変わったということと、今だとカジノがかなりハイテク化していると耳にしたことが理由です。今は昔以上に無数の監視カメラがあって、プレイヤーのトランプの札も見られている。ちょっと怪しい賭け方をする人を自動的に判別したりもするらしく、そこまでされるとさすがに攻略は限りなく不可能なので、セキュリティがもう少し甘かった頃にする必要がありました」
カジノ・タワーは上の階になるほどに賭け金が跳ね上がり、最上階では国家を動かすレベルの金額が動く。ルイは国の乗っ取りを企み、イタリア出身の青年、ピアッサらと組んで最上階を目指す。これがまさに、ひとつずつステージをクリアしていくRPGのような面白さ。
ブラック・ジャックやルーレットなどお馴染みのゲームだけでなく、聖書を使ったクイズ形式のものや、水が沸騰する時間を予測する賭けなどさまざまで、どれも実にスリリング。
「ギャンブルものであるからには、バラエティのある賭け事を過剰なまでに放り込んでみたかったんです。駆け引きの様子は学生の頃に好きだった麻雀漫画の影響が出ています(笑)。その頃、異常なまでに集めていたんですよ」
スピード感をもって読めるのは確かだが、なかにはゲームの内容が複雑でじっくり読ませるところも。
「ハッキングコンテストの箇所は自分でも図を描いたりしながら考えました。ゲラ作業の時に、校閲さんが図を描いてめちゃくちゃ考えた形跡が残されていて、申し訳なく思いました。百人中九十九人が理解できないと思いますので、そこは読み飛ばしていただけたら……(笑)」
デビュー短篇集『盤上の夜』でも、将棋や麻雀などのゲームをモチーフにしていたが、
「今回のほうが、ゲーム好きの面が露骨に出ています。最初の短篇を書いてから十年くらいなので、とりあえず原点回帰、というわけではないですけれど、こちらもタイトルに〝夜〟が入っていたりします(笑)」
ギャンブルに身を投じる人々
さて、ルイという青年はどのような人物をイメージしたのだろう。
「半分は、あの地域を旅している自分が投影されていると思います。ルイはもともと個人を助けたいという思いでカジノに来ましたが、それがいつのまにか社会変革という目的にすり替わり、妄執に駆られていく人物です。ルイのように何かに取り憑かれる体験は、人にもよりますけれど青春期にはままあることだと思います」
ルイには日本に恋人がいる。メンタルに不調をきたし病院に通う彼女は、多剤大量処方によって薬漬けとなっている。
「ルイがカジノに挑む動機は、その解決法となるような社会像を持っているからです。これはまあ、相当に頭のおかしいヴィジョンではあるのですが」
多剤大量処方と国の乗っ取りがなぜ繋がるのかは作中でご確認いただきたいが、ここで思い出すのは宮内さんの長篇、『エクソダス症候群』だ。火星を舞台にし、精神疾患史も盛り込まれたこのSF小説について以前インタビューした時、宮内さんは〈後期クイーン問題〉ならぬ〈後期バラード問題〉について語ってくれた。SF作家J・G・バラードの『コカイン・ナイト』では、人々が精神安定剤によって浅い眠りに陥っている状態が描かれる。
「そうです、今回もまさに〈後期バラード問題〉が念頭にあります。J・G・バラードの『コカイン・ナイト』に〈トランキライザーの浅い眠りから目覚めさせるには〉といったような言葉があって、それは今作にも出てきます」

ルイが現地で出会う人もさまざま。相棒となるピアッサがカジノに挑む理由のひとつは、考古学者だった父親がこの地で発掘した類人猿の骨の化石を取り戻すこと。
「ルイが何を考えているか分からないタイプなので、相棒はパーソナリティの安定した人物にしようと考えました。類人猿の骨の化石という設定は、エチオピアでルーシーが発掘されたということから思いついたものです(※1974年にエチオピアでアファール猿人の化石化した骨がルーシーと名付けられた)」
また、ルイが協力を乞うアシュラフという女性はソマリア出身で、ケニア人の夫は内戦によってイエメンに逃れ離れて暮らしている。
「私がイエメンからアフリカに渡ろうと港をさまよっていた時に、知り合った通訳がケニア出身の男性だったんです。妻は国に残しているということで、このあたりは彼の話が反映されています。イエメンでも内戦が始まってしまったので、あの夫婦は今どうしているのだろうと思います」
他にも、母親がピーナッツ売りだった人物や、ツーリスト・マリッジ(裕福な外国人が貧しい村の若い女性と結婚するが、その後妻を捨てて帰国する国際問題)で生まれたという人物も。
「舞台にした地域の周辺は今なお厳しい状況が続いているので、なんらかの切実なバックボーンを抱えた人たちの話が多くなりました。私が旅で見てきたものも多く反映されていて、ピーナッツ売りもどこかを旅した時に子供たちがピーナッツ売りをしていたのが印象的だったのでした。ツーリスト・マリッジについては、当時イエメンで読んだ新聞に書かれていました」
説教師やラスボス的存在など、みな個性豊かで強烈な印象を残す。
「ちょうど旅にドストエフスキーの『白痴』を旅に持っていって読んでいたので、その影響か、やたらと長回しの台詞が多いです(笑)。たぶん、自分が今まで書いた小説の中で、この作品の登場人物がいちばんおしゃべりです」
ルイもピアッサもその他の人間も、別の動機があるにせよ、賭け事をせずにはいられない人間たちだ。「なんのためにギャンブルをするんだい」というルイの問いに、ピアッサは「そりゃ、神に近づくためだろうな」と答える。
「神あるいは神的なものに近づこうとするのは、ギャンブルのひとつの本質だと思います。ギャンブル依存症から抜け出すための会などでは、まず神を自分より上において、その下に自分がいることの再確認から始めると聞いたこともあります。逆に言えば、ギャンブル依存症と神はとても密接な関係にあるわけです。ギャンブルには自分に神を重ね合わせるという、とても不遜だけれどある種、甘美な動機がある。もっと単純に言うなら、サイコロでもなんでも、当たれば単純に自分が予言者になったかのような気持ちを味わえます。今回はカジノの攻略が主軸なので、ギャンブルの魔に取り憑かれた人の話ではないですが、そういう心理もいつかまた書いてみたいところです」
タイトルの〝黄色い夜〟は、砂嵐で視界が黄色くなる現象のことだ。視界を遮るものとして、さまざまな解釈ができるが、
「イエメンで乗り合いタクシーに乗っていたら、雨が降った後に突然砂嵐の黄色い壁が現れて、ホワイトアウトというか、イエローアウトとなったのでした。今回の比喩としての黄色い夜は、何かおかしな思想を醸成してしまう場のようなものを想定しています」
そして妄執に駆られながら、最上階を目指すルイたちが行きつく先とは……。
「ラストは決まっていました。ある種の青春の終わりのようなものが訪れるというスタイルを考えていました」
当時の勢いはそのまま残した
過去の短篇から出来上がった本作。
「短篇を書いたのが二〇〇五年くらいですから、二十六歳くらいの時。作中の、二十代の謎のソウルフルな何かはあるけれど理屈としてはおかしいようなところを、理解できるように書き直しつつ、当時の勢いは残すという、その調整に時間をとりました。当時の私は何を考えていたんだろうと解読して地ならししていく作業でもありました。ルイが神学論議みたいなことをしている場面などがあって、今読むと彼が何を言っているのかさっぱり分からない(笑)。そういう部分はばっさり削りました」
変遷の末、ベストな形で単行本になったといえる本作。確かに濃密で読み応えがある。ここまで書けるなんて、宮内さんご自身も賭け事に強いのでは?
「いつも貧乏旅行なのでカジノには行きません。ただ、さすがにラスベガスに行った時は別で、ブラック・ジャックとクラップスで勝ちましたが、その後ポーカーにチャレンジして全部吐き出して帰ってきました(笑)」
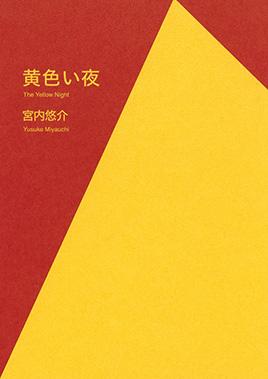
集英社