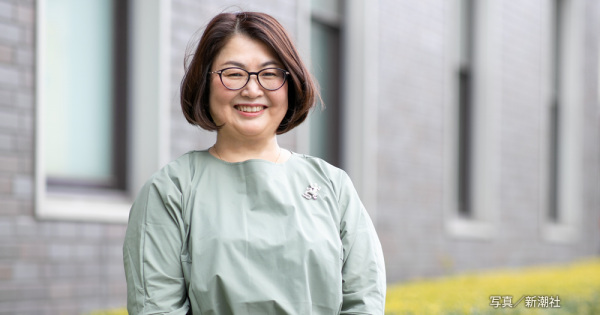山本文緒さん『自転しながら公転する』
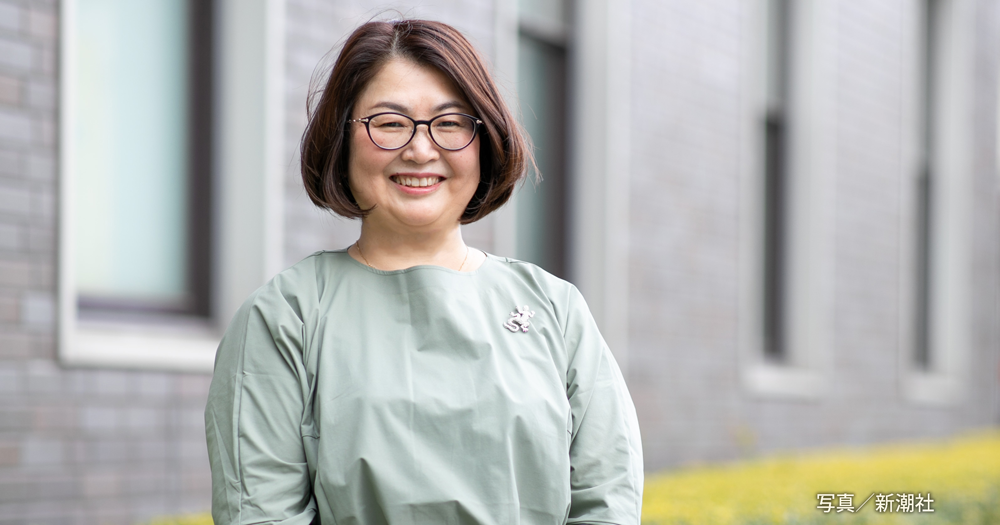
〝この人がいなくても生きていける〟から始まることもあると思うんです
山本文緒さんの七年ぶりの新作長篇がいよいよ刊行になる。『自転しながら公転する』は、茨城県の牛久を舞台に、一人の女性が恋に、仕事に、家族との関係に悩みもがく姿が描かれる。出発点は〝少女漫画〟だったというが、そこに込められた思いとは?
舞台は牛久のアウトレットモール
主人公は2年前まで東京のアパレル会社で働いていた与野都。重い更年期障害を抱える母の面倒を見るよう父に乞われ、茨城県牛久の実家に戻り、現在はアウトレットモールの女性向け衣料品店で働いている。32歳となり、地元の友達が恋人を作り結婚していくなか、彼女は自分の将来が見えない状況で──山本文緒さんの新作長篇『自転しながら公転する』は、一人の女性が仕事、恋、家族との関係に悩みながら進む姿を丁寧に描き出す。これが実に7年ぶりの新刊である。だが実は執筆の開始はずいぶん前だったという。
「はじめは書下ろし小説として書き進めていたのですが、その途中で担当編集者が亡くなり、ショックで止まってしまって。その後、連載という形で再開することになりました。時間が空いた分、いろんな要素を盛り込むことになって、当初の予定の倍くらいの長さになりました」
牛久を舞台にしたのは、
「以前、つくばに住んでいたことがあり、舞台となるアウトレットモールにも買い物に行っていました。その時は小説に書くつもりはなかったんですが、面白いところだなとは思っていて。アウトレットモールというと軽井沢にあるような、きらびやかなイメージを持っていたんですが、牛久のモールは地元密着型だったんです」
ある雨の夜、車が故障して困っている都を助けてくれたのが、モール内の回転寿司店で働く貫一だ。後日お礼がてら食事することになるが、地元の友人は彼のことを「ただのヤンキー」などと馬鹿にする。それでも、都は貫一に惹かれていく。この二人の恋愛の行方が、物語の大きな軸となっている。
「コミックスで10巻20巻あるような少女漫画をイメージしていました。そういう漫画って、主人公が誰とくっつくかでひっぱりますが、それってすごいことだなと気づいて。これが〝恋愛小説〟と呼べるかはわかりませんが、誰と誰がカップルとして成立するのかを、長い小説で書けたらと思いました」
都を東京から帰郷して契約社員として働くアパレル店員という設定にしたのは、
「ずっと牛久に住んでいる人と東京に住んだことがある人ではメンタルも違うだろうと考えました。アウトレットモールには食器店やスニーカーのお店などもありますが、やっぱりアパレルが一番多いので、主人公の働く先もそこにしました。執筆にあたって一度アパレルの方にも話を聞かせてもらいました。それと、20代だと何も考えずにのびのびできるけれど30代になると先のことを考えなくちゃならなくなる。でもまだ全然若い、ということで32歳にしました」
店ではそつなく仕事をこなし、店長や正社員、アルバイトとの間で中立的な立場をとっている彼女は、あまり自分の意見を言わないタイプ。
「周囲を観察していて、今どきの女の子は私の世代とは違い、親や友達に対して、乱暴な言葉を使いながらもすごく気を使っているなと、つねづね感じていました。そういうところを書きたかった」
貫一は一見、地元育ちのヤンキーという印象だが、読書家であったり、簡素な生活を送っていたり、料理上手であったりと、少しずつ意外な面を見せていく。
「都と正反対ですよね。洋服好きでたくさん買いこむ彼女に対して、貫一は風呂も洗濯機もない部屋でシンプルに暮らし、お金を使わなくても比較的快適に暮らしていける人。本人にその自覚はないミニマリストです。恋愛についても、パートナーがいないなんて不安で寂しい、という考え方はない。でも、自分の時間を人に差し出すことに躊躇はない。本もよく読むし料理もしてくれるし、私としては大変理想的な男性ですね(笑)」
人助けも厭わない貫一だが、若い頃は悪いこともしていた様子。また、都と交際を始めても、将来結婚するためにお金を貯めるといった様子はなく、むしろ途中で無職になってしまう。
「そういうところから自由な人ではあるんです。ただ、学歴もない自分は普通の女の子の夫としては歓迎されないんだろう、という卑屈さはありますよね。それと、都がひっかかっているのは善行と悪行のバランスが悪いというか。いいこともすれば悪いこともする人で、都にはそれが理解できないから魅力を感じるともいえます」
性格の異なる都と貫一だが、会話も弾むし、互いにとても楽しそう。このあたりの二人の心地よさそうな描写はさすが。
「一緒にいると快適で楽しい時間が流れていくというのは、少女漫画の快感なんじゃないでしょうか(笑)」
だが、都に言い寄る年下のベトナム人男性も現れて……。
求めるものが明確かどうか
印象的なのは、都が友人と3人で食事をする場面。一人は貫一のことを「無計画なワーキングプア」と言って別れることを勧め、もう一人は彼の言動について「ちゃんとした人だと思う」と評価する。
「友達に気を使って思っていることを言わない世代の子たちも、何も考えていないわけじゃなくて、言ってもいい場面になったら言える。むしろ、何も言えない都のほうが物事をややこしくしているのではないか、ということを書きたかった場面ですね」
他の二人がはっきり意見を言えるのは、
「パートナー選びに対して明確に志向があるから。ここが大切でここはそんなに気にしない、ということが決まっている。都はそこが決められていないから揺れている。まあ、決めればいいというものでもないんですけれど、決めないと悩みはいつまでも続く、ということを表したかったですね」

恋人に何を求めるのか、相手と結婚したいのか、その後どう生きていきたいのか。恋愛に限らず仕事についても、都のように明確な目標や目的が定まらない人は昨今多いだろう。
「今は結婚することだって当たり前ではなくなっている。生き方の選択肢が多い時代ですが、それは自分で考えて選ばなきゃいけないことが多いということでもありますよね」
都は友人から、〈迷いの根本が、自活できる経済力がないこと〉と指摘される。確かに自分に経済力があれば、将来の不安は半減されるはず。
「今の日本では、子どもを産んで正社員として働いて経済的に自立して時間も体力も確保することが望まれていて、ムリゲーをさせられている感じがします。いろんなことを若いうちから模索しないといけない。大変だと思います」
貫一だって将来についての明確なヴィジョンがないわけだが、
「もしお互いと出会わなかったら、二人はそれまで通り、流されるままに、むしろ自分の趣向をつきつめていたのでは。貫一は家賃3万円のアパートで充足して生きていけただろうし」
確かに都は、はじめて貫一のアパートを訪れた際、〈この人が自分と関わることで、彼のどこか充足した生活を侵略することになりそうだと、勝手に罪悪感を覚え〉ている。
「男女が付き合うということは侵略しあうことでもあって、必ずしもいいこととは言えない気がします。今は一人で生きて一人で死んでも寂しいわけではない、という価値観もありますし。〝この人がいないと生きていけない〟という考え方も素敵だけれど、〝この人がいなくても生きていける〟という結論を一回出してから始まることもあると思うんです」
仕事も実家も、悩みは尽きず
また、彼女は仕事についても悩む。辞表を出した年下の店員、杏奈から辛辣な言葉を浴びせられることもあれば、店長とアルバイトたちの狭間に立たされることもあり、また、セクハラに遭うことも。
「私も若い時にアルバイトで店員をしたことがあるんです。店長が気に食わないとか、エリア担当がセクハラをするとか、昔も同じようなことがありました(苦笑)。杏奈については、都は今どきの人に見えて、実はもう古く見えつつある雰囲気を出したかったですね。20代前半の杏奈は都のような服の買い方はしないんじゃないかなと思うし。セクハラについては、昔だったら〝それがどうした〟で片づけられてしまっていたけれど、今は苦情を訴えることもできるので状況は多少よくなったなと思います」
家族は頑固オヤジな側面のある父と、ほぼ寝込んで過ごしている母の二人。更年期障害というと深刻に受け取られなさそうだが、彼女のように日常生活に支障をきたすケースもあるという。
「今の時代、都の父親のように、自分の娘に介護のために仕事をやめろというのは価値観が偏っていますよね。娘のことを考えているようで考えていない父親です。母親の桃枝の更年期障害は、誰でもここまで重くなる可能性があるし、それは怖いことだなと思っています。私は桃枝と同じ世代なので、実は彼女のほうが書きやすかったですね(笑)」
女は結婚して男に養ってもらうもの、という考え方の父親が、貫一を認めるかどうかも大問題。一方、母親の桃枝はまた違うことを考えている。作中、桃枝の視点に切り替わる部分があり、彼女も自分のこの先を考えていると分かる。つまり本作は母と娘、世代の異なる女性二人が自分の未来について考え、模索する物語としても読めるのだ。
意外なプロローグとエピローグ
雑誌連載の時にはなかったのが、プロローグとエピローグ。これがあるのとないのとでは、読み心地がかなり違う。
「連載時からプロローグとエピローグのプロットは決まっていて、単行本にする際につけ加えるべきかどうか悩みました。ただ、『なぎさ』を出した時に、この先が知りたかったという声がたくさんあったんです。エンタメ小説としてはきちんと結末を見せたほうがいいのだろうと反省し、足すことにしました。でも今でも蛇足ではなかったかと不安なんです」
というが、この部分があるからこその感慨が絶対にある。特にエピローグで「幸せだった?」と聞かれた人物の答えがいい。〝幸せにならなきゃいけない〟というプレッシャーから解放してくれる言葉だ。
前作『なぎさ』から実に7年ぶりの作品。またしばらく新作を待つことになるのかが気になるところでもあるが、
「あちこちで書いた短篇がたまっているので、来年以降に出せたらいいなと思っています」
というから、こちらも楽しみ。
山本文緒(やまもと・ふみお)
1962年神奈川県生まれ。99年『恋愛中毒』で吉川英治文学新人賞を、2001年『プラナリア』で直木賞を受賞した。著書に『あなたには帰る家がある』『眠れるラプンツェル』『絶対泣かない』『群青の夜の羽毛布』『落花流水』『ファースト・プライオリティー』『アカペラ』『なぎさ』など、エッセイに『そして私は一人になった』『再婚生活』など多数。
(文・取材/瀧井朝世)
〈「きらら」2020年10月号掲載〉