吉川トリコ「じぶんごととする」 11. 優しい自己責任論者のためのエンディングノート
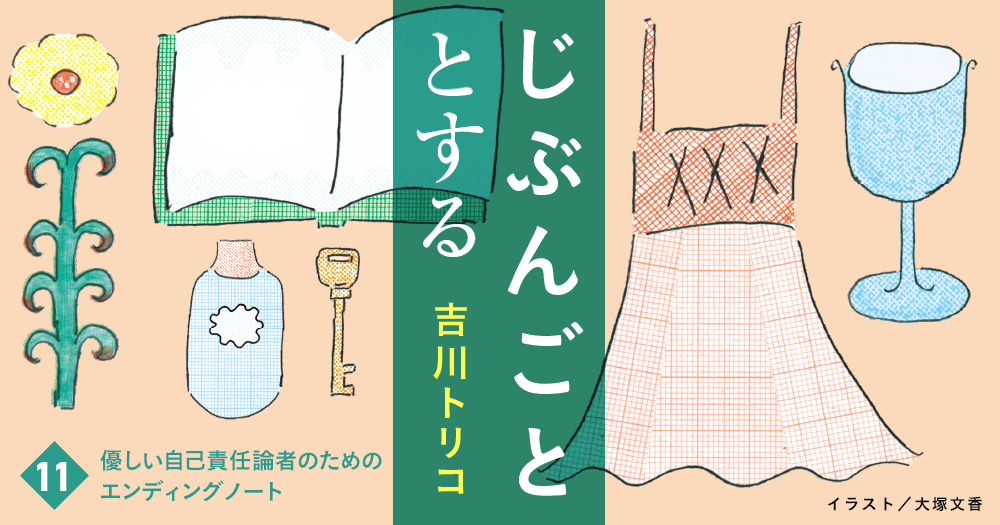
作家・吉川トリコさんが自身の座標を定めてきた、あるいはこれから定めようとするために読んだ本を紹介するエッセイです。
人に迷惑をかけてはいけないと、いつのころからか、強迫観念のように思い詰めている。
二〇〇〇年代初頭、小泉政権下に台頭しはじめた自己責任論の影響をもろに食らい、見事なまでに内面化してしまった哀しき狂戦士、それが私である。だれにも頼らず自分一人の力で生きのびてきた女戦士フュリオサのように、新自由主義が吹き荒れるこのマッドな時代を生きている。
三姉妹の長女で、「みなし家長」として育てられたことも関係しているのだろう。母親ゆずりのクソマッチョな気質も自己責任論的な思考と相性がよかった。自分で自分の責任を取ることを美徳とし、もし仮にどうしても他人の手を借りなければならないときは、それ相応の対価を支払わねばならぬと思っているようなところがある。等価交換の原則については『鋼の錬金術師』で履修済みである。
したがって、金銭を媒体にしてプロの手を借りることにはまったく抵抗がないのだが、問題は家族や友人に甘えられないことだ。自己責任論者のうえにせっかちなので、なんでも一人で決めて、なんでも一人でやってきた。これまで大きな怪我や病気をしたことがなかったからまだなんとかやってこれたが、この先、年をとるにつれ、自分一人でできることはかぎられてくるだろうし、金にものをいわせた外注だけではどうにもできなくなる日がくるだろう(老後の金の心配もつねにべったり貼りついている)。
そのとき私はどうしたらいいのだろう。だれかに迷惑をかけるぐらいなら、いっそ死んでしまいたい。本気でそんなふうに考えている自分が自分でも心配である。
二〇二一年に刊行した『余命一年、男をかう』は、私と同じように、自己責任論者養成ギプスを身につけて生きてきた四十歳の女性が主人公の小説である。タイトルそのまんま、余命宣告をうけた主人公が金で男を買い、予後の面倒と看取りまでをお願いする話だ。
人に迷惑をかけてはいけないとどれだけ気張ったところで、人は一人では生きられないし、一人で死ぬことさえできない。自分の足で立って生きるということとだれかと手をつなぐということは、決して相反することではない。ことさらに自分を強く大きく見せる必要もなければ、弱い自分を恥じることもない。大人になるということは、だれかに手を伸ばし、助けを求める勇気を持つことなのではないか。もし自分がだれかに助けを求められたら、そのときできる最大限の親切を惜しみなくかえしてやる。よりよく生きるということは、そうしたちいさな歩み寄りと善行を積み重ねていくことなのではないか。
といったようなことを考えながら、自己責任論の圧力がよりきゅうきゅうと高まっていたコロナ禍のまっただなかに厳粛な気持ちで書いていたのだが、いかんせん作者も主人公も自己責任論者養成ギプスがバッキバキにきまっているものだから、終盤、物語を進めるのにほんとうに苦労した。きれいごとだと読者に思われたくはなかったが、それでもやっぱりきれいごとを書きたかった。いまある現実から乖離しすぎず、どう落としどころをつけるか、その塩梅がむずかしかった。主人公がどのようにギプスから解放されたかについては、つい先日、講談社文庫から文庫になったばかりなので、実際に読んでたしかめてみてください(唐突な宣伝)。
執筆にあたってさまざまな本を読んだが、死や病気にまつわる本がとくに多かった。がん告知を受けた人の闘病記、ターミナルケア、終活、自殺、孤独死、尊厳死、遺産相続や死亡後の手続きについての本など。
そのとき読んだ中でいちばん強烈だったのが、村井理子さんの『兄の終い』である。ある夜、何年も会っていなかった兄の死を報せる電話が宮城県の警察からかかってくる。それから、怒濤の勢いで兄をしまうまでの五日間の記録である。
突然、兄の遺体を引き取りにきてくれと言われたって、仕事もあるし、日々の雑事もある。家族や犬のことだってほっぽってはいけない。兄の死に悲しみをおぼえるより先にまず生活があって、兄の死をやっかいな面倒ごとのようにとらえてしまう。そのような心の動きが包み隠さず率直に書かれていて、身につまされる読者は多いだろうと感じた。
私はといえば、どちらかというとしまわれる側に心を寄せ、いたたまれなさで溶けそうになりながら読んでいた。私にはこのような境遇の兄はいないけれど、私がこの兄の立場になる可能性はおおいにありそうだと思って、とてもひとごとではいられなかった(生き別れの父がいるが、幸か不幸か、縁が切れている。死んだら相続放棄の連絡ぐらいはくるかもしれない)。
真ん中の妹(ま)とは、毎日のように連絡をとりあっているし、おたがい夫に先立たれたら二人で暮らそうといまから話しているが、十一歳年の離れた下の妹(ゆ)とは、数年に一度顔を合わせるかどうかで、連絡をとりあうこともほとんどなく、完膚なきまでの「ザ・疎遠」である。とくに嫌っているとか、仲が悪いとかそういうわけではないけれど、気づいたときにはそうなっていた。
私も(ま)も子どもがいないので、我々の終いが(ゆ)にのしかかる可能性はかなり高い。なにそれこわい! 莫大な遺産は無理でもせめて火葬代と手間賃ぐらいは用意しておかないと!と『兄の終い』を読んですぐ、思わずコープ共済の保障内容を確認してしまった。
- 1
- 2








