町田そのこさん『星を掬う』

人生に意義や意味を見出して希望を持ってほしかった
『52ヘルツのクジラたち』で本屋大賞を受賞した町田そのこさんが、待望の受賞後第一作を上梓。『星を掬う』は、幼い頃に出奔した母親と大人になって再会し、一緒に暮らすことになった女性の物語。この二人はもちろん、周囲の女性たちの事情をも交え、さまざまな痛みと苦しみ、やがて見つける光を描き出します。
新作は、離ればなれに生きてきた母と娘の物語
今年『52ヘルツのクジラたち』で本屋大賞を受賞した町田そのこさん。待望の受賞後第一作『星を掬う』は、幼い頃に母に捨てられたという心の傷を引きずる女性が、大人になって意外な形で母親に再会する、沁みる物語だ。
実は今年、本屋大賞受賞が決まってからは胃薬を飲み続けていたという。
「嬉しいと同時に、自分には早すぎるとしか思えなくて。もっと実力をつけてからという気持ちで、賞に憧れてもなかったんです。次に書くものは賞に見合うもの、賞を貶めないものを書かなければ、という思いがすごくありました」
本作の第一稿は、ノミネートが分かった後、発表の前に書き上げたという。
「でも、気持ちが浮ついた期間が過ぎた五月の終わりくらいに読み返して、これは駄目だと思いました。編集者さんに〝書き直します〟と伝えてから、頭と最後以外は全部書き直しました。改稿で設定がまったく変わったキャラクターもいるくらいです」
小学一年生の時に母親・聖子が出奔、高校生の時に父親を亡くし、祖母と爪に火を点すような生活を送ってきた千鶴。その後祖母も亡くし、結婚するも仕事で失敗した夫・弥一は横暴になり、離婚したものの彼は今も彼女を訪ねてきては暴力を振るい、金を巻き上げていく。
「人によっては〝どうして逃げないの〟と言うと思います。でも、法的な繫がりがなくなっても追いかけてくる人っている。どんなに逃げても興信所を使われて見つけられてしまうという話も耳にします。こういう粘着質の男性は女の人を所有物のように扱い、相手の人格を損ねるんですよね」
最悪のクズっぷりを見せつける弥一だが、「クズ男って、書いていて楽しい(笑)」と町田さん。やがて弥一は千鶴の勤務先のパン工場にまで姿を見せ、怖くなった彼女は辞表を提出。職場の主任の女性も、「可哀相」などと言って心配している態度は見せるものの、千鶴が退職を決めてほっとしている様子。このあたりが非常にリアルだ。
「〝可哀相〟という一言で問題を片付けてしまう人っている。でも言われた方はその言葉でくくられることで、自分の存在価値を貶めてしまうんですよね。千鶴はずっと〝可哀相〟という言葉に押し込められて、結果的に自分でもその中で生きてきたような人です」
そんな折、意外な出来事が。ラジオ番組に出来心で母との思い出を投稿したところ、それを聴取した恵真という女性が局に連絡を寄越し、会うことになったのだ。彼女は現在、聖子と一緒に暮らしているという。千鶴の事情を知った恵真は自分たちと一緒に暮らそうと提案。千鶴は最初、自分を捨てた母親に頼りたくないと拒否するが、「母親の責任を果たせ」と、利用するつもりでいればいいと説得され、さらに、まだ五十代の聖子が初期の若年性認知症だと知り、母の家に行くことにする。
女性四人の共同生活
聖子たちが暮らしている〝さざめきハイツ〟は元社員寮で、広めの食堂やそれぞれの個室、庭もある建物で、聖子と恵真、彩子という四十代の女性が暮らしている。そこに千鶴が加わることになる。
「そもそもは、『52ヘルツのクジラたち』に子どもを虐待する母親が出てきますが、あの母親側の視点から書きたかったんです。母にも母の事情があったんだろう、と思うから。それで、最初に書いたのは、聖子さんが子どもを置いて出ていったのには理由があって、それを追っていくという、少しミステリ要素のある筋でした。でもそれだと、私は母の気持ちも娘の気持ちも、両方書きたかったはずなのに、うまくいっていないと気づいたんです」
女性四人の共同生活が始まる部分からラストの前までを、全面改稿した。その際にいちばん変わったのは、聖子の人物造形だったという。
「最初の原稿では、聖子さんも千鶴と同じようにウジウジして、娘を捨てた罪悪感にとらわれている人物でした。でも、娘を捨てて逃げたんだからこそ、その責任を背負いながらも自由に生きてきた強い人にしたくなって。そんな母の背中を見て、千鶴が学んでいく話にしたくなりました。認知症に関しては、以前、私の祖母がそうなった時に、同じように認知症になった方やそのご家族のブログを漁るようにして読んだことがあったんです。若い世代の認知症の人を書くことで、読者も共感しやすくなるんじゃないかという思いがありました」
二十二年ぶりに再会した母娘だが、聖子の反応はそっけなく、千鶴は失望。また、恵真が聖子を「ママ」と呼び、可愛がられている様子にも心を乱される。それでも、弥一が追いかけてくるかもしれないと恐怖を抱く千鶴は、〝さざめきハイツ〟にひきこもる。千鶴と聖子の仲はぎくしゃくしているものの、ヘアサロンに勤める恵真や、家事を完璧にこなす彩子との生活はなかなか楽しそうでもある。
「自分なりの、新しい家族の姿を考えながら書きました。ちゃんとそれぞれのプライバシーもあるし、必要なときには私もいずれああいうところに住みたいですね(笑)」
印象に残る食べ物も登場。たとえば、生クリームではなくマヨネーズを使った「うそっこバナナサンド」。
「うちの母親がよく作ってくれたんです。母に訊いたら大叔母から教わったそうで、当時は生クリームが手に入らなかったのかもしれません。私は子どもの頃、それがバナナサンドだと思っていて、本物のフルーツサンドを食べた時にびっくりして(笑)。母に言ったら、あのバナナサンドはうそっこだよ、って。私はうそっこのバナナサンドも好きだったんですが、以前恋人に作って〝しみったれている〟と?られてからは人に言えなくなってしまって。自分の子どもにも作ったことがないです」
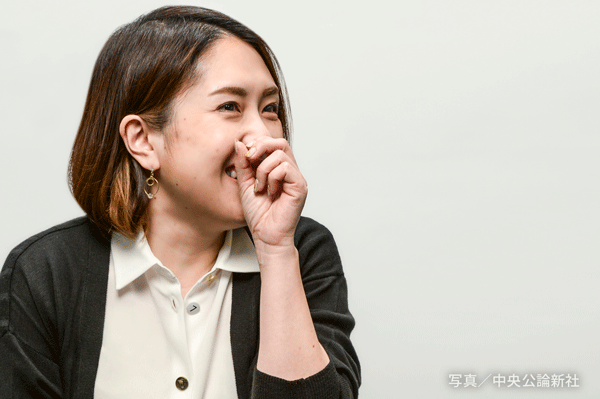
と町田さん。実際作ってみたところ、バナナとマヨネーズがとろりと混ざり、甘じょっぱくて美味しかったので、ご興味のある方はぜひ。また、人気のスイーツが出てくる場面で、きっと読者はニヤリとするはず。
もちろん食べ物だけでなく、印象深い言葉もたくさん登場する。たとえば、千鶴を無理やり外出させようとした際の聖子の言葉。
〈傷口ってのは、痛いの痛いの飛んでけって撫でるだけじゃダメなの。汚れた傷口をたわしでこすってごみを出さないといけないときだってあんのよ〉
きっと聖子も、そんなふうに生きてきたのだろう。また、母親への恨み節が止まらない千鶴に、ハイツにやってくる医師・結城がこんなことを言う。
〈自分の人生を、誰かに責任取らせようとしちゃだめだよ〉〈そういうのは十代で整理しておけって〉〈せめてこの二十代の間でどうにかしたほうがいい〉
「私も、〝親のせいで〟ということを言ったことがあるんです。本当は東京か大阪に出たかったのに、親に〝結婚するまでは家にいろ〟と言われてきたせいで、だから自分には自立心がないんだと思っていました。三十代半ばくらいでやっと、親のせいにするのは恥ずかしいなと気づいて。もっと早くに目を覚ませと平手で打ってくれる人がいたらよかったと思うので、結城さんに代弁してもらいました」
他の同居人の事情も次第に明かされていく。千鶴が目を奪われるくらい美しい恵真も、聖子と一緒に暮らすようになったのには理由がある。
「恵真ちゃんは千鶴とは対照的な存在にしました。表も裏も美しくて、千鶴の劣等感を刺激するんですよね。千鶴も私もそうですが、人はどうしても他人を表面的に見てパッケージングしてしまうところがある。表面だけでは分からないんだと千鶴が自分で気づいていく過程が書けたらいいなと思いました」
家事が完璧な彩子も、かつて家庭を持ち、娘もいるという。母親としての彼女は、聖子とはまた違う姿勢を見せる。
「最初は、彩子さんは母親になった経験のない人にしようかと思ったんです。でも、〝お母さん〟もいろいろだと書きたくなって、ああいう展開になりました。彩子さんは子どもを溺愛するタイプで、聖子さんは突き放して見守るタイプ。千鶴と彩子さんが親子だったら、ベタベタした友達母娘になったかもしれない。親子にも相性はあるのかなと感じます。相性が良くなくても長く一緒にいればじわじわと馴染んでいくのだろうけれど、千鶴のように人格が確立した後で再会した親子の場合は難しいところがありますよね」
逃げた後の人生に希望を持ってほしかった
町田さんはプロットをかっちり決めて書き始めるタイプではない。まず冒頭部分を書いて、そこから連想して話を広げていくという。それで、葛藤を抱える千鶴がそれをどう乗り越えていくか、説得力を持って書き切るのだからさすがだ。
「難しかったです。でも、改稿して聖子さんの性格を変えてからは、すごく筆が乗ったんです。聖子さんに関しては、新しいお母さん像が書けたかなと思っています。家族を守り労わるのでなく、生き方そのものや、人生の幕の引き方に対する考え方を見せ、背中で教えるところがありますよね」
千鶴と一緒に、読者の心も動かされていく本書。読み終えた時には、現実の社会で同じように苦しい状況にいる人たちに対しても思いをはせてしまう。
「八方ふさがりの状態でも、何かアクションを起こせば、きっと生きやすい方向に導いてくれる人がいるはず。千鶴もラジオに投稿したことがきっかけで状況が変わったんですよね。彼女には聖子さんの家があったけれど、そうでない人にとってはシェルターの存在はすごく大きいですよね」
そうして避難した後の生活のことも気になる、と町田さんは言う。
「相手から見つからないように逃げるということは人生をリセットするようなものですよね。だけど、リセットした後の人生に希望を見出せないと辛い。だからこの小説でも、千鶴が前を向くだけでなく、自分の人生に意義や意味を見出して希望を持てるようになってほしかったです」
プレッシャーを感じるなかで、ここまでの作品を書き上げた町田さん。
「書き直さなきゃ、と思えたのが嬉しかったです。自分は書き続けていける、大丈夫だと思えました。読む方それぞれ好き嫌いはあると思いますが、私はいまの自分の実力を出し切ったものが書けたなと感じています。今後もこうした話を書きたいし、クズ男の出てこない(笑)恋愛小説も書きたい。それに、笑って元気が出るようなコメディ小説を書きたいですね。私も辛い時は三浦しをんさんや北大路公子さんのエッセイを読んで笑って励まされているんです。そうしたものが書けるよう、もっと実力をつけたいし、笑いのセンスも磨いていきたいです(笑)」
町田そのこ(まちだ・そのこ)
1980年生まれ。福岡県在住。「カメルーンの青い魚」で、第15回「女による女のためのR-18文学賞」大賞を受賞。2017年に同作を含む『夜空に泳ぐチョコレートグラミー』でデビュー。21年『52ヘルツのクジラたち』で本屋大賞受賞。著書に『ぎょらん』『うつくしが丘の不幸の家』など。
(文・取材/瀧井朝世)
〈「WEBきらら」2021年11月号掲載〉




